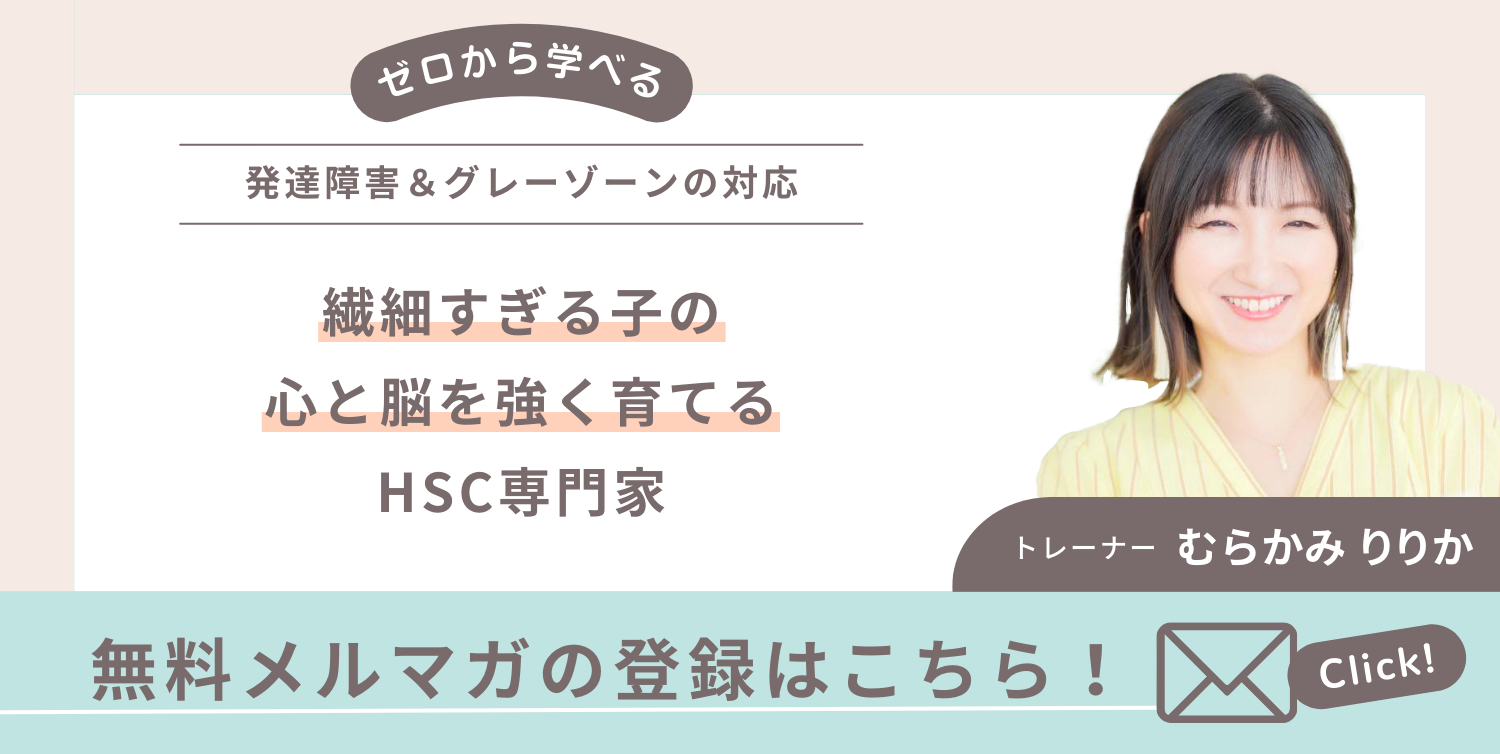「行きたくない!」「やりたくない!」と拒否する繊細な子の言葉の裏には、脳の防衛反応が隠れています。この記事では、逆効果になりがちなNG対応と、繊細な子が行動・挑戦するための親子のコミュニケーションを、体験談とともに紹介します。
【目次】
1.繊細な子の子育てが楽になる秘訣は親子のコミュニケーション
2.「行きたくない」の裏にある繊細な子の防衛反応
3.繊細な子に逆効果なNG対応
◆感情に感情で対抗する
◆理屈で覆そうとする
◆共感する
4.繊細な子の背中を押す3ステップ
①子どもの効く耳を開く
②気持ちをいったん「預かる」
③行きたい(やりたい)理由を作る
1.繊細な子の子育てが楽になる秘訣は親子のコミュニケーション
繊細な子どもを育てていると、学校、習い事にお出かけ…「行きたくない!」「やりたくない!」と全力拒否をされ対応に困ることはありませんか?
そんな困りごとは、全て親子の会話・コミュニケーションで解決できます。
私には、周囲の環境からの刺激をひといちばい敏感に受け取る、繊細な小学生の息子がいます。
数年前までは、学校も習い事もお出かけも「行きたくない!」が常だった息子ですが、親子のコミュニケーションを変えたことで、自分から行動・挑戦できるようになりました。

そんな息子から、先日久しぶりに「絶対行きたくない!」という言葉を聞きました。
その週末、親族で旅行があるのですが、メンバーは、おばあちゃん・ひいおばあちゃん・息子・そして親戚。
そう…わけあって母は行かないのです!
それをおばあちゃんから聞かされた息子は拒否反応!
「お母さんがいないなんて嫌!」
「絶対無理!」
「絶対行きたくない!」
断固として「行かない!!」と主張する繊細な息子に、おばあちゃんは「じゃあ一人でお留守番するねんね!」と感情的な対応に…。
息子はもちろんヒートアップしてますます行きたくなくなって、「おかあさ〜ん」と泣きついてきました。
「お母さんがいないなんて嫌!」
「お母さんと寝たい!」
「お母さんといたい!」
「絶対楽しくない!!」
「電車なんて乗りたくない!!」
行きたくない理由を延々と訴える息子。
私はそんな息子の「絶対行かない!」を、あることをして「行ってくる〜♪」に変換することができました。
何をしたか?
ただ会話をしただけなんです!
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
指示出しゼロの子育てで
たった3週間で癇癪が着く!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.「行きたくない」の裏にある繊細な子の防衛反応
繊細な子が「行きたくない」「やりたくない」「できない」と言うとき、実はその言葉の裏には脳の防衛反応が隠れています。
繊細な子の脳は、刺激を強く受け取りやすく、安心できない状況ではすぐに「危険信号」を出す特性があります。
つまり、脳がフルパワーで「守らなきゃ!」と働いてしまうのです。

その結果、表に出るのは「行きたくない」というシンプルな言葉。
ですが、その背景にはこんな気持ちが潜んでいます。
・不安:「失敗したらどうしよう」
・恐怖:「大きな音や、みんなの注目が怖い」
・未知への抵抗:「やったことがないから不安」
・完璧主義:「できない自分を見られたくない」
これらはすべて、繊細な子の脳が「危険を避ける」ために働く自然な反応です。
「やりたくない」という言葉は、わがままや怠けではなく、脳からのSOSサインだと受け止めてあげることが大切です。
ママが「この子の脳は今“守るモード”なんだ」と理解できると、感情的に対応するのではなく、上手に背中を押す対応へと切り替えられます。
3.繊細な子に逆効果なNG対応
上手に背中を押そうと、お母さんもあの手この手で一生懸命頑張るのですが、「なぜか逆効果…」ということはありませんか?
この章ではやりがちなNG対応を紹介します。
◆感情に感情で対抗する
感情的に「行きなさい!」とぶつかっても、親子のコミュニケーションは絶対にうまくいきません。
子どもの脳はますます「感情脳」優位になり、理解する脳も、思考する脳もうまく働かないような状態です。
私たち大人も感情的になっているときは冷静な判断ができませんよね。
子どもも同じで、感情的なコミュニケーションはストレスになるだけでなく理解脳、思考脳の成長にまで影響してしまうので良いことは一つもありません。
◆理屈で覆そうとする
「お母さんいなくても大丈夫だよ」
「きっと楽しいよ」
「電車楽しいよ」
このように必死に説得しても「絶対行きたくない!」の壁は強固すぎて覆せません。
むしろ「そんなことない!」と聞く耳を持たず、さらに反発を強めてしまいます。

◆共感する
繊細な子どもにとって、実は「共感」も逆効果です。
繊細な子の脳はネガティブな感情に共感することで、ネガティブな感情が増してしまうからです。
子育て本などでは「気持ちに共感しましょう」と言われているので、驚かれるかもしれませんね。
「行きたくない!」「やりたくない!」という言葉に対して、「そうだよね〜」「お母さんといたいよね」と繰り返すと、逆に「そうなの!」と気持ちが増幅し、行きたくない感情が脳内で強化されてしまいます。
毎日の声かけで“脳のクセ”は変えられる!
子どもが持つ力を発揮できるようになる
4ステップの声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
4.繊細な子の背中を押す3ステップ
繊細な子の脳に届くコミュニケーションを知っていれば、子どもの不安を落ち着かせ、「行きたくない!」を「行きたい!」に変換することができます!
3ステップで紹介しますね。
◆①子どもの効く耳を開く
まずはお母さん自身が子どもの感情に振り回されないことが大事です。
お母さんが落ち着き、そして子どもを落ち着かせて、会話ができる状態を作るところからスタートします。
息子が「絶対行かない!」とヒートアップしているとき、私自身は自分の感情スイッチを押さずに、まずは「おいで〜」と膝に乗せました。
スキンシップによる皮膚刺激は、感情脳と太いネットワークで繋がっているので、感情を落ち着かせてくれます!
穏やかな声を作ることで自分も子どもも落ち着ける効果があるので、聴覚が敏感なお子さんには特に効果的です。
そうして少し落ち着かせて「ねぇ聞いて、おかあさん」と、お母さんの声が素直に届く「聞く耳が開いた状態」にしてから会話をスタートしました。
会話は始め方が非常に大事!
聞く耳が閉じた状態では優しく言っても厳しく言っても何言ってもムダだからです。
◆②気持ちをいったん「預かる」
前の章で「共感は逆効果」とお伝えしました。
ではどうするか?
「お預かりしますね」のスタンスで肯定も否定も共感もしません。
行きたくない理由や感情をぶつけてくれている時は
「そうなんだね」
「それで?」
「そうなんだ〜」
と、こんな魔法の言葉で穏やかにただ受け止めます。
そして子どもの本当の感情を引き出して言葉化していきます。
アドバイスやコメントを言いたくなっても封印です!

◆③行きたい(やりたい)理由を作る
子どもが行きたくない、やりたくない気持ちを十分吐き出せたなと思ったら、最後は「やる理由」を作ります。
私は繊細な息子の心を動かしそうなネタを探して提示しました。
「でもさぁ、恐竜博士くるらしいよ〜(旅行に参加する親戚)」
「でもさぁ、ウルトラマン大好きなあの子が〇〇くんに来てほしいみたいだよ〜」
「恐竜とかウルトラマンとかで遊べるし、たくさんお話できるね〜」
この「でもさぁ」と共に、ポジティブな見通しを持てるネタをイメージしやすいように伝えることが、繊細な子どもの「絶対行かないから!」を脳からはがす秘訣です。
息子は「そうなの?」みたいな顔をして1階にそそくさと降りていきました。
ウルトラマンのオモチャをひっぱりだし、いろいろとチェックしてたようです。
しばらく待ち、私が1階に降りていくと「お母さん!ぼく行くことにしよー♪」と、自分で決断しました。
行きたい理由を作ろうとする時も、絶対にこちら都合なことは述べず、全く説得しようというオーラは出さず、「わぁ楽しそう」という口調で話すこともポイントです。
いかがでしたか?
子育てをラクに楽しくするには、繊細なわが子の心と脳のタイプにあった対応をするしかありません!
わが子にあった親子のコミュニケーションで、繊細な子の行動力を育てていきましょう。
▼動画でも学べます!繊細な子へのNGな問いかけ
この投稿をInstagramで見る
繊細な子どもの心と脳を強くする秘訣をお届けしています!
執筆者:むらかみりりか
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
(発達科学コミュニケーショントレーナー)