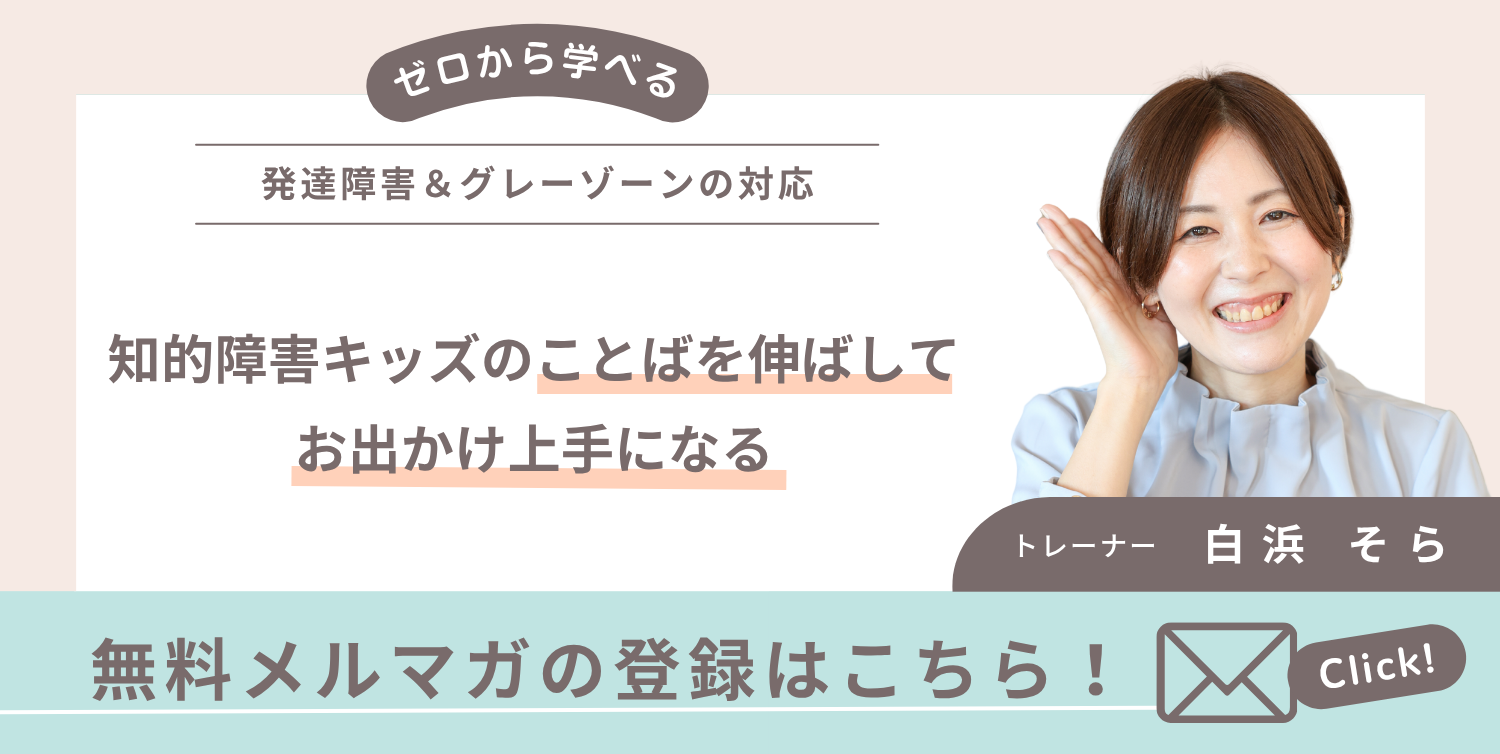言葉が遅い子は、自分の思いをうまく伝えられるようになると、言葉が伸びていきます。「伝わった!」という成功体験が、言葉を育てる脳の栄養になるからです。おうち療育で、まずは「ちょうだい!」など『要求のことば』を育て、伝える力を伸ばしましょう。
【目次】
1.言葉が遅い、話しかけても反応がないわが子を前に、私が感じていた焦りと迷い
2.療育に通っても言葉が増えないのはなぜ?言葉の土台が育ちにくい理由
3.ママに「伝わった!」という成功体験が言葉を伸ばす鍵になる
4.言葉が遅い子が「ちょうだい!」と伝えられるようになる『おうち療育』2ステップ
1.言葉が遅い、話しかけても反応がないわが子を前に、私が感じていた焦りと迷い
言葉が遅い子の言葉を増やすには、「りんご」「バナナ」とひとつひとつ単語を教え込んだほうがいいと思っていませんか?
結論、「ちょうだい」「やって」などの「要求のことば」を育てれば、子どもは自分の思いを伝えられるようになり言葉が増えます。
わが家の娘は、重度知的障害で自閉スペクトラム症(自閉症)です。
5歳まで喃語だけで、自分の気持ちが伝えられず、毎日かんしゃくを起こしていました。
当時の私は、「言えることばを増やせばいいんだ!」と思い、「絵本だね〜」「バナナだね〜」と、言葉を教え込もうと必死でした。
けれど、言葉を教えても増えず、話しかけても反応がない。娘のかんしゃくに私もイライラ。
「もう、ことばで言ってよ!」と強い口調になってしまうこともありました。

そんなときに出会ったのが、『ことばを教える』のではなく、『ことばの脳を育てる』という考え方でした。
その『ことばの脳を育てる関わり』を続けていく中で、娘に「ママに伝わった!」という成功体験を積み重ねることができました。
すると、これまで視線やクレーンで伝えていた娘が、食べたいものを「ちょうだい」、やってほしいことを「やって」と、言葉で伝えられるようになったのです。
今では、笑顔でコミュニケーションが取れるようになりました。
次では、言葉の発達が遅い子が、療育に通っても言葉が増えない理由についてお伝えします。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
3週間で癇癪が落ち着き
毎日が穏やかに過ごせるようになる!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.療育に通っても言葉が増えないのはなぜ?言葉の土台が育ちにくい理由
「たくさん話しかけてくださいね」
「焦らず見守りましょう」
そう言われて努力しても、思うように言葉が増えない。
療育にも通っているのに、なぜ?と思うママも多いのではないでしょうか。
言葉が出にくい理由はいくつかあります。まずは、言葉が育つまでの流れを見てみましょう。
◆①言葉の発達は「順番」を追って育ちます
1歳前後には「マンマ」「ワンワン」などの一語文、
2歳ごろには「ママ来て」などの二語文、
3歳ごろには「昨日○○した」など、少し長い文を話すようになります。
この流れには個人差がありますが、発達がゆっくりな子は、この流れに時間がかかることがあります。
人と目を合わせたり、声に反応したりする「やりとりの力」がまだ育ちきっていないことがあるのです。

◆②言葉が遅れる主な原因
・聴こえの問題(中耳炎など)で音が聞き取りにくい
・脳の発達特性(自閉症傾向など)により、相手の視線や声に気づきにくい
・会話のテンポが速く、理解が追いつかない
・おとなしい性格で、自分から表現する機会が少ない
こうしたことが重なると、人と一緒に『見る・聞く・感じる体験』が少なくなり、言葉を使う準備が整いにくくなります。
◆③「教える」だけでは言葉は育たない
「りんご」「バナナ」と言葉を教えることも大切です。しかし、それだけでは「話したい」気持ちは育ちません。
なぜなら、子どもが言葉を覚えるのは、ママとのやりとりの中で「伝わった!」と感じたときだからです。
この体験が、脳の中の言葉の土台を伸ばしていくのです。
次では、その『伝わった』体験を生み出す、「同じものを見る力(ジョイントアテンション)」について紹介します。
3.ママに「伝わった!」という成功体験が言葉を伸ばす鍵になる
子どもが「言葉を使いたい」と思うきっかけは、ママと気持ちが通じたときです。
療育や言語訓練を頑張ってもなかなか言葉が伸びないと感じるとき、必要なのは「教えること」ではなく、「伝わる体験をつくること」。
そのとき大事になるのが、「同じものを見る力(ジョイントアテンション)」です。
これは、ママと子どもが同じものに注目することで、「共同注視」とも言われます。
たとえば、子どもが公園でコスモスを見つけたとき。
ママが「コスモスだね」と声をかけ、子どもも同じコスモスを見ていたら、それがジョイントアテンションです。
ママが「教える」よりも、子どもが興味を示しているものを「一緒に見る」ことで、子どもは、
「ママに伝わった!」
「ママが見てくれてる!」
と感じます。

そして、
「もっとやってみよう!」
「もっと伝えたい!」
という気持ちになるからこそ、言葉の脳がぐんぐん伸びていくのです。
次の章では、子どもの伝える力を伸ばすために、おうちでできる2ステップの関わり方を紹介します。
情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!
”脳のクセ”を育て直す声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
4.言葉が遅い子が「ちょうだい!」と伝えられるようになる『おうち療育』2ステップ
言葉を育てるいちばんの近道は、「子どもの興味にママが合わせること」です。
どんなに「見て!」「聞いて!」と呼びかけても、子どもが興味のないことには、なかなか注目できません。
だからこそ、まずは『ママが子どもの見ているものに興味・関心を示す』ことで「ジョイントアテンション」を育てることが大切です。
ここでは、子どもが「ちょうだい!」と伝えられるようになるための、おうちでできる2ステップを紹介します。
◆①子どもを観察する
まずは、子どもがどんなものを見て、どんなことに夢中になっているかを観察します。
「何を見ているのかな?」
「どんな遊びが好きかな?」
と、宝探しをするような気持ちで見てみましょう。
◆②子どもの視線の先に声をかける
ママが見せたいものに注意を向けさせるのではなく、子どもの視線の先にママが合わせて声をかけるのがポイントです。
たとえば、子どもが葉っぱを見ていたら「葉っぱだね!」、電車を見ていたら「電車だね!」と、子どもが見ているものに言葉を添えましょう。
このとき、子どもの脳の中では「これが葉っぱなんだ」「これが電車なんだ」と意味がつながります。

そして子どもは、「ママが自分の見ているものをわかってくれた!」と感じ、「伝わった!」という成功体験が積み重なります。
この体験をくり返すうちに、子どもから「ママ、見て〜!」と声をかけてくれるようになります。
ママに伝わる言葉を引き出してあげることで、おうちでも幼稚園や保育園でも、自分の思いを言葉で伝えられるようになっていきます。
子どもの興味にママが合わせて「ジョイントアテンション」を育てることで、「ちょうだい」「やって」などの要求のことばを出すことを目指していきましょう。
脳を育てて「話したい!」を引き出す。ことばが伸びるおうち療育を発信しています!
執筆者:白浜 そら
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
(発達科学コミュニケーショントレーナー)