周りと比べて、一つ一つの行動が遅いわが子。小学校で集団活動を行う子どもの様子を見ていると不安になり、つい口うるさく言ってしまう発達障害凸凹子育て中のママはいませんか?でもママが適切な声かけをすれば、子どもが自ら行動するようになります!
【目次】
1.一つ一つの行動が遅い子ども、取り掛かりが遅い子ども
発達障害・グレーゾーンの不注意タイプの特性を持つマイペースな子どもたち。わざと行動を遅くして困らせようとしたり、わがままを言っているわけではありません。
おしゃべりで、明るくて、人懐っこく、ちょっぴりマイペース君。小さいときから好きなことに、すごく集中して楽しみ、おしゃべりも上手なわが子。
ところが、小学校へ進むと一斉指示で、行動の切り替えを要求されることがどんどん増えていく。すると、わが子の長所と思っていたことにあれ?と不安を感じ始める。
小学校生活では、ほとんどすべてが決められたカリキュラムを、担任の先生の指示に従ってこなさなくてはいけない。 けれど、なかなか素早く切り替えられず、周りよりも取り掛かりや行動が遅いこともしばしば。
みんなで一斉に 「はい、○○ページをひらいて、○○行から読んでいきましょう。」
「次は生活の授業なので、赤白帽をかぶって、探検バックをもって、廊下に並びましょう。」
ほかのことを考えているのか、周りのお友達がすでに指定のページを開き終えて待ってるときに、教科書を引き出しから出している。
赤白帽をロッカーに取りに行っても、なかなか割り込んでまでとれず、モタモタしてクラスで1番最後に並んでいる。
授業参観でたまたまそんな様子を見たら…あなたは、どうしますか?
これ、実は過去の私のことです。あの頃の私は、子どもが自宅に帰ってくるとすぐに 「周りをよく見て!先生のお話ちゃんと聞こうね。」 と言っていました。
その後も子どもの学校での生活が心配で、「今日は、何を教えてもらったの?」 とちゃんと授業を聞いているか、チェックするために質問をしていました。
大体1年生の半ば頃までは、忘れたー。 とほとんど期待の答えは戻ってきませんが…。
また、不注意タイプで連絡帳や給食時に使うマスクセットも学校によく忘れてきました。 そのたびに、取りに行ったり、メモを張り付けたり。 毎日、忘れ物をしないように口うるさく言っていました。
するとだんだんわが子は、以前のキラキラした表情が減り、自信をなくしていってしまったのです。

そして、自信をなくしたわが子は
「僕は、毎日一生懸命頑張ってる!!みんなのペースに合わせようとしているのに、周りのみんなも先生も責める。 そしてママまで僕を責める。僕はこんなに頑張っているのにこれ以上どうしたらいいの?」
と、期待に応えられてない自分へいら立ち、不安、心の悲鳴を言うようになってしまったんです。
息子言葉でようやく、取り掛かりや行動が遅いのは本人が意図してやっていることではないことや息子は息子なりに必死に頑張っているということに気が付きました。
このように、小学校入学をきっかけに子どもの発達が心配になるお母さんはたくさんいらっしゃいますよね。
2. 発達障害、グレーゾーン、マイペースな子どもが自信をなくしてはいけない理由
自信をなくすとどうしていけないのでしょうか?
自分への自信をなくした子どもは、自分は周りの期待の応えられない悪い子、だから「どーせ僕はダメな子なんでしょ!」と思うようになってしまいます。
すると、なにかを頑張ってやってみよう!と気持ちがなくなってしまいます。
自分で頑張ってやってみても、どうせ叱られるからやってくれるのを待とう。無駄に叱られるのはめんどくさい。だからやらない! と、言われないとやらなくなる。
取り掛かりが遅いこともますます助長され、次第に自分からはやらなくなってしまうのです。

しかし人間の脳は、行動して発達していきます。 行動が減っていけば、その部分の発達は進みません。
反対に自分の行動を友達・先生・一番接触の多いお母さんに、褒められて肯定された!と感じたらどうなるでしょうか。
子どもに自信ができて「もっと頑張ってみよう!自分もできるようになりたい!」と自らを行動したくなります。
たとえ、すぐうまくできなくても、行動すれば脳は発達していくのです。
自信を持つこと、行動することが大切。これまでもさまざまな場面でお伝えしてきました。
3.不注意で行動や取り掛かりが遅い子どもが自信をつけるには?
自信のなさを改善して、自信をつけるには、「 現状のままで、いいよ。その調子!」とできていることを認めて、褒めてあげたらいいんです。
それが、子どもの行動を増やして脳の発達を加速させる早道です。
毎日一緒に過ごす時間が1番長いお母さんが、積極的に子どもに声をかけてあげることはとても大切です。
「毎日、頑張って学校行ってるね。」
「一生懸命ノートをとっていたね。」
「ママ頑張っている姿を見られて凄くうれしかったよ。」
「教科書を早めに出しておく準備力がだんだんついてきたね ♪」
「ちゃんと連絡帳書いてきたね」
こんな風に、お母さんにありのまま褒めてもらえて、認めてもらえたら、子どもがもっと頑張ろう!と自分でやりたくなっていきます。こうして行動量が増えていき、脳の発達が進んでいくのです。
発達障害・グレーゾーンの子どもたちは、たとえお母さんができてないところを指摘しなかったとしても、先生や友達から日々自然に注意されてしまうことが多いですよね。これが積み重なって心の傷となっていきます。
それなのに、自宅でまで「遅いよ。早くしなさい!」ではその子にとって自信を無くし、マイナスにしかならない言葉かけですね。
つまり、「取り掛かりが遅いから早くしよう」と声をかけても子ども伸びないということです。
だから、お母さんは、子どもの心と行動のペースを守る人になってあげてほしいんです!

一歩行動が遅いタイプの子ども。いつか自信をもって、自分で乗り越えていける子に育ってほしいと思うなら、あえて、できてない、直してあげたい指摘はスルーしましょう。
そして、
「それでいいよ。」
「頑張っていたね。」
「準備力って大切だね。」
と普段から、折に触れて、伝えてあげてください。
子どもが自分でしっかりと行動できるようになるまでは、子どもに寄り添いながら待ってあげることが必要です。
お母さんが、子どもの心と行動のペースを守る人になって、今できているところを認めて褒める習慣にする。 そうすれば、徐々に自信が復活してきます!ぜひ試してみてください。
またこちらの記事では、子どもの行動力を育てる秘訣をお伝えしています。合わせてチェックしてくださいね。
発達を学び、子育ての成果を教え合う勉強会の様子をこちらの記事で紹介しています↓
学校での困り事を解消したいお母さんはこちらもぜひ参考にしてください!
↓↓↓
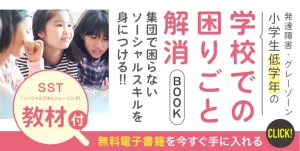
「気になる行動」への適切な対応法をメール講座でお伝えしています!
▼ご登録はこちらから
▼無料小冊子プレゼント▼
3つの質問で
今のあなたにぴったりな情報を
お届けします!
↓↓
執筆者:八木香り
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)





