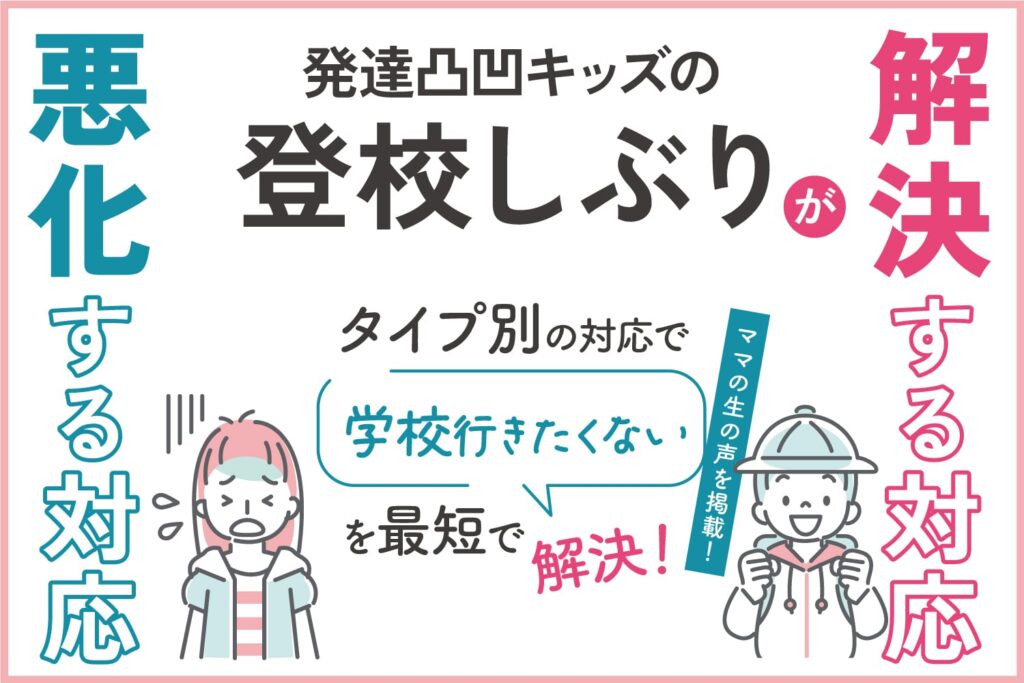発達障害ADHDの小学1年生が忘れ物ばかりするときの対策をご紹介します!小学生のお子さんに、何度注意したとしても、忘れ物が多いのには理由があります。この記事では、3ステップで忘れ物をしないようにする方法をお伝えします!
【目次】
1.小学生になって忘れ物が多いことに困っていませんか?
2.1年生の頃から忘れ物ばかりの娘にイライラ
3.ADHDの小学生は特に忘れ物が多い!…実は本人が一番困っています!
4.発達障害ADHD小学生に忘れ物が多いときの対策3ステップ
①忘れ物したことを責めない!
②どんなことでも褒めて、自信を付ける!
③子どもと一緒に忘れ物をしない方法を考えよう!
1.小学生になって忘れ物が多いことに困っていませんか?
小学生になると、幼稚園や保育園のときとは違い、先生が個別に対応してくれることは少なくなりますよね。
そんな状況もあり、我が子に忘れ物が多いことに気付き、思い悩むお母さんも増えています。

発達障害グレーゾーン・注意欠陥多動性障害(ADHD)傾向の、特に不注意が目立つタイプの小学生の子どもを育てていると、「どうして何回注意しても忘れ物するの?」と思うことはありませんか?
・毎日必要なハンカチ・ティッシュなどの持ち物を忘れる
・学校に連絡帳や大切な手紙を忘れてくることが多い
・えんぴつ・消しゴムなどの持ち物がどこかに消えてしまう
親としては毎日注意しているんだから、そろそろ覚えてくれても良いでしょう?って思いますよね。
小学生が忘れ物をしない方法なんて、注意してあげるくらいしか思いつきませんし、お子さんに早く成長してほしいと考えるのではないでしょうか。
2.1年生の頃から忘れ物ばかりの娘にイライラ
実は、私も小学2年生の娘に忘れ物が多いことで、毎日頭を悩ませていました。
1年生の始めのうちは、「まだ慣れていないし、しょうがない」と思えたのですが、夏休みが近づいてくる頃になっても、忘れ物ばかりする娘に対して、イライラすることが多くなりました。
さらに下にきょうだいが2人いることから、娘のことばかり見ているわけにもいきません。
娘の忘れ物に気を配り続けることに完全に疲れてしまいました。

「なんで毎日同じこと注意されるの?」
「ちゃんと自分でやってよ!」
など、キツい態度で接していました。
「注意されたら自分で考えて、きっと忘れ物はなくなっていく!」と思っていた私でしたが、娘の忘れ物はなくなるどころかさらに多くなるという悪化の一途をたどっていました。
そして責められ続けた娘は、1年生の夏休み明けころから、ちょっとしたことで怒鳴ったり、急に叫んで泣き出したりするようになってしまったのです。
学校でも友達にキツくあたってしまったりと、どんどん状況は悪化していきました。
もう忘れ物どころの話ではありませんでした。
3.ADHDの小学生は特に忘れ物が多い!…実は本人が一番困っています!
そもそも、何回注意されても忘れてしまうのには、脳に特性があるからなんです!
発達障害グレーゾーンのADHD傾向のある子どもは、脳の特性から“不注意・多動性・衝動性”といった症状が現れると考えられています。
これらの特性を簡単に説明すると、
不注意:気が散りやすい、失くし物や忘れ物が多い
多動性:じっとしていられない、しゃべり過ぎる
衝動性:話し終わる前に話し始める、急にカッとなる
これらすべてが当てはまるわけではなく、不注意だけ目立つ子もいれば、多動性や衝動性が目立つ子、不注意・多動性・衝動性のすべてを合わせもっている子など、その子によって特性は様々です。
ただ、ひとつ共通しているのは、どれも本人の意思ではコントロールするのが難しいということ。
自分ではどうにもできない脳の特性が原因で、いつも同じような忘れ物ばかりしてしまうのです。

お母さんとしては、
「毎回注意しているのに忘れるなんて怠けてる!」
とイライラしてしまうことも多いかもしれません。
でも実は子ども自身も、
「いつも忘れ物しちゃうなんてなんかおかしいな」
「自分はみんなと違うのかな」
と、思っていることが少なくありません。
年齢が上がるほど、自分のことを客観視できるようになっていき、できない自分を感じて自己肯定感が下がってしまう可能性があるのです。
自己肯定感が下がると自信を失い、行動もできなくなってしまいます。
脳は行動することにより発達するので、行動しなくなると脳は発達しません。
そして、失敗が増えると、さらに自信を失い、また自己肯定感も下がるという悪循環に陥ってしまうのです。
私はこの悪循環を断つために、娘の忘れ物を減らし、成功体験を積ませて自信をつけさせようと考えました。
次項では、私が実際に行った、忘れ物を減らして成功体験を積むための3ステップをお伝えしますね!
4.発達障害ADHD小学生に忘れ物が多いときの対策3ステップ
小学生になってからは、常に忘れ物が多いことで困っていた娘ですが、少し工夫するだけで忘れ物が減っていきました。
その忘れ物をしないようにする効果的な方法をご紹介しますね。
◆①忘れ物したことを責めない!
まず、お母さんに一番最初にして欲しいことがあります!
それは、忘れ物をしたことを責めないということ。
お子さんは今までに、家だけでなく、おそらく学校でも忘れ物が多いことを注意され続けているはずです。
注意され続けた結果、「忘れ物をしないなんて、自分にはできない」という意識が定着していきます。
そして、自分で忘れないように意識して動くということをだんだんとしなくなってしまうのです。
せめて家では、お母さんがそのことを理解してあげて、忘れたことを責めないであげてください。
◆②どんなことでも褒めて、自信を付ける!
次にして欲しいことが、どんなことでも良いので褒めてあげるということ。
別に特別なことじゃなくて大丈夫です!むしろ当たり前のことに対して、褒めてみてください。
・「お帰り~」とハグをする
・「お!水筒持ち帰ってくれたね!」
・「連絡帳見せてくれてありがとう!」
など、これらの言葉も、子どもを肯定する立派な褒めの言葉です!
できていることを認めてあげることで「自分は大切にされてる!」「自分はできる!」と、子どもは感じ、それが自信に繋がっていくんです。
一見、忘れ物と関係なさそうに感じるかもしれませんが、自分に自信がつくと、自分で考えて行動することができるようになっていきます。
その結果、忘れ物も今までより、グッと減っていくのです!!

◆③子どもと一緒に忘れ物をしない方法を考えよう!
忘れ物をしても、お母さんには責められることがなくなり、できていることを常に褒めてもらっていることで、お子さんには必ず自信がついてきます。
そうすると、だんだん素直に話が聞けるようになってくるのです。
このタイミングで、忘れ物をしにくくなるような環境を整えてあげましょう。
例えば…
・ランドセル置き場の近くに、持ち物チェックリストを貼る
(ホワイトボードに貼り、できた項目に磁石でしるしを付けていくなど)
・学校によく置き忘れるものを手に書いてあげる
・えんぴつ・消しゴムなどは、子ども本人がすごく気に入ったものを買ってあげる
・あらかじめ先生には、我が子の特性を伝えておき、時間があるときには、声をかけたり、サポートしてもらえるようにする
など、その子に合った忘れ物をしない方法を探っていきましょう!
そして、忘れ物をしなかったときには、最高の笑顔で褒めてあげてください!
お母さんの笑顔の効果は絶大なんです!
きっと今よりもやる気が出て、忘れ物が少なくなるはずですよ!
執筆者:渋沢明希子
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
(発達科学コミュニケーショントレーナー)