発達障害・ADHDの小学生の子どもが忘れ物が多くてお悩みではありませんか?忘れ物が多い子どもたちは学校の先生やママから注意されることが多く、自己肯定感が下がりがち!持ち物管理ができるようになる対策をご紹介します。
【目次】
1.忘れ物が多いADHD小学生の息子の筆箱はいつもスカスカ⁉
2.忘れ物が多いのはADHD・発達障害の特性!
3.効果的な忘れ物対策!5つのアイデア
1.忘れ物が多いADHD小学生の息子の筆箱はいつもスカスカ⁉
私は注意欠陥多動性障害(ADHD)傾向の長男とグレーゾーンの次男を育てるワーキングマザーです。
一般的に小学生低学年の男児は忘れ物が目立ちますが、ADHDタイプの子どもは、さらにずば抜けて忘れ物が多いです。
特に小学生になると、保育園や幼稚園時代と違って、毎日学校に持っていかなければならない・持ち帰ってくる持ちものが増えます。
例えば、こんなことありませんか?
「教科書とノートは準備していたけど、ドリル忘れている!」
「タブレットや習字の道具を持っていくの忘れた!」
「連絡帳?書いてないよ!」
「宿題のプリントを持って帰ってきていない!」
などなど。
さらに、筆箱をあけてみるとスカスカ!鉛筆や消しゴムがないことも日常茶飯事です。
しかも子どもは無関心で鉛筆や消しゴムがなくなっていることなど伝えてはくれない…。
授業参観後の懇談会では、つかさず引き出しと棚のチェック!
出るわ出るわ!ハンカチや鉛筆やらぐちゃぐちゃなプリント。
しまいには上着2着も置いたままでした。
ママとしても「今日は忘れ物していないよね?」「ちゃんと持って帰ってきてね!」「授業をちゃんと受けられているのかな?」と心配になりますよね。

また、忘れ物が毎日続くと「また忘れたの!?」「何度言ったらわかるの!?」なんて強い口調でつい言いたくなってしまいますよね…
2.忘れ物が多いのはADHD・発達障害の特性!
実はこうした忘れ物の主な原因は、発達障害ADHDタイプにある「不注意」の特性によるものなのです。この特性が、忘れ物の多さに影響します。
不注意とは
●重要な用事でも期限を守れない
●物事を順序立てたり、やり遂げられない
●必要なものをなくす、忘れ物が多い
ママと一緒に登校前の準備をシッカリしても、登校後は、自分自身で持ち物の管理をしなければなりません。
しかし発達の「不注意」の特性を持つ子どもには、これがとても難しいことなのです。
子どもが、学校へ登校したら、やることがたくさんあります。
・下駄箱で靴をはき替え、教室に移動する
・ランドセルを開け、教科書やノートは机の中へ
・宿題は提出用の箱へ
また、授業が始まると、教科で使う教科書やノートや資料などを机から出したり、ロッカーに取りに行くなど、準備のための一連の行動が伴います。
これらに加えて、日直当番や給食当番があったり…。
特別な教材を購入する際には、集金袋の持ち帰りなどもあり、学校内での子どもの行動は、ママが想像している以上に複雑です。
こういった行動一つひとつに「不注意」の特性が作用し、教材を忘れる、連絡帳の書き忘れ、鉛筆・消しゴムの紛失、ノートなどの忘れ物が起きてしまいます。
また、朝家を出るときは寒かったのに、日中暖かかくなると上着を脱いでしまいそのまま学校に忘れてくることになるのです。
子どもによっては、「何を」「どんなときに」「どう使うべきか」を理解していない可能性もあります。
こういったことを踏まえて、忘れ物を防ぐ対策を考えてみましょう。
「忘れ物に気づいて、困れば、自然に学習するのでは?」と思うママもいるかもしれません。
でも、発達障害・ADHD傾向の子どもはそうもいかないのです!
なぜなら、発達障害・ADHD傾向の特性を持つ子どもは、忘れ物だけでなく日常のあらゆる状況で、困りごとを抱えています。

自分自身で困りごとを改善する余裕はないのです。
3.効果的な忘れ物対策!5つのアイデア
そこでママが、子どものの困りごとにいち早く気づいて、1日でも早く、1つでも多くの困りごとを減らしてあげる必要がありますね!
そのために、今日からできる忘れ物対策として5つのアイデアをご紹介いたします。是非参考にしてくださいね。
◆①持ち物リストを玄関ドアにかけておく
発達障害の特性のある子どもは、目で見た情報の方が理解しやすい、という特徴があります。
「玄関のリストを見てね」と声かけをプラスすると、忘れ物を減らす効果が上がりますよ。
◆②ファイルケースを使って、教科ごとに棚を仕切る
発達障害の子どもは、整理整頓が苦手な子どもが多いです。
教科ごとに場所を区切ってあげると、出し入れがしやすくなります。子どもも、自分で整理整頓できる力がつきます。
◆③学校で使う「お道具箱」を透明タイプにチェンジ
お道具箱が不透明で、中身の見えないタイプだと「物が見えない=物の存在を忘れる」ことになります。
学校の先生と相談して、可能であれば中身の見える、透明タイプのお道具箱に変えてみましょう。
◆④教科ごとに色や目印をして区別化!
教科ごとに色を決めて、教科書やノート、時間割表にマスキングテープやペンで印をつけます。
国語なら赤、算数なら青…という風に決めておくと、文字が読みづらいお子さんにも分かりやすいです。
また、発達障害・ADHDタイプの子どもに多いのが、文字より写真の方が記憶に残りやすいという特性があります。
写真と実物を見比べてそろえると、絵合わせのような感覚で準備ができます。
◆⑤プリントや宿題専用のクリアファイルを使う
プリントや宿題を、授業で使う教科書やノートと一緒に入れておくと、すぐに見つけることができずに、提出を忘れてしまいます。
専用のクリアファイルを用意し、すぐに見つけられるようにマスキングテープで目立たせたり、紐を通してすぐに取り出せるように工夫します。
子どもと一緒に作ると、持ち物管理の意識も高まります!
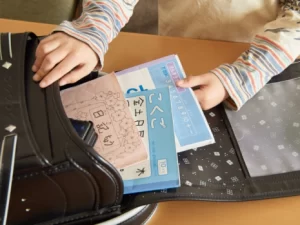
そして、ママのひと工夫した声かけがポイントになります!
必要な持ち物、当番などがあるときは、こまめに声かけをして、忘れていたことを思い出させてあげましょう。
例えば「今日の宿題は、漢字プリントだっけ~?」と宿題について、さりげなく思い出させてあげたり、
「明日は体育があります!何が必要でしょうか~?」とクイズ形式にして、子どもに答えてもらうなどです。
ここでは、ママがイライラしながら注意するような声かけはしないのが大切です!
子どもが楽しめるように、歌やリズムなどをまじえて声かけをするのもオススメです。
ただし、一度思い出しても、また忘れてしまうことがあります。それでも、忘れたことを責めずに根気強く穏やかに伝えましょう。
そして、鉛筆や消しゴムの予備は十分に用意し、筆箱の中身が足りなければ、補充してあげましょう。
物を無くさないようにしてもらいところですが、「消しゴムが無いよ!どうしよう!」という困り感を減らしてあげる方が先です。
また、体操服なども手に入る機会があれば、家用に予備を持っておくのも1つの対策ですね。
そして忘れ物をしなかった日はたくさん褒めてあげることが大切です!
褒めてあげることで、「忘れ物せずにできた!」を実感させて、子どもの自信をつけていってあげてくださいね。
いかがでしたか?
ADHDタイプの発達障害傾向の子どもの忘れ物は、ママにとって悩みの種ですよね。
しかし「忘れ物はしてしまうもの」とママが心の準備をして対策すれば、子どもの発達とともに、忘れ物も減っていきます。
できることから実践してみて、我が子に合う忘れ物対策を見つけていきましょう!
▼▼忘れものが多い子のワーキングメモリーを鍛える方法を知りたい方はこちら▼▼
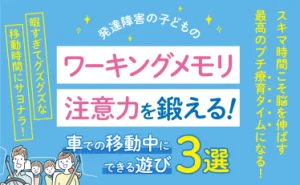
発達障害・ADHD傾向の子どもに関するお悩みの解決方法を他にもご紹介しています!
執筆者:渡辺 みゆき
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)





