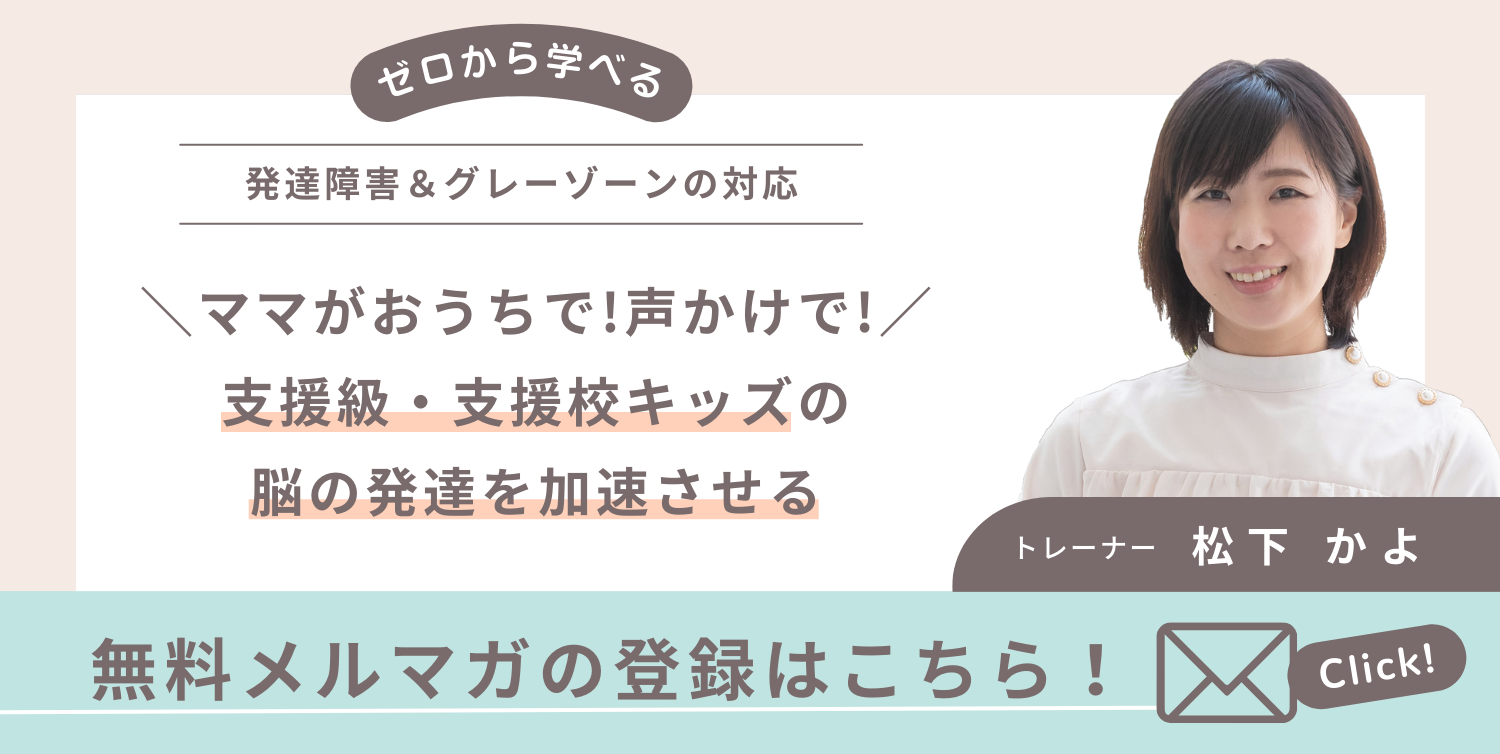普通学級でつまずき授業についていけないお子さんは、周囲に理解されにくく困難を抱えて自信を失いがちです。「努力不足」と思われがちですが、親が子どものペースに合わせたサポートをすることで自信を取り戻して本来の力を発揮できるようになります。
【目次】
1.授業についていけないと困っている子どもたち
2.普通学級でつまずく子どもの特徴と学校の現状
3.ママが一番のサポーター!お家でできるスキルアップ術
1. 授業についていけないと困っている子どもたち
「どうしてうちの子は普通学級の授業についていけないの?」と感じたことはありませんか?
何度教えてもなかなか覚えられない!
先生から「頑張ればできるよ」と言われても、子どもにとってハードルが高く、親としてもどうすればいいのか悩むことが多いでしょう。
もし、こうした状況に心当たりがあるなら、お子さんは学校生活に困難を抱えているかもしれません。
でも、大丈夫!
子どものペースに合わせたサポートがあれば、自信を取り戻して本来の力を発揮できるようになります。

・読音が苦手で文章をスムーズに読めない
・宿題に時間がかかる
・連絡帳の板書が写せていない
・先生の指示を理解できず忘れ物が多い
など、何も言わなくても自分ができないことを理解していると感じたことはありませんか?
子どもたちは親が思っている以上に、自分の「できないこと」に敏感です。
集団生活の中で周囲からは見過ごされがちですが、実は本人はとても困っているのです。
頑張っているのに報われず、「もっと頑張れ!」と言われるたびに「できない自分」を責めてしまう。
その結果、「どうせ頑張っても無理」と新しいことにチャレンジする意欲まで失われていきます。
本来はできるのに適切なサポートが受けられないためにどんどんできなくなっていくのはとても悲しいことです。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
3週間で癇癪が落ち着き
毎日が穏やかに過ごせるようになる!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.普通学級でつまずく子どもの特徴と学校の現状
普通級でつまずきやすい子どもたちは、日常的にさまざまな困難を抱えていることがあります。
「頑張ればできる」と言われても、実際には思うようにできない。
しかし、これは努力不足ではなく、そもそも子どもの脳の特性や情報処理の仕方に違いがあるからです。

例えば、一度にたくさんの情報を処理するのが苦手な子は、黒板の内容をノートに写すのに時間がかったり、先生の指示が理解できず指示通りに動けないことがあります。
感覚に特性がある子は、教室の音や光に敏感で、周囲の環境がストレスになってしまいます。
こうした子どもたちは、人一倍努力しているのですが、その頑張りが評価されることはほとんどありません。
「できない自分」を強く意識することで自信を失い、ますます勉強や学校生活がつらくなってしまうのです。

発達の特性があっても、学習の遅れが目立たない場合、「頑張ればできる」と誤解され、必要な支援を受けられないことがあります。
そのため、親が「明らかに困っている」と感じていても、学校側には理解されにくいのが現状です。
子ども自身も、周囲の子どもたちと比べて「自分はできない」と感じることが増え、学校生活に対する不安を募らせていきます。
情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!
”脳のクセ”を育て直す声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
3.ママが一番のサポーター!お家でできるスキルアップ術
普通級でつまずくお子さんが、自信を取り戻し、学校生活をスムーズに送るために、家庭でできるサポートがあります。
それは、できることから始めること。
学校の授業は集団指導が基本ですが、家庭では一人ひとりのペースに合わせた対応が可能です。
そのため、家でのサポートを工夫することで、学校での困りごとが減り、授業に対する不安を軽減することができるのです。

我が家の例をひとつご紹介します。
私のグレーゾーンの娘も小1で普通学級についていけなくなりました。
「学校に行きたくない!」といった娘はみんなより書くことが遅くて焦ったり、給食の牛乳パックを開けるのに手間取ったことなどを打ち明けてくれました。
そんな娘と私がやったことは、みんなと一緒のことをやってほしいという気持ちは抑えて、娘のできることからやること。
書くことが遅いことをサポートするために、子どもが楽しく取り組んているなぞり書きをしたり、好きな絵を写して描いたりしました。
すると娘は楽しく取り組むようになり絵も字も上手になり、自信を取り戻していきました。

真面目な親ほど、「どうしてできないの?」と悩み、子どもを何とか変えようとしがちです。
しかし、「まあ、いっか」と肩の力を抜くことも大切です。
みんなと同じことをできるようになること、学校に行くことがゴールではなく、子どもが安心して学び続ける環境を作ることが一番の目標です。
そのためには、親自身が「子どものできないこと」ばかりに注目せず、「できていること」に目を向けることが重要になります。
子どもが安心できる環境を作ることで、子どもが「自分ならできる」と思える経験を増やすことが、長い目で見たときに大切なのです。
無理に学校に合わせず、子どもにあった方法を一緒に考えていきましょう。
執筆者:松下かよ
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
(発達科学コミュニケーショントレーナー)