ADHDの子どもには「理解+柔軟さ+個別対応」がある学校がベスト。高校受験などで学校を選ぶときは単に偏差値や通学のしやすさだけでなく、子どもの「生きやすさ」「心の居場所」という視点で選ぶことがとても大切です。
【目次】
1.ADHD傾向の子どもの高校選びが大切なわけ
2.高校見学にたくさん行くメリットとは?
3.登校しぶり、勉強嫌いなADHD傾向の息子の高校選びに迷いました。
4.学校の他に「もう一つの場所」
1.ADHD傾向の子どもの高校選びが大切なわけ
注意欠陥多動性障害(ADHD)の子どもは、集中力が続きにくい、衝動的に動いてしまう、忘れ物が多い…といった特徴があります。
一方で、興味のあることには驚くほど集中する力や、独自の発想力、行動力も持っています。
ですからADHDキッズの高校選びは、単に成績や進学先のレベルではなく、その子が「安心して学べる環境」が整っているかどうかが何より重要です。
しかし、周囲の理解がない環境では「怒られる」「注意される」「自己肯定感が下がる」ことが増え、本来の力を発揮できなくなります。
本人の特性を理解し、サポートしてくれる学校であれば、長所を活かしながら成長することができます。
●担任の先生が特性理解に前向き
●学校全体でインクルーシブ教育を実施している
●支援員(サポートティーチャー)がいる
●保護者と連携を大切にしてくれる
こうした学校では、子どもも「自分はここにいていい」と感じられ、安心して通えるようになります。
子どもの「生きやすさ」「心の居場所」という視点で選ぶことがとても大切ですね。

2.高校見学にたくさん行くメリットとは?
まず高校見学に実際に足を運ぶことを提案します。パンフレットやサイトではわからない校舎の雰囲気や生徒・先生の様子を実際に感じ取れるからです。
そして、学習環境や部活動、通学時間など、子どもにとっての「合う・合わない」を母の目線で確認できます。
また、たくさん見学することで、「ここはよかった」「これはちょっと違うかも」と判断基準が明確になってきます。
それから、お子さんが見学に行けなくても保護者が一人でも学校を見学する効果もありますよ。
子どものために行動している姿勢が伝わりますし、子どもも「お母さんが色々調べてくれた」と安心します。
保護者が冷静な目で見られるから、子どもに客観的なアドバイスができます。

たくさんの見学を通して、「うちの子にはここが向いているかも」と思える学校に出会える可能性も高まりますよね。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
3週間で癇癪が落ち着き
毎日が穏やかに過ごせるようになる!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
3.登校しぶり、勉強嫌いなADHD傾向の息子の高校選びに迷いました。
我が家の息子は、中学3年間での欠席は20日程度で、登校しぶりもありました。
それでも少しずつ発達科学コミュニケーションで学んだスキルで早退や遅刻をしながら学校と向き合ってきました。
受験生になって高校選びに悩み、可能な限り高校見学に足を運ぶことにしました。
高校受験では、学力よりも「本人が行きたいと思える高校」を大切にしてもらいたいという想いで、中学2年生の夏からなんと10校もの高校見学へ!そのうち4校は「お代わり見学」もしました。
また、確約がもらえないだろうと思っていた私立高校でも個別面談をすると受け入れていただけました。
私は、息子に高校でやりたいことを見つけて行きたい学校を選んでほしいと思っていました。
たとえば、勉強があまり好きではなかったので、普通科ではなく調理師免許が取れる食育系や農業高校など、手に職をつけられる道がいいのではないかと考えていました。
しかし、驚いたのは、勉強が好きではないはずの息子が「大学に行って経営学を学びたい」と言い出したこと。
漠然とですが「社長になりたい」という夢とキックボクシングでプロライセンスを取得したいという夢を持ち始めたのです。

では、どのような視点でサポートをしながら高校を選んだのか次でお話しますね。
情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!
”脳のクセ”を育て直す声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
4.学校の他に「もう一つの場所」
息子は高校で何をやりたいかという視点では選べませんでした。高校でもキックボクシングに通いたいというスタンスだけ。
最終的に息子が選んだのは、なんと「行きたい高校」ではなく、「通っているキックボクシングジムに通える高校」。でした。
見学に行った10校のうちこの条件を満たせるのは、2校でした。1校目は、自宅から自転車で40分かかる公立高校、2校目は支援がある自転車で10分以内の私立高校でした。
私立高校は土曜日も学校があることに不満があり、公立高校は通学に時間がかかることに不安を抱えていました。
そこで、実際に自転車でどのくらいかかるのか受験前に試してみました。公立高校の大半は、土日の休みが確保されるので、疲れを取ったり、自分の時間を大切にできます。
今は、高校生活とジム通いの両立を考え、自転車で高校へ通学し、帰宅後は電車で夜のジム通いという生活スタイルに。学割定期も活用して、自分のペースで日々を過ごしています。
私立高校ほど公立高校は、学校の支援はありませんが、学校の他に自分の居場所(ジム)や目標(プロライセンスをとる)があることが、子どもが生きやすい環境づくりにつながります。
「発達の特性に支援のある学校にすべきだ」と決めつける人もいますが、本当の意味での“自立”って、自分に合った環境を自分で選び、折り合いをつけながら進んでいく力なのかもしれませんね。
親としては、「支援がなくて大丈夫かな」「困った時に誰か手を差し伸べてくれるだろうか」って、心配になりますが…。
しかし、学校の他に「もう一つの居場所」があることが、
●ストレスを発散する場所
●自信を持てる時間
●努力すればできる”という実感
を得られているのかもしれないと思っています。
母としては、やっぱり楽しい学校生活を送ってほしい。だからこそ、自分の意志で選んで、自分で決めてほしい。

ただ、正直なところ「高校に入ってもまた登校拒否になってしまうかもしれない」という不安は、今も心のどこかにあります。
でも、その不安は“今ここ”であれこれ心配しても仕方ない。実際にそうなったときに、そのときの息子に合わせて対応を考えればいい。
「これは私の人生ではなく、息子の人生。」
だからこそ、彼が選んだ道を信じて、私は一歩引いた場所から見守っていきたい。そう思えるようになりました。
子どもも成長しています。先回りな行動を(過干渉)をやめて、自立を促し困ったときに手を差し伸べられる親子関係でいたいですよね。
▼▼癇癪や暴力がおさまると兄弟喧嘩もグッと減りますよ!こちらもどうぞ▼▼
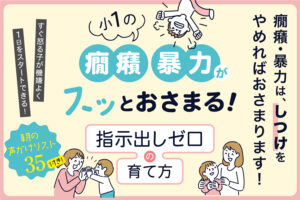
発達凸凹中学生の子育でのヒントをお伝えしています。
執筆者:神田久美子
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)







