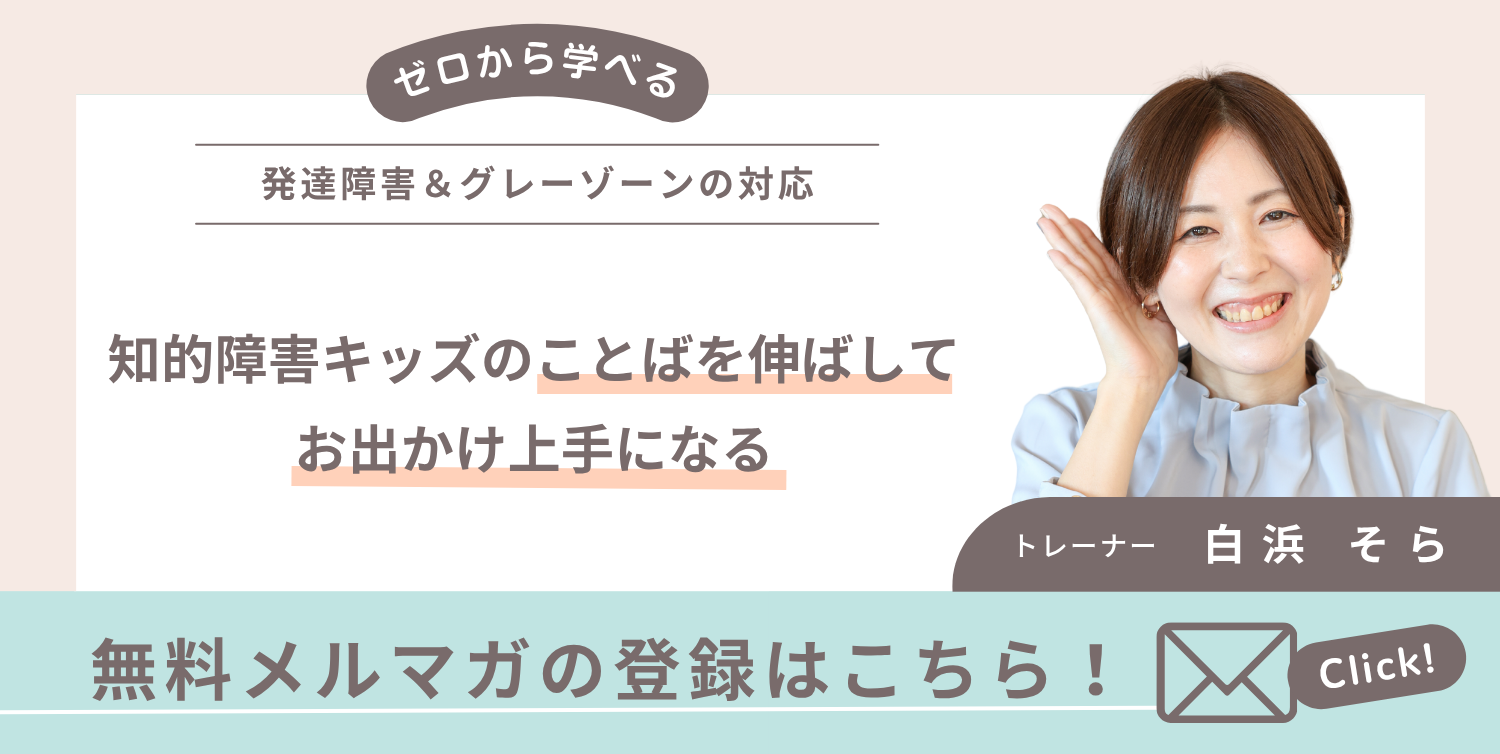模倣しない子に、無理に真似をさせる必要はありません。発語が遅い・模倣しない子も、「おうむ返し」の関わり方で言葉は伸びます。ママが声やしぐさを真似して返すことで、「わかってもらえた」という安心感が育ち、話したい気持ちが生まれます。
【目次】
1.模倣しない子が話さないのは「安心して真似できる準備」がまだだから
2.ママが真似すると子どもの脳が安心して発語が育ちます!
3.発語が遅かった娘が笑顔で話し出したストーリー
4.今日からできる!おうむ返しで言葉を引き出す関わり方
1.模倣しない子が話さないのは「安心して真似できる準備」がまだだから
模倣しない子が話さないからといって、「話す力がない」「できない」わけではありません。
多くの場合、模倣が起きていないのは、安心してやりとりできる準備がまだ整っていないだけです。
自閉スペクトラム症(ASD)や知的障害のあるわが子に、
「言葉を増やしたいけれど、どう関わったらいいかわからない…」
「“あけて”って言わせようとしても、全然言ってくれない…」
そんなふうに悩んでるママは少なくありません。
実は、発語が遅い・模倣しないと感じるお子さんほど、「子どもに真似をさせる」よりも、「ママが子どもの声やしぐさを真似して返す関わり」が大切になります。
なぜなら、言葉は「教えられたから出る」のではなく、安心できる人とのやりとりの中で育っていくものだからです。
◆①言葉の発達のステップ
子どもの言葉の発達には、順序があります。
・0歳では「あー」「うー」などの喃語
・1歳前後には「ママ」「ブーブー」などの一語文
・2歳前後になると「ママきた」「これちょうだい」などの二語文
・3歳以降では会話や質問が増え、語彙も広がっていきます。
このスピードには大きな個人差があります。
「まだ話さない=遅れている」ではなく、今は言葉を育てる準備をしている段階なのです。
発語が遅れる背景には、いくつかの要因が関係していることもあります。
・発達のペースがゆっくりしている(個人差)
・言葉を理解する力がまだ育っていない
・音や言葉を聞く機会が少ない
・おとなしい・慎重などの性格傾向
・聴覚や発達の特性による影響
お子さんによって、話す準備が整うタイミングはそれぞれ違います。
だからこそ、無理に言葉を引き出そうとせず、安心してやりとりできる環境を整えることが大切です。
◆②発語が遅い子が共通して見せるサイン
発語がゆっくりな子や模倣が少ない子には、次のような特徴が見られることがあります。
・声をかけても反応が薄い
・音や言葉を聞いてもすぐに真似しない
・視線が合いにくく、人よりも物への興味が強い
・言葉よりも動きや音で気持ちを伝えようとする
こうした様子があっても、「話す力がない」わけではありません。
今は「聞く」「理解する」「真似する」といった、話すための土台が育っている途中です。

多くのママが「もっと話しかけなきゃ」と努力されていますが、言葉を教えようとするほど、子どもの脳が緊張してしまうこともあります。
大切なのは、「ママが自分をわかってくれた」と感じる体験です。
次の章では、ママが子どもの真似をすることで、脳がどう変わり、発語が育っていくのか、具体的に解説します。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
指示出しゼロの子育てで
たった3週間で癇癪が着く!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.ママが真似すると子どもの脳が安心して発語が育ちます!
言葉の発達の始まりは「教える」ことよりも、ママが子どもを真似することから始まります。
「え?真似するのは子どもじゃないの?」と驚くかもしれません。
しかし、子どもは安心できる人、好きな人のことはよく観察しようとするものです。
だからこそ、ママが子どもの声やしぐさを真似することで、子どもは「ママがわかってくれた!」と感じて安心します。
子どもはママへの興味を深め、「ママと関わりたい」「ママの言葉を聞きたい」という気持ちが育っていきます。

興味のない言葉を教えられるよりも、自分の声や動きをママが返してくれる方が、子どもにとってずっと楽しい体験なのです。
「ママも同じこと言ってる!」「ママがわかってくれた!」と感じたとき、子どもは笑顔になります。
その「楽しい」という気持ちが、安心につながり、言葉を話したいという意欲を育てていくのです。
次では、発語が遅かった娘が笑顔で話し出すようになった、わが家の実践をお伝えします。
3.発語が遅かった娘が笑顔で話し出したストーリー
わが家の知的障害と自閉スペクトラム症のある娘は、単語は出てきたものの「おかあちゃん」「せんせー」など数個だけでした。
言えていた単語が消えてしまったり、一度だけ言えた言葉が次には出てこないこともあり、なかなか単語が増えませんでした。
私が「りんごだね〜」「バナナだね〜」と声をかけて真似させようとしても、娘は見ているだけで、なかなか口に出すことができなかったのです。

私は「どうしたら言える言葉が増えるんだろう…」と悩んでいました。
そんな時に出会ったのが、『子どもに真似をさせる』のではなく、『ママが子どもの真似をする』という関わり方でした。
最初は半信半疑でしたが、娘が「おーでー(おいで)」「こっち」と言っている時に、私も「おいで〜だね!」「こっちだね!」と真似して返してみました。
くるくる回っている時には、一緒にくるくる回ってみたりもしました。
すると、娘は笑顔でもう一度「こっち!」と教えてくれたり、私が「妹ちゃんどこだろう〜」と言うと、「妹ちゃん?」と真似して返してくれたり…。
少しずつ、言葉が定着する場面が増えていったのです。
この経験を通して、「ことばを教える」よりも、「気持ちが通じ合う」経験の方が、子どもの中に「話したい気持ち」を育ててくれるのだと確信しました。
では、実際にどうやって子どもの真似をすればいいのでしょうか?次では、実際におうむ返しで言葉を引き出す関わり方について紹介します。
毎日の声かけで“脳のクセ”は変えられる!
子どもが持つ力を発揮できるようになる
4ステップの声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
4.今日からできる!おうむ返しで言葉を引き出す関わり方
発語が遅い・模倣しない子には、ママが「教える人」ではなく、「言葉を楽しむ相手」になること。それが、発語を伸ばす一番の近道です。
ここでは、毎日の生活の中でできる「おうむ返し」の関わり方を2つ紹介します。
◆①子どもの「声」や「しぐさ」をそのまま返す
お子さんが「あうあうあう」と喃語を言ったり、「バナー(バナナ)」「おかー」など少し不明瞭な発音をしていたら、ママも「バナーだね〜」「おかーだね〜」とそのまま返してあげましょう。
もしも「今、言えたかも?」と思う瞬間があったら、すぐにおうむ返しで受け止めてあげてください。
正しい発音に直す必要はありません。
「ママが聞いてくれた!」という経験が、言葉を話す自信と安心を育てていきます。
◆②曖昧でも受け止めて、やりとりを楽しむ
「何を言っているんだろう?」と思う声でも、ママが「そうだね〜」「そう言いたかったのね」と笑顔で返してあげましょう。
うまく言えたかどうかよりも、「伝えようとしている気持ち」を受け取ることが大切です。
このやりとりの積み重ねが、「ママと通じ合えた!」という嬉しさになり、発語の土台を育てていきます。

ママのおうむ返しは、言葉の練習ではなく、心をつなぐやりとりです。
ママが子どもの声やしぐさを真似して返すことで、「ママと話すのって楽しい!」という気持ちが育ち、言葉は自然に増えていきますよ。
無料電子書籍でもっと詳しく学べます!
↓↓
模倣しない子のことばの力を、ママの関わりと笑顔で伸ばすヒントを動画でご紹介!
模倣しない子についてのよくある質問(FAQ)
Q1:模倣しない子の言葉は、これから増えていきますか?
A1:結論、言葉は「脳が育つ関わり」で伸びていきます。言葉の遅れは能力の問題ではなく、安心や「うれしい!」が足りていないだけの場合も多いもの。
詳しくは おうち療育で言葉を増やすママのほめ方 を参照。
Q2:模倣しない子は、どうしたら自分から言葉で伝えられるようになりますか?
A2:「伝わった!」という成功体験を積み重ねることが大切です。言葉は教え込むよりも、ママに思いが伝わった経験から伸びていきます。詳しくは 言葉が遅い子の言葉が伸びる!『おうち療育』2ステップ を参照。
Q3:話しかけても無視されるのは、言葉がわからないからですか?
A3:声そのものに気づけていない状態です。 自閉症の子は、耳よりも目から入る情報を優先して処理するため、背後からの声や長い声かけが届かないことがあります。目の前に行き、短い言葉で伝えることで、反応が変わる場合があります。
具体的な関わり方は 話しかけても無視!?3歳自閉症児がママの声かけに応えるコツ にまとめています。
脳を育てて「話したい!」を引き出す。ことばが伸びるおうち療育を発信しています!
執筆者:白浜 そら
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
(発達科学コミュニケーショントレーナー)