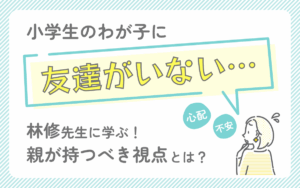クラスで浮いている、友達ができない、そんなわが子を見ると不安になりますよね。けれど「協調性がない=障害」ではなく、自分らしさを磨いているサイン。この記事では、その理由と家庭でできるサポート法を紹介します。
【目次】
1.協調性がないのは障害?協調性がない子の特徴
2.「クラスで浮いている」「友達ができない」理由は?
3.協調性がないのは天才!才能を伸ばすおうちサポート法
4.友達に興味がなく一匹狼だった娘のその後
1.協調性がないのは障害?協調性がない子の特徴
「クラスで浮いている」「友達ができない」と感じるわが子を見ると、ママとしては心配になりますよね。
ですが、協調性がない=障害というわけではありません。
協調性とは、考えが違う人の意見も尊重し、同じ目標に向かって協力して行動できる力のこと。
協調性は段階を経て育つ力で、決して“性格が悪い”わけでも“障害”でもないのです。

たとえばこんな特徴が見られる子は、「協調性が育つ途中段階」にあることが多いです。
・自分の興味を優先してマイペースに行動する
・団体行動より一人遊びが好き
・相手に合わせるより、自分のペースを崩したくない
・気持ちの切り替えが苦手
わが家の娘もそうでした。
保育園ではブロックや絵本など、その時の「やりたいこと」を優先。特定の友達を作らず、ひとりで黙々と取り組む時間が好きでした。
小学校に入っても休み時間は読書に夢中で、「おにごっこしよう」と誘われても「邪魔された」と感じてしまうことも。
そんな姿に「協調性がないのでは?」と不安を感じたこともありますが、今思えば娘は「自分の世界」を大切にできる子だったのです。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
3週間で癇癪が落ち着き
毎日が穏やかに過ごせるようになる!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.「クラスで浮いている」「友達ができない」理由は?
協調性は“生まれつき備わっている力”ではなく、発達の段階を踏んで育つ力です。
たとえば幼児期には、
①一人遊び(自分の世界で没頭)
↓
②並行遊び(同じ空間にいても関わらない)
↓
③傍観行動(他の子の様子を見て学ぶ)
↓
④連合遊び(一緒に遊ぶけれど、目的はそれぞれ)
↓
⑤協同遊び(同じ目標を協力して達成)
という順序で社会性が育ちます。
この流れを経て、ようやく「相手の気持ちを考えて行動する=協調性」が芽生えます。

そして小学生になると、「相手の意見を聞いて調整する」「場の空気を読む」といった高次な協調性が育ち始めます。
つまり“今はまだその途中段階”であることも多いのです。
また、協調性の形は一つではありません。
・誰とでも仲良くでき、みんなをまとめるリーダータイプ
・少人数で協力しながら実行できるタイプ
・一人で集中してチームに貢献するタイプ
このように、ひとりひとりタイプが違うのです。
「みんなと同じように行動しない=協調性がない」と決めつけるのはもったいないですね。
友達ができない子どもは問題?悩むママに手にいれてほしい視点をご紹介しています▼▼
クラスで浮いてる小学生の社会性の育て方が3ステップでわかります▼▼
情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!
”脳のクセ”を育て直す声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
3.協調性がないのは天才!才能を伸ばすおうちサポート法
協調性が未熟に見える子は、「なぜ?」「どうして?」という探究心や好奇心が人一倍強いことが多いです。
人に合わせるよりも「自分の好き」を大事にできる力が強いからこそ、ひとり時間を大切にしているのです。
この特性を伸ばすには、まず「好きなことをとことん追求できる環境」を整えましょう。

少々常識から外れていても、「そう思ったんだね」「おもしろい発想だね」と親が受け止めることが、個性を潰さず才能を伸ばす第一歩。
誰かを傷つける行動でない限り、「どうしたら実現できるかな?」と一緒に考えてみてください。
夢中で取り組む経験は、集中力や自己効力感を高め、他者との共同活動への土台になります。
さらに、協調性の芽を育てるには、ママとの1対1の会話がいちばんの近道です。
「伝わった!」「わかってもらえた!」という安心体験の積み重ねが、「相手の話も聞いてみよう」という気持ちを生み、他者への関心につながっていきます。
コツは、子どもの好きなことを話題にすること。
「へぇ、どうやって作るの?」「それって何が面白いの?」と質問し、 “話して伝える”“聞いてもらえる”という小さな成功を重ねていきましょう。
協調性がないと感じる子の才能を育てる関わり方がわかります▼▼
4.友達に興味がなく一匹狼だった娘のその後
協調性がないように見えたわが家の娘も、4年生の冬ごろから少しずつ変わってきました。
「○○ちゃんってゲームが上手なんだよね」と、好きなゲームをきっかけに、自分の世界から外の世界に興味が向いていきました。

自分とは違う考え方をする友達との会話が「楽しくて仕方がない!」という雰囲気でした。
ある時、友達2人の間でいざこざがあり間に立たされた時は、「私はひとりでも楽しめるタイプだから、どちらとも距離をとる」という選択をしていました。
結局先生のサポートもあり、また元の3人友達に戻ることができましたが“みんなと仲良く”を無理に目指さなくても、自分のペースで人と関わる力が育っていたのです。
協調性がないように見える子は、周りに合わせるよりも“自分を知る”ことに一生懸命な時期。
それは人と心地よく関わるための大切な準備期間です。
ママが「あなたはあなたでいい」と信じてあげることで、子どもは安心して他者と関わる勇気を育てていきます。
焦らず見守るまなざしが、自分軸を失わずに人と関わる力を持った人へ育てていくのです。
友達ができない小学生が心配になったら、することはコレ!▼▼
よくある質問Q&A:協調性がないままだとどうなるの?
Q1.協調性がないまま大人になると困る?
A.困る場面もありますが、それは「自分の気持ちを伝えるスキル」が未熟な場合です。自分の考えを整理して相手に伝える力と、相手の立場を理解する力が育てば、問題にはなりません。むしろ、他人に流されずに自分の意見を持てる強みとして活かせます。
Q2.協調性がない子は社会に出てやっていける?
A.はい、大丈夫です。最近の社会では「個性」「創造性」「論理的思考」がより重視されるようになっています。小学生のうちは、「自分の考えを安心して話せる」「好きなことに集中できる」経験を積むことが、将来の自立的なコミュニケーション力の土台になります。
Q3.協調性を育てるには何から始めればいい?
A.まずは家庭の中で「会話のキャッチボール」を増やすことから。 子どもが話しているときは、最後まで聞く・相づちをうつ・気持ちを言葉にして返す(例:「それは嬉しかったね」)など、 “共感される心地よさ”を体験させてあげましょう。 この安心感が、外の世界で他人と関わる勇気につながります。
子どもの困りごとが次々に出てきて困っているママへ。根本対応がわかります!
執筆者:本田ひかり
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)