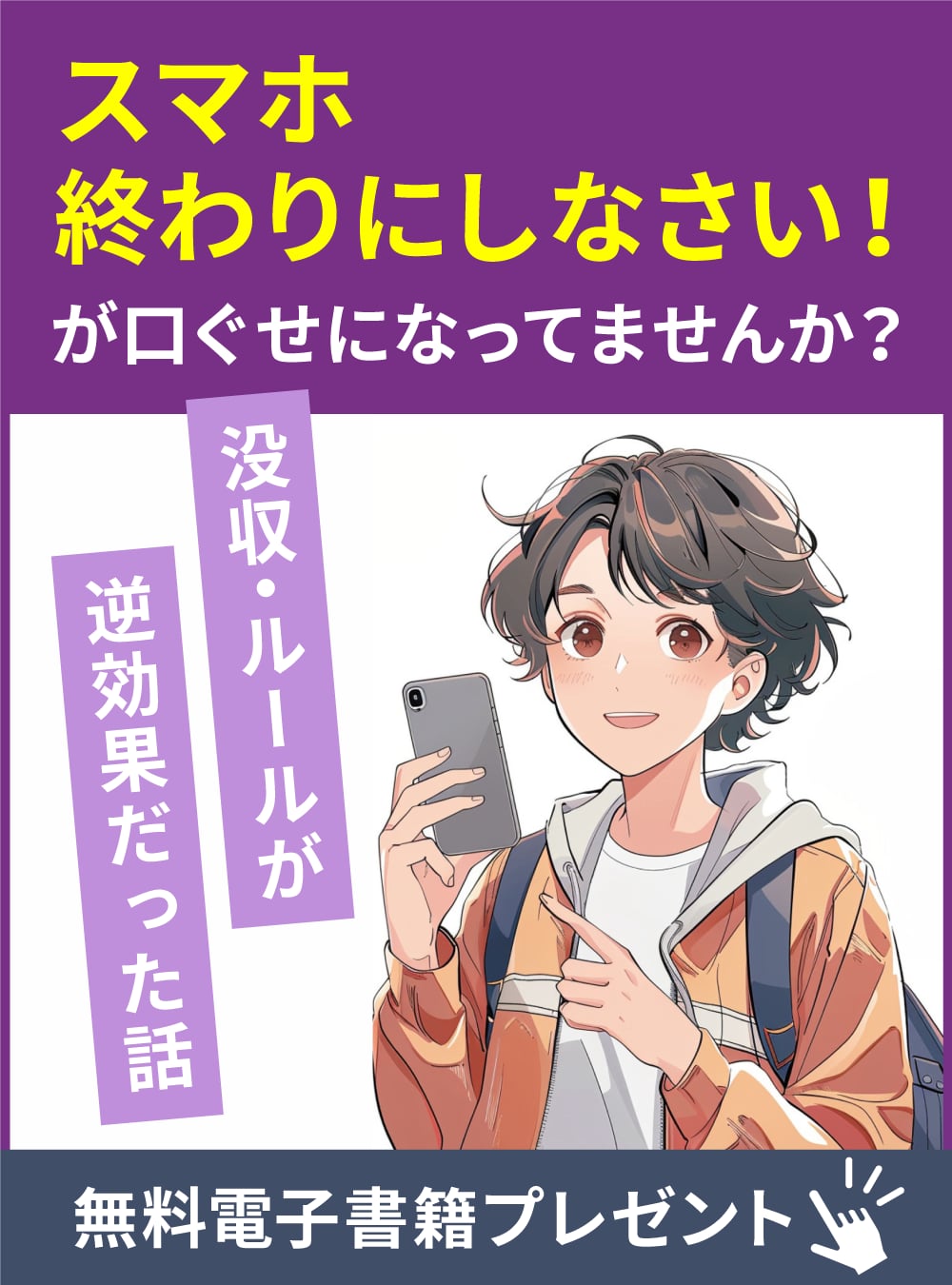不登校の子どもが外に出られない理由は、甘えではなく「脳が外は危険」と判断してしまうためです。まずは家の中で安心できる体験を増やし、好きなことを一緒に楽しむことで、「行ってみたい」という前向きな気持ちが自然に生まれていきます。
【目次】
1.不登校になってから人の視線が気になり外出できなくなった娘
2.不登校の子どもが外出できない理由は?単なるわがまま?
3.好きをきっかけに、親子の時間が動き出した!
4.親子で楽しむ「推し活」が、外出の第一歩に
①STEP1:家の中で好きなことを共有する時間をつくる
②STEP2:安心して外出できる環境を整える
③STEP3:親自身が楽しむことへの罪悪感を捨てる
1.不登校になってから人の視線が気になり外出できなくなった娘
子どもが不登校になり、家から出ようとせずに毎日ダラダラしていることに不安を感じていませんか?
我が家の娘は、小学校4年生の2学期から完全に不登校になり、毎日家の中で過ごすようになりました。テレビやYouTube、ゲームが日課。
外出しても、人の視線を気にすると体がこわばり、「もう帰りたい」とすぐ帰宅をしていました。
私も、娘を置いて出かけることに罪悪感があり、気がつけば、家と職場の往復だけ。心がどんどん疲れていきました。

そんなある日、娘が夢中で見ているドラマに気づきました。
「このドラマ面白いの?」と聞くと、ストーリーも好きだけど、その俳優さんのファンになったようでした。
無気力だった娘の中で、「好き」が動き出した瞬間でした。
この記事では、外に出られなかった娘と罪悪感に縛られていた私が、親子で「推し活」を楽しみ外出できるようになった3ステップをご紹介します。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
指示出しゼロの子育てで
たった3週間で癇癪が着く!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.不登校の子どもが外出できない理由は?単なるわがまま?
娘が外に出られなかったのは、「行きたくない」わけでも「わがまま」でもありません。それには脳のしくみが関係しています。
◆①感覚が敏感で疲れやすいタイプ
人混みや大きな音、光やにおいなど私たちが何気なく感じる刺激が、敏感な子どもには強すぎることがあります。
こうした刺激を感じると、脳の中の「警報装置(偏桃体)」がすぐに反応してしまいます。
危ないかもと感じると、体は緊張し、心も落ち着かなくなります。 娘の場合は、この反応がとても強く出ていました。
また、外出先で疲れる体験が続くと、脳が「外=しんどい場所」と記憶してしまいます。
さらに、「外に出さなきゃ」という親の不安も敏感に感じ取り、そのプレッシャーがストレスになっていることもあります。
◆②人が怖い・不安を感じやすいタイプ
友だちや周りの人からどう思われるのかが気になる、失敗したら笑われるかもと感じる。
こうした対人不安は、過去の嫌な経験を思い出しやすく、「また同じことが起きるかも」と脳が危険信号を出してしまう反応です。
つまり、行きたくないと人を避けるのは、自分を守ろうとしている脳の反応なのです。

◆③想像力が豊かで不安を先に感じるタイプ
発達障害や発達障害グレーゾーンの子は過去の失敗や緊張した経験などのネガティブな記憶が残りやすく、未来にも不安を重ねてしまうのです。
もし道に迷ったら?誰かに話しかけられたら?と、まだ起きていない不安をリアルに想像してしまいます。
つまり、外出を嫌がるのは甘えではなく、「外は安心できない場所」と脳が判断しているだけだったのです。
焦って外に出そうとするより、まずは家の中で安心を取り戻すことが大切です。
私も、娘をどうにか外へ連れ出そうとしていた時期がありましたが、うまくいかないたびに、私も娘もますます自信をなくしていきました。
そんな時に気づいたのが、外に出ることよりも、好きなことを一緒に楽しむことでした。それが、娘の「行ってみたい」という気持ちを引き出すカギになったのです。
3.好きをきっかけに、親子の時間が動き出した
不登校になった娘は、家でドラマや動画ばかり見ていました。 でも、ある俳優さんを好きになり、所属するグループのファンになってから、表情が変わりました。
その俳優さんとそのグループの出演番組や曲を一緒に楽しむうちに、「外に出さなきゃ」と焦っていた私の気持ちが、ふっと軽くなりました。

娘が笑顔で話す時間が増え、私も心から笑えるようになりました。
私が本当にやるべきだったのは、娘を頑張らせることではなく、“楽しむ力”を取り戻してもらうことだったのです。
次の章では、不登校になり、外出できなかった娘が少しずつ前に進めるようになった、親子でできる3つのステップをご紹介します。
4.親子で楽しむ「推し活」が、外出の第一歩に
外出できなかった娘と私が変わるきっかけになったのは、一緒に好きなことを楽しむ時間を持ったことでした。
ここからは、わが家で実践した3つのステップをご紹介します。
◆①STEP1:家の中で好きなことを共有する時間をつくる
外に出られない時期は、無理に外に出そうとせず、家の中でできる楽しい体験を増やしました。
・娘が好きな俳優さんが出ているドラマを一緒に見る
・所属するグループの冠番組をリアルタイムで一緒に見て、そのあと録画で見返す
・ライブDVD、MV鑑賞会
家の中に笑顔が増えると、自然と安心できる空気が生まれました。
焦って外に連れ出すよりも、まずは「家を安心基地にすること」が大切です。
◆②STEP2:安心して外出できる環境を整える
少しずつ気持ちが安定してきたころ、推しの映画が公開されることになりました。
聴覚過敏が出ていた娘には、大きな音がする映画館は正直ハードルが高いだろうと感じていました。
そこで私は、
・行き慣れた映画館
・平日朝のすいている時間
・大きな音が苦手な娘のために、後方で周りに人が少ない席
を選び、安心して挑戦できるように準備しました。
結果、最後まで楽しんで映画を観ることができました。この「行けた!」「楽しかった!」という成功体験が、次の外出への自信につながりました。

◆③STEP3:親自身が楽しむことへの罪悪感を捨てる
以前の私は、自分だけ楽しむなんて…と罪悪感を感じていましたが、娘と一緒に推し活をするうちに私に変化が生まれたのです。
気づけば「一緒に楽しむ」つもりが、私の方がどんどん夢中になっていました。
ファンクラブに入り、グッズを集めたり、SNSで情報をチェックしたりして、娘と共有していきました。
私が全力で推し活を楽しむことを自分自身に許したことで、娘の中でも楽しむ力が育ち始めました。
娘は「楽しむことは恥ずかしいことじゃない」と感じるようになりました。
その結果、娘は推しのためなら外出もためらわなくなりました。
人混みでも落ち着いて過ごせるようになり、聴覚過敏も少しずつ和らいでいきました。
今では、外出が怖かった娘が、自分から「ライブに行きたい」「聖地巡礼に行きたい」と話すようになりました。
自分で夢を描き、その実現を考えられるようになったのです。
子どもは、親の表情や感情から安心を感じ取ります。
親が笑顔で夢中になっていると、子どもの脳も「安心モード」になります。
その結果、子どもは少しずつ自分の世界を広げ始めます。
いかがでしたか?
外に出すよりも、まずは心をひらくことから。
子どもの行動は、安心の中で育っていきます。
親が笑顔で楽しむ姿こそ、子どもにとっての安心基地であり、「自分も大丈夫」と思える原点になります。
だから、どうか今日も、ママが自分を笑顔にしてあげてくださいね。
その笑顔が、きっと子どもの行動を後押ししてくれます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 不登校の子どもが外出できないのはなぜですか?
脳の「警戒モード(偏桃体)」が強く働き、人混みや音、視線などの刺激を危険と感じてしまうためです。甘えではなく、脳の反応によるものです。
Q2. 無理に外へ連れ出さないほうがいいですか?
はい。無理に外へ出すと「外=つらい場所」という記憶が強くなります。まずは家の中で安心しながら楽しい時間を増やすことが、長い目で見ると一番の近道です。
Q3. どうすれば外出できるようになりますか?
家の中で好きなことを共有する → 安心できる外出環境を整える → 親自身も楽しむことを許す、という3つのコツで、自然と「行ってみたい」という意欲が育ちます。
もっと「安心の中で子どもが動き出すヒント」を知りたい方へ。
外に出られなかった子が少しずつ前に進めた理由を、メルマガで詳しくお届けします。
外に出られなかった子が少しずつ前に進めた理由を、メルマガで詳しくお届けします。
執筆者:有須 みさと
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)