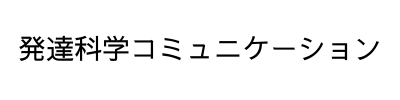ギフテッドの子どもたちは 「特異な才能」 を持っている一方で、「環境や関わり方次第で、その才能が潰れてしまう」 ことがあります。どんなことが原因になるのか、一つずつ見ていきましょう。
1.環境だけじゃ守れない!才能を潰しかねない5つの落とし穴
ギフテッドの子どもたちは、生まれながらにして強い好奇心や高い知的能力を持っています。
けど、その才能は、“正しい関わり”がなければ発揮されないという大きな特徴もあるのです。
いくら教材や体験を与えても、日々の関わり方次第で才能が眠ったままになることも…。
特に、次のような関わりや環境は要注意です。
① 「普通」を押しつける関わり
→ 好奇心や発想力を抑えられ、「自分は変?」と自信をなくします。
② 過度なプレッシャー
→ 「失敗が怖い」「やるなら完璧でないと」と挑戦を避けるようになります。
③ 感情を受け止めてもらえない環境
→ 「わかってもらえない…」と心を閉ざし、自分の感情を表に出さなくなります。
④ 退屈を強いられる日々
→ 学ぶ意欲を失い、「やる意味ある?」と無気力になります。
⑤ 「ありのまま」を認めてもらえない関わり
→ 孤独感や自己否定が強くなり、才能を隠すようになってしまいます。

2.才能が伸びるカギは「環境+関わり方」
私も当初は「才能を伸ばすには“環境”が大事」と考えていました。
安心して学べる場所、自由に選べる教材、挑戦できる時間…これで十分だと思っていたのです。
生徒さんの中にも、小さな頃から、学びを深められるようにと学年を超えて学ぶ仕組みを活用していたママもいました。
けれども、最初は楽しそうに通っていた習い事に行かなくなり、自分を否定する言葉が増えた子が多かったんです。
それより大事だったのは、ママの「声かけ」だったのです。
✅ 子どもの気持ちを受け止める
✅ 小さな挑戦を見つけて肯定する
✅ 失敗を責めず、挑戦できたことを認め、次を応援する
こうした関わりを続けるうちに、息子も生徒さんのお子さんたちも言葉が変わっていきました。
「どうせできない…」が、「やってみようかな」に変わったのです。
もしかしてギフテッド?
チェックできます!
↓↓↓
3.「普通」に合わせようとして、才能を潰しかけた私の失敗
息子は、言語理解が非常に高く、好奇心のかたまりのような子でした。
でも小学校に上がると、集団行動を求められる中で、好奇心が旺盛なのが裏目に・・・。こんな言葉を繰り返し浴びるようになったのです。
「みんなと同じにしなさい」
「勝手に発言しないで」
そのたびに、息子は“自分らしさ”を少しずつ手放していきました。
気づけば、問題行動が増え、私も不安になり「普通でいて」と願うように…。
その結果──
✔ 自分をわかってもらえないと感じ、心を閉ざす
✔ 完璧でいなければと感じ、挑戦を避けるようになる
✔ 言葉にはできるのに、感情を表現できなくなる
本当は「才能を伸ばすための環境」だったはずのものが、
いつのまにか、息子を苦しめる環境になっていたのです。
けど──
私が関わり方を変え、「安心して自分らしくいられる」声かけを意識するようになってから、息子は少しずつ変わり始めました。
✨ 自分の「好き」を話すようになった
✨ 「やってみようかな」と挑戦する気持ちを持てるようになった
✨ 感情を言葉にして、人とつながろうとするようになった
才能は「環境」だけでは守れません。
けど、「関わり方」は今日からでも変えられる。
私たち大人の「今のひと言」で、ギフテッドの子どもの“その子らしさ”を守り、伸ばしていくことができるんです。

4.ママの声かけが“好き”や“やってみたい”を引き出すスイッチになるんです
「ギフテッドの才能を伸ばすには、環境が大事」
──それは、確かに正しいことです。
けど実は、どんな環境にいても、それを活かすのも、台無しにするのも、“関わる人の言葉”なのです。
だからこそ、特別なことをしなくても、
今日からできる関わり方を、少しずつ始めてみませんか?
🌱 子どもの気持ちを、そのまま受け止めてみる
🌱 「なんで?」ではなく、「そう思ったんだね」と返してみる
🌱 小さな挑戦にも、「やってみたね」と声をかけてみる
✨そのひと言ひと言が、
子どもの“好き”を守り、才能を育てる大切な種になるんです。
執筆者:発達科学コミュニケーショントレーナー 神山彰子
次にオススメする記事は、こちら▼