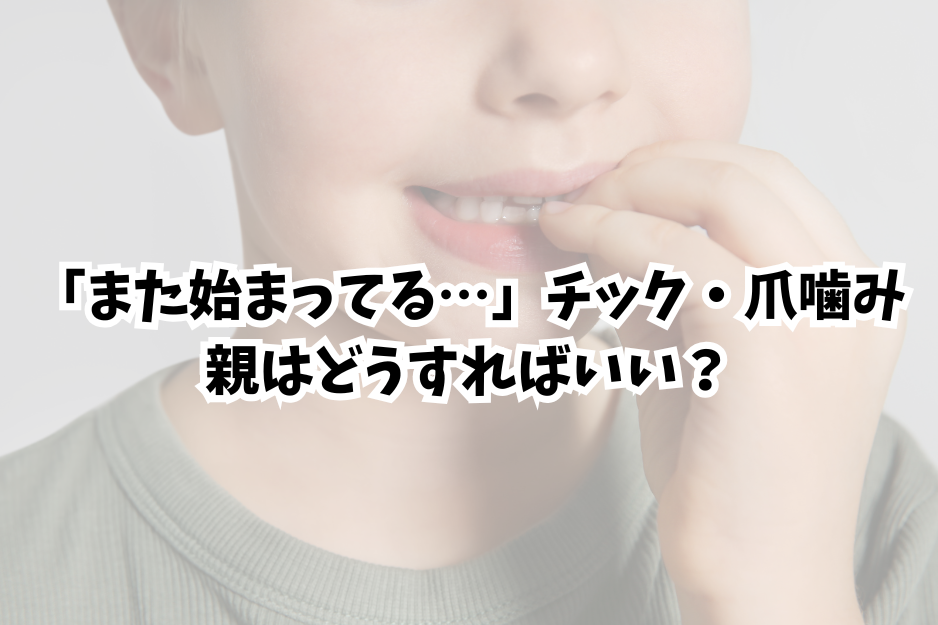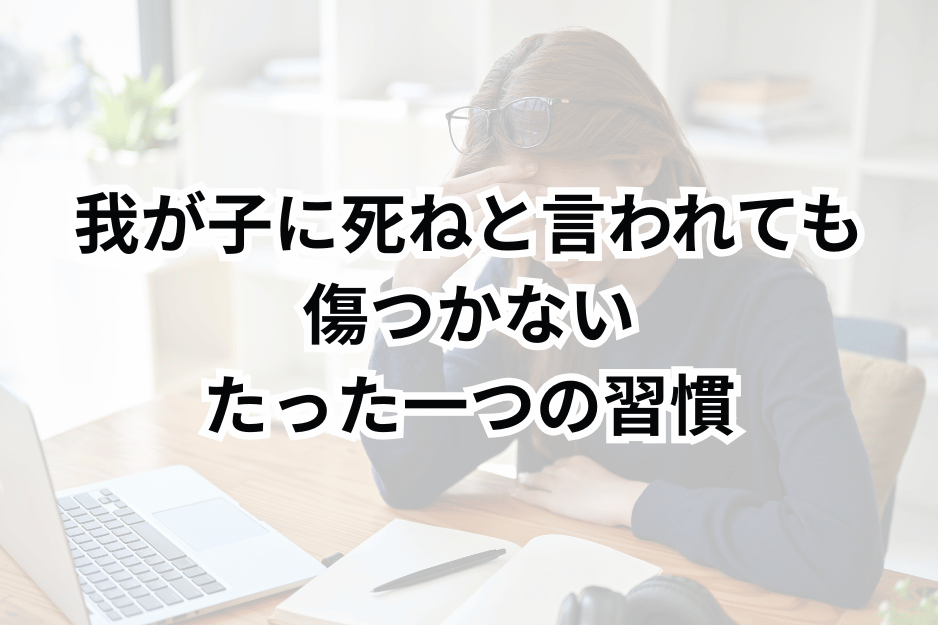その「また…」は、あなただけじゃありません。決して珍しいことではなく、中学生のお子さんからの相談も増えています。一度おさまったチックや爪噛み、再発すると不安になりますよね。原因と正しい対応、親ができる見守り方をわかりやすく解説します。
その「また…」は、あなただけじゃありません
一度は落ち着いたと思っていた、わが子のチックや爪噛み。
ふと気づくと、また始まっていた…。
「あれ?また爪を噛んでる…」
「目をピクピクさせてる…もしかしてまたチック?」
そんなとき、お母さんの頭に浮かぶのは、
-
「前より悪くなってるかも」
-
「私の関わり方、間違ったのかな…?」
-
「また癇癪が戻ってくるのかも…」
という、どうしても湧いてくる“あの不安”。
ですが、まず伝えたいのはこれです。
「ぶり返した=失敗」ではありません。
その行動は、お子さんからの“サイン”なんです。
実際にあったご相談から
あるお母さんから、こんなご相談をいただきました。

「以前ひどかった癇癪が落ち着き、家の空気が穏やかになったんです。
だけど最近、YouTubeを見ているときにずっと爪を噛むようになって…。
初めてじゃないぶん、“またか”と思ってしまって、ちょっとショックでした。」
チックや爪噛み、どうして“また出る”の?
それは、子どもが「無意識で不安や緊張を処理しようとしているサイン」です。
-
環境の変化(進学・クラス替え・習い事のストレス)
-
親子の距離感が近すぎたり、過干渉になっている
-
日常の中で“安心できる時間”が足りていない
こうした状況に置かれたとき、子どもは「言葉で伝える」代わりに、チックや爪噛みという行動で“心の調整”を始めます。
幼児期だけじゃない。中学生にも多い相談です
チックや爪噛みは「小さい子だけのもの」と思われがちですが、
実は、小学校高学年〜中学生の保護者からの相談も年々増えています。
-
「思春期で話しにくくなってきた」
-
「イライラして無言で爪を噛んでる」
-
「受験のストレスかもしれない」
そんな背景のあるご家庭がとても多いのです。
「自然に治る」のか?
多くの場合は成長とともに落ち着いていきます。
ただし、無理にやめさせようとしたり、親が過剰に反応してしまうとかえって長期化・悪化することもあります。
親ができる関わり方5つのポイント
気づいても「スルー」が基本
→ 「また噛んでる」「やめて!」はNG。注目されることで行動が強化されてしまいます。
怒らない、焦らない
→ 親の不安が伝わると、子どもも「何か悪いことをしてるのかも」と混乱します。
別の安心行動を提案する
→ 感触ボールを握る/ペン回し/お手玉など、無意識にできる代替行動を。
日常の“安心ルーティン”をつくる
→ 一緒に寝る時間・甘える時間・ふざける時間など、感情のクッションを。
言葉で整理できるようサポート
→ 「最近緊張することあった?」と心を言語化する練習を、日常の中で少しずつ。
その行動は、“戻ってきた”んじゃなく、“伝えてる”だけ
「また始まった…」
そう感じるときこそ、子どもが何かを伝えようとしているチャンスです。
あなたが気づいたこと自体が、すでに第一歩。
正しく対応することで、行動は必ず落ち着いていきます。