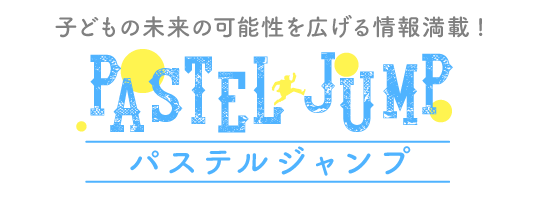1.学校から帰ったら寝ちゃう子|それって疲れすぎサイン?
2学期も中盤にさしかかり、学校に登校したもののヘトヘトに疲れて帰ってくる様子はありませんか?
帰ってくるなり寝転がったり、倒れ込んだり、おやつを食べてすぐ寝てしまったり。
そんな様子を見て、とても疲れているのはわかるけど、
「夕方寝たら夜寝れなくなるから寝ちゃだめだよ!」
「もーまた寝ちゃったの?」
「宿題やっちゃいなさいって言ったのに」
と翌日に影響することを心配して子どもを叱ってしまっていませんか?
もしかしたら、お子さんは敏感なタイプのお子さんかもしれません。
HSC(Highly Sensitive Child:人一倍敏感な子)の傾向のある子は、外からの刺激に敏感な傾向を持っています。
そのため、学校という大勢の子どもや先生が集まる空間はとても疲れやすいところです。
教室のザワザワした音
給食の匂い
大勢のクラスメイトの動き
などが、五感からたくさんの情報として自分の中に入ってくるんです。
定型発達の子どもでは、無意識に不必要な情報を取り込まないようにできるのですが、敏感な子たちはそれができずに大変です。
たくさんの情報が脳に入ってきて自分でコントロールできないのは、大人が思う以上にしんどいことなのです。
毎朝を迎えるのが怖かったママが
気持ちを前向きにする作戦を立てられるように!
▼「学校行きたくない」の詳しい対応をこちらから▼
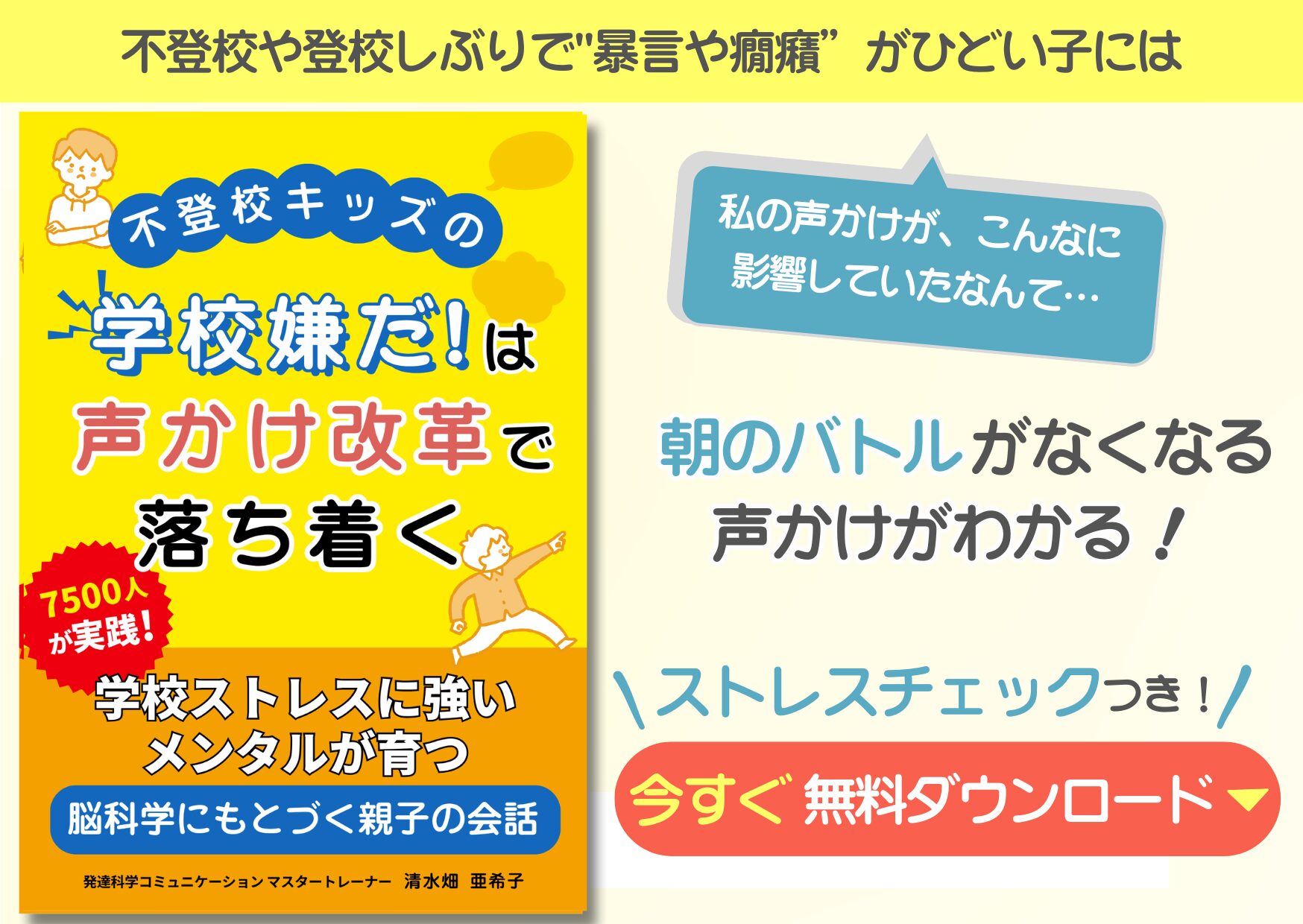
2.学校から帰るとパッタリ…眠り続けていた我が子
我が家の娘は、小学3、4年生の頃に登校しぶりがありました。
その頃、娘にとって学校は、
「みんなうるさい」
「給食食べたくない(嫌いな味があるから)」
「先生が怖い」
と言い、毎日ヘトヘトで帰ってくると、玄関を開けてすぐにランドセルを背負ったまま倒れ込む…というのが恒例となっていました。
そこからの私の役割は、
私は娘からランドセルを下ろし、
手を引っ張りながらなんとか寝倒れたままの娘をリビングに連れていく。
寝ころんだままおやつを食べさせたり、
好きなYou Tubeを寝転がりながら見れるようスマホを渡す!
(こんな状態では宿題などできるはずがないです)
寝転がりながら、そのまま寝てしまうこともあったり、そこで寝なくても夕飯を食べてお風呂に入るまでの間に寝てしまったり…
こちらのタイミングで起こすと…
眠くて機嫌が悪く、泣いたり怒ったり!
「うるさい!」
「なんでもっと早く起こしてくれないの!」
「明日テストあるのにもう無理だよ!」
「ママのせい!!」
こんな大癇癪が起きるので私は正直娘を起こしたくありませんでした。
寝ててくれていれば私の心は穏やかでいられるからです。
しっかり眠って疲れがとれれば、楽しく親子で一日あったことを会話したり、ゆっくりお風呂に入ったり、宿題をしたりと、夜の遅い時間に落ち着いてできました。
しかし、あまりに夕方に寝すぎると今度は夜に眠れないということも起きるようにもなりました。
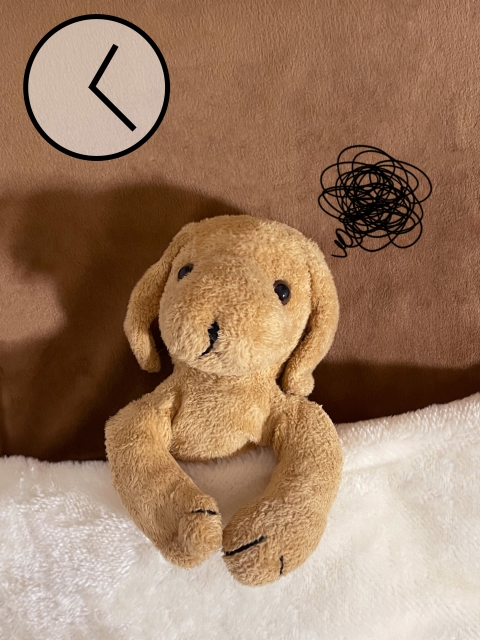
「眠れないなら無理しないで本とか読んでたら眠くなるよ〜」
と伝えても、繊細で不安が強い娘は「このまま朝まで眠れなかったらどうしよう〜」と心配しすぎて辛そうでした。
「もうどう声をかけたらいいのかわからない…」ママへ。
今のお子さんのストレス度合をチェックできる
【無料シート】はこちら
▶ 声かけチェックシートを見てみる
3.敏感で気持ちが疲れた学校後は体の疲れもピークに!
学校から帰るとクタクタなのに、先生からは「いつも何も問題ありませんよ」と言われているかもしれません。
そんなお子さんは、学校では200%くらいの気力で頑張って気を張っているんです。
いつも緊張状態なので、体の力も入ってしまい、リラックスして授業を聞いたり友達と遊んだりできていません。
だから、夕方には疲れがピークに達し、気力を消耗。
おウチに帰ってきて“ホッ”っとすると、緊張が解けてリラックス。
そこから眠気が襲ってくる・・・という体とメンタルのリズムになっているんです。
疲れが残って明日行けなかったらどうしよう…
そんな不安は声かけで解消できます
詳しい声かけが学べる小冊子プレゼント中!
4.翌日に響かない!敏感な子どもが疲れをリセットできる声かけ
◆「眠たかったら寝ちゃおうよ!」
学校から帰ってきて眠るのは、娘にとって必要なリセット時間なのだと感じた私は、まずは「眠たかったら寝ていいよ!」と伝えるようにしました。
眠たいのに、宿題や課題をやらせようと思っても集中できるわけがありません。
まずは疲れをリセットすることが先決でした!
◆起きる時間を決めてもらう
「15~20分程度の昼寝は日中の疲れを取るために有効」というような研究結果があるのは有名ですが、そのくらいで起こしてもすぐに覚醒せずに寝ぼけて機嫌も悪く、娘には逆効果でした。
そのため、娘に、
「眠かったら寝ていいんじゃない?寝ちゃったら何時に起こしてほしい?」
「今日のうちに何かしておきたい事はある?」
「お母さんも手伝えるから教えて」
と「起きたらやりたいこと」を聞くようにしました。
「明日は算数のテストある」
「明日リコーダー持って行かないと」
などと教えてくれたら、
「了解!じゃあ何時に起きたらいいかな?」
「起きたらおやつ食べてから頑張ろうか?」
と聞きました。
人は、「やりたいこと」「楽しみなこと」があると起きられます!
娘は、お風呂の時間なども考慮して、「じゃあ◯時には起こしてほしい!」と伝えてくれました。
すると、自分で「◯時に起きるんだ。」と意識できるため、起こすとスッと起きることができるようになりました。そして起きてからグズグズすることなく、自分で決めたことにスムーズにとりかかれるようになりったのです。
この質問のおかげで事前に宿題や明日の準備をする時間を決めることが身についちゃいました!

繊細で疲れやすい子の中でも、疲れがとれる睡眠時間は人それぞれ。
ママだけで対策を練って与えるのではなく、一緒にどうしたいかを相談することで、子ども自身がストレスと向き合う力がつき、乗り越える力もついていきます!
今日から子どものストレスへ立ち向かう力をつけてあげるお母さんになりませんか?
ぜひ、今回お伝えした2つの方法を試してみてくださいね。
「子どものことわかっていても、実際どんな言葉をかければいい?」
そんなママの疑問をすぐ確認できる無料小冊子があります!
▶ すぐに使える声かけがわかる小冊子を無料でダウンロードする
執筆者:すずき真菜
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
疲れて学校に行きたくないと言われたら…
▼1分で正しい対応法がわかります!
学校で疲れやすい子が
強くなれるおウチでの対応や声かけを
メルマガでお届けしています!
▼