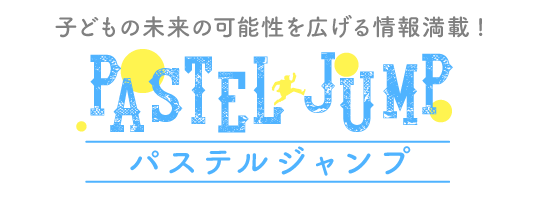1.友達トラブルから学校を休むように…どうすればいいの?
今回のテーマは、人間関係のつまずきは学校生活のつらさに直結…
思春期女子の「友達嫌い」は脳を育てれば解消する!です。
発達科学コミュニケーションの基礎講座を受講されたNさんからいただいたお子さんの変化成長について今回はお話します。
娘さんは中学1年の思春期の女の子、自閉スペクトラム症(ASD)グレーさんです。
登校しぶりを繰り返しながらなんとか学校に行っていたお子さんが次第に学校を休むことが増えてきました。
帰宅すると、お子さんはいつもイライラを爆発させてお母さんに八つ当たり。
お母さんもそれに巻き込まれて言い返して力ずくで、なんとか落ち着かせようとしていました。
親子関係もギリギリの状態…。
そんなときに発達科学コミュニケーションの講座受講をご決断くださいました。

今このサイトをお読みのあなたにおススメ
7500人の親子が実践中の声かけが無料!
▼詳しくはこちら▼
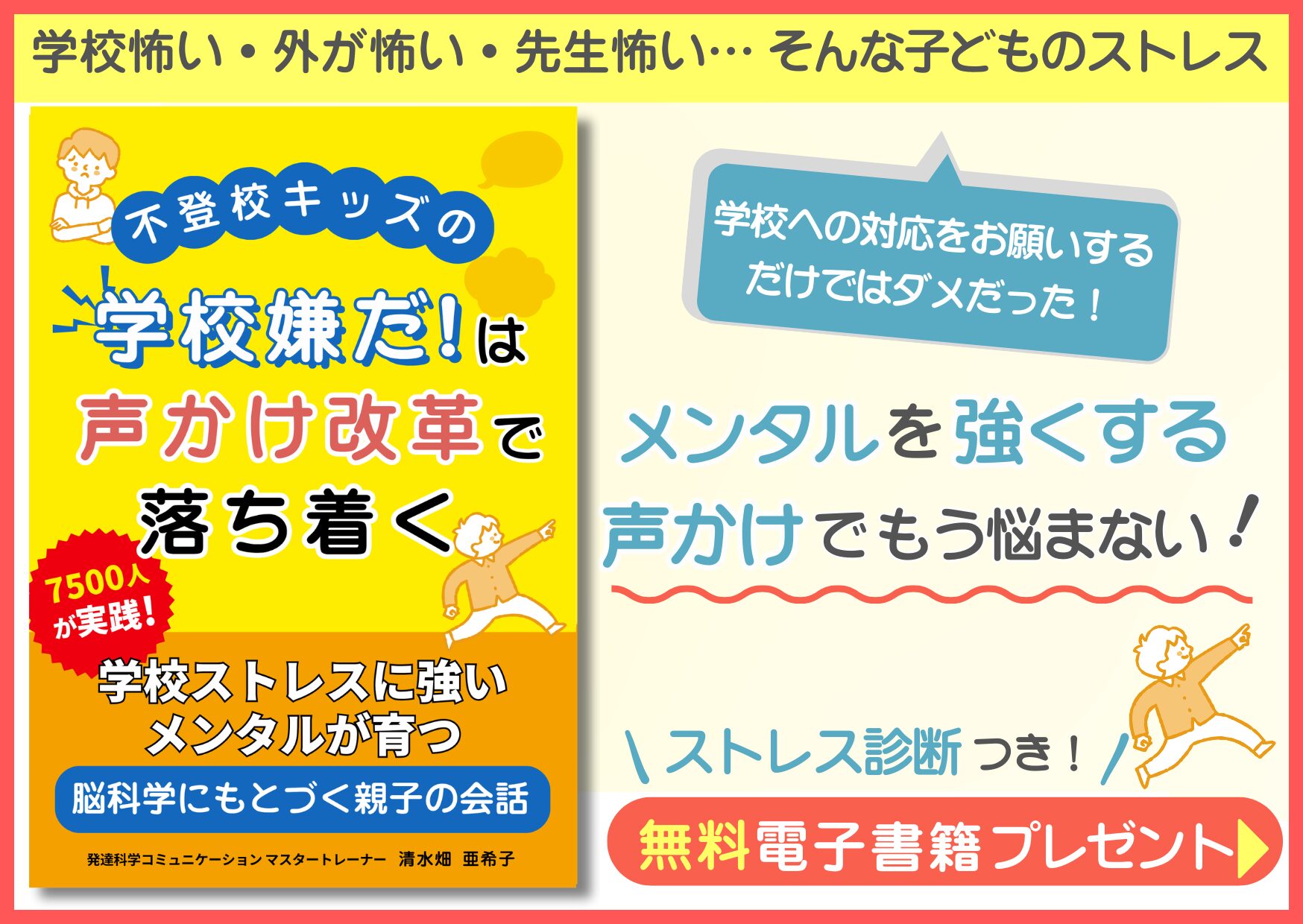
2.友達づきあいが上手くいかない本当の理由とは?
初期のころのお子さんの発言で、友達トラブルの様子がうかがえる発言がありました。
「あの子とは意見が合わない。 もうあんなやつ友達じゃない。
あんなやつがいる学校、もうぜったい行かないから」
この発言には、実はASDグレーさんの友達づきあいの特徴的なスタイルが垣間見えるんです。
✔こだわりが強い故に、想定外の違う意見は受け入れ難い
✔自分が想定していることと違うことは想像しにくいので、不安を感じやすい
✔故に、防衛反応として人をシャットアウトしてしまう
自己主張が一方的だったり、一人の方がラクと感じたり、これがASDグレーさんのコミュニケーションスタイルとして見られる、一つの傾向なんです。
とはいえ、思春期の女の子はグループをつくって、その中で密に人間関係をつくっていくお年頃です。
一人で平気!と口では言ってても疎外感を感じたままでは、お子さんの自信はいつまでたっても回復しませんし、「学校に自分の居場所を感じない」「行く意味を感じない」となると、さみだれ登校や不登校に繋がっていってしまいます。

3.友達関係が劇的に改善!思春期女子との親子関係もスムーズに
こんな背景がある、ということを知った上で、Nさんが学んだ発コミュの対応を実践してくださったら、娘さんはどう変わっていったのか…?それを、ここからご紹介しますね。
娘さんの一番の変化は、こだわりの強さが解消して
柔軟に、お友達のことを受け止めることができるようになったことです。
お友達の言い方がちょっとキツい言い方でも
「今日は体調が悪いだけかも」
「いつもは優しいし」
と割り切れるようになりました。
授業でのグループ発表で自分がやりたい方法じゃなくても「まあいいか」と受け入れられるようになりました。
そして、いつもイライラして、八つ当たりするようなコミュニケーションはなくなり
穏やかに話ができるようになっていきました。
お子さんも、もちろんいつでもコンディションが良いわけではありませんので
ちょっとイライラしたり、家で八つ当たりすることも時々はありましたが
お母さんが適切に落ち着かせる対応を知っているので
上手にクールダウンができるようになっていきました。
親子のコミュニケーションもどんどんスムーズになっていくので、お母さんとお子さんはこれからの進路のことや勉強のことなど、一緒に相談しながらチャレンジできるようにかわっていきました。

Nさんは発コミュの講座を学んでくださっているのでもちろん色々な関わり方のテクニックを駆使したことでお子さんの成長を引き出すことができましたが…
こちらの記事を読んでくださっているみなさまにも
今日から使っていただける対応のポイントがあるので最後の章でご紹介します。
"毎日学校に行けなくても大丈夫です!"
毎日の声かけを変えて
子どもの脳を育ててストレスをリセット!
▼今読めば進級進学前に間に合う!▼
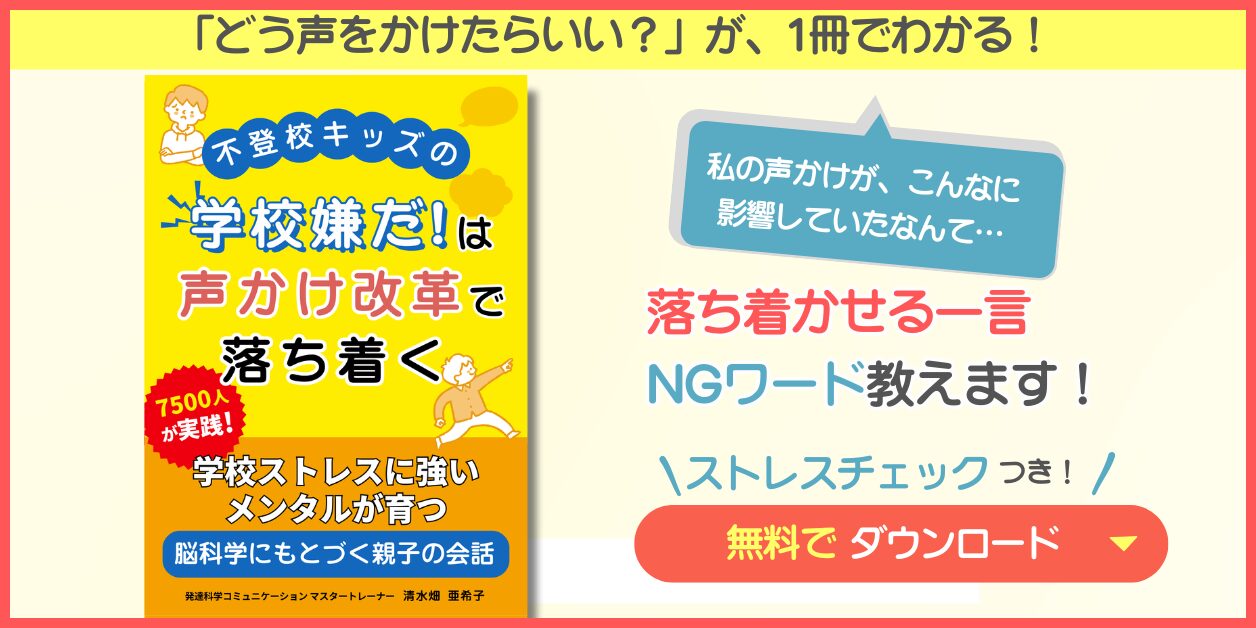
4.感情を落ち着かせるために工夫したい会話のコツ!
それは、「コミカルに」を普段の会話で常に意識してくれたこと、です。
自閉グレーっ子さんはネガティブな記憶を蓄積する天才です。
だから、感情を司る脳がいつもネガティブ。いつもイライラ。
そうなると、こだわりの強さはどんどん増していく一方ですし
相手を攻撃するようなコミュニケーションスタイルになりやすいので、
友達トラブルも起こりやすくなります。
感情の脳を落ち着かせるには「コミカル」なプラスの情報を入れてあげるとGood!
例えば、服が脱ぎっぱなしになっているときに
「ちょっと、片付けなさいよ!」ではなく
「わお!こんなところに服がおちててびっくりー!」と明るく伝える。
動画をずっとみていて、なかなかご飯にきてくれないときに
「いつまで動画見てるの!」ではなく
「う…もう…お腹が減って歩けないかも」と明るく演じてみる。
などなど。
お子さんの脳にはプラスのメッセージが届くので、感情の脳が落ち着きやすくなっていきます。

加えて!もう1つ大切なのは
子どもは、お母さんのコミュニケーションスタイルを見て学ぶ、ということ。
お母さんが穏やかに、明るく、お子さんに関わる姿をみて
お子さんは、それを真似て外で実践します。
「コミカル」には子どもの脳を落ち着かせる役割も
子どもにコミュニケーションを教える役割もあります。
思春期のお子さんにも今日から使えるワザですので、ぜひ実践してみてください!
執筆者:清水畑亜希子
(発達科学コミュニケーションマスタートレーナー)
▼思春期の友達トラブルで学校を休みがちな子どもに悩んでいませんか?脳科学を使った関わり方で親子関係も友達トラブルもラクになります!