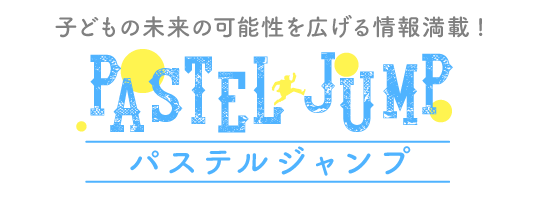勉強に取り組むことができなくなった
不登校キッズの
学習意欲の回復方法
をテーマに
お伝えしています!
前回までのメルマガは
お母さんにとっては
ちょっとヤキモキする
内容だったかもしれません。
なぜなら…なかなか勉強の本題に
入らないから(笑)
ですが、目指すのは、
子どもを根本的に発達させること
です。
明日の宿題をやるなら
叱ってでもやらせればいい…
泣きながらでもやらせればいい…
ではなくて
発達を加速して
できることを増やしていく
本人が「やってみよう」と
うごきだすこと、
そこを目指しているからです。
グレーっ子の脳は
エンジンをかけてあげる
順番があって
「こっちを先にやってね」
というのがわかっているんです。
だから、遠回りのように
感じたかもしれませんが
子どもの発達を加速するなら
それがいちばんの近道
と私も「本気で発達をさせたい」
という想いで、
お話をさせていただいております^^
…ということで、ここからも
「脳が育つスモールステップ」で(笑)
お話をしていきます。

発達科学の視点で解き明かす。
不登校が続く不安を「成長のステップ」に変える
親子の対話術。
▼詳しくはこちら▼
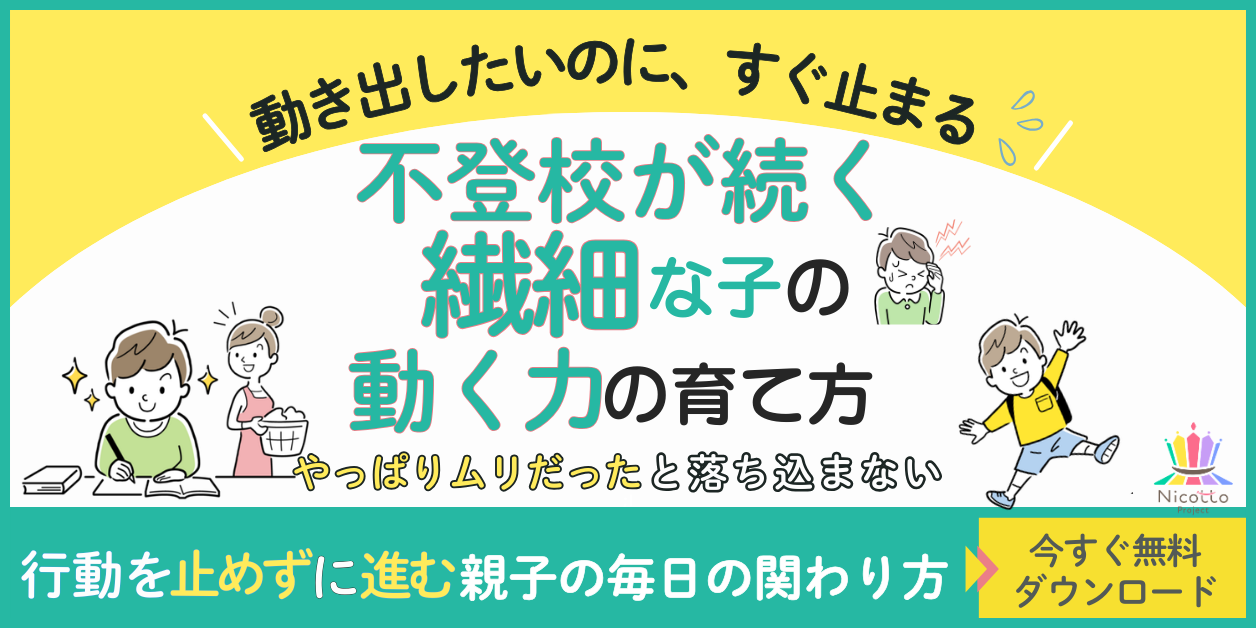
クリック後メールアドレスの入力で登録できます!
さあ、お子さんが、少しずつ
勉強に興味をもって
取り組みはじめたら…
お母さんに
やってほしいことが
2つあります。
1つ目は
お子さんの集中できる時間(長さ)
お子さんの集中しやすい科目
を発見すること、です。
2つ目は
書くこと、読むこと、
聞くこと、喋ること、
どれが得意なのか?
を発見すること、です。
わが家の息子が中学2年の時に
私はこの法則を発見しました。
集中できるのは1日10分!
得意なのは小学校の算数の計算問題!
衝撃ですよね(笑)
中学生なのに…です。
ですが、脳科学的にみると
あれもこれもやって
”よくわからない…”という
時間をいくら過ごしても
理解力も記憶力も伸びない。
あたりまえですよね、
わからないんですから。
だから、「わかる!」の
体験を積ませてあげる。
そうすると脳を使う時間が
増えていくんです。
つまり、発達しやすくなる。
"毎日学校に行けなくても大丈夫です!"
毎日の声かけを変えて
子どもの脳を育ててストレスをリセット!
▼今読めば進級進学前に間に合う!▼
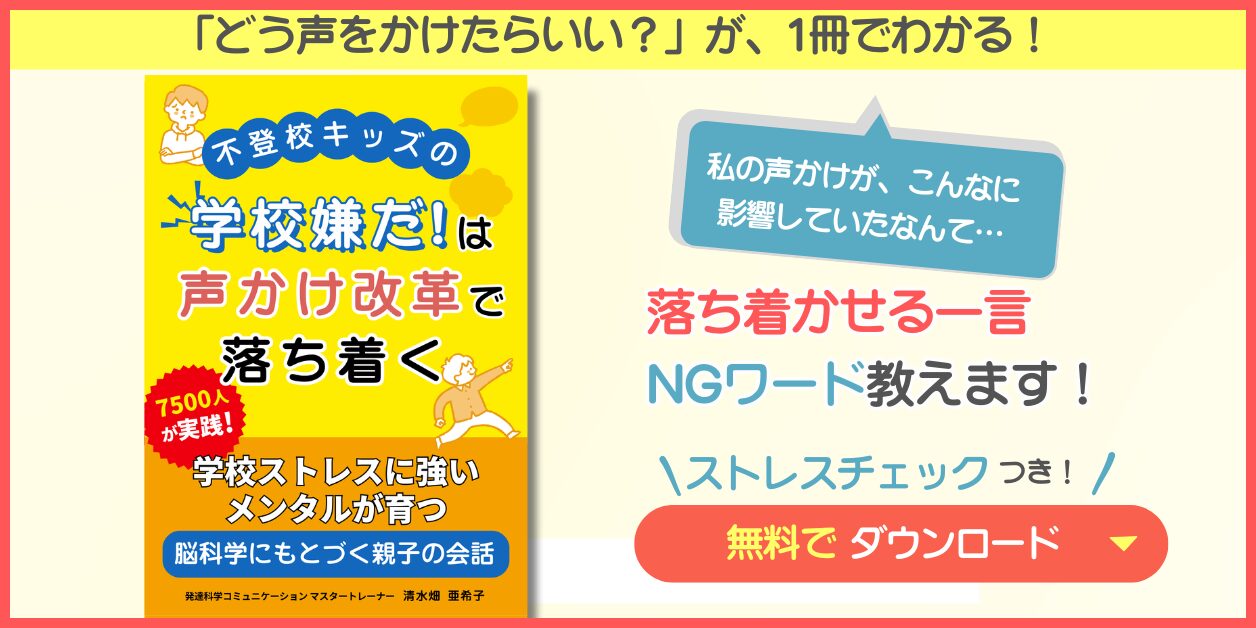
じゃあ、中2で、そんな状態から
スタートした息子は
どう成長していったのか?
「俺、計算問題ならできる!」
(小5の問題ですが…)
↓
中学のテスト勉強で「計算問題」
にフォーカスして取り組む
↓
テストもそこだけ取り組めばOKにする!
↓
採点を見ると「自分がやったところ」
にまるがついている。
「やったらできるんだ!」自信が育つ。
↓
じゃあ、他の教科もやってみようかな
と、授業を聞くようになる、
宿題を出すようになる。
↓
集中できる時間が増えてくる。
・
・
・
と進んでいき
高校受験をむかえた中3の冬には
1日4時間・5時間と
勉強をするようになりました。
勉強嫌いにさせることなく、
ただ確実にできることは増やしていく、
そのために最初にやってほしいのが
お子さんの集中できる時間(長さ)
お子さんの集中しやすい科目
を把握すること、なのです。
そして、2つ目のお話。
書くこと、読むこと、喋ること
どれが得意なのか?把握をしましょう。
不登校のお子さんは発達の特性を
持ち合わせているお子さんも実は多い。
いわゆるグレーさんなので
気づかれずに思春期を迎える
お子さんも多いんですよね。
書くこと、読むこと、
聞くこと、喋ること、
の苦手なことを
克服するようなやりかたは
小学校3−4年生以降は
お勧めしません。
勉強してもしんどくなるばかりで
どんどん嫌いになるからです。
もし、お子さんが、
仮に書くことが苦手なら
「書く」作業は
別の方法に変えてあげてOKです。
お母さんが書いてあげる、
タブレットやスマホで
音声入力させてあげる、
パソコンを使わせてあげる、
いろいろあっていいです!
つまずき、ストレスになる部分を
取り除いてあげながら
「考えることができた」
という体験をさせてあげることが
大切です。
日本の勉強は、どうしても、
「たくさん書く」
「正しく書く」
が主流ですが、
それは凸凹の子たちにとって
大きなハードルになることも多い。
他の力が苦手なお子さんも一緒です。
読むのが苦手な子に
音読10回!みたいな宿題、
いや、そりゃ、辛いですよね。
などなど。
苦手なことよりも
得意なことから
取り組ませてあげましょう!
スモールステップが
最大の近道、です。
じゃあ、苦手なことは、
ずっと苦手なままなの・・・?
気になるところですよね。
続きはまた次回。
執筆者:清水畑 亜希子
(発達科学コミュニケーションマスタートレーナー)
▼750人の生徒さんが「学んで良かった!」と納得の脳科学に基づいた親子のコミュニケーションのコツをお届け!