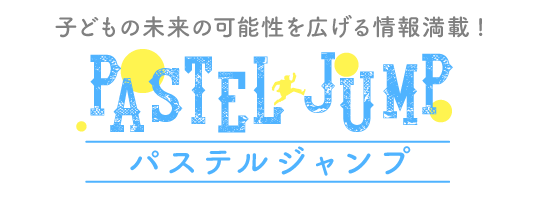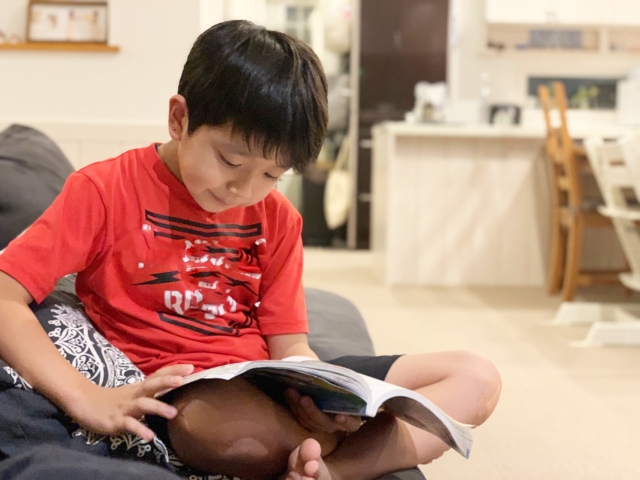1.音読が苦手で宿題を嫌がりませんか?
学校の宿題の音読をやりたがらないお子さんに困っていませんか?
発達が他のお子さんよりちょっと凸凹しているお子さんの中には読むことが苦手なお子さんがいます。
その大変さは、大人が想像するよりもはるかに大きいはず。だから、読むことから逃げようとするお子さんもいます。
それをしつこく克服させようとすると、結果的に勉強全体が嫌い!学校も嫌い!という状態になってしまうので注意が必要です。
大切なのは、音読をさせることではなく、『読むとおもしろい!読むと色々なことが知れて楽しい!』と子どもに思わせてあげることです!
この記事では音読が苦手な子の発達チェック方法と、楽しく本が読めるようになるサポートについて解説します!
実は、音読の仕方から発達の特性傾向を知る方法がありますのでご紹介しますね!
▼テクニックを探す前に。
まず知ってほしい“動けない理由”があります!

メールアドレスの入力で無料でお届けします!
2.国語の音読のつまずきからわかる!3つのタイプ
お子さんはどのタイプに近いでしょう?お子さんのタイプがわかれば、どんな学習サポートが必要なのかを知るヒントになります。
タイプ①棒読み・高速読み
正しく読んでいるけれど、ビックリするほど「棒読み」だったり、びっくりするほど「高速読み」だったり。
これは、自閉症スペクトラム(ASD)の傾向のあるお子さんに多い読み方の特徴です。
タイプ②読むことに集中できない
途中で話し始める、おちゃらけ始める、最後まで読まない、ソワソワしながら読むなど、読み始めても途中で別のことに意識がいってしまうタイプ。
これは、注意欠陥多動性障害(ADHD)の「集中力不足によって音読が長続きしない」という特徴が出ています。
タイプ③正しく読めない・意味が分かっていない
・1文字ずつ読む→文章ではなく1文字ずつをたどるような読み方です。
・書いていないことを読む→特に文末などを勝手に変えて読みます。雰囲気で読もうとするのです。
・同じところを何度も読む、読み飛ばしが多い→同じ行を何度も読んだり、逆に行を読み飛ばしたり。視覚認知の苦手さのあるお子さんに見られます。
・読めない字が多くスラスラ読めない→読めるところはスラスラ読むけれど、漢字や特殊音節(小さい文字の部分)で毎回詰まってしまう。
・読めてはいるけど意味がわかっていない→読んだのに意味が全然わからない!声を出すことに一生懸命で、読むことと理解することが同時に処理できない。
これらは、学習障害(LD)の中で「読み」の苦手があるお子さんたちに多い困りごとです。

3つのタイプはあくまでも行動面からみて分類したものですので、このチェックだけで発達障害の有無の診断はできません。
しかし、どうやって支援をするのかを考えるのに、一つの目安になると思います!
3.子どもの発達タイプ別の音読サポート法
「読み」が苦手なお子さんへのサポートとして、次のような方法があります。タイプ別にご紹介します。
タイプ①棒読み・高速読みのASDタイプ
正しく読めてはいるけれど、「棒読み」だったり「高速読み」だったりは、自閉症スペクトラム(ASD)の傾向のあるお子さんに多い読み方の特徴です。
特性上、聞いている人、相手のことを考えるのが苦手なので、「聞かせる」読み方、伝え方ができていないのです。
例えば、テレビのアナウンサーの話し方を参考にしたり、メトロノームのようなリズムを刻む道具を使って、音読のペースを掴んでみると良いでしょう。
タイプ②読むことに集中できないADHDタイプ
注意欠陥多動性障害(ADHD)のお子さんは集中して読めない状況をなんとか誤魔化すために、おちゃらけて声を変えてみたり、意味不明なマイルールを作って文を変えたりします。
非常にユニークですが、お母さんからしたらイラっとする音読になることもあります。
目に入ってくる文字や挿絵などの情報量が多いために、集中できないのかもしれません。
クリアファイルに紙を挟んだものや定規などで他の部分を隠して、行ごとに読んでみる方法を試してみてください。
タイプ③正しく読めない・意味がわかっていないLDタイプ
学習障害(LD)の中で「読み」が苦手なお子さんには、次のようなサポート方法があります。
・どこを読んでいるのかわからなくなるタイプのお子さんには、クリアファイルに紙を挟んだものや定規などで他の部分を隠して、少しずつ見るようにする
・音声読み上げのアプリケーションや録音図書(DAISY)を利用する
・サポートの先生に読む作業を助けてもらう
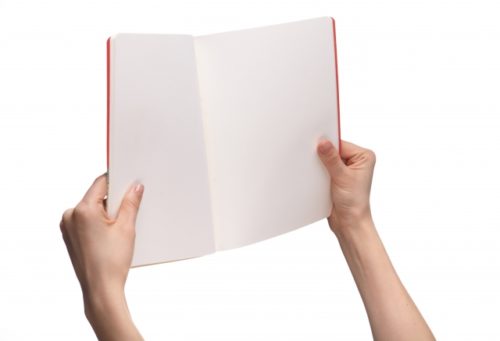
今、もし毎日学校に行けなくても
"大丈夫です!"
毎日の声かけを変えて
子どもの脳を育ててストレスをリセット!
▼今読めば進級進学前に間に合う!▼
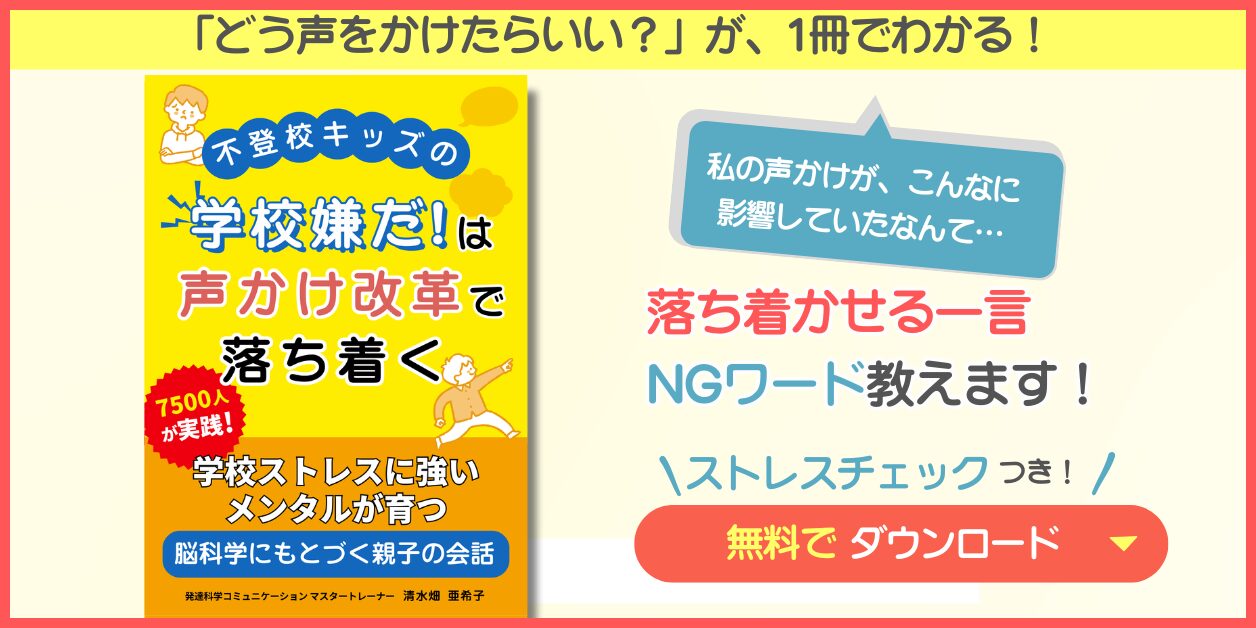
4.勉強嫌いになった子の自信を取り戻すために大切なこと
今回は「音読」を軸にチェックしましたが、音読が苦手なお子さんは「読み」以外にも特性をもっている可能性があります。
それも知った上で、お子さんの「意欲を潰さない」対応の方法を考えてほしいと思います。
特に、高学年以上、思春期のお子さんのママは気をつけてください!
年齢やこじらせ感によって対応を考えた方がいいのです。
世間で「いい」と言われることを片っ端からやっても効果が出ません。
勉強が苦手な発達障害・学習障害を持つ思春期のお子さんたちは、高学年になるまでにたくさんの失敗体験を積んできています。
「○○しなさい!」
「できるようになるまで練習して!」
「○時間は勉強しなさい」
…と毎日命令し続けると、勉強はおろか学校へ行くことすら拒否し始めるかもしれません。
苦手なトレーニングをさせて「嫌だ」という感情を持たせないことが大事です。
苦手なことを強要しなくても、お子さんが自分で「考える」ことで「ちゃんと勉強した」という成功体験を積ませてあげればいいのです。
苦手なことをやらせようとし過ぎると、できることまでやらなくなる恐れがあります。
パステルジャンプ上級講座生のSさんは、不登校になり勉強いっさい拒否になった小学生の息子さんとこんな過ごし方をしてくれました。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
小学4年生で不登校になった息子は、学校を休む直前まで宿題タイムは癇癪を起こしていました。
音読は嫌いで家ではほとんど読みませんでした。読書感想文なんかもとても嫌がって…
不登校になってからは、息子がよく見ていたyoutubeの字幕を一緒に見て、私がそれとなく読み上げたり、息子に「なんて書いてあるのか教えて」とお願いしたりするようにしていました。
これだと、息子は嫌がらなかったんです。
楽しく読む時間を過ごすことで、息子は興味の持った株式投資の本がほしいと言い始め、そこから本をたくさん読めるように。今でも声に出して読むことは好きではないですが、読書で知識を得られる嬉しさを知って読むことが大好きになりました!
不登校だから勉強遅れたら…という心配もありましたが、息子自身が楽しく頭を使えるようになったことが嬉しいです!
ーーーーーーーーーーーーー

いかがですか?
まずは、勉強への苦手さを取り除くことからスタートすることで、今までの「できる勉強すらやらなかった」という状態から脱却させてあげましょう。
「子どもの意欲を潰さない」これが、子どもの自信を取り戻す近道ですよ。
執筆者:清水畑亜希子
(発達科学コミュニケーションマスタートレーナー)
勉強が苦手な思春期のお子さんが自信を取り戻す、意欲を潰さないアプローチ法を発信中!
▼▼▼