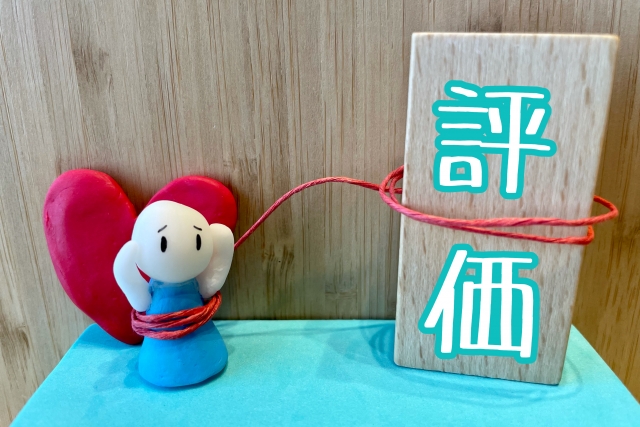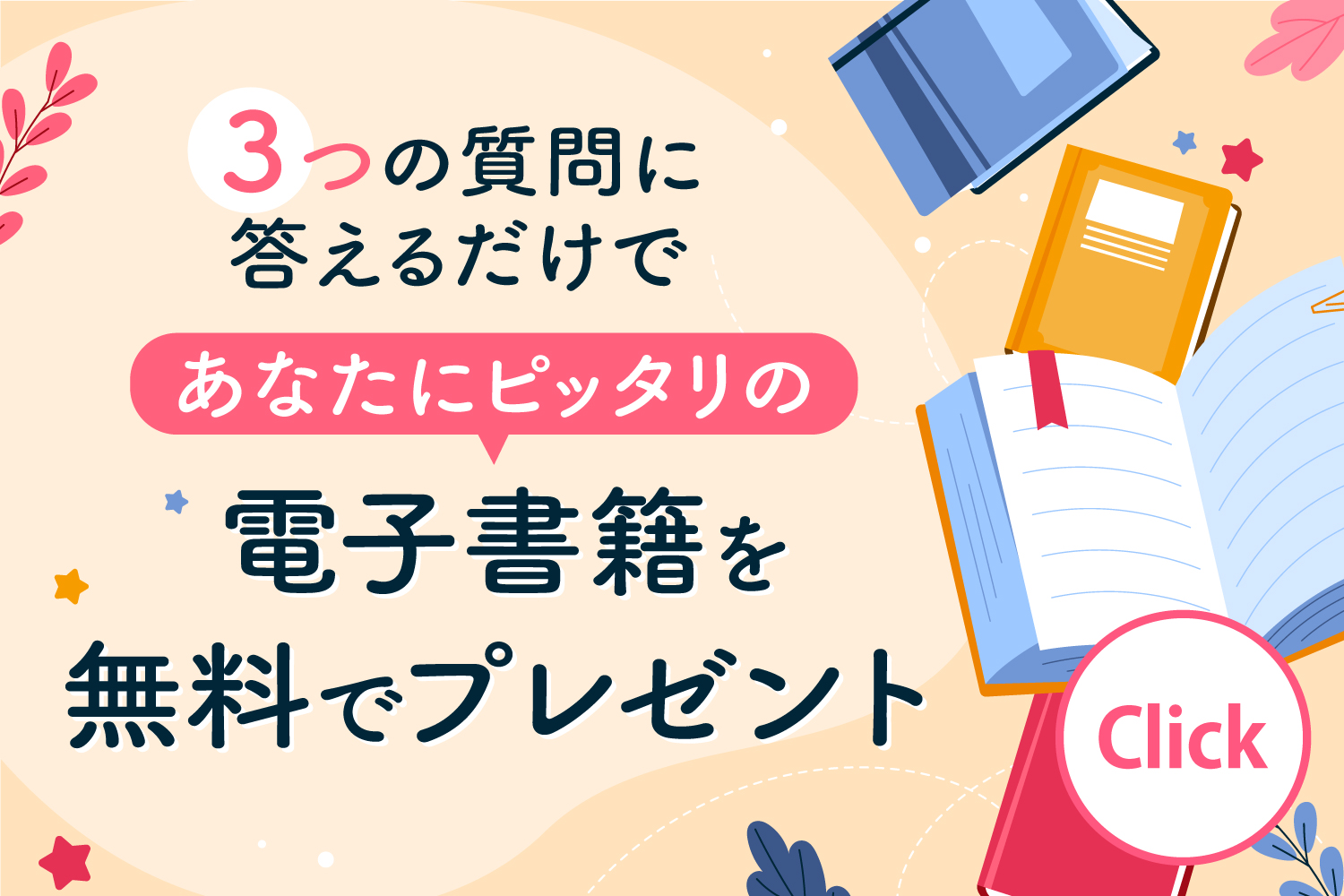娘は現在、小学生です。周りを見る余裕が出てきたのは良いのですが、周りのお友達と自分との比較をするようになりました。今後、比較をすることで、自己肯定感が下がってしまわないかが心配です。まだ低学年ではありますが、今からできる気持ちがネガティブにならない対応はありますか?
7歳・女の子のママ

お子さん自身が周りを見る余裕ができたというのは大変喜ばしいことではありますね。しかし、喜ばしい反面、比較して自己肯定感が下がってしまう心配をされる気持ちもわかります。今回は、自分の苦手も受け入れつつ自己肯定感を下げない声かけをお伝えします。
発達科学コミュニケーションリサーチャー みずおち梨絵
【目次】
1.どうして他人と比較すると落ち込むの?
2.周りを意識するようになっていくことは成長の証
3.家庭でできる!自己肯定感を築く2つの声かけ
①誰にでも得意と苦手があるんだ!
②比べる相手は常に過去の自分だよ!
1.どうして他人と比較すると落ち込むの?
皆さんは自分と他人とを比較して、「自分はなんてダメなんだろう?」と落ち込むことはありませんか?
あの人は、こんなこともできる!あんなところも素晴らしい!と、いつか自分もあの人のような人間になりたい…とか。
子どもの世界でも早ければ低学年の後半から、そして思春期の時期には周りのお友達と自分を常に比較してしまうことが多くあるのです。
思春期は周りの目を気にしたりするようになると言われています。
友達と自分を比較することで、優位に感じることができれば良いのでしょうが、劣等感をいだいてしまうこともありますよね。それにより、精神的にも苦しくなっているお子さんが多くいます。
自分が劣って見えると心に深い傷ができやすく残ってしまうものがあります。しかし、友達と比較しているときって、大体が友達の良い部分と自分のダメだと思う部分を比べてしまっているのですよね。
大人の私たちだって同じような経験があるはずです。大人でも常に誰かと比較して自信を失い自己肯定感が下がってしまうことはあるので、子どもだったらなおさらですよね。

他人との比較は人間の癖と言っておられる専門家もおられるくらいなので、その癖は早いうちに改善したいものですよね。
子どものうちに、比較癖を改善して自己肯定感を下げることなく成長ができたら良いと思いませんか?
もし、お子さまが低年齢であるならば、早いうちから人と比較する癖を改善する関わりをしてあげたいと思いませんか?
今回は、我が家の自己肯定感を下げずに自分自身と向き合っていける秘策をお伝えします。
ぜひ最後まで読んでくださいね。
2.周りを意識するようになっていくことは成長の証
我が家にも小学生低学年の子どもがいます。
もともとのんびりマイペースで、周りの友達のことはあまり気にすることもなく、我が道を行く!という子でした。
小学校は集団生活のため、我が道をいくわが子に発破をかけるつもりで「ほら!だからみんなに笑われるんだよ!」なんて意地悪な声かけをしても、全く気にする様子はありませんでした。
たとえ集団行動についていけていなくても、周りの目を気にしすぎて困り事が多いよりは、逆にマイペースはわが子の長所だと感じていました。
しかし、子ども達が成長し学校生活に慣れてくると、いろんな友達にも意識がいくようになり話題にも上がるようになりました。
私としては、わが子が周りをみる余裕ができたと少々喜ばしいことだと思っていました。
そんな我が子が、ある日宿題をしながら私にこう伝えてきたのです。
「ママ!算数のここがわからなくて困っていたら、〇〇ちゃんが、もうわかんないの?と言うの。私は〇〇ちゃんみたいにできないし…〇〇ちゃんは何でもできるから。悔しかった。」
悔しかった!の言葉を次へのステップにして、頑張る力になれば良いのでしょうが、そのときの我が子は明らかに気持ちが凹んでいました。
とてもじゃないけれど、「悔しいなら頑張らなきゃ!」なんて言えませんでした…
あんなに周りの様子を気にも留めなかった子が、周りを意識し始めて劣等感をいだく状況が続くと、明らかに我が子の自己肯定感は下がってしまうと危機感を覚えました。

そこでこれから迎える多感な思春期を視野に、自己肯定感をいかに下げないよう家庭でできることを準備することにしました。
子育ては褒めたり、認めたりして伸ばす!と一般的には言われています。それと同時に我が家では自己肯定感を育てる基本的なことを子どもに声かけしていくことにしました。
次にお話しますね。
3.家庭でできる!自己肯定感を築く2つの声かけ
我が家はまだ低学年ではありますが、周りと自分とを比較することを徐々にし始めています。家庭では、褒めたり認めたりするのと同時進行にプラスして、2つの声かけをしています。
◆①誰にでも得意と苦手がある!
まずは当たり前のことですが、人間は誰しも得意と苦手の両方が存在します。
どんなに素晴らしい人であっても苦手な部分は必ず持っているということを知ることが大切だと考えています。
前々項で書いた通り、人は誰かと比べるときに必ずと言っていいほど、相手の得意な素晴らしい部分と、自分の苦手でできない部分を比べているものです。
我が子も同様です。他人の素晴らしい部分を素直に尊敬するのはとても良いことだと思います。しかし、そこを比べて自分を卑下するなんて勿体無い!
別に相手の粗探しをするということでは決してありません。ただ、人間には得意と苦手という両極のことが存在するんだよ!ということを知っていてほしいと思っています。
我が子には、自分が苦手な部分は助けてもらいなさい!得意な部分は誰かを助けてあげなさい!ということを常に声かけしています。
◆②比べる相手は常に過去の自分だよ!
2つ目の声かけです。
比較をするときの軸って、いつしか他人軸になってしまっているんですよね。
そこを自分軸で考えられるようになると、比較をするのは過去の自分。ですので、我が子にかける声がけは次のようにしています。
「前は、自分の気持ちを伝えるのに時間がかかったけど、今は考えたことを伝えられるようになったね。」や、
「〇〇の話しがとてもわかりやすくなったよ。前とは別人だよ!」など。
かける言葉も、私自身が我が子の過去との比較で伝えるようにしています。

育児をする上でも、他人軸にならず、自分軸や我が子軸が出来上がると本当に楽になりますよ!
もちろん、お友達の良いところは素直に尊敬し、我が子との会話の中でお友達のことを褒めたりすることはたくさんあります。
最近では娘自身が、周りを気にはしつつも自分軸を持って気持ちを切り替えていけています。
先日も、「お友達とは得意なことが違うから、私はこっちを頑張ることにした!」と帰宅してから話してくれました。
思春期真っ盛りのお子さんはもちろん、娘のようにまだ低学年であったとしても、早いうちに自分軸を作り、自己肯定感を育てる対応をしていきたいですよね。
自分の苦手は、得意な人に助けてもらう!自分の得意は誰かを助けることができる!
日頃の関わりで、思春期に脅かされやすい自己肯定感を守っていきましょう!
こちらの記事でも、お家で育てることができる自己効力感と自己肯定感のことをお伝えしています。あわせて読んでみてください。
自己肯定感を育てる声かけをお伝えしています!
▼ご登録はこちらから
▼無料小冊子プレゼント▼
育てにくい子が3ヶ月で変わる!
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
↓↓↓
執筆者:みずおち梨絵
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)