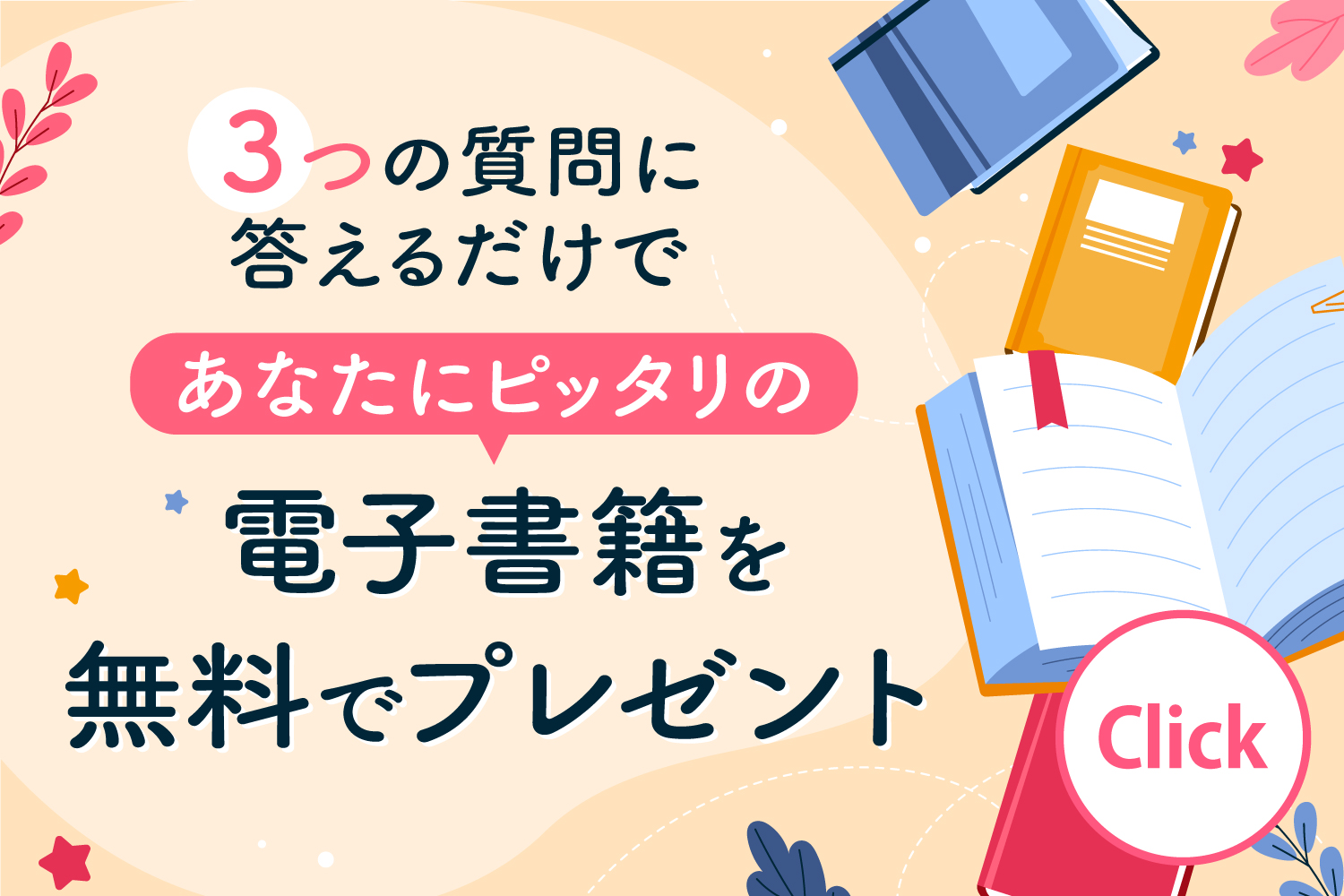発達障害・ADHDの我が子が嘘をつく…お母さんはショックを受けますよね。「このまま嘘つきになったらどうしよう」と不安になると思います。実は子どもが嘘をつくには子どもなりの理由があります。今すぐできる子どもの嘘対応策についてお伝えしていきます。
【目次】
1.発達障害・ADHDの子どもが嘘をつくのが心配
2.子どもが嘘をつく理由とは
①怒られたくないから
②注目してもらいたいから
③子どもにとって理由があったから
3.嘘をつく子どもが素直になる3つの対応
①怒られたくない嘘の対応:共感する
②注意を引く嘘の対応:スルーして肯定する
③理由のある嘘の対応:子どもの気持ちを聞いてあげる
1.発達障害・ADHDの子どもが嘘をつくのが心配
発達障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)の子どもの困った行動の中に「嘘をつく」という問題があります。
片付けが終わったてないのに「片付けた」
「宿題終わったの?」終わっていないのに「宿題やったよ」
友達を叩いて泣かしたのに「叩いていない」など
事実でないことを平気で言ってしまうことがあります。
子どもが嘘をついたときはお母さんとしてはショックを受けるものです。
今までは素直で隠し事もせずに育ってきたのに、どうして嘘なんてついてしまうの?
このまま嘘つきになってしまったらどうしよう…と不安になってしまいますよね。

つい「どうして嘘をつくの?」「嘘はいけません!」と頭ごなしに怒ってしまうことも無理もないこと。
いくら叱っても注意しても嘘をやめない我が子に困ってしまいますよね。
2.子どもが嘘をつく理由とは
発達障害・ADHDの子どもは脳の特性があり嘘をつくことに理由があります。
今回は3つの理由に分けて説明していきますね。
◆①怒られたくないから
発達障害・ADHDの子どもが嘘をつく一番の理由は、お母さんに怒られたくないからです。
お子さんは特性からじっとしていられない、忘れ物が多い、不注意など、怒られる機会が多くなります。
ただでさえ普段から怒られているので、
これ以上お母さんに怒られたくない
↓
怒られないないよう自分を守ろう
と、とっさに嘘をついてしまうことがあります。
◆②注目してもらいたいから
発達障害・ADHDの子どもの中には注目されることを好み、親の注意を引くために嘘をつく場合もあります。
お母さんが忙しくて子どもとの会話が少なくなると、子どもはかまってほしいという気持ちから気を引くため嘘をついてしまいます。
「叩いていない」
↓
本当は叩いたけれど嘘をいている
↓
「どうして嘘をつくの?」お母さんが怒ってる
(かまってくれた=注目してくれた)
↓
また嘘をつく
お母さんが反応することで嘘をつく行為が強化されてしまいます。
◆③子どもにとって理由があったから
発達障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)タイプの子どもは、衝動的に行動してしまうことがあります。
友達から嫌なことを言われたので、衝動的に叩いてしまった。
→けれど「叩いていない」と嘘をついてしまう。
授業が面白くなかったので気になる物の方に一直線に行ってしまい、席を立ってしまった。
→けれど「立っていない」と嘘を言ってしまう。
このような場合は子どもなりの理由があって、特性により衝動的に行動したことで、悪かったなと思いながら嘘をついてしまうのです。

以上のように子どもなりの理由がわかると、子どもを責めることや不安な気持ちは和らぎますよね。
3.嘘をつく子どもが素直になる3つの対応
では子どもが嘘をついたときに、お母さんはどのような対応をすればいいのでしょうか。
今回は3つの対応ポイントをお伝えしていきます。
◆①怒られたくない嘘の対応:共感する
子どもが怒られないために「(片付けをしていないけれど)片付けをした」と嘘をつくときは、子どもの気持ちにしっかり共感することがポイントです。
子どもにとって片付けをすることはめんどうで大変なことです。
「片付けするのって大変だよね」と共感しながら、「今からお母さんと一緒にしようか」次の行動に誘ってみましょう。
お母さんが自分の気持ちをわかってくれた!と思うことができれば、嘘が減ってきますよ。
◆②注意を引く嘘の対応:スルーして肯定する
お母さんの注意を引くための嘘については、大袈裟に叱ったりと反応するのではなく、見逃すことも必要です。
「へーそうなんだね」と聞き流してしまいましょう。
その上で、嘘をつかなくてもお母さんはあなたのことをしっかり見ているよと伝える必要があります。
時間を取って話を聞いてあげたり、スキンシップ遊びをしっかりしていきましょう。
時間がなくても声掛けだけでもできることがありますよ。
子どもの行動を見て
「テレビ見てるんだね」
「宿題してるんだね」
「ご飯食べてるね」
と肯定的な声を掛けてあげましょう。
子どもの行動をそのまま伝えてあげるだけで、ちゃんと自分を見てくれている!と感じるようになってきます。
◆③理由のある嘘の対応:子どもの気持ちを聞いてあげる
子どもにとって言い分がある嘘に関しては、その理由をしっかり聞いてあげることが必要です。
頭ごなしに事実を叱っているだけでは、わかってもらえない体験だけが積み重なって、お母さんとの信頼関係が作ることができません。
その場しのぎで「嫌なことがあれば、嘘をつく」という癖がついてしまいます。
・友達を叩いたのは、自分が嫌なことを言われたから
・授業中席を立ったのは、先生の話が面白くなかったから
このように理由があるなと思う場合は「どうしてそんなことをしたの?」と子どもの気持ちを聞いて、気持ちを語らせてあげましょう。
お母さんが自分の気持ちを聞いてくれた、理解してくれたと感じると、親子の信頼関係が育ってきます。
0点のテストでも隠さず見せられるような「嘘をつかないような親子関係」を今から作っていきましょう。

発達障害・ADHDの子どもは特性が影響して嘘をついてしまうことがあります。
子どもが嘘をついてしまっても、お母さんの適切な対応で子どもの嘘をなくし、親子関係を良くていきましょう。
発達障害の子どもの困りごとの対応について多数お伝えしています!
▼ご登録はこちらから
▼無料小冊子プレゼント▼
育てにくい子が3ヶ月で変わる!
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
↓↓↓
執筆者:石井花保里
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)