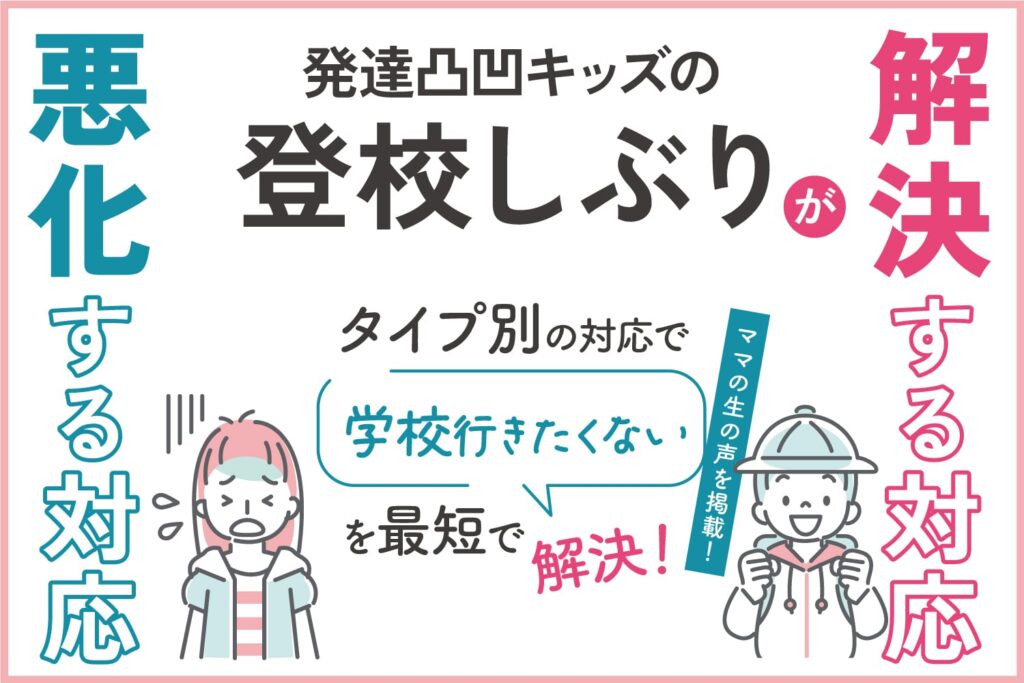中学生・高校生のスマホ依存に対して、時間制限や「取り上げるよ!」といった没収は逆効果となることが多く、かえって依存を深めてしまう可能性があります。子どもが自らスマホを手放せるようになるためには、親の対応や環境づくりが重要です。
【目次】
1.なぜ中高生はスマホ依存症になりやすいのか?
2.反抗期の息子にスマホ制限や没収は逆効果!荒れるだけでした
3.中高生にスマホ制限や没収は逆効果なのか?
4.親子バトルに発展させないスマホ依存を手放す方法
2.反抗期の息子にスマホ制限や没収は逆効果!荒れるだけでした
3.中高生にスマホ制限や没収は逆効果なのか?
4.親子バトルに発展させないスマホ依存を手放す方法
1.なぜ中高生はスマホ依存症になりやすいのか?
中高生の子どもがスマホ依存にならないように「もうやめなさい!」って口酸っぱく注意し、言うことを聞かなければスマホ制限や没収をされているご家庭も少なくないはずです。
中高生がスマホ依存になりやすいのは、思春期特有のストレスや孤独感を手軽に紛らわせる手段としてスマホが機能し、現実からの逃避や快楽の追求が依存を招くためです。
しかし、反抗期の中高生にスマホ制限や没収は逆効果なんです。
強制的にスマホに制限をかける行為は、スマホ依存症としての禁断症状を起こしやすくさせてしまうんです!
そもそも中高生がスマホ依存に陥りやすい主な理由として、次の理由が挙げられます。

●友人関係の影響
中高生は友人との関わりがとても重要な時期です。SNSやメッセージアプリを通じて友達と常に繋がっていたいという欲求が強く、スマホがその主要な手段になっています。これが過度なスマホ使用に繋がることがあります。
●刺激と快感を追い求める脳
中高生の脳はまだ発達途上で、特に報酬系が敏感です。スマホの通知やゲーム、SNSの「いいね!」などが ドーパミンを分泌し、快感を得やすくなります。これが依存を促進する要因となり、繰り返しスマホに手を伸ばす行動が強化されます。
●自己管理能力の未熟さ
自己管理能力がまだ完全に発達していないため、スマホの使用時間を自分でコントロールすることが難しい場合があります。特に、ルールが緩い環境では、時間の使い方が偏りがちです。
●情報や娯楽へのアクセスの容易さ
スマホは多くの情報やエンターテインメントに簡単にアクセスできるため、好奇心が強い中高生には魅力的です。動画やゲーム、SNSのコンテンツは無限にあり、終わりがないため時間を忘れて使い続けてしまうことがよくあります。
●家庭内のスマホ使用環境
家族全体でスマホをよく使う環境だと、中学生もその影響を受けやすくなります。家庭でのスマホの使い方にルールがない場合、親の影響でスマホ依存に陥ることがあります。
さらに、日本では子どもたちがスマホを持ち始める年齢が毎年低年齢化しています。スマホを持たせる年齢で一番高いのが12歳(小学校6生~中学1年生)と言われています。
特に中高生となると自分専用のスマホを購入してもらう子どもが多く、同級生とのコミュニケーションもスマホを使ってのやりとりがほとんどです。
また部活や塾などで帰宅時間が遅く、それから友達とLINEやゲームなどで遊ぶことになるので必然と夜遅くまでスマホをいじっています。
中高生は、大人ほど自制心が利かないことが多いため、より深刻なスマホ依存症に陥りやすいと言われています。
スマホ依存症の初期症状として
・ゲームやYouTubeをやめられない
・勉強や宿題をしない
・課金してしまう
・SNSからの友達とのトラブルや犯罪
・眼精疲労 視力低下
・昼夜逆転
・イライラ 不安
などがあり、不登校の引き金になってしまうケースも増えています。
中学生や高校生は、部活のストレスや疲労、人間関係に加え、日々勉強のプレッシャーも感じ、そういった不安を解消するためにスマホに依存しやすいのです。
さらに発達障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)の中学生は時間間隔が乏しく過集中なりやすいので、なおさらスマホ依存に陥りやすいですよね?
2.反抗期の息子にスマホ制限や没収は逆効果!荒れるだけでした
我が家も、キッズ携帯は持たせていましたが、中学卒業するまではスマホを持たせるつもりはありませんでした。
なぜなら、ADHD傾向の息子は時間感覚がなく、ゲーム時間を決めても全く守れなかったのでスマホ依存になってしまうのではないかと不安があったからです。
反抗期の子どもは、自立心や自己主張が強まる時期です。この時期にスマホを強制的に制限したり没収したりすると、親への反発心が強まり、状況が悪化する可能性があります。
しかし、状況は変わり、中学生になった息子は遊び歩いて、帰宅するのが遅かったので、緊急連絡できるようにこれを機にスマホを持たせることにしました。
購入時息子とルールを決めて、携帯会社に時間と閲覧の制限を設定してもらったものの、1週間たたずに時間制限を解除してしまい、息子のやりたい放題!ほぼスマホ依存症の手前までに発展してしまったのです。
食事やトイレへいくのもスマホを持ち歩き、休みの時はテスト勉強はおろか、10時間以上スマホを使用していることもありました。
使用時間のルールを破ったのでスマホを取り上げようとすると、「返せ。くそばばあ。」と暴言を吐く始末。それに対し、私が注意するとモノを投げたり、弟へ当たったりする行動がみられました。
困り果てていた矢先に、発達科学コミュニケーションに出会い、同じ問題を抱えている親御さんのケースを知りました。
スマホ依存症に対してスマホを取り上げたり使用制限をかけたりすることは逆効果だったのです!
なぜならスマホが無いこと自体にイライラしてしまうので、余計にストレスを感じてしまうからなんです。

スマホ制限や没収が逆効果になってしまう理由を次で詳しく説明しますね。
3.なぜ中高生にスマホ制限や没収は逆効果なのか?
確かに言うことを聞かない中高生には保護者である親の責任があるので、強制的にスマホの使用を制限したり没収するケースがほとんどだと思います。
しかし、強制的に制限や没収をした結果、次のような悪影響も起こしやすいのです。
●ストレスの増加
突然スマホを制限すると、心理的なストレスが増える可能性があります。特に、スマホが日常のリラックス手段や情報収集の重要なツールになっている場合、無理に制限することでイライラや不安を感じることがあります。
●依存の強化
スマホを過度に制限すると、その反動でスマホへの欲求が逆に強まることがあります。制限が解除された際に、以前よりもさらに多く使用する「リバウンド効果」が起こり、結果的に依存が悪化する可能性があります。
● 代替手段の欠如
スマホの代わりになる有意義な活動や趣味がないまま制限をかけると、暇な時間にどう過ごしていいかわからなくなり、さらに不安や孤独感が増すことがあります。これにより、ストレスや退屈感が増してしまうこともあります。
●社会的な孤立感
スマホは現代社会において、友人や家族とのコミュニケーション手段として重要です。スマホを制限しすぎると、友人や同僚とのやり取りが減り、孤立感を感じることがあります。この孤立感が精神的な負担になることも考えられます。
● 自己管理能力の低下
他人による強制的な制限がかかると、自己管理する能力を育む機会が失われることがあります。自分で時間管理をする力が身につかないため、制限がなくなると再び過度に使用する傾向が強まることがあります。

このように、スマホの制限が強すぎたり、代替手段がない状態で無理に行われると、かえって問題が悪化することがあるため、柔軟な対応が求められます。
そして我が家では非常識な対応でスマホをやりたい放題にさせた結果、親子バトルをしないで自らスマホを手放せるようになりました。最後にお伝えしますね。
4.親子バトルに発展させないスマホ依存を手放す方法
親子バトルを避けるためには、子どもの気持ちに寄り添い、共に解決策を見つけていく姿勢が大切です。
一方的な制限ではなく、対話を重ねながら信頼関係を築くことで、スマホ依存の改善につながります。
いつもスマホで親子バトルを繰り返していた我が家でしたが、ある日出先で息子と2人ででかけると、あるポスターが目に入りました。
「ねぇ、あの字ってなんて書いてあるか見える?」と息子に尋ねると「●●までは読めるけど、少しぼやける。」と息子が言いました。
「もしかしたら、視力が落ちているかもしれないね。」と私。
「え、回復するよね?まだ大丈夫でしょ?」と不安げな息子。
「何が原因かわかるかな?携帯ってブルーライトが出ていて、視力も落ちるし睡眠にも影響あるらしいよ。」
「寝る前1時間はデジタルデトックスで見ない方がよく眠れるらしいよ。成長ホルモンが出て背も伸びるらしいよ。」と私が言うと
息子から「じゃあ、時間を減らせばいいよね。」と発言がありました。
息子がゲームやYouTubeしているときに、何度も「目が悪くなって、攻撃的になってしまうからやめようね。」と注意していたのですが、興奮している息子の脳には届いていなかったようです。
脳が興奮状態のときは興味のない言葉は届かないので、話すタイミングを見極めることが必要です。
子どもが落ち着いているときに「ちょっといいかな?」と話してみましょう。

その後気づきを得た息子は、友達とゲームするとき「やめる時間を決めよう。」と提案できるようになりました。(長期休みはいつもより長く使用していますが昼夜逆転にはならずに済んでいます。)
また、YouTubeの残り映像時間をみて、「あと30分もかかるから、今日はやめておこうか。」と調整するようになりました。
きっかけと気づきを与えて子どもを肯定し続ければ、自分で動けるようになります。
親からしてみれば、もう少しスマホの使用時間を短くしてほしいですが、息子の意志を尊重し、制限や禁止する言葉かけはやめました。
「ゲームやめたんだね。」「盛り上がって楽しそうだね!」と認めていくことで、親子関係も良くなっていきました。
また、部活や習い事にも積極的に取り組むようになり、必然とスマホ時間が減りスマホ依存症を脱することができたのです!
テストが終わったときや休みの日はスマホ時間が長くなることもありますが、最低限ラインのやるべきことはやるようになり、ON/OFFの切り替えができるようになりました。
息子の友達の中にはスマホを没収されてしまい、友達と遊んだり出かけたりしているときも常にスマホをいじっていたり、家族が寝静まってから夜中にスマホを使っていた子もいました。
それから、スマホ契約を解除されてしまった別の友達は、フリーWi-Fiが使用できるお店へ夜22時まで出歩いていた子もいました。
スマホ制限や没収することで、別のトラブルが発生するも否定できませんね。
我が家は一般的なご家庭に比べたら、スマホ使用時間は長いかもしれませんが、先日テスト1週間前に息子から「スマホを預かっておいて」と言ってきました。
スマホを預かった分勉強してくれるのかな?と期待もしてしまいましたが、祖父のパソコンでYouTubeをしっかりみてから、テスト勉強を始めていました。
行動制限や禁止する言葉かけは、子どもの脳には響かず反抗するだけなんですね。
みなさんも発達科学コミュニケーションで脳のはたらきを学び、子どものできることを増やしませんか?
▼▼注意力をアップさせて子どものコミュニケーション力を育てましょう▼▼

発達凸凹中高生反抗期の子育でのヒントをお伝えしています!
執筆者:神田久美子
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)