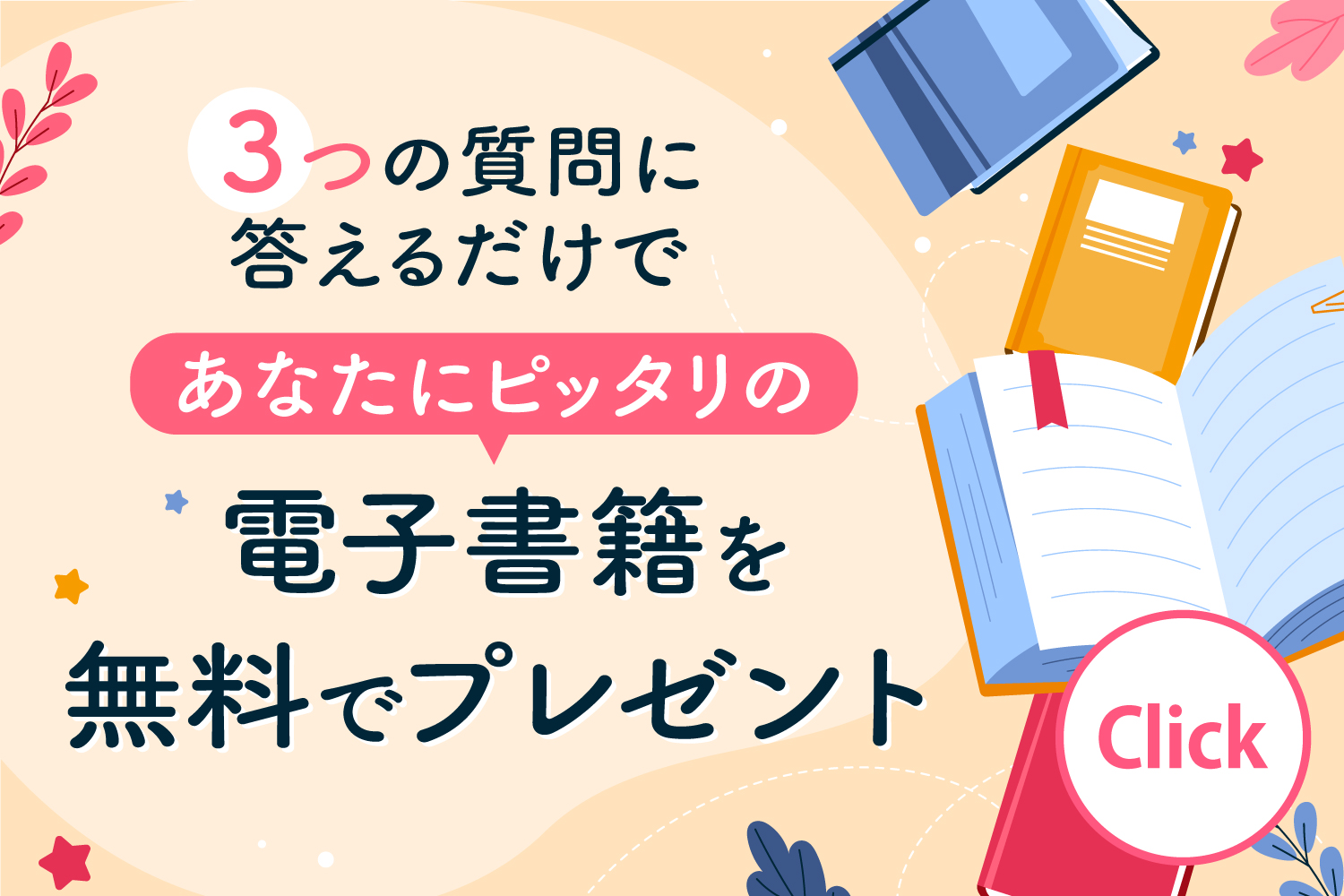子どもが連日同じ動画ばかり何度も見るのが気になりませんか?あまりの回数に病気や障害を疑うことも。しかしその行動、やめさせなくて大丈夫です!何度も見ている動画を子どもの興味を広げることに活用しましょう。その方法をご紹介します。
【目次】
1.子どもが同じ動画を何度も見る…もしや病気?障害?
2.同じ動画を何度も見る心理とは?
3.何度も見ている動画を子どもの興味を広げることに活用しよう!
①子どもが何を見ているのか観察
②動画から「好き」を発見して行動に繋げる
③子どもに役割を与える
1.子どもが同じ動画を何度も見る…もしや病気?障害?
子どもが大好きなYouTubeなどの動画タイム、気づくといつも同じ動画ばかり見ている!ということはありませんか?
実はこの行動、あまりにもこだわって見続ける場合は発達障害が関係していることもありますが、無理にやめさせる必要はなく、むしろ脳の発達に活用できるんです。
連日同じ動画を見続けるわが子を見ていると、親としては「このままだと興味や知識の幅が狭くなってしまうのでは…」と心配になってしまいますよね。
私も現在6歳の息子に対し、そう思っていた1人でした。
息子は2歳半頃から自分の見たいものを意思表示するようになっていったのですが、要求されるのはほぼ毎日全く同じもの。
別のものを見ることを提案すると、怒って拒否します。
連日繰り返し見て内容を丸々覚えているのに、毎回初めて見るようなリアクションをしていました。
その大人からするとちょっとシュールな姿に、始めは「飽きないのかなぁ…」と少し呆れる程度でした。
ところが年月が経ってもなかなか変わる気配がない様子を見て、次第に「何か変なのでは?もしかしたら、病気か障害?」と心配するようになりました。

その後息子は発達障害グレーゾーンとわかりました。
動画の繰り返し視聴は続いていましたが、動画の内容をよく記憶している息子を見て、あるとき私は「この繰り返し見るという行動を、逆に何かに使えないか?」と考えを変えました。
そして、息子の見ていた動画をきっかけに家族でおでかけをし、本人の興味や知識の幅を広げることに成功したのです!
次項からは、子どもが同じ動画を何度も見る心理と、見ている動画を活用し、子どもの興味を広げる方法についてお伝えしていきます。
2. 同じ動画を何度も見る心理とは?
◆何度も見て理解したい・覚えたい
繰り返し見るということは、子どもは見たいからその動画を見ています。
興味があるので、内容を覚えたい、自分も同じようにしてみたいという感情が湧き起こり、それが何度も同じ動画を見るという行動に現れるのです。
子どもはよく、大好きなアニメや動画で出てくるキャラクターのモノマネをしますね。
声色から間の取り方まで、また動きまでそっくりにできて感心してしまうこともあります。
あれはやはり、何度も見て研究した成果です。
モノマネ(アウトプット)するには、繰り返しの研究(インプット)が欠かせません。
・どんな登場人物が出ているか
・どんなセリフがあるか
・セリフの意味は?
・どんな声色・口調で語られているか
・どんな特徴的な動きやポーズがあるか
・話の展開はどう進むか
短い動画だとしても、研究ポイントはたくさんあります。
はたから見ると「同じことの繰り返し」に見えても、子どもたちは見続けることで新しい発見を重ねているのです。
◆同じものを見るのが安心
一方で、話の展開がわかっている方が不安な気持ちにならずに楽しめるという観点もあります。
例えば大人がホラーやミステリー映画を見る場合、次に何が起きるかわからないというハラハラ・ドキドキ感を味わうのが楽しみですよね。
ホラーやミステリーでなくても、初めて見るものに対しては「次に何が起きるんだろう?」と期待感を抱いたり恐る恐る不安を感じたりしながら見ると思います。
この不安や緊張感が、子どもにとっては楽しみというよりストレスになります。
ストーリーもセリフも全てわかっていても、「いつもと同じ」が安心なのです。
特に発達障害の子の場合、
・繰り返しの行動を好む
・こだわりが強い
という特性から、よりいつもと同じ安心感を求めがちになります。

またお話の中に決めゼリフのようなものがある場合、展開を追いながら
「このシーンがあってその後こうなって…このセリフきたー‼」
というのに快感を覚えることもありますね。
脳はわかることの方が楽しいと感じるので、知っている方を選びたくなるようにできているのです。
3. 何度も見ている動画を子どもの興味を広げることに活用しよう!
同じ動画を何度も見るというと、一見興味や知識が偏ってしまうように思えます。
しかし、その動画に関連することで何か別の「行動」につなげることができれば、子どもの興味を広げていくことができます!
その具体的な方法を、3ステップでご紹介します。
◆①子どもが何を見ているのか観察
まず、どんなものを見ているのか改めて確認します。
お母さんのタイミングが良いときに、家事の手を止めて子どもと一緒に動画を見ながら観察するのがおススメです。
子どもは自分の好きなことにお母さんが興味を持ってくれるととても嬉しいので、動画の内容について色々自分から話してくれるかもしれません。
私は「子どもが動画を見る時間=自分は家事に集中する時間」となることが多いので、子どもが何を見ているのかなんとなくしかわかっていませんでした。
しかし子どもがどんなものを楽しんでいるのか知りたいと思い直し、少し家事の段取りを調整して一緒に見る時間をとるようにしました。
◆②動画から「好き」を発見して行動に繋げる
何を見ているのか把握できたら、見ているときの子どもの様子をよく観察してみます。
動画を見ている途中、子どもの感情が高ぶる場面を見つけるのがポイントです。
良い笑顔になったり、映っているものの名前を嬉しそうに言ったり。
そこに子どもの「好き」が隠れているかもしれません。
「好き」が見つかったら、そこに関連して日常でできる行動・活動がないか考えてみます。
わが家の長男は乗り物が大好きで、乗り物関連の動画を良く見ています。
特に日本各地のその土地特有の乗り物が紹介される場面になると、とても興奮して「ぼくもこれに乗りたい!」と言っていました。
そこでお休みの日に乗り物系の博物館に行ったり、車で行けそうな距離であれば実際に乗りに行ったり、乗るのは難しくても見に行けるスポットを調べて見に行ったりしました。
◆③子どもに役割を与える
動画をきっかけに少しずつ行動ができるようになってきたら、子どもに家族の中でのその子だけの特別な役割を与えてみます。
息子は乗り物関連の動画からたくさんの乗り物やおでかけスポットをインプットしていたので、わが家の「おでかけ企画大臣」に任命しました。
そしてこの夏、家族旅行を計画するときに息子に相談したところ「奄美大島に行きたい!」と案を出してくれました。
奄美大島で
・四輪駆動探検車に乗ってアマミノクロウサギを見たい
・カヌーに乗ってマングローブの森を見たい
・水中観光船「せと」に乗ってサンゴを見たい
と、やりたいことも具体的でした。
すべてYouTubeでのインプットです。
私は息子に教わるまで「アマミノクロウサギ」なんて生物がいることも知りませんでしたし、奄美大島にマングローブの森があることも知りませんでした。
息子がYouTubeから得た情報のおかげで、家族全員でとても素敵な自然体験の旅をすることができました。
実物を見たりツアーガイドさんのお話を聞いて、
「アマミノクロウサギは夜行性なんだよ」
「車のライトが当たると目が赤く光るんだ」
と知識もパワーアップしました。

さらにこの旅行の後、息子は動物や海の生き物への関心が強くなり生き物系の動画もたくさん見るようになりました。
夏から秋にかけて、動物園・水族館にも10か所以上行きました。
図鑑も併せて動物や生き物の知識も深めています。
以前は子どもが同じ動画を何度も見ることに不安を抱いていましたが、動画をきっかけに行動や活動に繋がれば本人や家族の世界が広がっていくことがわかりました。
息子は今でも同じ動画を何度も見ていることがあります。
ですが、見て終わりではなく、おでかけ企画大臣として色々なおでかけスポットを提案してくれます。
興味の幅が広がり、「ここ行きたい!」「あれやりたい!」という積極的な発信も増え、今後の成長も楽しみです。
子どもが毎日同じ動画を何度も見るのが不安という方に、この記事がお役に立てれば嬉しいです。
わが子の脳の特性を知り子育ての悩みを解決したい方、まずは無料メールで学べます!
▼ご登録はこちらから
▼無料小冊子プレゼント▼
育てにくい子が3ヶ月で変わる!
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
↓↓↓
執筆者:諸住乃莉子
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)