夏休みに入り勉強しない子どもにガミガミ。そんな毎日に疲れていませんか? 実は「勉強しない」には、発達障害の特性が関係してることもあるんです。子どもの特性を理解し、イライラを減らしながら親子でラクに過ごす夏休みのヒントをお届けします。
【目次】
1.中学生の勉強しない子どもにガミガミ・・・もう限界!
2.勉強しない中学生は発達障害?本人も気付けない“やる気ゼロ”の理由
3.勉強ができない中学生もOK!やる気を引き出す親の関わり方と3つの工夫
①自己肯定感をあげる声掛け
②「ながら」勉強もOKにする柔軟な見守り
③好きなことを生かした学習スタイルの提案
1.中学生の勉強しない子どもにガミガミ・・・もう限界!
夏休み、朝から晩までゲーム三昧の中学生。
「先に宿題やりなさい!」と毎日ガミガミ・・・。
そんな毎日に気が付けば私自身が「中学生勉強しない息子に疲れた」と限界寸前でした。
もしかして、勉強しない中学生の息子は発達障害?
実は、勉強ができない中学生の子どもの中には、発達障害の特性が関係しているこもあります。
まずほその背景を知り、親の関わり方を変えるだけで、子どもの“やる気”と“考える力”を育てることができます!
我が家の息子は、典型的な「勉強ができない中学生」。
授業内容についていけず、わからないことばかりが積み重なっている様子でした。
とはいえ、高校受験のことを考えると焦る毎日。
つい私は、息子を無理矢理イスに座らせて、終わるまで横につきっきりで「勉強しないから、わからないんでしょ!」と叱ってました。

そして1学期が終わり待望の夏休み!・・・かと思いきや。
「宿題多すぎやねん!できるわけないやろ」とブチ切れの息子。
私も「また夏休みも子どもとバトルか」とぐったり。
こんな私が宿題バトルを繰り返さず、親子で笑顔で過ごせる楽しい夏休みを過ごすことができたヒントをお伝えしますね。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
3週間で癇癪が落ち着き
毎日が穏やかに過ごせるようになる!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.勉強しない中学生は発達障害?本人も気付けない“やる気ゼロ”の理由
「勉強ができない中学生」「中学生 勉強しない」に困っているママ。
実は、子どもが自分から勉強に向かえないのは“やる気の問題”ではないこともあります。
その原因の一つが「脳の特性」と「脳のストレス反応」です。
勉強ができない中学生は、やる気がない訳ではなく注意欠陥多動性障害(ADHD)という脳の特性が関係していることがあります。
ADHDの子どもは、集中することや情報を整理することが苦手という特性があります。
そのため、授業で聞いたことを整理できず、「わからない」が積み重なりやすくなります。
その結果、勉強がイヤになり、「やらない子」になってしまうことも。
また、勉強に対して苦手意識があると勉強することにストレスを感じ、「逃げモード」になりがちです。
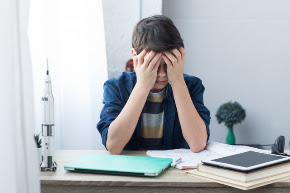
ADHDの子どもは、このネガティブなイメージが強く残る傾向にあるため、さらに「勉強しなさい!」というのは逆効果なのです。
しかし親は、「勉強しないと将来困るのはこの子なのに…」という思いからガミガミ叱ってしまいます。
だけど本当に「勉強ができれば将来安心」なのでしょうか?
実際には、勉強が苦手でも社会で生き生きと活躍している人もいれば、成績はふつうでも自分で考えて動ける子が活躍するケースもあります。
今、社会で求められているのは「正解を出す力」より「自分で考える力・心の力」です。
こうした力は、テストの点数では表せませんし、机に向かう勉強だけで身につくものでもありません。
そして、叱られてイヤイヤやる勉強では、育ちにくいのです。
私たち親が本当に望んでいるのは、「テストの点がいい子」ではなく、「困難を乗り越えて生きていける子」ですよね?
だからこそ今は、「勉強しなさい」と言うよりも、「やってみようかな」と思える土台をつくってあげることが大切なんです。
では、どうすれば「中学生勉強しない子どもに疲れた」と悩む毎日から抜け出せるのでしょうか?
次は、ママができる“ラクになる関わり方”をご紹介します。
情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!
”脳のクセ”を育て直す声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
3.勉強ができない中学生もOK!やる気を引き出す親の関わり方と3つの工夫
勉強しない中学生の息子は発達障害かも?と不安を抱える毎日から抜け出すために、親はどんな関わり方をすればいいのでしょうか?
ポイントは、ママの声かけと日常の関わり方にあります。
ここでは、勉強ができない中学生にも効く “やる気スイッチ” を押す3つの工夫をご紹介します。

◆①自己肯定感をあげる声掛け
ゲーム三昧で叱ることばかり…と感じる前に、実は日常には“できていること”がたくさんあります。
たとえば
「起きてきたね、おはよう」
「ご飯食べに来たんだね」
そんな声かけだけでOK!
思春期の子には「すごいね!」よりも、行動をそのまま言葉にする“さりげない肯定”が届きやすいんです。
◆②「ながら」勉強もOKにする柔軟な見守り
勉強に苦手意識があると、机に向かうだけでストレスです。
そんなときは、少しハードルを下げてみるといいですよ!
音楽をかけながら、ソファで単語を覚える、YouTubeで歴史の解説を観る…など、環境をゆるめることで「やってみようかな」が生まれます。
“ながら”でもOKと思えることで、自分から取り組む力が育ちます。
◆③好きなことを生かした学習スタイルの提案
子どもが好きなものには、学びのヒントがいっぱい!
たとえば、野球好きの息子はメジャーリーグ中継で自然と英語にふれる機会が増えました。
単語や発音も、勉強というより“楽しい体験”として身についていきます。
「好きなこと × 学び」で、無理なく学習につながる環境がつくれます。
親の対応次第で、「やらされる勉強」から「やってみたい勉強」へ変えていくことができます。
小さな声かけ、ちょっとした工夫から中学生の“勉強しない”に悩むママも、ラクに・前向きに夏休みを乗り切れますよ。
子どもの癇癪に困り果てているママ!対応策をご紹介しています!
執筆者:平野 可奈子
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)





