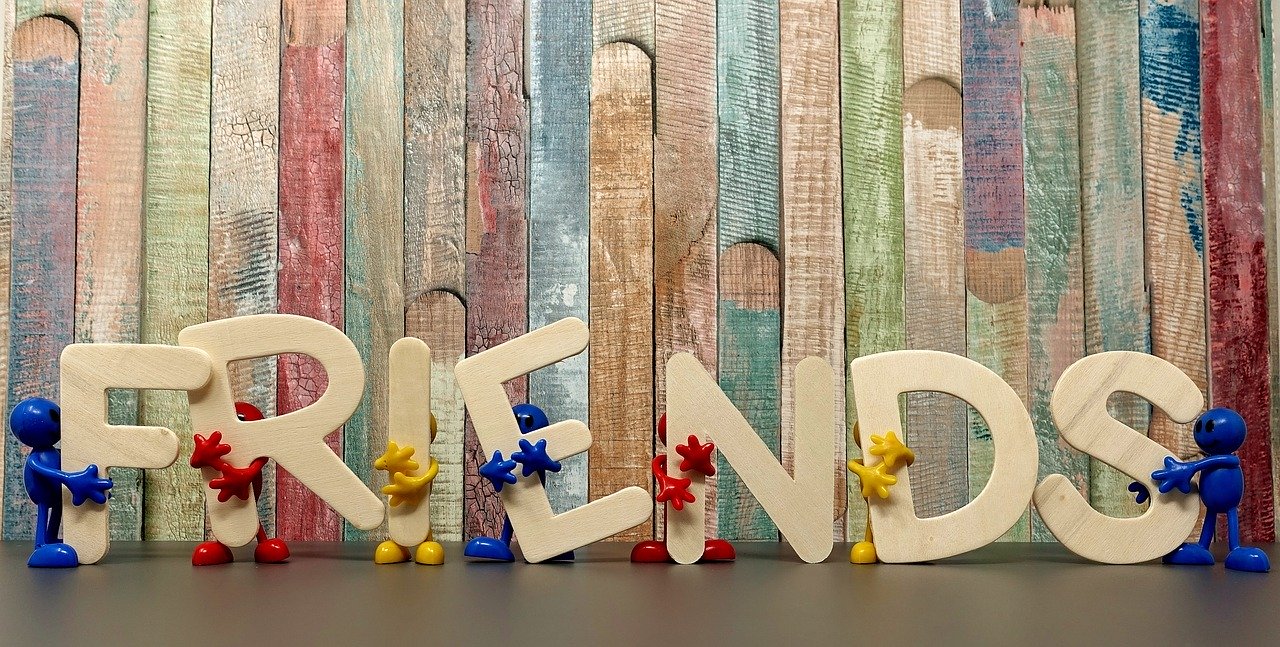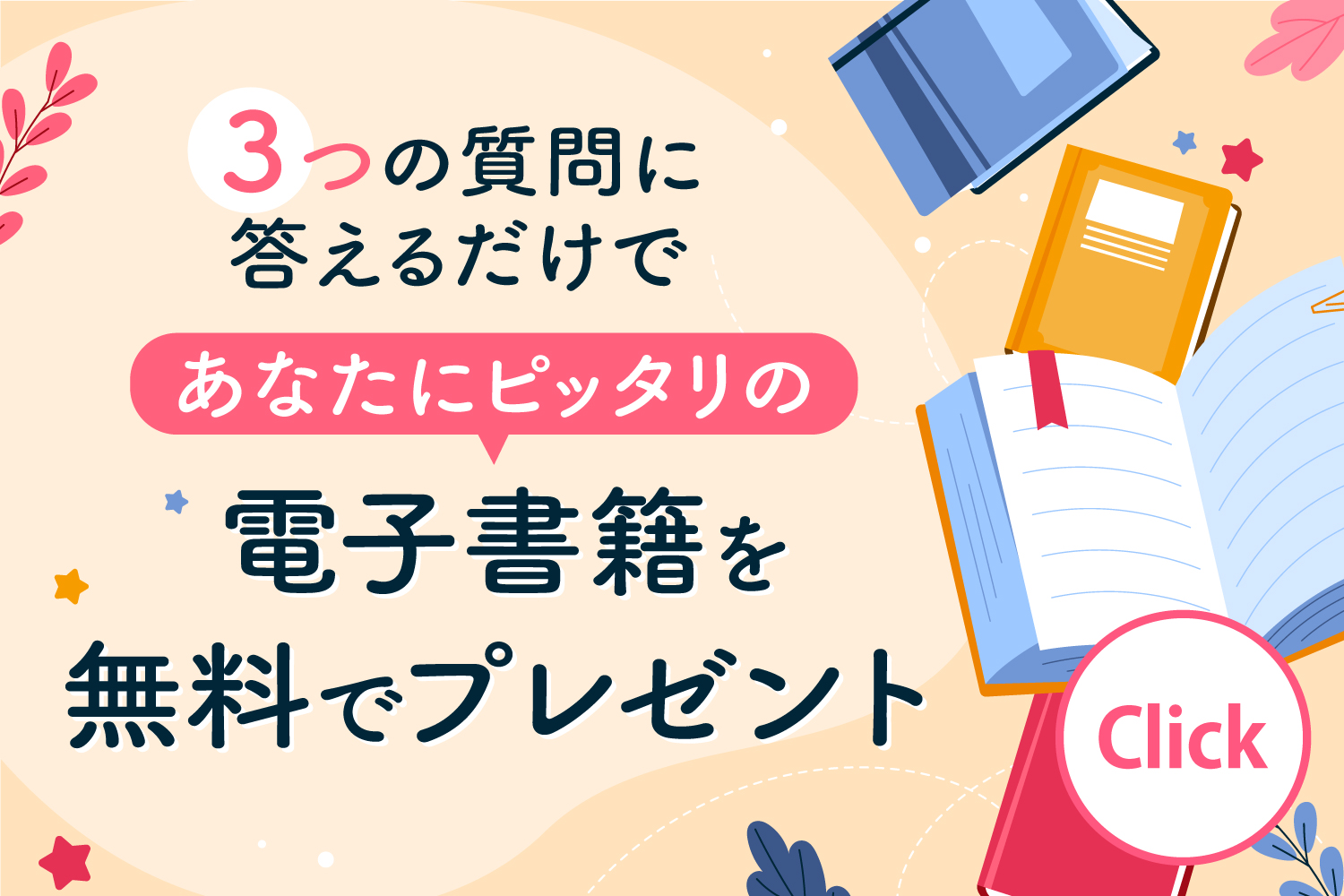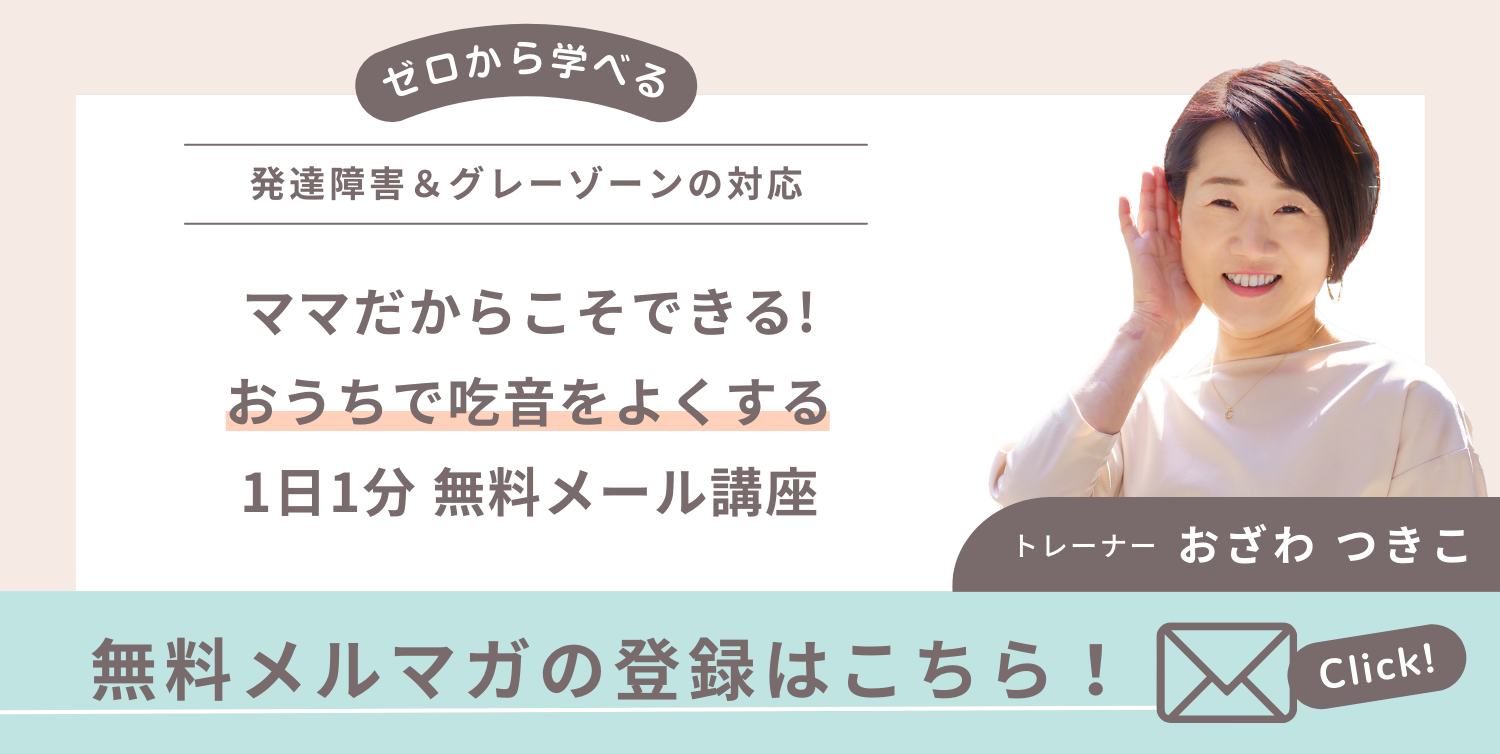小学生になると自然に友達ができると思っていたのに、子どもに発達障害があって友達がいない!と心配しているママはいませんか?特に自閉症傾向の子は社会性が乏しく人との関わりが苦手。そんな特性のある子どもの友達作りの解決法、お伝えします!
【目次】
1.「特定の友達がいない」と心配していませんか?
2.発達障害ASDタイプの子に友達ができない理由
①人との関わり方が苦手
②コミュニケーションが苦手
③想像力が乏しい・こだわりがある
3.どの本にも載っていない!自閉症タイプの子の友達の作り方
◆ステップ1:「〇〇」が子どもの初めての親友になる
◆ステップ2:お友達を家に招待する
1.「特定の友達がいない」と心配していませんか?
私の娘は小学4年生。発達障害自閉症スペクトラム(ASD)グレーゾーンです。
さかのぼること保育園時代。個人面談で担任の先生から
「クラスの中で女子グループができているのですが、娘さんはどこにも属していません。お母さんは、どうお考えですか?」と言われました。
そのときは「そんなこと言われたって、どうしたらいいの?」と不安になりました。
時が流れ、小学校に入学してからも娘は特定の女子グループに属することはありませんでした。
休み時間は一人で過ごし、クラスの子達とは先生を介して関わることが多かったようです。

ただ、先生の目には友達関係で悩んでいる様子もなく、マイペースに学校生活を送っているように見えていたそうです。
母親としては特定の友達がいないことは心配でしたが、本人が気にする様子もなかったので「本当に一人が好きなんだな」とありのままを受け入れるようになっていました。
そんな小学2年生のクリスマスの頃。土曜授業を終えて、自宅で昼食を食べていた娘が突然、
「これから〇〇ちゃんと〇〇ちゃんが家に来るから。」
と言い出したのです。 その数分後、本当にお友達がお母さん方とお茶菓子をもって現れました。
この日をきっかけに3人の関係は3人の仲良しグループに変わっていきました!
今日は、発達障害ASD グレーゾーンの子どもに友達ができにくい理由を紐解きながら、友達のいなかった娘がどうやってお友達を作ることができたのかご紹介します。
子育てのお悩み解決BOOKプレゼント中!
↓↓
2.発達障害ASDタイプの子に友達ができない理由
発達障害は自閉症に限らず、診断名がついていたとしても症状は様々です。
特に、自閉症タイプの場合、知的な遅れがある子から知的に非常に高い子、言葉の遅れがある子から言葉の発達が早い子など、かなり症状の幅が広く、友達ができない原因も様々です。
タイプ別にするのは難しいのですが、強いて言うならお子さんはどのタイプでしょうか?
ひとつひとつ見ていきましょう!
◆①人との関わり方が苦手
相手の気持ちや状況を考えないで、マイペースに行動してしまうため、「社会性がない」と言われてしまうことがあります。
遊びの中でも、飽きたり、興味がなかったりすると、途中で勝手に遊びから抜けてしまったり、自分が決めたルールを友達に強要してしまうなど、「自分勝手」「わがまま」と思われることがあります。

◆②コミュニケーションが苦手
発達障害自閉症タイプの子どもの中には、言葉の発達が早い子と遅い子がいます。
言葉の発達が早い子は、
・よく話すけど、自分の言いたいことだけを話してしまう
・思いついたことをそのまますぐに口に出してしまう(空気がよめない)
・思いついたことをそのまますぐに口に出してしまう(空気がよめない)
こんな傾向があります。
また、難しい言葉や漢字表現、英語表現を好み、大人びた言い方ややけに丁寧な言い方をして場にそぐわない話し方をしてしまうこともあります。
さらに、冗談や比喩はわかるけど、皮肉がわかりにくく友達からの皮肉を受け止められず、一層相手をイラつかせてしまうこともあります。
言葉の発達が遅い子は、会話がコロコロ変わる「女子トーク」についていけず、1人困りながらもその場にいて、実は苦しんでいるということもあります。
◆③想像力が乏しい・こだわりがある
想像力が乏しいので、友達の表情から気持ちを読み取ることや、場の雰囲気を察することが苦手です。
また、言われたことを表面的に受け取りやすく、言葉の裏の意味を理解しにくい傾向もあります。
こだわりがある子は、「ごっこ遊び」やストーリーのある物語は作れるのですが、パターン化しやすく、決まりきった言動が多くなりがちです。
自分のルールを友達にも押し付けてしまうので、遊びが成立しにくいこともあります。
娘の場合、どのタイプにも当てはまるところがあります。
けれども、果たしてそれは娘だけでしょうか?
きっと定型発達の子どもでも、社会性が未熟な小学生はみんな大なり小なり同じような困りごとがあるはずです。
発達障害、自閉症タイプの子どもの場合は特に、社会性や協調性を発揮する脳の発達が遅れることが多いので、子どもの頃は同年齢の子よりも、人間関係を築くのが少し出遅れてしまうかもしれません。
しかし、私は娘の脳が発達し、気のあう友達さえ見つかれば、きっと親友とよべる関係を築けるだろうと信じていました。
そこで、私がしたことは2つです。次の章でご紹介しますね。
発達グレーゾーンの困り事を
大人に持ち越さない
親子のコミュニケーションがわかります
↓↓↓
大人に持ち越さない
親子のコミュニケーションがわかります
↓↓↓
3.どの本にも載っていない!ASDの子の友達の作り方!
では、友達のいなかった娘に、私がお家で実践した2つのことをご紹介します。
◆ステップ1:「〇〇」が子どもの初めての親友になる
まずは、「ママ」が子どもの親友になる、ということ。
自閉症の特性がある子どもは、自分のペースで、自分の好きなことをすることを好む傾向があります。
ですから、子どもがだれかと一緒に遊ぶ、他者と気持ちを通わせることの楽しさを十分経験することが大切です。
まずは、ママが一番多く子どもと会話を重ねて欲しいと思います。
そして、いい話ばかりじゃなく、時にはママの間違いや失敗も子どもにみせてあげてください。
「ママね、今日までに終わらせなきゃいけない仕事をすっかり忘れて大ピンチだったんだよ~。焦ってもうパニックになりそうだったけど、〇〇さんが手伝ってくれてなんとか間に合ったんだ。」
など、ママの失敗談にプラスしてどうやって攻略したかも伝えてください。
子どもはこのような会話を通じて、困ったことや失敗したことの解決策を知ると同時に、ママに話してもいいんだ!と理解して、何かあれば相談してくれるようになります。
ですから、子どもが失敗や悩みを打ち明けてきてくれたときは大チャンス!
「そっか~。それは焦ったよね~。」と共感し
「話してくれてありがとう。」と子どもの行動を認め
「困ったときは誰かに助けを求めればいいんだよ。」 と、どうしたらいいかを提案する。
「話してくれてありがとう。」と子どもの行動を認め
「困ったときは誰かに助けを求めればいいんだよ。」 と、どうしたらいいかを提案する。
子どもの話した内容をジャッジせず、まずは話してくれたことを肯定的に受け止める、さらっと次の攻略法も教えてあげてくださいね。
親友って、楽しいことを共有するだけではなく、時にはお互いの悪いところを指摘しあったり、励ましあったり、すべてを受け入れる関係ですよね。
まずは親子で「なんでも話せる」そんな親友のような関係を作ってください。
話すのが苦手な発達障害の子どものコミュニケーション力の伸ばし方がわかります▼▼

◆ステップ2:お友達を家に招待する
私が妊娠中だったときのこと。
ふと買い物に立ち寄ったお店の店長さんが、私の大きくなったお腹をみて、
「女の子かな?大きくなったら友達を家に呼んで遊ばせなさい。そうしたら友達がいっぱいできるよ」
とアドバイスしてくれたことがありました。
当時は、不思議な人というか、「怖い!何この人!」と思っていました。
しかし、私が娘に友達がいないことを悩み始めたときに、ふとその言葉がよみがえってきたのです。
そして「もしかしてあのおじさんは予知能力か何かがあるのかもしれない!?」と、娘にことあるごとに提案をしていました。
「友達ができたらお家に呼んで遊んでいいからね」
「お友達と一緒にお家で遊べたら楽しいよね」
「お友達と一緒にお家で遊べたら楽しいよね」
そんな風に日頃から娘に伝えていたその結果が、あの2年生のクリスマスの頃に現実になったのです。
つまり…
ステップ1、ママと友達になってコミュニケーションの経験を積む
ステップ2、ママ以外と関わりをもってコミュニケーションの経験を積む。
2年生になると、登校時間が同じというだけの接点で、違うクラスの友達とも毎朝一緒に通学するようになっていました。
あとから分かった話ですが、クラスも学童も異なる3人だったので、娘が家に招待するまではそれほど深い仲ではなかったようです。
でも、あの日を境に親同士の交流も生まれ、3人の仲良しグループができました。
いかがでしたか?
家庭でママが子どもの親友になれば、社会性やコミュニケーションスキルを自然と教えることができます。
そして、頻繁にではなくても、お友達を家に招待してあげることで友達関係を深めるきっかけが作れるのです。
ぜひ一度、お試しください!
ママとの会話でASDキッズのコミュニケーションスキルがグングン伸びる方法をご紹介しています
執筆者:おざわ つきこ
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
(発達科学コミュニケーショントレーナー)