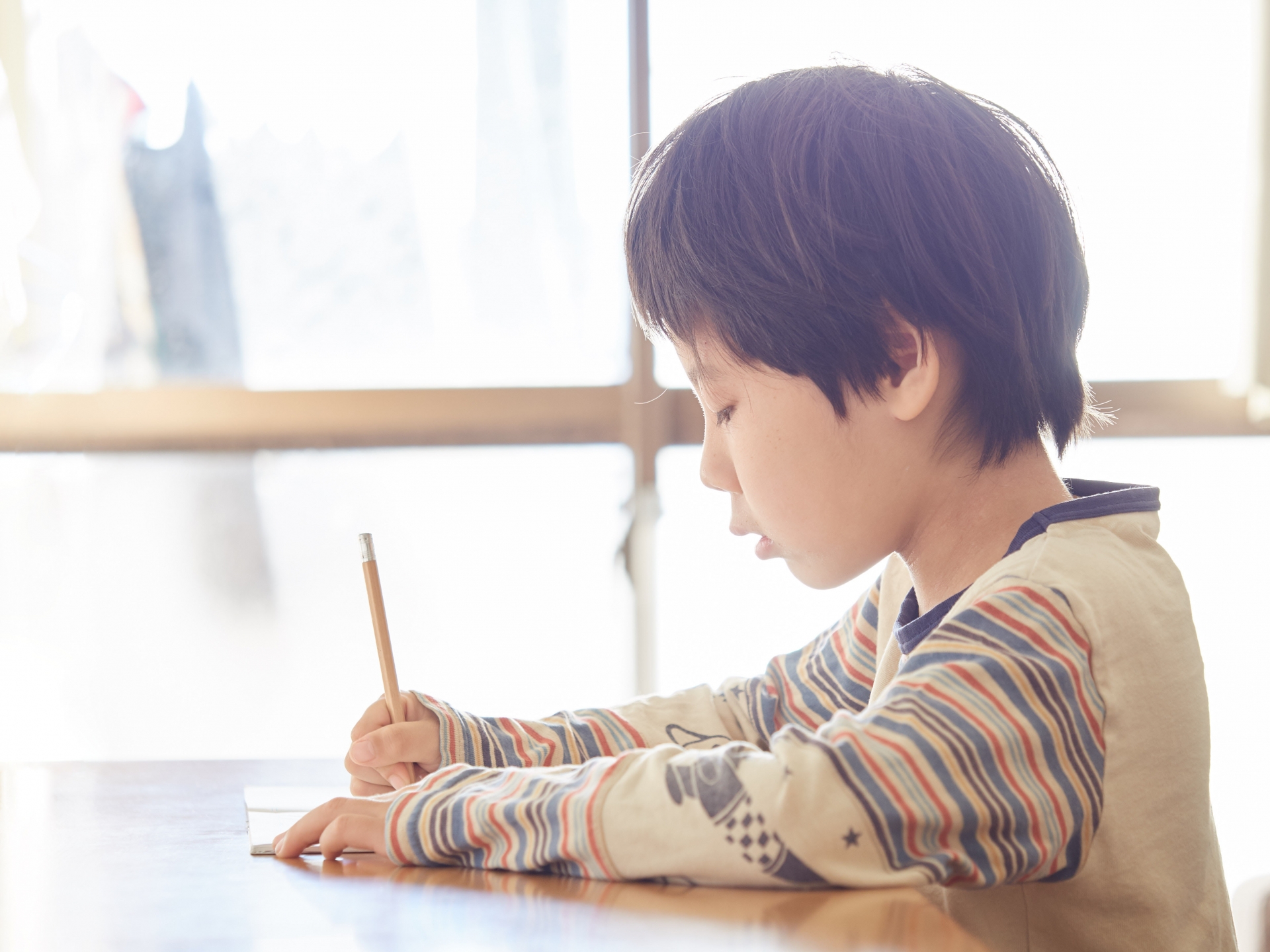| 発達障害・ADHDグレーゾーンの子どもには、リビング学習が合うのでしょうか。それとも学習机でしょうか。片付けが苦手な発達障害・ADHDグレーゾーンの子どもが集中して勉強できる環境の整え方をお伝えします。 |
【目次】
1.息子が小学生になりリビング学習に憧れた私
2.発達障害・ADHDの子どもが勉強に集中できない理由はリビング学習にあり⁉
3.発達障害ADHDタイプの子どもが集中できるようになった学習机のメリット3つ
◆①学習専用スペースのため、勉強道具は出しっぱなしでもよい!
◆②広い学習スペース
◆③学習机の大収納でかんたん片付けスペースが確保できたこと
1.息子が小学生になりリビング学習に憧れた私
新年度が始まり、宿題が本格的に始まったお子さんも多いのでは無いでしょうか。
数年前から流行りのリビング学習。小学校低学年のお子さんがいらっしゃるご家庭では、取り入れている方も多いかと思います。
リビングという学習環境ならば、毎日の学習習慣をつけるためにお母さんが見守るなかで勉強させることができます。
さらに、お子さんのやる気が出ないときや、わからない問題があった時にすぐにフォローができるというメリットがありますよね。

リビング学習の理想の姿、ちょっと想像してみましょう。普段過ごすリラックスしやすいリビングのダイニングテーブルで、お母さんに見守られながら勉強開始。
勉強にだんだんと集中してくる、我が子。わからない問題が出てきたら、気軽にお母さんに質問、そしてお母さんはそれに優しく答えて勉強が進む。
集中が途切れたら、お母さんとちょっと会話を楽しんだりして、リフレッシュしたらまた勉強に戻っていく我が子。
そのうち勉強が好きになってきて、だんだんと決めた時間になったら、自分から宿題を始めるようになる…
そんな想像をしていたのは、何を隠そうワタクシ、でした。
2.発達障害・ADHDの子どもが勉強に集中できない理由はリビング学習にあり⁉
リビング学習の合い言葉はズバリ、「リラックス」です。
ところがお子さんの性格や特性によっては、そのメリットがそのままデメリットになってしまうこともあるのです。
特に発達障害・ADHD傾向のある子どもたちは周囲の環境が大事。
・視界に何か入ると集中できなくなる
・まわりの雑音が気になり集中できなくなる
というように、その子が集中できない原因があるはずです。そんなときはお子さんの様子を観察して対応を変える必要があるのです。
また、別の面でのデメリットもあります。
それは宿題に使った勉強道具の片付けです。
発達障害ADHDグレーゾーンの場合、片付けが苦手なお子さんは多いのでは無いでしょうか。
リビング学習では多くの場合宿題の時間は夕飯前。勉強の場所をダイニングテーブルとしていると、夕飯ができたら途中でもかならず片付けなければなりません。

そして、ADHD傾向の子どもは不注意傾向があるので勉強に必要な道具をすべて、宿題を始める前に準備しておくことが難しく、宿題の途中で道具を取りに行くことも頻繁に起こります。
そういったことが続くことで取りに行く間に別のものに注意がそれてしまうことも勉強に集中できない理由となってしまうのです。
実際のところリビングのダイニングテーブルという学習環境は我が家ではデメリットしかありませんでした。
3.発達障害・ADHDタイプの子どもが集中できるようになった学習机のメリット
そこで、我が家では学習机を採用することにしました。置き場所は親が見守れるように、リビングにひと続きの和室に設置しました。
片付けが苦手な発達障害ADHDグレーゾーンの子どもにとっての学習机のメリット3つをご紹介します!
◆①学習専用スペースのため、勉強道具は出しっぱなしでもよい!
もちろん、「すべてきっちり一人で毎回片付ける」これができたら最高です。でもちょっと待ってください!片付けが苦手なお子さんにとって、これはとーってもハードルが高いことなんです。
苦手だからこそできるようになって欲しい、という気持ちはわかりますが、苦手を伸ばすのはスモールステップで徐々に。なおかつ楽しめる方法で!が鉄則です。
お片付けが大の苦手なら、保留にできる場所の確保も手段の一つです。
◆②広い学習スペース
これ、以外と盲点だと思うのですが、発達障害ADHDタイプの子どもは不器用、という特性があることが多いのです。
つい腕が当たって、消しゴムや鉛筆、ふで箱が床に落ちてしまう。教科書や、辞書やノートやいろんなものを広げるのにスペースが必要で、狭いスペースに上手く重ねて広げる、といったことが苦手だったりします。
ダイニングテーブルほどではなくとも、ある程度広めの机が勉強しやすいと思います。
◆③学習机の大収納でかんたん片付けスペースが確保できたこと
日本の学習机あるあるで、学習机って収納スペースがたくさん確保されてますよね。
小学生にもなると所有物がものすごく増えます。
その子の持ち物のほとんどをまとめて収納できる、というメリットもありますし、なにより勉強で使う道具がすぐ手の届く場所にあり、座ったまま辞書など手に取れて、しまうのも座ったままできます。
鉛筆削りも手を伸せばとれる、教科書も座ったまま取れる場所にあり、
すべてがラクに手に取れる
ということも注意を勉強からそらせること無く続けられるメリットでもあります。
コンパクトな学習机もたくさんありますが、片付けが苦手な発達障害ADHDタイプの子どもには、ある程度広めの学習机がオススメです。
このように、我が家の場合はリビングから目が届く学習机が最適な学習環境でした。

お子さんの性格や特性に合わせた勉強に集中できる学習環境づくりができたらいいですね。
学習机のメリット3つ、参考になれば幸いです。
執筆者:広路貴代江
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)