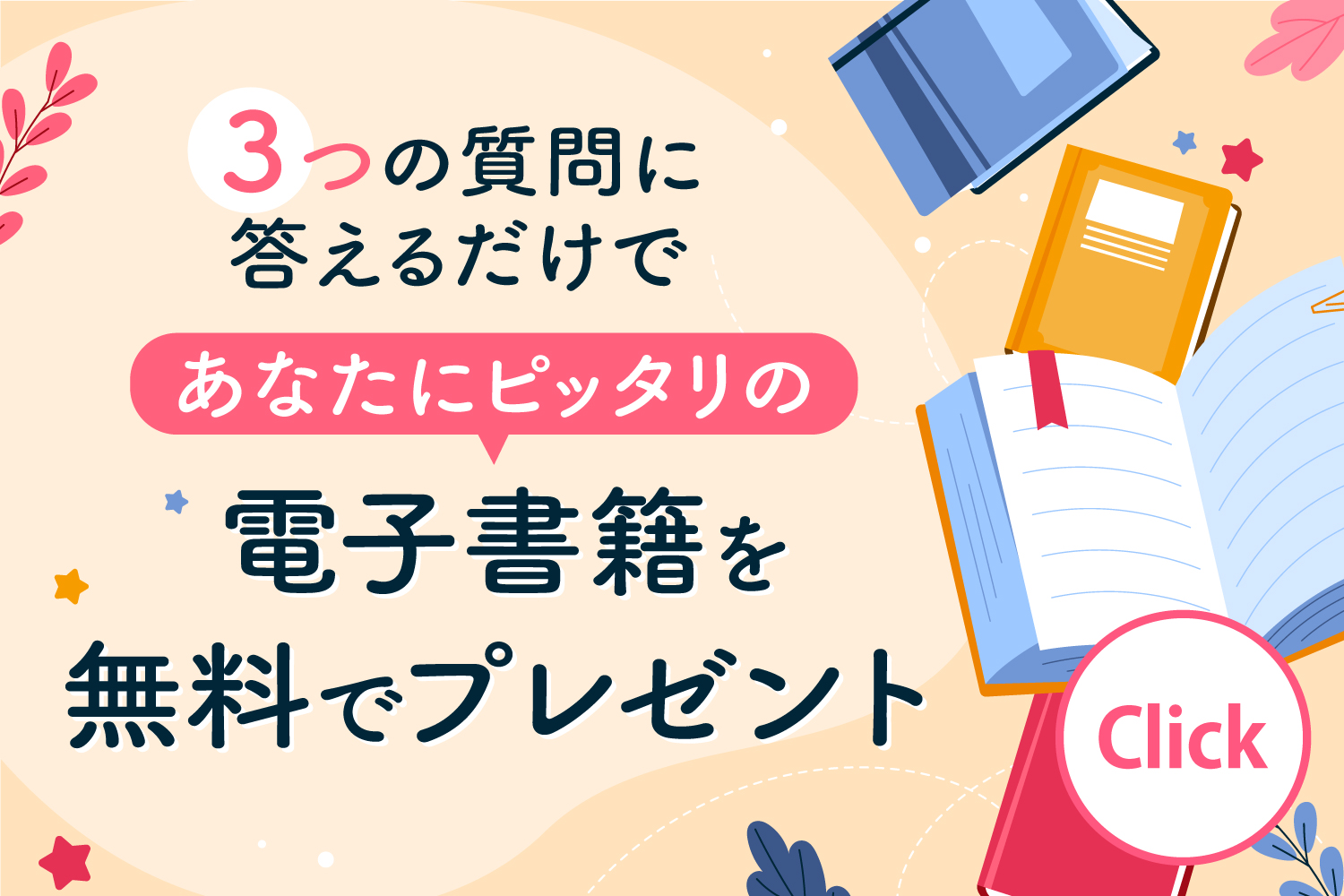発達障害ADHDタイプの息子は、毎日連絡帳が書けません。連絡帳を書かないため、宿題の内容、明日の時間割や持ち物が分からず、忘れ物をして先生から注意されてばかり。どのように支援すれば、連絡帳が書けるようになるのでしょうか?
9歳・男の子のママ

我が家の発達障害ADHDタイプの息子も、連絡帳が書けず、忘れ物の多さから先生に注意されていました。しかし、息子の特性を理解し工夫したことで、連絡帳を書くことを習慣化することができました。そんな我が家の実例を参考にしてみてくださいね。
発達科学コミュニケーション
リサーチャー 依川晴美
【目次】
1.連絡帳を書かけなくて、NG対応をしていた過去
2.発達障害ADHDキッズが連絡帳を書けない理由
3.連絡帳が習慣化できた3つの工夫
◆連絡帳を書くと、良いことあるなと子どもが感じる声かけ
◆ご褒美の導入でやる気をあげる!
◆学校にいるときの支援の工夫
1.連絡帳を書けなくて、NG対応をしていた過去
発達障害グレゾーンキッズのお母さんで「子どもが連絡帳を書いてこない!」とお悩みの方は多いですよね。
連絡帳を書くことは、大人にとってはとても簡単なことのように感じるかと思います。
ですが、実は発達障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)の子どもにとっては、難しい課題がいくつもあります。
連絡帳を書くことを習慣化させるには、周囲の工夫や支援が必要になることがあります。

普通は、連絡帳を書き忘れて帰ってきたら、子どもを叱りますよね。
「ちゃんと書かせて帰らないと、忘れ物をしてばかりでこの子が困るから」
「当たり前のことはきちんとできるようにさせたい」
そんな想いから、良かれと思って注意をされていることと思います。
過去の私も先生に叱られないように、連絡帳を書いたかどうかチェックしていました。
学校から帰ったあとに、わざわざまた学校に戻らせて、翌日の時間割を聞きに行かせたこともありました。
「連絡帳を書かないとかえって面倒なことになる」と子どもに思わせようとしたのです。
けれど、そんなことをさせても全く連絡帳を書くようにはなりませんでした。
それどころか、忘れ物をしてたびたび先生に注意され、家では毎日お母さんに叱られて。
子どもがどんどん自信を失っていくという負のスパイラルに陥っていったのです。
2.発達障害ADHDキッズが連絡帳を書けない理由
どうして、発達障害ADHDキッズは連絡帳を書けないのでしょうか。
どんな困りごとを抱えているのか、という視点でお話していきますね。
まず、机の中から連絡帳を見つけられない場合、見る力や注意力が弱いことが原因のひとつとして考えられます。
探し物をしていて、目の前にあるのに見えていないなんてことはありませんか?
見る力が弱いと、たくさんの教科書の中から連絡帳だけを探すことに難しさを感じます。
次に、書くタイミングが分からないという場合は、連絡帳を書く時間だと気が付かずに別のことをしている可能性があります。
これは過集中といって、定型発達の子ども以上に自分の興味や関心があることに集中しやすいという特性のひとつです。
夢中になるのは良いことですが、学校という集団行動が必要な場所では、切り替えが必要な場面もありますよね。
みんなで一斉に黒板の時間割を写す方法だと、やっと気が付いて書き始めても、消されてしまって書ききれないことも。
そもそも、書くのが面倒くさいと言う場合は、興味の幅が狭く、連絡帳を書いて帰ることは重要だという認識が子どもに全くないということも考えられます。
これらは、発達障害ADHDタイプの特性としてみられるもので、連絡帳を書くという行動の習慣化を困難にしているのです。
子どもが出来ていないことをできるようにするためには、叱って言い聞かせるよりも効果的な方法があります!
連絡帳を書けない発達障害の子どもへの工夫を3つお伝えします。
3.連絡帳を書くことが習慣化された3つの工夫
◆連絡帳を書くと、良いことあるなと子どもが感じる声かけ
まずは、子どもの意識の中に、連絡帳を書くのは重要だ!と意識付けすることが大切です。
叱ることより効果的なのが、肯定の声かけです。
「今日は連絡帳を書いて帰ったね」
「とても読みやすく書けたね」


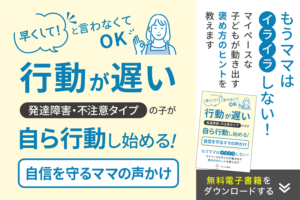
「明日のことが分かるって良いね、安心だね」
など、肯定的に声をかけ連絡帳を見ながら一緒に準備をしましょう。
たとえ全部書いていなくても、字が汚くても、何か言いたくなる気持ちをグッと抑えて、できているところを見つけて伝えてあげてください。
最初は、ほめるところなんてない!と思うかもしれません。
けれど、状況をそのまま言葉で伝えるだけでも肯定の声掛けになります。
ぜひ、〇〇しているね、という声かけをはじめてみてくださいね。
お母さんが優しく一緒に準備してくれた、ということが子どもにとって「よかった」と思えるきっかけになるはずです。
まずは一旦叱るのをお休みして、肯定の声かけを意識してみてくださいね。

◆ご褒美の導入でやる気をあげる!
ご褒美があるとやる気がでるのは、大人も子どもも同じですよね。
我が家のご褒美は
5回(毎日)書けたら…週末ゲーム時間1時間
4回書けたら…週末ゲーム時間30分
3回書けたら…週末ゲーム時間15分としていました。
4回書けたら…週末ゲーム時間30分
3回書けたら…週末ゲーム時間15分としていました。
ゲームが大好きな子どもなので、ゲームを使ったご褒美で、連絡帳を書くことを意識させるように工夫しました。
書けた日はカレンダーにシールを貼るなどして、目に見える形で意識付けをしていきます。
書けなかった日も叱らず、諭さず、書いてきた日だけほめるという対応がポイントです。
書けない日も「そっか、そんな日もあるよね。」と連絡帳に対し、ポジティブなイメージを保てるような声掛けをしましょう。
連絡帳を書けたときはお母さんが笑顔で褒める!この笑顔に勝るご褒美はありません。
◆学校にいるときの支援の工夫
連絡帳が見つからないことへの工夫については、連絡帳をランドセルのポケット部分に入れて目に付くようにし、子どもが気付きやすいようにしました。
さらに、連絡帳を書くタイミングを逃すことへの工夫としては
・机の隅に「連絡帳を書く」というメモを貼る
・連絡帳を書いているかを気にかけてもらうことを先生に依頼(先生もお忙しいので、できる範囲でのお願いです。)
さらに連絡帳を書くことが面倒な場合は、書くことをなるべく少なくする工夫が効果的です。
小さくコピーした時間割を挟んでおき、その時間割と違う部分のみ書くというスタイルにしてみたこともあります。
コピーした時間割と同じ教科のところは「〃」もしくは「空欄」でOKにしました。
これらの工夫で子どもを支援し、学校での困りごとを減らしていきました。

3つの工夫を根気よく続けるうちに、今では連絡帳を書くことがきちんと習慣化されました。
黒板を消されるタイミングに気付いて「ちょっと待って!」と言えるようになったほどです。
また、ときには連絡帳の内容を覚えて帰ってくるという日も見られるようになりました。
子どもが 明日の予定を把握することへの意識を持てるようになったと実感しています。
発達障害ADHDキッズが連絡帳を書けるように工夫して、お子さんの自信につなげてあげたいですね!
ゲーム好きな子どもと上手に付き合う方法はこちら↓↓
▼子どもの自信を守る声かけはこちらから!▼
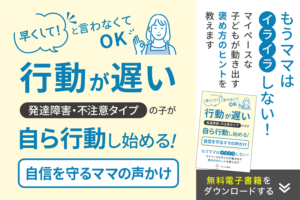
子どもの困りごとを解決して明るい子育てにシフトチェンジしましょう!
▼ご登録はこちらから
▼無料小冊子プレゼント▼
育てにくい子が3ヶ月で変わる!
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
↓↓↓
執筆者:依川晴美
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)