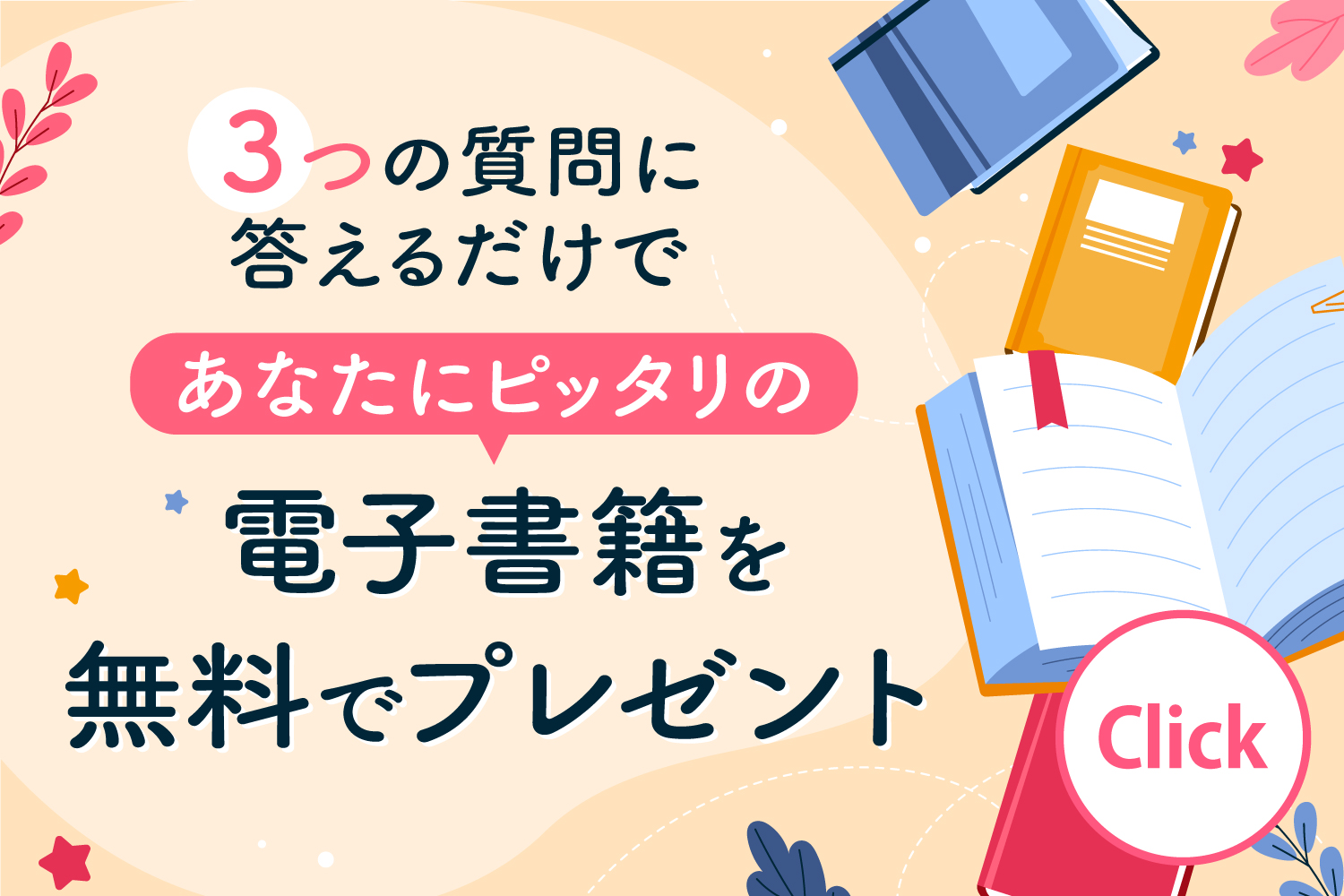| 発達障害の子どもが初めての経験や苦手なことを心配しすぎて行動できない、なんてことはありませんか?発達障害の子は不安が強く、やる前から先のことを心配して尻込みしがち。そんな不安の強い子どもの心配しすぎを解消する方法、お伝えします。 |
【目次】
1.不安が強い発達障害の子どもはなにかと心配しすぎ?
2.発達障害の子どもの不安が強い原因とは
3.不安が強い子どもに絶対やって欲しい対応
4.子どもが「挑戦してみよう!」と思える作戦
◆気持ちを吐露させる
◆不安の見える化
◆ワクワクする挑戦で成功体験を積む
1.不安が強い発達障害の子どもはなにかと心配しすぎ?
発達障害、特に自閉症スペクトラム症(ASD)の傾向がある子どもが不安が強く、心配し過ぎなんてことはありませんか?
大人にとっては「そんなことが心配なの?」と思うようなことも気にして行動にうつせないことがあるかもしれません。
わが家のASDタイプの娘も、まだ起きていない先のことを心配しては行動できずに固まってしまうことがよくあります。たとえば…
今度、病院で検査をしてもらわないといけない
体育の授業で体力測定がある
新しく外国人の英語の先生がくることになった
体育の授業で体力測定がある
新しく外国人の英語の先生がくることになった
など、いつもとは違う新しいことや、本人が苦手だなと感じることは、一気に不安におそわれます。

大人からすると病院受診して検査するだけ。
体育で体力測定があるだけ。
新しい先生が来るだけ。
ですから、大人はつい「大丈夫よ」とか「心配し過ぎよ!」などと言ってしまいがちです。
しかし、子どもの心の中は不安でいっぱい。 ママの言葉もすんなりと受け入れられないのです。
一体、どうしてそんなにも不安になってしまうのでしょうか?
2.発達障害の子どもの不安が強い原因とは
発達障害の子どもは、予測できないことや、初めての経験に対して面白そうとかワクワクするといったポジティブな反応はなかなか起きてきません。
これは、神経伝達物質であるセロトニンの影響が大きいといわれていますが、脳の特性によって、大丈夫かな、心配だなといったネガティブな反応がなにより先に起きてしまうのです。
さらに、先のことを想像するのが苦手で予測が立てられないため、気持ちの準備ができないことも原因となっています。

そのため、子どもは不安や心配ばかりを大きくしてしまい、「やってみても出来ないかもしれない」「だめかも!」と行動を起せなくなってしまうのです。
すると、日々決まったスケジュールをこなすことはできても、新しい出来事には拒絶反応を示すようになってしまいます。
これが、こだわり行動として定着してしまうと余計に行動できなくなって厄介ですよね。
では、そんな子どもの不安からくる心配しすぎに、どんな関わり方をしていけばいいのでしょうか?
3.不安が強い子どもに絶対やって欲しい対応
不安になりやすい原因が脳の特性の1つとすると、不安にならないで!心配しないの!と言っても無理なこと。
まずは、子どもの不安に寄り添って、気持ちを理解してあげることが大事です。
私も娘に「不安だよね~」とぎゅ~っと抱きしめて共感する対応はずっと行っていました。
ただ、子どもが感じている不安がこれで解消できるのか?というと…実は、どこかへ消えてなくなったりはしていないのです。
むしろ、ママも分かってくれるんだ!と自分の感じた不安を肯定されたかのようにとらえ、さらに不安が強くなる子もいます。

もちろん、理解して共感することは大事です。
しかし、それだけでは子どもが新しいことに立ち向かって次の行動をする気持ちにはなかなかなれないのです。
いつまでたっても怖いからやらない、ママ助けて~ではモヤモヤしてしまいますよね。
4.不安が強い子どもが「挑戦してみよう!」と思える作戦
わが家では、子どもの不安を解消して、新たな行動にうつすために子どもと一緒に作戦を立てています。いくつかご紹介しますね。
◆気持ちを吐露させる
何か不安なことがあっても、その気持ちを言葉にすることって意外と難しいですよね。
けれども、そんな気持ちを少しでも吐き出すことで、どんな気分だったのか、何が心配だったのか、子ども自身が気持ちを整理することができます。
ですから、子どもが少しでも気持ちを吐き出させやすいように
初めての検査って緊張しちゃうよね?
体育館、ざわざわして音がうるさくなかった?
新しい英語の先生、優しそうな先生だった?
と、まずはイエス・ノーで返答できる質問をしてあげてください。
そして 「うん、少し緊張したよ」という返事から、少しずつ子どもの気持ちを引き出せるような会話をしてあげましょう。
すると、子どももただ不安だと感情的になるのではなく、冷静に受け止められる余裕がでてきます。

◆不安の見える化
次に、これから起きることがわからないで心配し過ぎてしまう…ならば何が不安なのか、どうしたらいいかを子どもに分かるように伝えます。
例えば、病院での検査はこんなことをするよと、検査する機械の画像や、動画を見せて説明するのです。
こういう機械の中に寝っ転がってたら終わるんだよ。
いろんな音が聞こえてくるけど、痛くないからね。
すると、ただ怖い!と思っていた検査も、前もって確認することで何をされるのかがわかるので、検査当日には「あ、これ前に見たやつ」と気持ちに余裕をもって受けられます。
学校の行事などは前もって情報をもらったり、直接先生からも説明をしてもらうようにしました。
紙に描きながら説明したり、写真や動画を使ったりして説明するとより具体的で伝わりやすいですね。
これは、不安を見える化するということ。
何も情報がなかったときと比べて子どもが想像しやすくなり、行動することへのハードルが下がっていきます。
◆ちょっとした経験で成功体験を積む
だれでも苦手なことはやりたくない。けれども興味があることなら、ちょっと怖いけどやってみたい、そんなことはありませんか?
そこでおすすめなのが、子どもの興味のあることに関連させて小さなチャレンジを促してみることです。
例えば、
・料理好きな子には、作ったことがないメニューにチャレンジしてみる。
・本が好きな子には、欲しい本を買う時には自分で支払いをしてみる。
など、興味のある、好きなことをやるタイミングでちょっと頑張ったらできることをやらせてみるのです。
このときのポイントは、無理強いはさせないこと。 ちょっと頑張れはできるという提案をしてあげてくださいね。
すると、やってみたらできた!という成功体験を積むことができ、それが子どもにとって自信となり次にチャレンジする意欲につながってきます。

いかがだったでしょう? 気持ちを吐き出し、その不安を分かりやすく見える化する。
さらに、小さな成功体験を少しずつ積み重ねることで、不安が強い発達障害の子どもが自分で自信をつけることにつながってくるのです。
子どもは成長していくにつれて、親の助けなしにやらなければいけないことがたくさんでてきます。
そのときに、いろいろな経験が子どものやる気を後押ししてくれるよう、まずは、小さな成功体験を積んで自信をつけてあげてくださいね。
▼▼不安が強い子が学校で安心して過ごせる方法を知りたい方はこちら▼▼
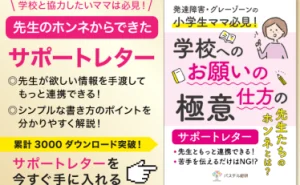
不安が強い子どもに自信をつける方法、多数ご紹介しています!
▼ご登録はこちらから
▼無料小冊子プレゼント▼
育てにくい子が3ヶ月で変わる!
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
↓↓↓
執筆者:井上喜美子
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)