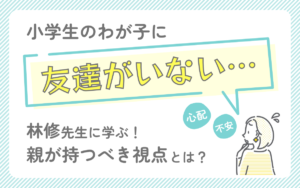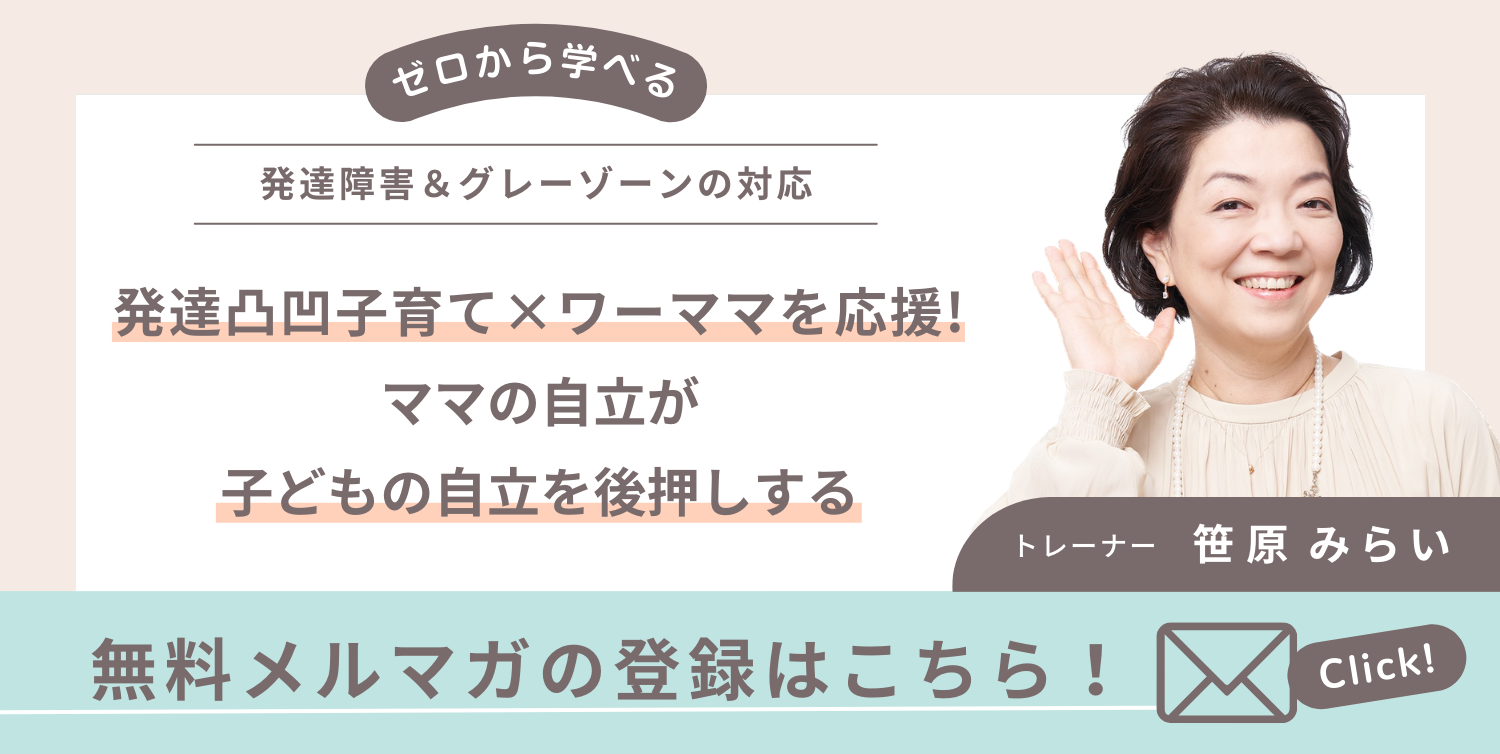発達障害の子どもとの会話のキャッチボールがうまくできないと悩んでいるお母さんはいませんか?実は会話することは、ただ話せばいいのではなく多くの脳の機能を使い成り立っています。今回は親子の会話で脳を発達させて会話力を伸ばすトレーニングをお伝えします。
【目次】
1.会話のキャッチボールができない子どもに悩んでいませんか?
2.発達障害の子どもの会話がうまくできない理由
3.親子の会話で子どもの脳を育む方法とは?
4.会話のキャッチボールができない子の会話力をあげる3つのトレーニング
◆好きなことを話させる
◆お母さんに聞いてもらいたい!を高める
◆気持ちに寄り添いどんどん話させる
1.会話のキャッチボールができない子どもに悩んでいませんか?
子どもと会話をしていても、
・なんだか話がかみ合わない
・何がいいたいのか伝わってこない
・あちこち話が飛んでしまう
・自分の言いたいことだけ一方的に話す
・何がいいたいのか伝わってこない
・あちこち話が飛んでしまう
・自分の言いたいことだけ一方的に話す
そんな子どもの様子に不安を感じることはありませんか?
発達障害の小学3年生の娘も話すことが苦手で、話をしていてもうまく会話のキャッチボールができないタイプ。
言いたいことがあっても「あのね、あのね…」ばかり言って次の言葉がうまく続かないのです。

そのためか、仲のよかったお友達ともいきちがいから喧嘩になったり、言葉が足りずにぶつかることも多くありました。
保育園の頃は「仕方がない、きっと小学生になったら会話もうまくなるだろう」と思っていたのですが、小学校に上がってもあまり進歩はみられません。
そのため「うちの子、なんでちゃんと話ができないんだろう…」といつも悩んでいました。
その後、娘は発達に遅れがあるということがわかり、私は娘の発達を促すため、発達科学コミュニケーションを受講することにしました。
今回は、わたしが発達科学コミュニケーションを学んだことで、親子の会話で子どもの脳を発達させてコミュニケーション力を伸ばす方法についてお伝えしたいと思います。
会話のキャッチボールが苦手な子のコミュニケーション力が伸びる方法をご紹介しています!▼▼
2.発達障害の子どもの会話がうまくできない理由
私たちは普段何気なく会話をしていますが、実は人が会話をするとき、脳はとても複雑なネットワークを使っていることをご存じですか?
脳の働きは大きく分けると、「視覚」「聴覚」「伝達」「記憶」「運動」「感情」「理解」「思考」を司る8つのエリアに分かれています。
会話をするときには
「話す内容をまとめる(思考)」
「実際に言葉にして声を出したり、口や舌を動かす(伝達)(運動)」
「話を聞いて理解する(聴覚)(理解)」
「話を覚えておいて、つながるように返答を考える(記憶)(思考)」
「相手の顔を見て(視覚)言葉を受け取った相手がどんな気持ちか確かめる(感情)」
というように脳の様々なエリアを使っています。
けれども、発達障害の子どもは、脳の特性からこの広いエリアを上手に使いこなしながら、スムーズに会話することが難しいのです。
発達障害・自閉症傾向のお子さんは、会話のキャッチボールが苦手なことが多いです。

そのため、言葉を知っていても意味が分からなかったり、比喩表現や冗談が通じない、相手が困惑しているのに言いたいことを一方的に話してしまう、なんてことが起きてしまいます。
また、相手が話している内容を覚えていられない、会話のテンポに合わせて返答が考えられないなど発達の未熟さが影響して、会話に支障がでてきてしまうこともあります。
コミュニケーション力の苦手さは発達の凸凹による脳の特性が原因の1つですが、このまま様子を見ているだけでは、失敗を重ねてしまい対人面での自信をなくしかねません。
子どものコミュニケーションに困った時の対応法をお伝えしています!▼▼
3.親子の会話で子どもの脳を育む方法とは?
会話が苦手な子どもに対して、会話の機会を増やそうと集団活動に参加させるお母さんも多いようですが、実はこの対応はあまりおすすめできません。
というのも、そもそも発達障害の子どもたちは学校や保育園などの集団で、先生が話す言葉を受け取ることが難しい子どもたちです。
他のことに注意がいって自分に向けて話しかけられたことに気づかない。
話す内容が自分のレベルよりももっと難しい内容で、理解に時間がかかっている。
そういった困難さがある中、いくら集団の中で多くの会話を耳にしているからといって、子ども自身がうまく受け取ることができていなければ、会話の上達にはつながらないのです。
では、子どもがうまく会話のキャッチボールができるようになるためには、どうしたらよいのか?

私が会話の苦手なお子さんのお母さんにぜひやってもらいたいこと、それは親子で1対1での会話を楽しむ時間をとることです!
集団の中で投げかけられた言葉をうまく受け取ることができない子どもも、お母さんとのマンツーマンでの会話では緊張せずに話せるはず。
また、お子さんのことを一番よく理解できているお母さんなら、子どもが受け入れやすい言葉を投げかけてあげられるのではないでしょうか?
いつも一緒に過ごしているお母さんとなら楽しい会話のキャッチボールを毎日、何度でも行うことができますよね。
つまり、お母さんが子どもと会話をすることは脳を伸ばすトレーニングになり、脳のトレーニングの効果が上がる「質」と「量」を充実させることができるのです。
次項では子どもと楽しく会話のキャッチボールができるようになるちょっとしたコツをお伝えしますね。
4.会話のキャッチボールができない子の会話力をあげる3つのトレーニング
子どもと楽しく会話のキャッチボールができる3つのトレーニングについてお伝えします。
◆好きなことを話させる
子どもの会話量を増やすには、まず子どもの興味があることや楽しいこと、好きなことを話させることです!
好きな食べ物、好きな人、好きなゲームやアニメの話でもいいですし、楽しみにしている行事のことでもいいですね。
私は娘が大好きな給食の話を毎日聞いています。
会話が苦手でも「今日のメニューは何だった?」「何が一番おいしかった?」「どんなものが入っていたの?」という興味のあることはほぼ完璧に覚えていて、嬉しそうに答えてくれます。
給食のメニューって、バラエティに富んでいてあまり家庭ではなじみのないものがあったりするので、私もどんな料理なのか興味深く、楽しく話ができる時間になっています。
娘が楽しそうに給食のことを話してくれる様子をみると、好きなものへの思いってすごいなあと感じます。
◆お母さんに聞いてもらいたい!を高める
自分の好きなことをお母さんに話したい!聞いてもらいたい!という気持ちに寄り添うことです。
子どもが何か話そうとする時、先回りしたり、さえぎったり、言い間違いがあってもそれはちがうよ!などと訂正したりしてはいけません。
子どもが話し出すまでじーっと待ちます。
まどろっこしいと思うかもしれませんが、子どもは脳が未熟なので話し出すまでに大人の何倍も時間がかかります。
それだけ脳を使っているのです。
この考えているときが一番脳が発達するチャンスですから、さえぎってしまったらもったいないのです。
さらに、聞く態度も大事です。
笑顔で楽しそうに、興味を持って聞くこと! お母さんが片手間に返事をしていることってすぐに見破られてしまいます。
ちなみに娘は「へえー!お母さん知らなかったなあ」と感心してあげると、とてもうれしそうにどんどん話をしてくれます。
ぜひ、短い時間でもしっかり向き合って聞いてあげてください。

◆気持ちに寄り添いどんどん話させる
子どもがどんなことを楽しいと感じたか、感動したポイントや、その時の気持ちに寄り添ってあげることです。
「たのしかった」「うれしかった」「いやだった」 その時の感情に共感してあげるといいです。
まだはっきり自分の気持ちをお話できない子もいるかもしれませんが、その時は話をしてくれたことから、お母さんが想像して
「それは〇〇ちゃん、たのしかったね!」
「〇〇って言われたのか~。そんなこと言われて嫌な気持ちだったんだね。」
「〇〇って言われたのか~。そんなこと言われて嫌な気持ちだったんだね。」
というように子どもが話すことに対しどんな気持ちで話しているのか想像して代弁してあげるといいでしょう。
もしも、お母さんが代弁したことが違っていたとしても大丈夫。
お母さんが子どもの気持ちを考えて話をするうちに、次第に当たるようになってきますよ。
さらに、子どもはお母さんに理解してもらえたと感じて、どんどんお話をしてくれるようになってきます。
いかがだったでしょうか?
ぜひ、親子での会話の機会を増やして、子どもの脳を発達させていってくださいね。
だんだんと家族以外の人とも会話のキャッチボールもうまくなって、自信もついてきますよ。
お母さんが学ぶから子どもの脳が発達します!こちらもご覧くださいね。
思春期の反抗期の子どもとの親子関係を良好にする会話術はこちらです。
▼【2023年7月最新刊】宿題の常識に縛られて親子で苦しまないで!▼
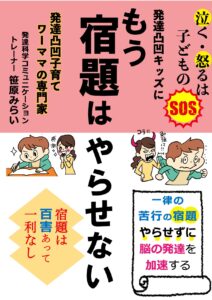
▼▼教育先進国には宿題なんてないんです!宿題しない方が良い脳に育つ!▼▼
▼登校しぶりは子どもが限界のSOS!▼
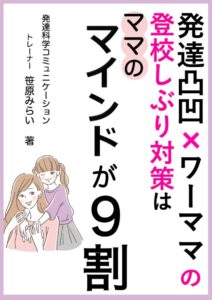
▼▼お母さんのマインドが子どもの登校しぶりを左右する!▼▼
▼ワーママの罪悪感をゼロにする!▼
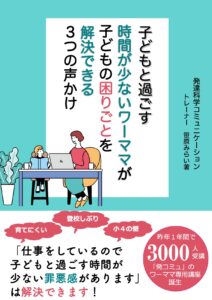
▼▼子どもと過ごす時間の質を高める方法をお伝えしています!コチラをダウンロードしてください▼▼
▼ゆったりIQっ子が支援級で伸びるヒミツ!▼
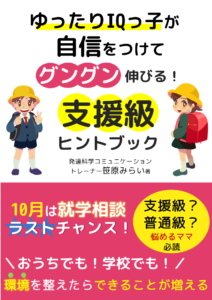
▼▼支援級見学でのポイントをお伝えしています!コチラをダウンロードしてください▼▼
▼夏休みの追い込みにも、新学期からも、宿題で怒り出すなら要チェック!▼
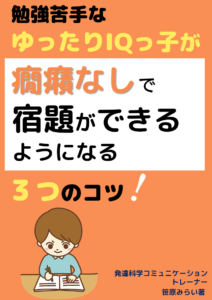
▼▼ゆったりIQっ子が「癇癪なし」で宿題ができるようになる取り組み方についてお伝えしています!コチラをダウンロードしてください▼▼
▼ついガミガミ言ってしまうママはぜひ読んでください!▼
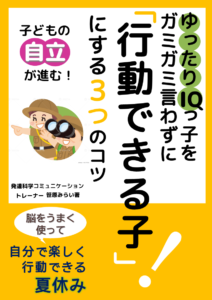
▼▼ゆったりIQっ子が「行動できる子」になるコツをお伝えしています!コチラをダウンロードしてください▼▼
▼学校に行きさえすればいいんじゃない!もっと大事なことがあるんです!▼
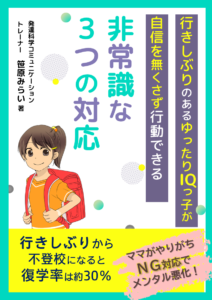
▼▼行きしぶりのゆったりIQっ子へのの非常識な対応をお伝えしています!コチラをダウンロードしてください▼▼
▼学校との連携で不安解消!子どもの良さを先生に伝えるサポートブック付き!▼
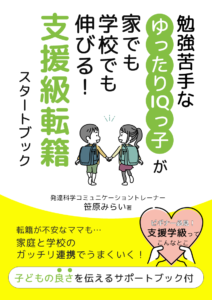
▼▼支援級転籍に不安を感じるなら、ぜひこの本を読んでみてくださいね!▼▼
楽しい会話のキャッチボールができる発コミュのヒミツを知りたい方はメルマガにご登録くださいね!
執筆者:笹原みらい
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
(発達科学コミュニケーショントレーナー)