小学校に行きたくないという発達障害の子の登校しぶりに悩んでいませんか?無理にでも行かせるのがこの子のためと毎朝子どもと格闘しているお母さんに伝えたい、登校しぶりの初期対応についてお伝えします。
【目次】
1.小学校に行きたくない…発達障害の子の登校しぶりは子どもからのSOS
2.子どもが登校しぶりをしたときのNG対応
3.登校しぶりを卒業する!乗り越えるためのおうちカウンセリング
1.小学校に行きたくない…発達障害の子の登校しぶりは子どもからのSOS
「小学校に行きたくない…」と、突然子どもから言われたら…お母さんはどう対応して良いか困ってしまいますよね。
発達障害の子の登校しぶりは、「もう限界!」という子どもからのSOSです。
SOSのサインにお母さんが適切に対応することで、登校しぶりは卒業できます。
登校渋りは突然始まることもあります。時期も様々で、新学期や連休明けなど環境の変化も関係しています。
特に発達障害・グレーゾーンのお子さんにとって4月からの環境の変化は、心身共に大きな負担になります。少しずつ慣れていきつつも、毎日の学校生活への緊張感は続いているんです。
この緊張感と疲れやストレスからくる心身の不調が合わさり、登校しぶりという形で出ることもあります。

発達障害グレーゾーンの子どもの中にはもともと学校が苦手な子どもが多くいます。
・ザワザワする教室の音、先生の怒鳴り声
・興味の持てない活動
・合わない学習方法
・求められる集団行動
・クラスメイトたちとの臨機応変なコミュニケーション
そういった周囲の環境と自分の特性とのアンマッチにより、学校に対して緊張や不安が高まりやすい性質を持っています。
もともとそうした特性のある中で、新しい学年になることでイレギュラーな活動が増え、限界を迎えた子どもが発するのが「小学校に行きたくない」というSOSなんです。
発達凸凹キッズの「学校行きたくない」はタイプ別で解決!無料プレゼント中▼▼
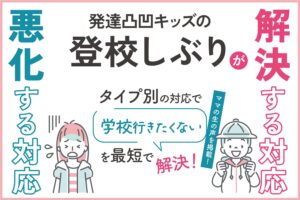
2.子どもが登校しぶりをしたときのNG対応
子どもが登校しぶりを起こすと、私たち親は非常に不安になりますよね。
「このままずっと学校に行かなかったらどうしよう」
「どうしてうちの子だけ」
「育て方が悪かったの?」
そんな不安から、親がしてしまいがちなNG対応が、無理にでも学校に行かせようとすることです。
いじめなどの理由がないにもかかわらず学校に行きたくないと言う場合、親からみれば子どもが甘えているだけに思えるのではないでしょうか。
甘やかしてはこの子のためにならない、休ませたら怠け癖がつく。そう思い、布団から出ない子どもをたたき起こし、叱りつけ、学校まで引きずって連れていく。

これはまさに、登校しぶりをする娘に対して私がしてしまったことです。
それで登校しぶりが改善されたかというと、むしろ逆でした。
不安症状はますます強くなり、このままでは本当にこの子は壊れてしまうと思うほどまで、子どもを追い詰めてしまいました。
先ほどお伝えしたように、発達障害グレーゾーンの子どもはもともと学校生活に合わない特性を持っています。
登校しぶりは決して発達障害の子どものわがままでも親の甘やかしでもありません。
ママから離れられない子の行き渋り対応がわかります▼▼
登校しぶりの原因がはっきりしない場合の対応がわかります▼▼
お子さんのこともご自分のことも責める必要はないのです。
今は登校することに対して不安や疲れを感じているということますから、ここで無理をさせるとこじらせる可能性がありますので注意して対応しましょう。
休み明けの登校しぶりを改善したい方はこちら▼▼
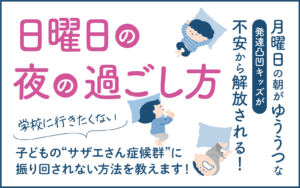
【10分で読めるシリーズ】月曜日の朝がゆううつな発達凸凹キッズが不安から解放される!日曜日の夜の過ごし方
3.登校しぶりを卒業する!乗り越えるためのおうちカウンセリング
では、子どもが登校しぶりをしたとき、どう対応すれば良いのでしょうか?
この章では、子どもの心を守りながら早期解決するための「おうちカウンセリング」について紹介します。
ポイントは、親の感情と子どもの感情を切り離して考えることです。
おうちカウンセリングは4ステップです。
①親の気持ちは保留する
②受け止める
③理解する
④共感する
登校しぶりをされると、なんとか行く気になるようあの手この手で言葉を投げかけてしまいがちですが、「学校に行かせよう」と思う気持ちはいったん封印してください。(保留)
子どもは「行きたくない!」というネガティブな気持ちでいっぱいで、お母さんの言葉を受け取れる状態ではないからです。
いつもと違う様子はないか、子どもの様子を観察し、
そっか~。
そうなんだ~。
と、肯定も否定もせず気持ちを受け止め、「心配なことがあったら話していいんだよ」と、安心して話せる雰囲気を作ってあげましょう。(受容)
親からしたら理解しがたいことも、ここでは否定せず聞いてあげてくださいね。
安心できた状態で、子どもがポツリポツリと話し始めたら、子どもが何を感じているのか、どんなことをわかってほしいと思っているのか、子どもの言葉をヒントに理解して代弁していきます。(理解)
子どもの気持ちをしっかり受け取ったうえで共感することで、子どもは「お母さんが自分の気持ちをわかってくれた」という満足感を得ます。(共感)
そうすると、お母さんの言葉を受け取れる余裕も出てきます。
「気持ちを話してくれてありがとう」と伝え、「ごはんにする?着替えからする?」と、いったん他の活動に切り替えたり、今日はどうするかの作戦会議をしたりと、行動に移していってくださいね。
登校しぶりは様子を見ていても解決しません。
長引かせないためには、朝の対応だけではなく日頃の声かけも大切です。
登校しぶりに悩んでいるお母さんのために、登校しぶりを早期解決する方法を1冊にまとめました。
無料で読めますので、ぜひチェックしてみてくださいね!▼

不安の和らげ方がわかります!▼▼
▼登校しぶりのOK対応とNG対応を会員限定・Nocotto!ライブで解説しました▼
登校しぶりと上手に付き合い、乗り越える方法をお伝えしています!▼▼
執筆者:水原沙和子
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)







