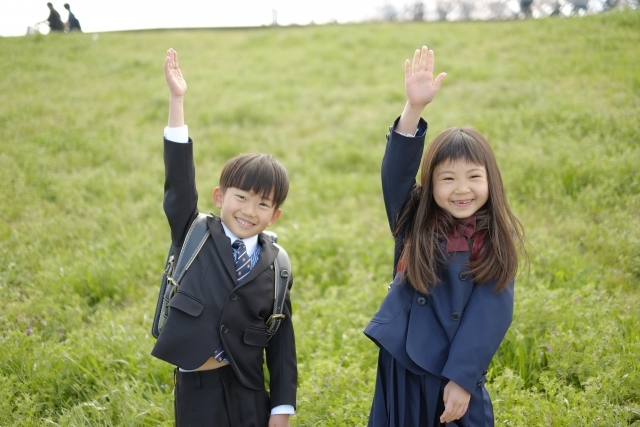長期休み明けって大人でも仕事に行きたくないですが、子どもから「学校に行きたくない」と言われるとどう対応したらいいか困ってしまいますよね。休ませたらそのまま不登校になってしまうかも…と不安もあるかもしれませんが、まずは子どもの気持ちに寄り添ってみませんか?
【目次】
1.「学校に行きたくない」は子どもの『SOS』かも
2.学校に行きたくない理由はそれぞれ違う
3.子どもの気持ちに寄り添う方法
1.「学校に行きたくない」は子どもの『SOS』かも
夏休みなどの長期休みが明けると「学校に行きたくない」と、登校をしぶる子どもにお悩みではありませんか?
わたしたち親世代の多くが「学校には休まず行きなさい!」と言われて育ってきたと思います。
共働き世帯も多い世代ですので、子どもに「行きたくない」「休みたい」なんて登校をしぶられると困ってしまう家庭も多いと思います。
最近子どもの様子がおかしいと感じたことはありませんか?
・表情が暗い
・だるそうにしている
・ため息をつくことが増えた
・学校や友達の話をしなくなった
・八つ当たりが増えた
・どこか上の空でいる
・いつもより甘えてくる
・機嫌が悪く暴言を吐いたり暴力をふるうようになった
などなど。
なにか思い当たることはありましたか?
こんな様子があれば、それは子どもが発する『SOS』のサインかもしれません。
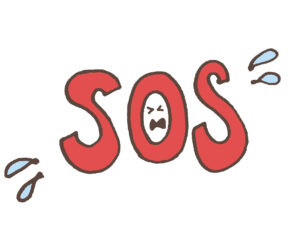
長期休み明けは登校しぶりが増えるタイミングです。
実はわたしも子どものころに不登校になった経験があります。
理由は、ただなんとなくです。
そのときはわかりませんでしたが、自分で気づかないうちにストレスが溜まっていたのかもしれません。
なぜ学校に行きたくないのか?
登校しぶりは不登校の前兆なのか?
学校に行きたくない子どもの気持ちに寄り添う方法をお伝えしますね。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
3週間で癇癪が落ち着き
毎日が穏やかに過ごせるようになる!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.学校に行きたくない理由はそれぞれ違う
子どもが学校に行きたくない理由は様々です。
・クラスになじめない
・友達とケンカした
・苦手な先生がいる
・勉強についていけない
・学校が遠くて歩くのが大変
・生活リズムが戻らない
・体調がすぐれない
・なんとなく学校に行きたくない
わたし自身、「なんとなく学校に行きたくない」という理由で長期休み明けから不登校だったことがあります。
実は、わたしのように「なんとなく学校に行きたくない」という理由で登校をしぶる子どもが多いことをご存じでしたか?
なぜ「なんとなく」なのか?というと、自分の気持ちを明確に言語化することが苦手だったり、思春期くらいの子どもであれば「理由をいうのが恥ずかしい」など様々です。
大人だって、ジムに通うと決めて入会しても「今日はなんだか気分じゃないから行きたくないな」っていう日ありますよね?
気分が乗らないときって、自分が思っているよりも疲れていたりストレスが溜まっていたりするんですよね。

また、親子関係が上手くいっていないことも登校しぶりや不登校の原因だったりします。
最近どんな会話をしましたか?
お子さんの好きなものがなんだか知っていますか?
勉強や将来についてプレッシャーをかけすぎていませんか?
子どものことって、意外と知っているようで知らないことが多かったりするものです。
では、登校しぶりが不登校の前兆なのか?というと、必ずしもそうであるというわけではありません。
長期休み中に遅寝遅起きの習慣が身についてしまい、お休み気分が抜けていないだけということもありますし、学校がイヤで本当に行きたくない場合もあります。
子どもが学校に行きたくない理由を知ること、学校に行きたくないという子どもの気持ちに寄り添うことで、登校しぶりや不登校への理解・解決へとつながることでしょう。
情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!
”脳のクセ”を育て直す声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
3.子どもの気持ちに寄り添う方法
それでは、子どもの気持ちに寄り添う方法をお伝えしますね。
まずは「休みたい」「行きたくない」という気持ちを尊重してあげましょう。

頭ごなしに「なんで学校に行きたくないんだ?」「休まないで行きなさい!」と子どもの気持ちを否定するような言動や、「行きたくないよね?」「休みたいよね?」という共感はNGです。
声のかけ方は
・行きたくないんだね
・休みたいんだね
と、事実を受け止めて声をかけてあげましょう。
どうして学校に行きたくないのか?無理やり話を聞きだしたりせず、子どもから話してくれるのを待ってあげてくださいね。
正直な気持ちを話してくれたら、「話してくれてありがとう」と伝えてください。
次に、安心して過ごせる環境を整えてあげましょう。
「学校に行きたくない」と言った時点で、子どもの心と身体はとても疲れている状態です。
「休んでもいいけど勉強しなさい」「ゲームはだめ」と、プレッシャーをかけられたり禁止されることが多いと、居心地が悪くなってしまいます。
好きなだけゴロゴロしたり漫画読んでゲームしたり、目いっぱい休ませてあげましょう。
子どものことが心配で、つい口を出したくなるかもしれませんが、子どもの話を聴き、子どもの様子を見守りましょう。
元気な様子が見られるようになってきたら、今後どうするか?聞いてみましょう。
ちなみにわたしが不登校になったとき、親は何も言わず、ただただ休ませてくれました。
学校を休んでいる間、学年主任の先生が定期的に家に来て他愛もない話をしたことを覚えています。
思う存分休んだこと、先生が定期的に家に来てくれたことで「このまま家で寝ていてもしょうがない」と思うようになり、再び学校に行くようになったのでした。
学校に行くことの何がそんなに嫌だったのか、今では思い出せませんが、あの時両親と先生が責めたり怒ったりせず、「行きたくない」というわたしの気持ちに寄り添い見守ってくれたことが、不登校の解消につながったのかもしれません。
大人が躍起になって学校に行かせようとするよりも、子どもがなぜ学校に行きしぶるのか?子どもの気持ちに寄り添い、子どものためにどんな関りができるのか?少し元気な様子が見られたら、今一度お子さんと話し合ってみてくださいね。
学校へ行くのが怖いという小学生への対応はこちらの記事を読んでみてくださいね。
発達凸凹キッズの子育てが楽しくなるコツを知りたい方におすすめのメール講座はこちら↓
執筆者:村上 惠子
(発達科学コミュニケーション・アンバサダー)
(発達科学コミュニケーション・アンバサダー)