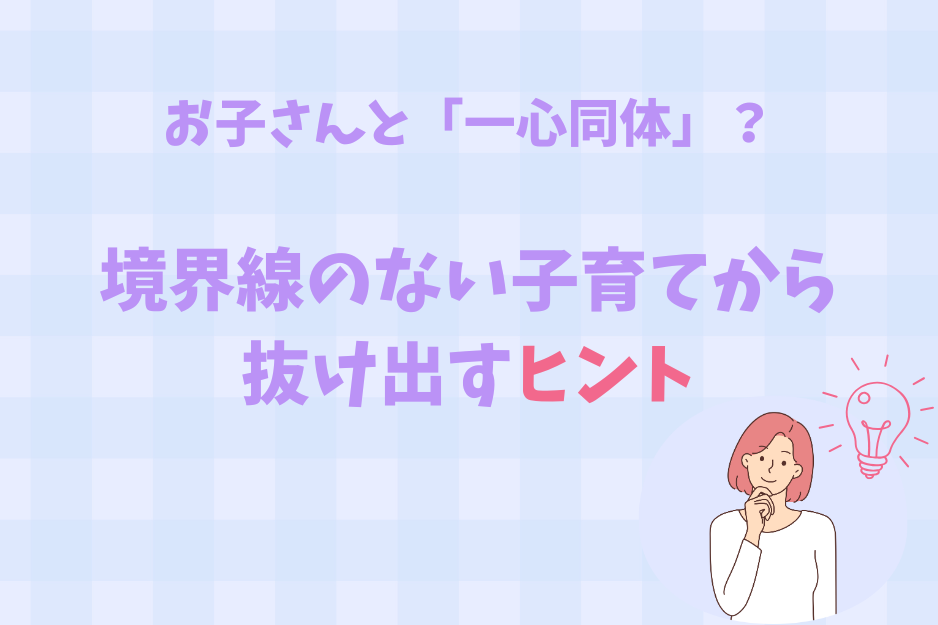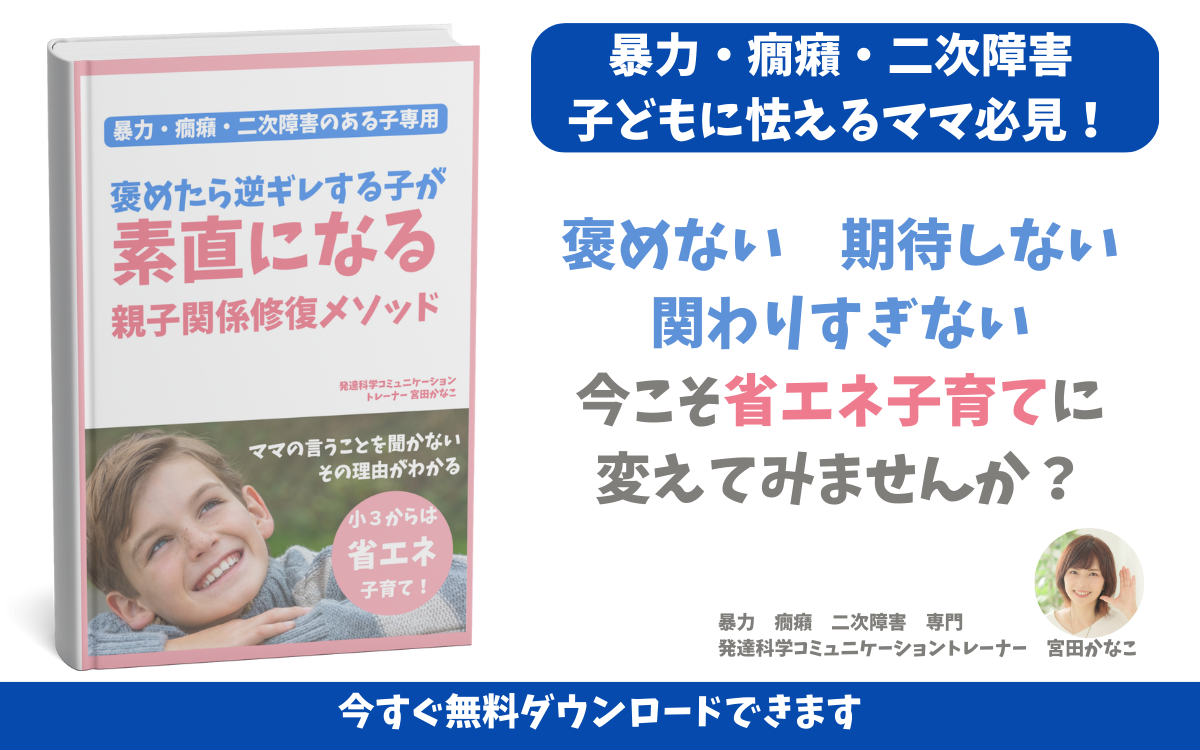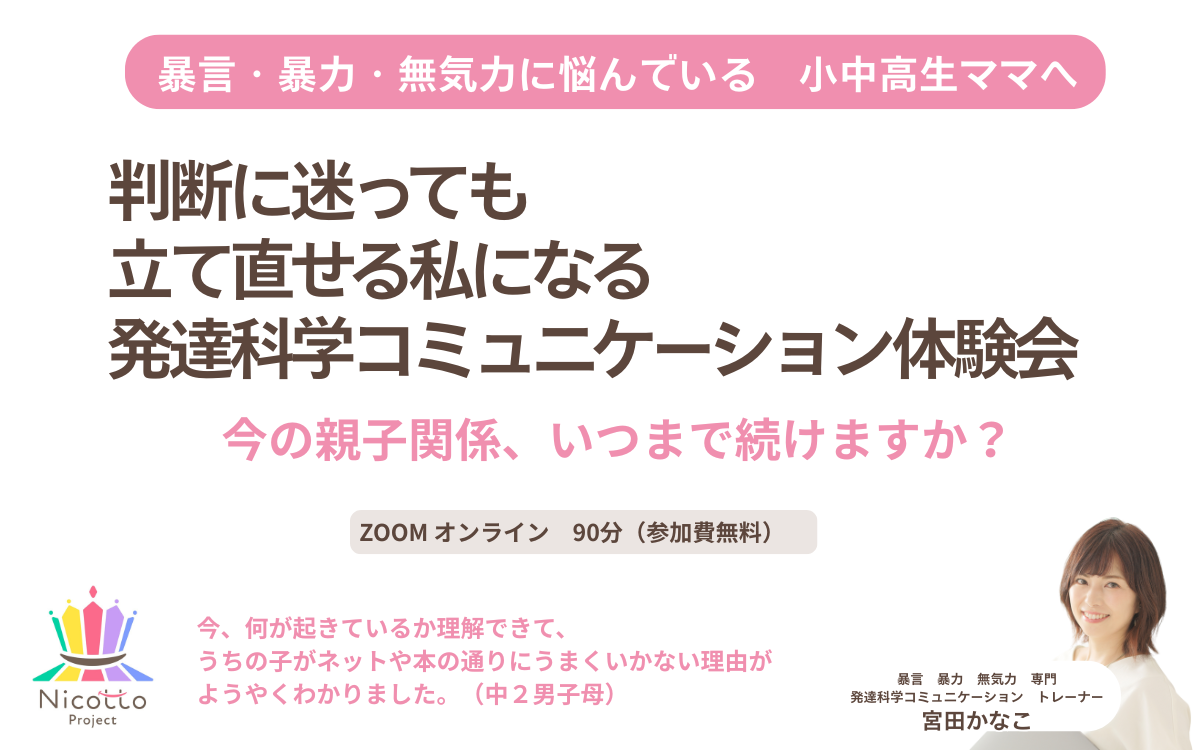お子さんのことで、なんだか心がざわついたり、過剰に心配になったりすることはありませんか? もしかしたら、それはお子さんと「一心同体」になっているサインかも?境界線のない子育てがもたらす影響と、そこから抜け出すためのヒントをお伝えしますね。
大切な我が子のことを思うあまり悩み事が絶えません!
なぜ「一心同体」の子育てになってしまうの?
子育てにおいて、親が子どものことを深く思うのは自然なことです。
しかし、その思いが強すぎると、無意識のうちに子どもとの間に境界線がなくなってしまうことがあります。
発達科学コミュニケーションに出会う前の私は、子どもと自分に完全に境界線がない状態でした。
そうして、子どもがどんどん反抗的になって暴言暴力がひどくなり、手がつけられなくなり、子どもに、「お前って生きている価値あんの?」と言われ、ようやく子どもではなく、自分のことを見つめなすようになりました。
そこで気づいたことが以下の通りです。
①過度な心配性
「うちの子は大丈夫だろうか」「何か問題が起きていないだろうか」と常に心配してしまうあまり、子どものことに過剰に介入していたのでした。。
②過去の経験
自身が親から過干渉を受けたり、寂しい思いをした経験から、「自分の子どもには同じ思いをさせたくない」という気持ちが強すぎることがありました。
③情報過多
インターネットやSNSで様々な子育て情報に触れる中で、「こうあるべき」という理想の親像に縛られてしまいがちで自分の軸がありませんでした。
なんと、現代人の1日に浴びる情報量は、江戸時代の一年分、平安時代の一生分とも言われています。
情報量は毎年増加しており、子どもも大人も大量のデータに囲まれている時代ですので、冷静に判断することが必要になっていきますね。
④核家族化や地域社会の希薄化
頼れる人が少なく、常に子どもと向き合っている中で、子どもの感情に引きずられやすくなっていました。
特に専業主婦で子育てしていたときは、子どものことが自分ごとになりがちでした。
また、発達科学コミュニケーショントレーナーになった今、たくさんの親御さんとお話をしていていつも感じています。
⑤愛情表現の誤解
子どものことを思うあまり、何でもやってあげることが愛情表現だと誤解してしまうことがありました。

いかがでしたか?これは私のことだと思った方もいるのではないでしょうか?
これらの要因が複雑に絡み合い、「一心同体」のような子育てに繋がってしまうことがあります。
「一心同体」の子育てがもたらすデメリット
「一心同体」子育てがもたらす子どもにとってのデメリット
①自己肯定感が低い子どもになってしまう
②子どもの自立が遅れてしまう
親が何でもやってしまうことで、子どもは自分で責任を持つことや困難を乗り越える力を育むことが難しくなります。
その結果、子どもは、思い通りにならないと、「おまえのせい」と親に言うようになってしまいます。
③主体性がない子どもになってしまう
常に親の指示や期待に応えようとするため、自分の意思や興味を持つことが難しくなり、主体的に行動できなくなることがあります。
④子ども自身がストレスを抱えてしまう
親の過度な期待や心配を感じ取り、プレッシャーを感じやすくなります。ありのままの自分を受け入れてもらえないと感じることもあります。
⑤親離れができない子どもになってしまう
自分で考える力や行動する力が育たないため、大人になっても親に依存してしまう可能性があります。
▼褒めても喜ばない、むしろ逆ギレする子どもも
みるみる素直になる省エネ子育て!
画像をクリックするとダウンロードできます
「一心同体」子育てがもたらす親にとってのデメリット
①子育てでのストレスや不安を感じ疲れやすくなる
子どもの感情や問題を常に自分のことのように背負い込むことで、心身ともに疲弊し、ストレスや不安を感じやすくなります。
②自分の時間がないと感じてしまう
常に子どものことを考えているため、自分の趣味や興味のあることを楽しむ時間を持てなくなり、自己肯定感の低下にも繋がります。
③夫婦関係が悪くなってしまう
子育てに対する考え方の違いから夫婦間で衝突が生じたり、お互いを責め合ったりする可能性があります。
子どもの前での夫婦喧嘩は、子どもの脳に悪影響です。
合わせてこちらの記事もお読みくださいね▼
④子育てをしていて孤独感を感じてしまう
子育てに没頭するあまり、友人との交流が減ったり、社会との繋がりを感じにくくなったりすることがあります。
特に、子どもが友達トラブルや、学校トラブルが多いと、周囲に遠慮して、ママ自身が、自分から殻に閉じこもってしまいがちです。
「一心同体」の子育てから抜け出すためのヒント

「もしかして、うちもそうかも…」と感じたら、少しずつ意識を変えていくことが大切です。今日からできる具体的なヒントをご紹介します。
①「私」と「子ども」の感情を区別する練習をしてみよう
お子さんが悲しんでいても、まずは「お子さんは悲しいんだな」と受け止め、その上で「私は今、どう感じているかな?」と自分の心に問いかけてみましょう。共感は大切ですが、感情を同一化する必要はありません。
同感と共感の違いはこちらをお読みください▼
②お子さんの課題は、お子さん自身のものと意識してみよう
学校の宿題や友達とのトラブルなど、お子さんが抱える課題に対して、すぐに手助けするのではなく、「どうしたらいいと思う?」と問いかけ、お子さん自身の問題解決能力を育てましょう。
③お子さんの力を信じること、見守る姿勢を大切にしよう
親が過剰に心配しなくても、子どもは成長する力を持っています。「きっと大丈夫」と信じて、少し距離を置いて見守ることも愛情です。
④完璧ではなくても、まぁいっか!の精神でいこう
完璧な親などいません。時には失敗したり、悩んだりしながら、子どもと一緒に成長していくのが子育てです。「まあ、いっか」という気持ちを持つことも大切です。
子どもの白黒思考や、完璧主義に悩むなら、ママ自身が思考を緩めることをお勧めします。
⑤できないこと探しではなくできたこと探しをしよう
いちばんの解決策はできていないこと探しをやめること。自分に対しても、子どもに対してもできたこと探し、良かったこと探しをすることで、子どもに対する見方も変わり、だんだんと信じて見守れるようになっていきますよ。
今日から少しずつ、お子さんとの間に境界線を意識することで、お互いを尊重し、穏やかな親子関係を築くことができるはずです。焦らず、ゆっくりと、あなたらしい子育てを見つけていきましょう。
2026年こそ、親子関係を変える第一歩を。
無料体験会実施中!
「うちでも変われる?」
「どう関わればいいの?」
「こんな悩み、私だけ?」
そんな不安がある方は、
ぜひ体験会にいらしてください。
どんなママも初めは不安です。
だけど、同じ悩みを抱えた仲間がいると
その瞬間から心がすっと軽くなります。
暴言・暴力・無気力な子どもが動き出す
“脳を育てる関わり方”を、
あなたのご家庭でも体感してみませんか
▼画像をクリックして詳細を見る