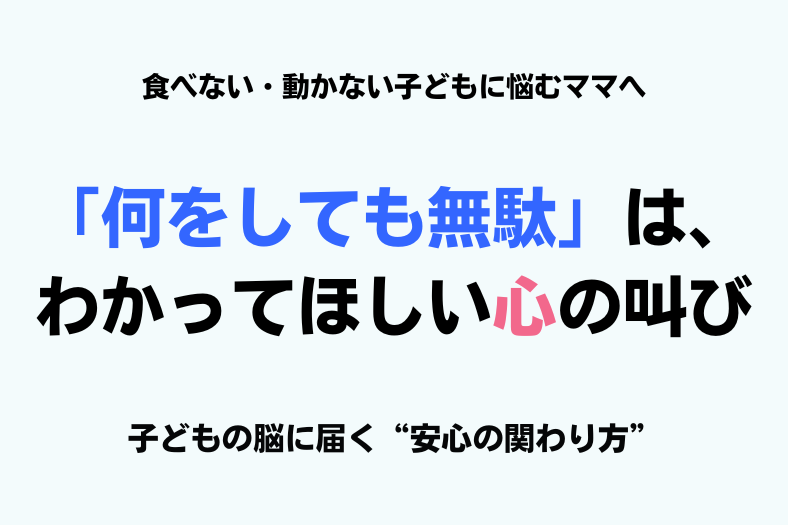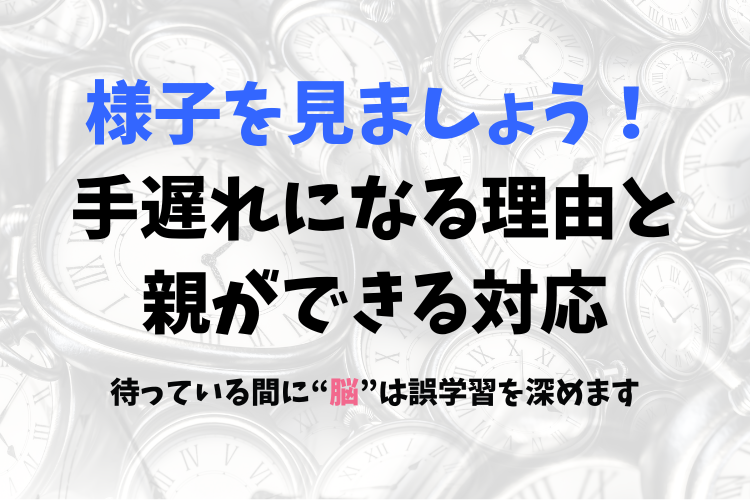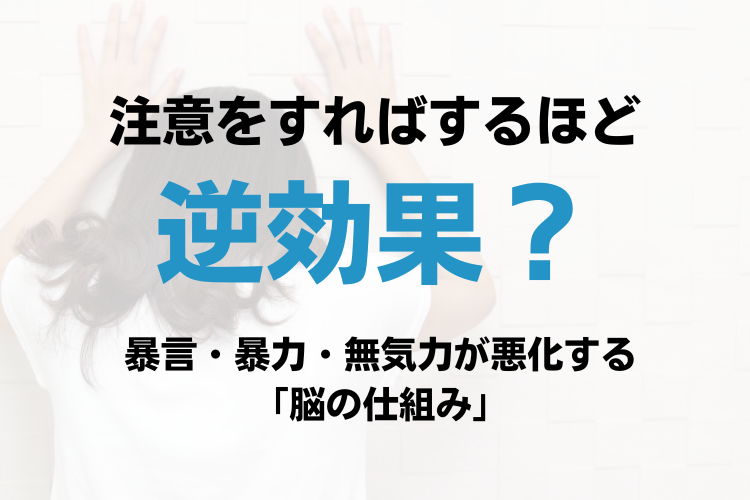「何をしても無駄」「食べても意味がない」
そう言って、ご飯を拒む子どもを前にすると、親の胸は張り裂けそうになります。
「食べないと死んでしまうんじゃないか」
「私の育て方が悪かったのでは」
そんな焦りと罪悪感で、心が追い詰められてしまう方も多いのではないでしょうか。
この「何をしても無駄」という感覚は、心理学では“学習性無力感”と呼ばれています。
うまくいかない経験が重なることで、「どうせ何をしても変わらない」と脳が思い込み、生きる力のスイッチを切ってしまうのです。
つまり、「無駄」という言葉は、諦めではなく、助けてという脳のサインなんです。
だけど、叱っても、励ましても届かないのは、脳が防衛モードに入っているから。
いま、子どもの脳は“戦うか、逃げるか”で精いっぱいなんです。
「食べない」は反抗ではなく、“脳のSOS”
子どもが「無駄」「食べない」と言うと、親としては「反抗している」「わざと拒否している」と感じてしまうもの。
けれど実際は、これは脳が限界までストレスを受けているサインです。
脳が過剰なストレスにさらされると、生きるためにエネルギーを節約しようとします。
「食べる・話す・動く」といった活動をストップさせ、心と体を守るモードに切り替えるのです。
つまり、子どもは「生きることをやめたい」と思っているのではなく、“生きるために止まっている”。
この違いを理解できるだけで、親の関わり方は大きく変わります。
言葉かけを「行動促し」から「存在の受容」へ
焦る気持ちから、ついこんな言葉をかけていませんか?
×「ちゃんと食べないと元気出ないよ」
×「お願いだから少しでも食べて」
×「そんなこと言わないの」
どれも愛情から出る言葉ですが、子どもの脳には「責められた」「理解されない」と伝わってしまいます。
代わりに、次のように言葉を置き換えてみましょう。
◎「いま、食べたくない気持ちなんだね」
◎「しんどいよね。ママここにいるよ」
◎「無理に話さなくて大丈夫。今日は静かに過ごそう」
行動を変えようとせず、“気持ちを理解された”と脳が感じることで、
少しずつ安心の回路が動き始めます。
食事の目的を「栄養」から「つながり」に変える
この時期の目的は、“食べさせる”ことではなく、“つながりを守る”こと。
食べても食べなくてもOKです。
「食べなきゃダメ」よりも、「一緒にいよう」の方が、脳にはずっと強い安全信号として届きます。
・テーブルの隅にお水やスープを置くだけ
・「ここに置いとくね」と伝えるだけ
・一緒にテレビを見ながら、何も言わず過ごす
食事を通じて「安心」を感じられる時間を作ることが、“生きる力”を取り戻す第一歩になります。
“何もしない勇気”が回復を早める
学習性無力感の状態にある子どもは、誰かに励まされたり助言されたりすると、「自分はダメだ」「どうせまた失敗する」と思い込みを強めてしまうことがあります。
だからこそ今は、言葉で変えようとせず、“安全”を感じさせることが最優先。
「食べなくても、ママはあなたを信じて見守っている」この静かなメッセージが、脳に“もう大丈夫”という信号を送ります。
焦って言葉を重ねるより、黙ってそばに座り、安心の空気を届ける時間こそが、何よりの支援になります。
“生きる力”を取り戻すためにできること
脳は安全を感じると、自然に回復しようとします。
1日数分でも安心して過ごせる時間が増えると、「食べてみようかな」「話してみようかな」が自然に出てきます。
すぐに結果を求めず、環境から整えることを意識しましょう。
-
光をやわらかくする
-
大きな音を立てず穏やかに静かに暮らす
-
癒しの音楽や香りを取り入れる
-
ママ自身が深呼吸をして落ち着く
ママの呼吸や声のトーンが変わるだけで、子どもの脳は「安全だ」と感じ、回復スイッチが入ります。
何をしても無駄は、わかってほしい心の叫び
「何をしても無駄」と言うのは、本当は「誰か、わかってほしい」という心の叫び。
行動を変えようとする前に、まず“心を休ませる”ことが大切です。
食べることよりも、「生きていていい」という安心を届けましょう。
そして、ママ自身が疲れたら、一人で抱えず、吐き出せる居場所を。子どもの回復は、ママの安心から始まります。