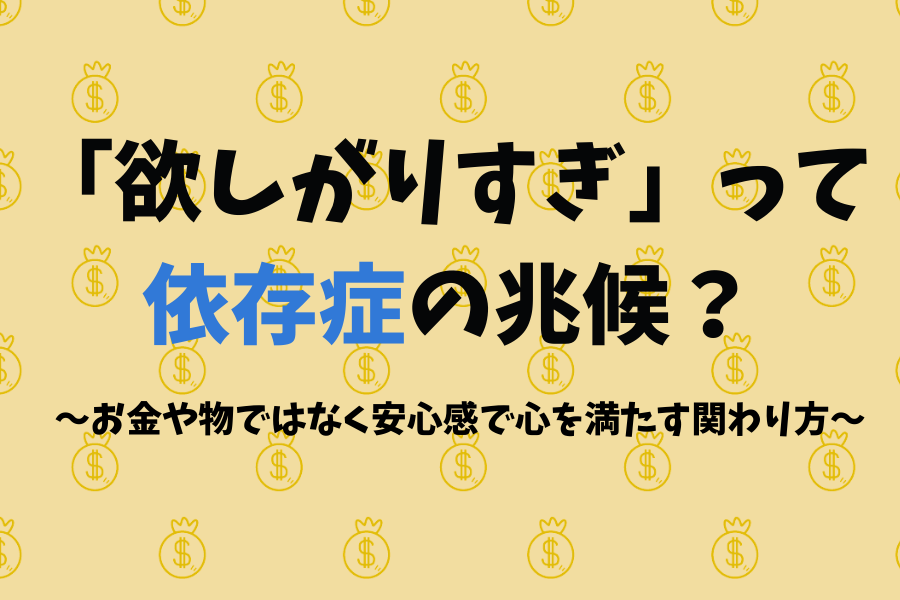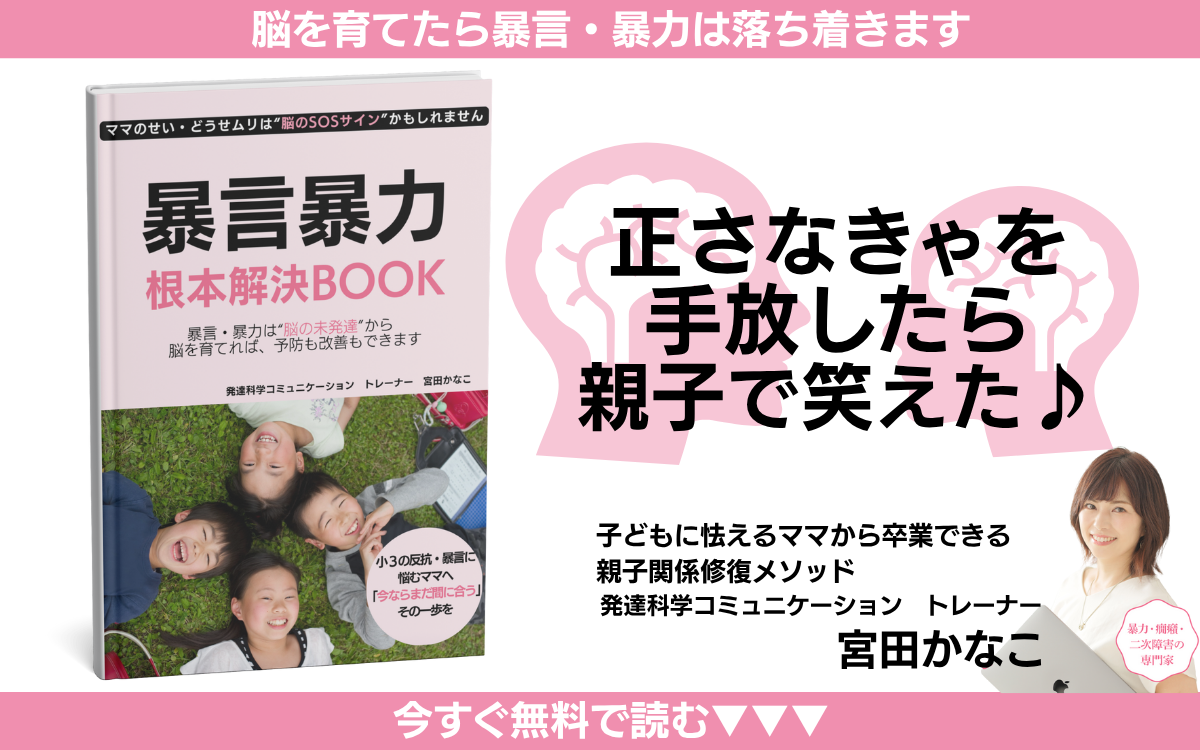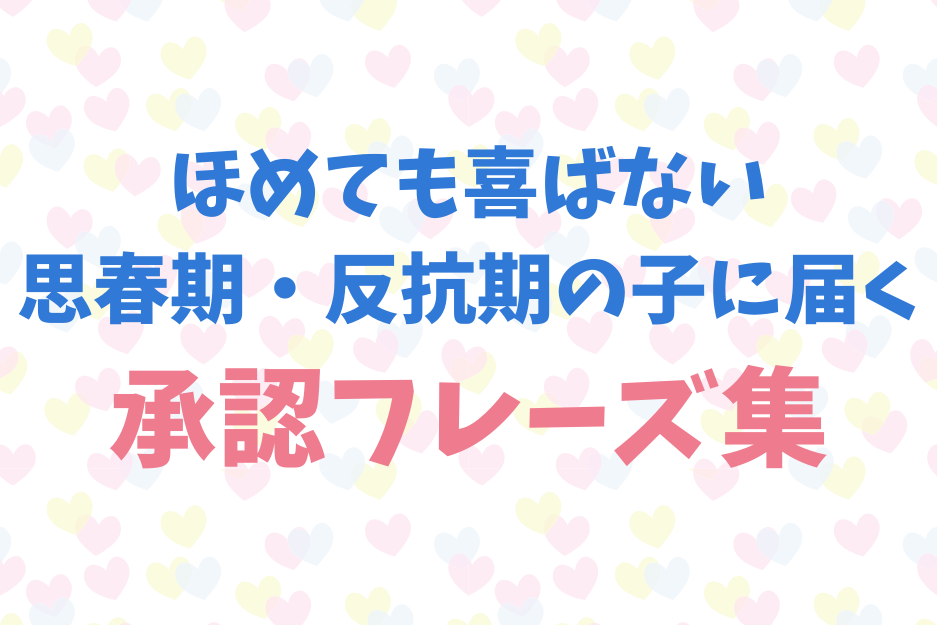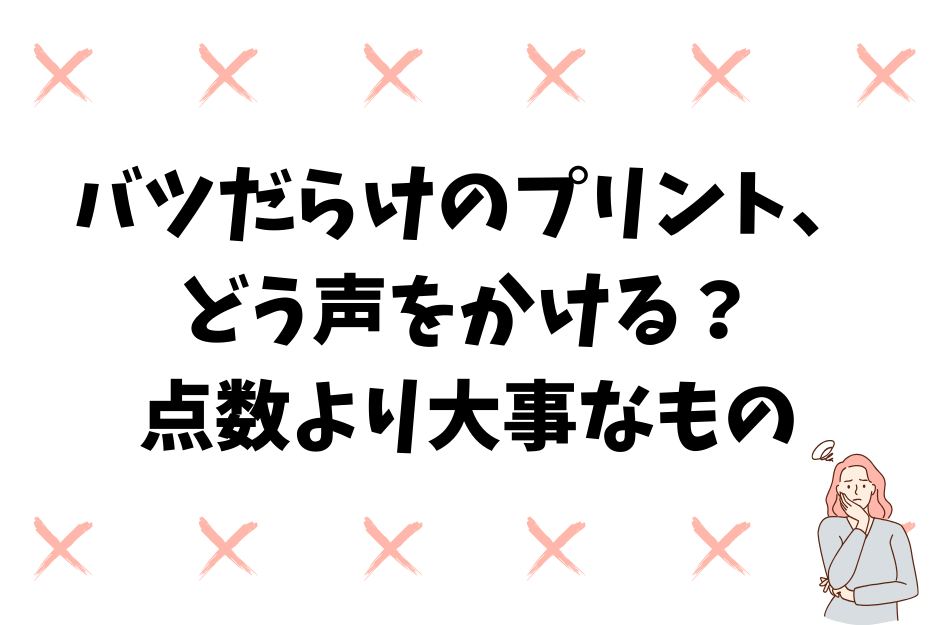「欲しい!」「やりたい!」の要求が強すぎて、親が振り回されてしまう…。
小さい頃から欲求が大きいと、毎日の生活にまで影響が出て不安になりますよね。
高校生のママからこんな声をいただきました。
依存しやすい脳について知りたいです!
「依存しやすい脳?について知りたいです。お金、物に対する欲求が身の丈に合っていなくて生活に支障が出ます…心が満たされていないから?の行動なのか。本当に依存症に足を突っ込んでいきそうで。とにかくとても小さな頃から欲求は大きくて大変でした。どこまで満たしてあげれば心は満たされるのか。まずは、肯定の注目を続けていこうと思います。」
脳の仕組みから見る「依存しやすさ」
実は、「欲しがりすぎる」行動の背景には脳の仕組みが関わっています。
脳には「報酬系」と呼ばれる、快楽や達成感を感じる部分があります。
この働きが未熟な子どもは、手に入れたものへの満足が長続きせず、すぐに「もっと欲しい!」と次を求めてしまいます。つまり「心が弱いから」ではなく、「満足が持続しにくい脳の仕組み」が原因になっていることがあるのです。
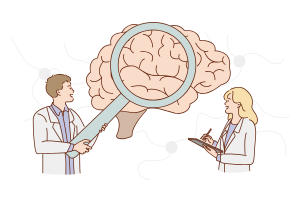
▼ママのせい・どうせムリは、脳のSOSサイン!
今すぐできることがあります。
画像をクリックするとダウンロードできます
「心が満たされていない」こととの関係
確かに、心の安心感が不足していると、外からの刺激(物やお金、遊びなど)で埋めようとする傾向は強まります。
けれど、与えれば与えるほど「もっと欲しい」が膨らむのは、脳の特性によるものであり、愛情不足や性格のせいではありません。
本当に必要なのは「物」ではなく「関係」
子どもの脳が本当に安心を感じるのは「物を手に入れた瞬間」ではなく、
「ママに認めてもらえた」「安心できた」と感じたときです。肯定の注目や承認の言葉は、子どもの脳に“満たされた経験”として積み重なり、少しずつ「足りない」が「安心」に変わっていきます。
じゃあ、どこまで満たせばいいの?
「欲しい」と言われるたびに無限に与える必要はありません。
大切なのは、“与える対象”を「物」から「関係」へと切り替えていくこと。肯定の注目や安心感の積み重ねこそが、依存的な行動を落ち着かせるための土台になります。
まとめ:焦らず、安心感を育てる関わりを
-
子どもの「欲しがりすぎ」は性格ではなく、脳の仕組みが関係している
-
物やお金を与えるより「関係の安心感」で満たすことが大切
-
肯定の注目を積み重ねることで、依存的な行動も少しずつ落ち着いていく
ご相談してくださったママが選んだ「肯定の注目」は、まさに正しい第一歩です。
焦らず、安心感を育てる関わりを続けていきましょうね。
▼併せて読みたい
子どもの“要求が止まらない”本当の理由〜甘やかしではなく、安心が足りない脳で起きていること〜