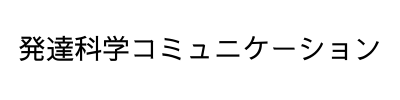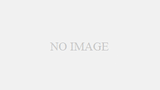おはようございます!
昨日のメルマガ
「未就学児のゲーム」というテーマに
興味ある人は
保存してね〜とお伝えしていましたが
実は思ったより反応がなかったので、
ゲームのお話ではなく
基本的な環境支援について
お話ししていこうと思います。
保存してくださった方ごめんなさい!
メインではありませんが
環境支援の中で取り扱っていきますね。
さて。
私は普段環境支援について
「構造化」という考え方を基に
お話ししていますが
そもそも環境支援とは何なのか。
お家でできる環境支援には
3つの種類があります。
1つめは空間環境
私がこのメルマガでもよくお伝えしている、
家の配置などの工夫を指します。
心を落ち着けるためのスペースや、
思い切り遊べるスペースなど
空間を明確にすることで、
どこで、いつ、何を、どうするかを
子どもにとって
理解しやすい環境にしていきます。
感覚過敏のあるお子さんには
音や光を遮断する工夫を施すのも
空間環境の1つですね。

2つ目は物的環境
例えば、
時間を守るために
アナログ時計を活用する
お支度ボードを使う
カードを使い感情を表現する
その子の苦手なことを
身の回りにある物でフォローし
自立を促していきます。

3つ目は人的環境。
人も環境の1つなんですよ^^
ママやパパ、先生など
周囲の人々の関わり方や
理解度を高めることを指します。
よりその子1人に適した会話や対応で
子どものストレスを緩和しつつ
脳を発達させていくことができます。

環境支援と言っても
いろんなパターンがあり、
どれも大切な要素になります。
発達科学コミュニケーションの声かけは
この3つ目の人的環境にありますが
私が講座で合わせて
お伝えしている「構造化」は
上記1、2つ目をご自宅で
ママができるようにすることを
目標にしています。
明日からは
色々な困りごとに合わせて
この3つの環境支援を
どう作っていけばいいのか
解説していきます。
困りごとと言っても
代表的な例になるので
この困りごとについて
できることが知りたい!
という方がいらっしゃいましたら
こちらのメルマガにご返信ください^^
ゲーム依存については
その1つについて取り上げますね!
では、皆さま良い祝日を♪
私は今日パパがいないので
子どもたちとこれから遊んできます!