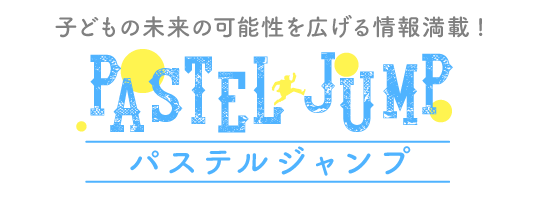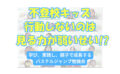1.「不登校が過去最多」その数字が本当に意味すること
という心配はご不要です。
整理してお話していきますので、ぜひお付き合いくださいね。
2025年10月29日に文部科学省が発表した
2024年度の不登校児童・生徒数(小中)は
35万3,970人(過去最多)
ただし、注目したいのは増え方です。
昨年度まで、+15.9%→ +22.1%
と急増していたのに
今年は+2.2%
一見、改善傾向かとも思えますが、実態はそうではありません。

データから読み取れるのは…
✔新たに不登校になる子→減り始めている
✔不登校が続いている子→増えている
という傾向。
背景には
✔オンラインで出席扱い
✔別室登校や校内支援センターなど、授業に参加しにくい子への環境整備
✔タブレット等の活用による、子どもの様子の把握
といった取り組みが広がりつつあり
その結果「欠席扱いにならない」ケースが
増えてきていることが1つあります。
つまり…
表の数字としては増えていないように見えても
支援が必要な子は減っていない
ここが大切なポイントになります。
では、なぜ支援が必要な子は減っていないのでしょうか?
次の章では、その理由について説明します。
今このサイトをお読みのあなたにおススメ
7500人の親子が実践中の声かけが無料!
▼詳しくはこちら▼
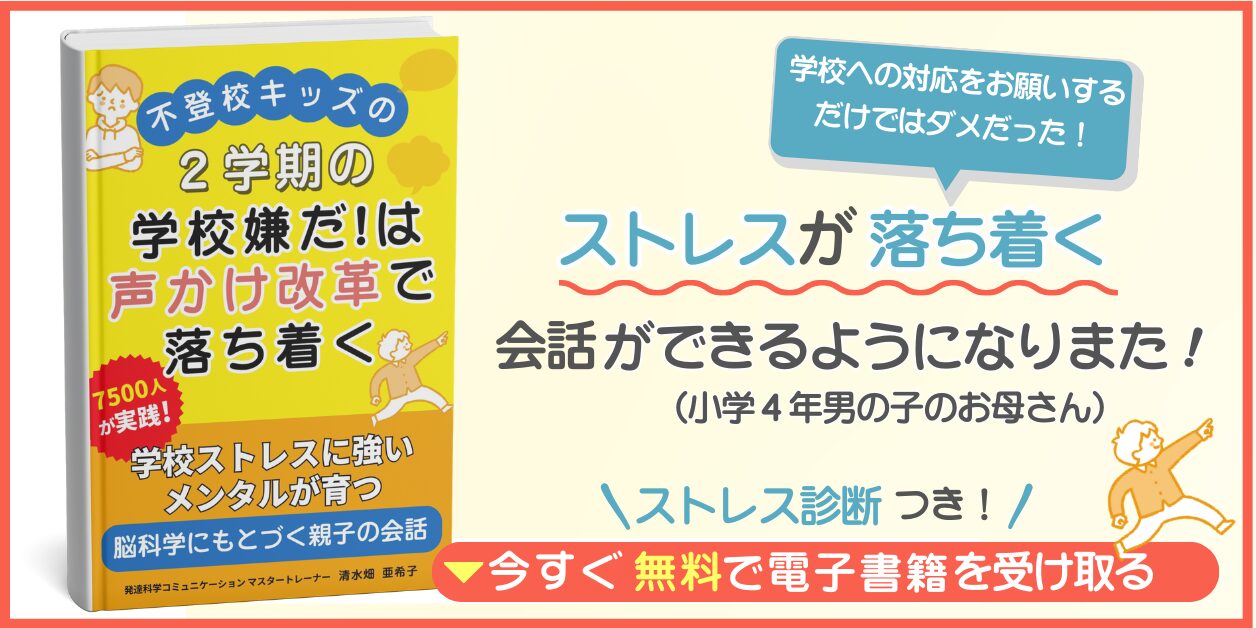
2.なぜ不登校は再発するの?本当に必要な力とは…
文科省の調査では
✔一度復帰しても約半数が再び不登校に
さらに
中学生以降は
✔70〜80%が再発する
という報告もあります。
だからこそ…
学校に戻る=解決
ではありません。

戻るための土台となる力
つまり
・不安をコントロールする
・集団のペースややり方にも順応できる
・自分の苦手なことにも取り組んでみる
・人との関わりにストレスを抱えすぎない
などなど、土台となる力の発達をさせてあげることが大切。
これは「急いで学校に戻せ!」ではなく
長期的、本質的なサポートが必要な時代に入ったということです。
"毎日学校に行けなくても大丈夫です!"
毎日の声かけを変えて
子どもの脳を育ててストレスをリセット!
▼今読めば進級進学前に間に合う!▼
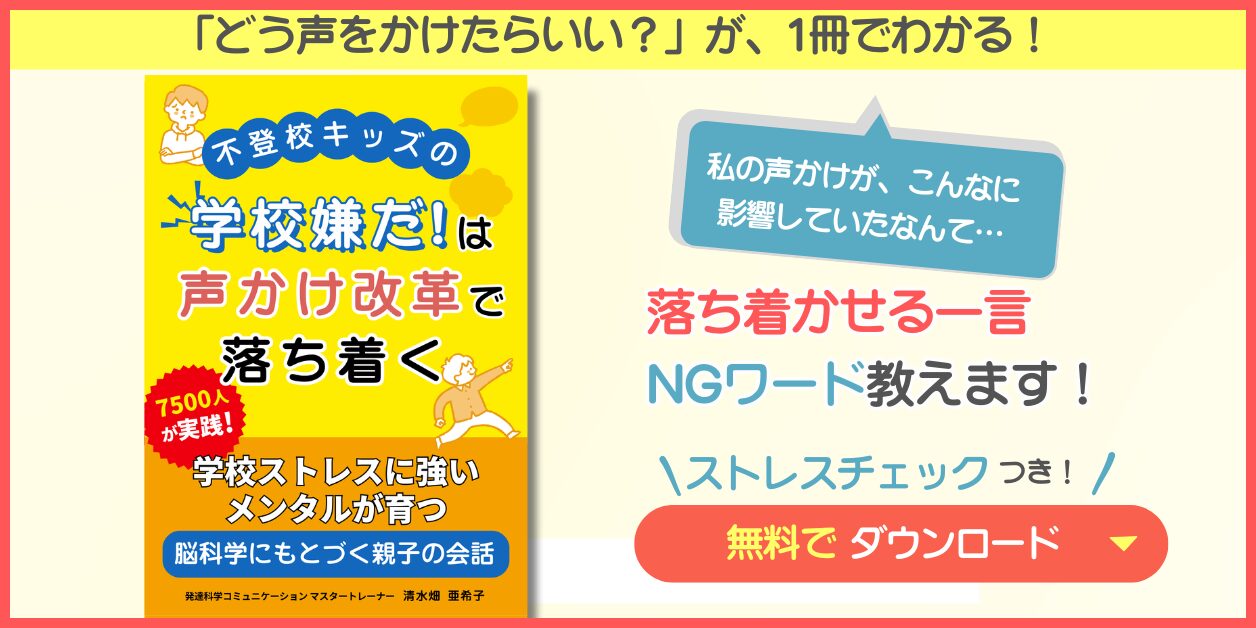
3.子どものサインを見逃さない!ママの気づきが回復の第一歩
教室でも、別室でも、フリースクールでも、自宅でも
大切なのは自信を育て“できる”を増やす
発達加速の視点です。
子どもが挑戦できる状態をつくってあげることです。
お子さんのサインにいち早く気付けるのは
いつもそばにいるママです。
✔表情
✔声色
✔会話の量
✔食欲の変化
✔小さなため息
その気づきこそが最大の支援のスタートライン。

お子さんにとって、ママはいつだって救世主です。
ここからは、お子さんが不登校になった時
どう回復へ導き
どう成長を創るかがカギです。
次回は、隠れ不登校・仮面登校の「SOSチェックリスト」
をお届けします。
お子さんの様子に少しでも違和感を感じているなら
ぜひご覧くださいね。
執筆者:清水畑 亜希子
(発達科学コミュニケーションマスタートレーナー)
▼「なぜ不登校から回復していかないの?」と悩むママへ。その“なぜ”がわかると、ママの関わりが変わり、子どもの未来が動き出します!