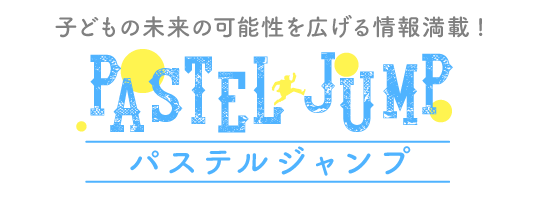1.勉強しない子の「スイッチ」が入らない理由とは?
宿題をやらない
テスト勉強をしない
テストの点数は散々…
という子どもの現状に、「学習習慣を身に着けさせないと!」とお母さんは頑張って毎日声をかけたり、評判のいい塾や家庭教師を探したりしているのではないでしょうか?
塾に行って楽しくお子さんは勉強できていますか?
家でもお母さんがちょっと声をかけるだけで机に向かうようになっていますか?
また、お母さんは子どもに声をかけるとき穏やかに声かけできていますか?
お母さんが頑張っているのに、子どもがなかなか勉強しないという場合、お母さんの頑張り方のベクトルが間違っているかもしれません。
子どもの勉強のことを考えると、イライラしたり過剰に心配になったりする場合、お母さんのサポート方法がお子さんに合っていないかもしれません。
/
勉強しなさい!ではなく、
「勉強してもいいかな」って思わせる
声かけがあります!
\
↓↓↓
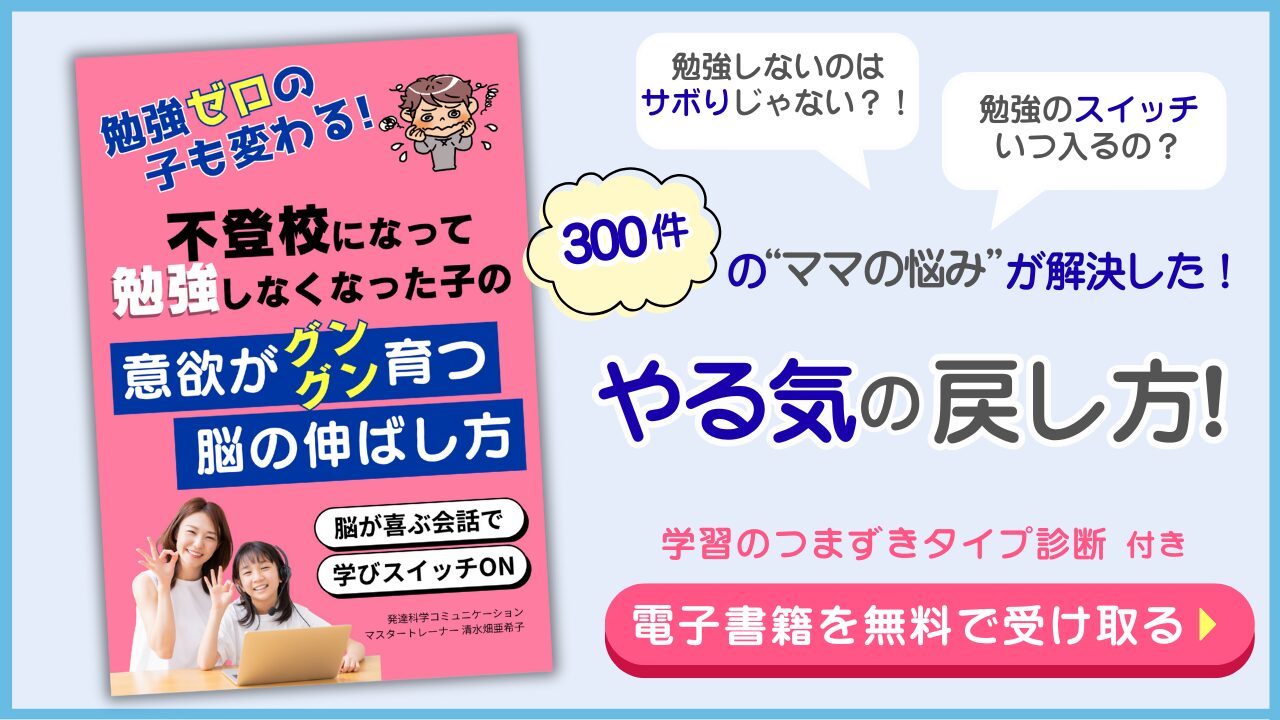
15秒で登録!メールアドレスに無料でお届けします!
今回は、お母さんも子どももハッピーになれる勉強スイッチの入れ方についてレポートします!

2.「頑張っても勉強しない」ママが気づいたやる気スイッチの真実
今回、勉強しない子の学習習慣をつける取り組みにチャレンジして発表してくれたのは、発達科学コミュニケーションNicotto講座生(上級講座生)のNさんです。
Nさんは、定型発達の小学生の双子のお子さん3人のママさんです。
双子のお子さんには、発達凸凹の長男くんがいます。長男の息子さんの、学校でのやるべきことをやらない、学校の勉強についていけない…という姿に悩み、色々な教育法を試し、息子さんに「頑張れ!」と言い続けていたそうです。
ところが、お母さんがどんなに頑張っても、息子さんが変わることはなく登校しぶりまでするようになってしまいました。
息子さんの心も体も限界になったサインを受け止めたNさんは、発達科学コミュニケーションを受講。苦手なことをひたすら訓練させる子育てを卒業し、子どもの得意を伸ばす子育てにチェンジしました。
すると、親子仲も良くなり、息子さんはどんどん自分らしさを発揮して学校でも活躍する等どんどん成長しています!
そんなNさんが、双子の息子さん達が遊びに夢中で勉強してくれないために、取り組んでみた声かけをご紹介していきます。
3.脳科学で解説!ご褒美の順番を変えるとやる気が続く理由
Nさんがまず調べたのは『実行機能』についてでした。
実行機能と聞くと、ちょっと難しそうな言葉…と思うかもしれませんね。
簡単に言うと、実行機能というのは、
最後までなにかをやり遂げるために必要な力です。まず、何かをやりたい!と思い、計画を立て、やる気を起こし、集中したり、適宜休んだりして、ものごとをやりとげるための脳の指令システムのことを言います。
皆さんは、お子さんに勉強してほしいとき、
「勉強したら〇〇していいよ!」
とご褒美作戦をとることが多いのではないでしょうか?
実は、このご褒美作戦、ご褒美がもらえる前の勉強が子どもにとってハードルが高すぎると、そもそもの「やりたい!」という子どもの思いが湧いてこないのです。
「勉強めんどくさいから、ご褒美もいらないや…」という思考になってしまうことがあるのです。
最初にやる気が起きないと、計画してやり始めるという行動にはたどりつかないのですね。
子どもが自ら勉強するようになるには、子ども自らがやる気を出してとりかかる気持ちを引き出してあげるようなご褒美設定が必要です!
そこでNさんが気がついたのは、ご褒美を先に体験させてあげるという方法。
息子さん達に実際に試してみました!
「宿題終わったら遊びに行っていいよ」ではなく、
「遊びに行ってきていいよ!帰ったら宿題しようね!」
と、言葉がけの順番を変えてみたそうです。すると、息子さんたちは喜んで遊びに行き、帰ってくるとしっかり勉強もするようになったのだそうです!

必死になって「勉強しなさい」と声かけしたり、高い教材を買ったりしなくても、こんなに簡単な方法で子どもの学習習慣をつけられるようになるなんて、驚きでした。
/
勉強しなさい!ではなく、
「勉強してもいいかな」って思わせる
声かけがあります!
\
↓↓↓
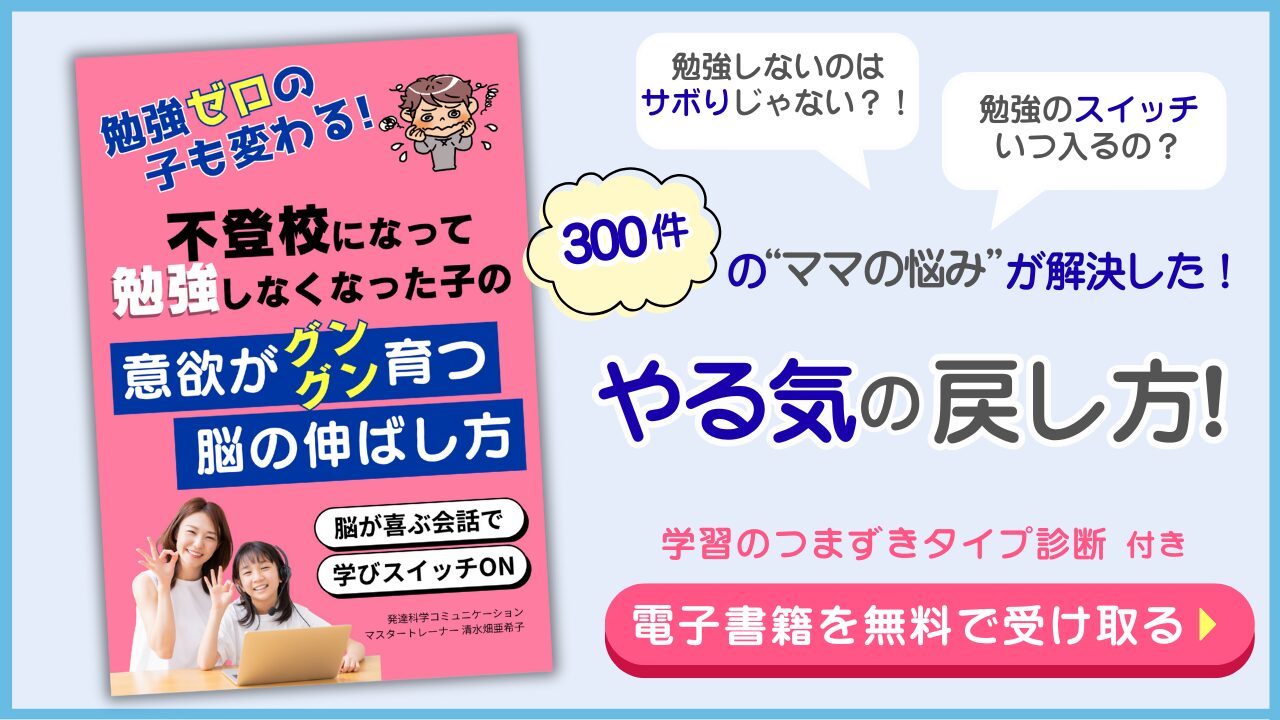
15秒で登録!メールアドレスに無料でお届けします!
4.ママが学ぶと子どもの勉強習慣が自然につく!脳科学コミュニケーションとは
勉強会に参加したママ達からは、勉強に前向きな感想が寄せられました!

難しい言葉の研究テーマでしたが、やることはシンプルで簡単だなと感じました。なぜ、ご褒美を使っても、子どもによってはうまく学習習慣がつかないのかということがわかり、私もさっそく子どもに試してみようと思いました!
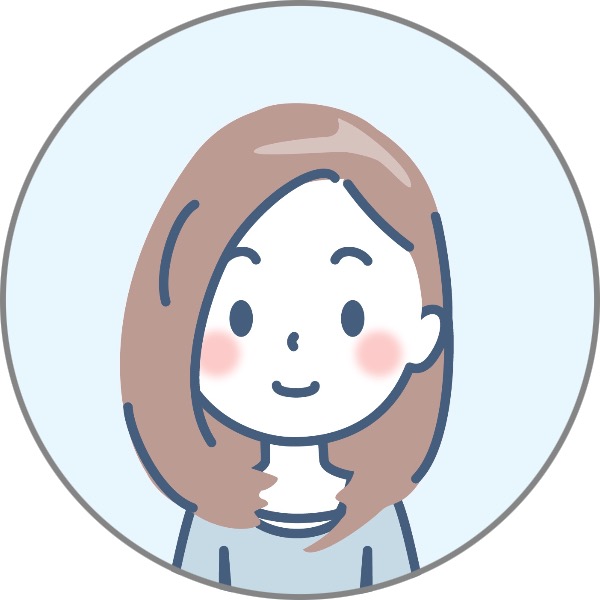
私がやらせたいことばかり考えて、子どものやる気をどうやって楽しく入れることができるのかという視点が全然ありませんでした。勉強させるよりも子どもが嬉しくノってくれる、勉強スイッチの入る声かけを考えたいと思いました!
発達科学コミュニケーションNicotto講座では、発達科学に基づいて子どもがおうちで成長できる方法の研究や発表を行う勉強会を月に2度開催しています。
基礎講座で学んだ知識を元に、更に子どもの成長を加速するために自分で脳科学や発達についての研究を進めていくことが出来ます。
そして研究したことを、みんなでおウチで子どもへ試してみています!
365日が研究です!
お母さんが研究力をつけ、我が子の特性を理解し、我が子にピッタリな子育てを見つけることができると、子どもの成長はどんどん加速されていきます。
勉強のことで悩んでいたことが嘘のように、子どもが伸び伸びと生活できるようになっていきますよ!
皆さんも、パステルジャンプで役立ちそうな記事を見つけたら、
実際にやってみる!
うまくいったら継続してやってみる。
うまくいかなかったらなぜだろう?と考える。
と、プチ研究をしてみてくださいね!

まとめ:勉強スイッチを入れるコツは「ご褒美の順番」だった!
子どもが勉強しないのは意志が弱いからではなく、脳の仕組みに原因があります。
「遊んでから勉強する」という順番を変えるだけで、やる気スイッチが入りやすくなります。
ママが学び、声かけを変えることで、勉強嫌いの子も自分から動けるようになります。
よくある質問(Q&A)
A. 「やる気がない=怠けている」と考えず、脳の疲れをリセットすることが大事です。遊びや休憩を先に入れることで脳の報酬系の回路が働きやすくなり、自然にやる気が戻ってきます。
A. 脳科学的には、楽しい体験を先に入れることでドーパミンが分泌され、集中力が上がります。これは甘やかしではなく、科学的に理にかなったやる気スイッチの入れ方です。
執筆者:パステルジャンプ編集部
▼勉強嫌いの子どものための発達基礎知識を毎日メールでお届けします!