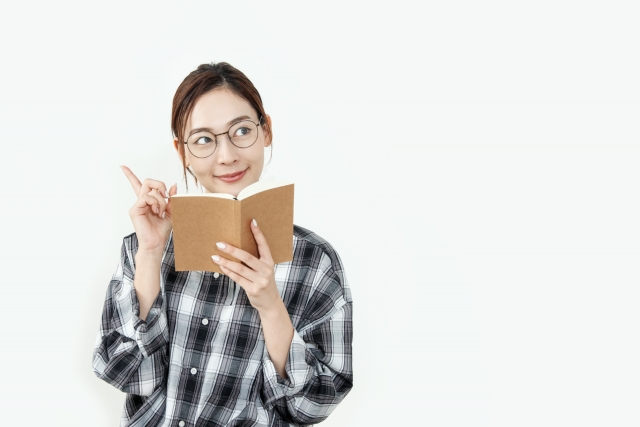| 宿題をやらないからと発達障害の子に「やりなさい!」とガミガミ言うのは絶対にNG!「宿題をしない子」にしてしまうかはお母さん次第です。特に発達障害の子への対応は気をつけないといけません。子どものやる気スイッチを入れる接し方を5つのステップで解説します。 |
【目次】
1.宿題をやらない発達障害の子にNGワードを使ってませんか?
小学生になると始まるのが毎日の「宿題」。
音読や計算、漢字練習など学年が上がるにつれて、量が増えて内容も難しくなっていきます。子どもにとっては決して好きなことではありませんよね。
発達障害の有無にかかわらず宿題は嫌な子の方が多いはずです。それでもやっていくことが当たり前。やらない子には親も声かけてをやるように促しますよね。
しかし、発達障害の子どもはなかなか取り組むことができず、親子バトルなることも多いと思います。そんな宿題をやらない発達障害の子に困っているお母さんに確認してみてほしいことがあります!
「どうせできない」を加速させてしまうような声かけをしていませんか?
実は、私たち親の世代は「宿題は嫌でもならなきゃいけないもの」と頑張ってこなしてきた世代。
宿題をしっかりやって当たり前、習ったことなんだから正解して当たり前、という考えがどうしても残ってしまっています。
例えば、
・宿題のドリルを頑張ってやり終え、〇付けしてみると全問間違えていた…
・字が汚い
ということは、勉強が苦手なお子さんにはあり得ることだと思います。
そんなとき、
「ここもここも同じ間違いをしてるじゃない!」
「何回おんなじ間違いをするの!?」
「もう〇年生なのに…」
「もっと丁寧に書きなさい!」
と責め立てたり、悲観したりしてしまっていませんか?これ、絶対にNG!子どもが自信とやる気を失って、「どうせできない」が加速してしまう声かけです。
これでは宿題をやらない子になってしまうのも当然かもしれません。ネガティブな声かけはNGです!

「宿題をしない子」への別れ路はお母さんの対応次第かもしれません!発達障害の子どもには、お母さんの宿題に対する考えと子どもへの対応が勉強嫌いにしない鍵となります。
2.どうして宿題は毎日あるの?~狙いとNGポイント~
どうして毎日宿題が出るのでしょうか?
おそらく、学校の先生方からすると、宿題を出すことには3つの狙いがあります。
①授業で習った内容を宿題に出して繰り返し学習させることで、授業内容を定着させる
②毎日勉強する習慣をつける
③指示されたことを確実にやり遂げる習慣をつける
たしかに、1度授業を聞いても完全に理解して覚えることはできません。学びの習慣をつけることは大事です。
指示されたことを確実に、しかも期限内にやり遂げることは社会に出てからの必須スキルです。
こう考えてみると、宿題の役割って大きいですよね。

宿題の役割が大きい一方、かえって宿題が意味をなしていないケースもあります。
本来、勉強の理解度や進捗、やる気、集中力、理解するのに必要な力は子ども一人ひとり違うはずです。
それなのに、クラス全員に同じ内容の宿題を出される、という現実があります。これがNGポイントです。
授業についていけない子が宿題に取り組むとどうなるのでしょうか?当然分からない問題だらけ、×だらけですよね。
このようなことが続けば、子どもは「どうせ宿題なんかやってもできない!」と思うようになっていきます。
「どうせできない」は、この後にどういう思考が続くと思いますか?
「どうせできない」
↓
「できないからしたくない」
↓
「したくないからやらない」
というネガティブな思考のループです。
「どうせできない」と思うと、やる意味も見いだせず、行動しないということに繋がりやすいのです。

勉強や宿題ができない、やりたくない、だからしない、ということをきっかけに、学校生活そのものに対してやる気がなくなってしまう可能性もあります。
これは脳の発達においてはとても重大な問題です。脳が発達していくためには行動することが不可欠だからです。
学習の定着に役立たない宿題で、子どもがやる気をなくして行動しなくなるなんて、絶対に嫌ですよね!
ですから、「うちの子、なんで宿題ができないんだろう?」と思ったら、まず授業の内容が理解できているのかをチェックしてください。
そして、お母さん自身に、
「うちの子にこの宿題はちょっと違うな」
「宿題よりもうちの子に必要な学びがあるはず」
という考えを必ず持っておいてほしいのです。
もしお子さんが「宿題できない自分はダメなんだ」と自信を無くしているなら、お母さんのこういった考え方はきっと救いになります。
もし、「できないからしたくない!」というネガティブなループに入っているのなら、少しでも「できるかも」とポジティブになるような工夫で、やる気と自信を与えてあげましょう。
3.宿題をしない子にしない!発達障害の子がポジティブに取り組める対応
子どもが取り組んだ宿題が間違いだらけだったり、字が汚かったとき、お母さんはどういう対応をすればいいのでしょうか?
まずは、お母さんの第1リアクションが大切です。宿題が間違いだらけだったとしても、「え!?これ何!?」「全部間違えてるじゃない!」と指摘したい気持ちはぐっと抑えてください。字が汚い時も同じです。
そして、深呼吸してから穏やかな声で「宿題やったんだね!」と事実を認めます。
そうです!子どもは宿題をやったんです。
最後まで苦手な宿題を頑張ったんです!この点はしっかりほめてあげてくださいね。
そして「見せてくれてありがとう」と言ってあげてください。まずは、よくできたかどうかではなく、宿題をやって見せてくれたことに注目してくださいね。
そして、どんなことでもお母さんは受け止めるよ!という姿勢を見せることで、何でも言える良好な親子関係を構築しましょう。
これで宿題をしない子にはならない防止はできました。しかし、間違いだらけの宿題はどうしたらよい?と思うお母さんもいますよね。そこで、「できた!」という成功体験でやる気を与える5つの接し方をご紹介します。

◆①子どもの不安に寄り添う
大人でも子どもでも、間違いだらけのドリルを見て平気な人間はいません。子どもも「お母さんがこれを知ったら、叱られるかも…」「お母さんが悲しむかも…」と不安を抱えています。
その不安を解消しなければ、子どもは都合の悪いことを親に隠すようになってしまいます。冗談を言って笑っていても、不安から目をそらすためにやっていると考えましょう。
もっと繊細な子どもなら、間違うのが怖いという理由で宿題をやらないということだって考えられます。このような状況では、子どもが学習を理解できているかどうかに関係なく、子どもの心の不安に寄り添うことが必要になります。
「間違っても大丈夫だよ」 「お母さんも子どもの頃はたくさん間違えたな」 など安心や共感する声かけをしてあげましょう。
◆②前向きになれる声かけ
同じようなミスをしているということは、1度正しいやり方を身につければ、全部正答するというメリットがあります。
これはチャンス!「ひとつひとつ、やり方を丁寧にみていこう」「1回覚えたら全部できるようになるよ」「一緒にやってみようか」 と前向きになれるような声をかけましょう。
◆③お母さんと一緒に取り組む
全部間違っているのであれば、そもそも、やり方が分かっていなかったという可能性が高いです。お母さんはまず1問、やり方を丁寧に説明し、一緒に回答してあげましょう。
子どもが「分かった!」「できた!」と実感できるように対応し、できたらしっかり褒めてあげましょう。
◆④時間と心の余裕を持つ
何問一緒に回答するかは、子どもの理解度にもよりますが、子どもが希望したら全問一緒にやるという時間と心の余裕を持つことも重要です。
お母さんから「一緒にやってみようか」と声をかけたのであれば、子どもの方から「分かった!自分でやれるからもういいよ」と言えるまで、じっくり付き合ってあげてくださいね。
◆⑤成功体験の積み重ね
不安を解消するためには、お母さんと一緒に一問一問回答して「できた!」という成功体験を積み重ねることが大切です。
この成功体験の積み重ねが、子どもたちのやる気をさらに加速させる源になります。ぜひ、宿題が間違いだらけのときこそ、「できた!」を実感できるような対応と声かけをしていきましょう。
いかがでしたか?宿題をやらない発達障害の子には
・授業を理解できているか
・「できないからやりたくない」と感じていないか
・ネガティブな声がけはNG
・ポジティブになる声がけや関わり
を意識してくださいね。
そして、大切なことは、たとえ勉強が苦手でも、「勉強嫌いにさせない」こと!
嫌いでなければ、後から十分挽回できますよ♪

宿題に関する記事はこちらにもあります。ぜひ併せて参考にしてくださいね。
▼勉強が苦手な子の脳をYouTubeで発達させることができちゃいます▼

勉強は苦手だけど、嫌いじゃない!と言える子に育てる方法はこちらから!
執筆者:丸山香緒里
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)