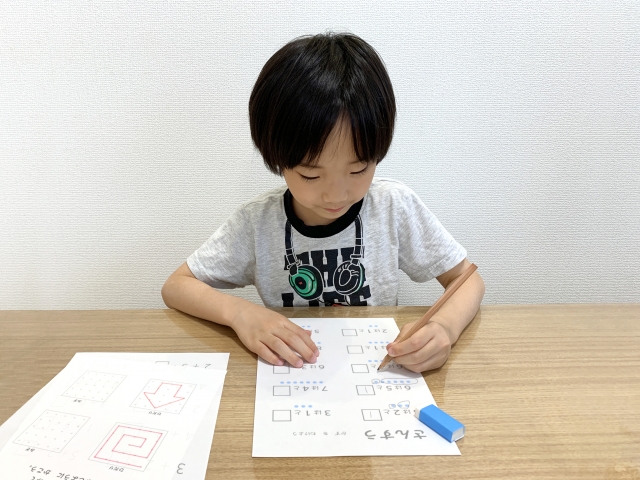| 発達障害の子どもの宿題に時間がかかり過ぎて、親子でイライラしていませんか?発達障害の子どもが宿題に集中できないのには理由があります。今日から毎日の宿題バトル・宿題地獄から抜け出したい方へ、宿題に時間がかかる子の集中力がUPする秘訣を伝授します! |
【目次】
1.発達障害の子の終わらない宿題にイライラ
2.だから時間がかかる…集中できない発達障害の子あるある
3.秘策①宿題をサクサク進められる魔法の言葉
◆お母さんからの肯定的な声かけ
◆終わっていることに着目した声かけ
4.秘策②「ご褒美」でやる気を倍増させる
5.秘策③適切なレベルの宿題を適切な量だけ取り組む
1.発達障害の子の終わらない宿題にイライラ
発達障害やグレーゾーンの子どもの宿題問題!困っているお母さんはたくさんいらっしゃると思います。
毎日宿題があるという学校が一般的。お母さんは宿題が進まない子どもを見て毎日イライラしていませんか?
実は、私もその一人でした。
息子は小学校2年生。発達障害・自閉症スペクトラムの診断がありますが、知的発達の遅れはないため、通常級で頑張っています。
うちの学校も、毎日必ず宿題が出ます。
音読、漢字練習、算数のプリント。週末には作文が出ます。
確かに量は少なくありません。けれど、私からすれば「集中すれば20分もあればできるはず!」という量です。
ところが、息子はなかなか集中できません。
1問解いては全く関係ないことを話し出したり、
丸付けの丸の形にこだわりだしたり、
ちょっとトイレ行ってくる!と脱走したり…
気が付けば1時間はあっという間に過ぎています。
振り返ってみると、宿題を解いている時間よりも脱線している時間の方が明らかに長い状況でした。
集中すれば20分で終わるのに、脱線ばかりで3倍以上の時間がかかる…なんて時間をムダにしているんだろう?と思うとイライラして仕方ありません。宿題に付き合う時間はまさに地獄でした。
私に限らず、子どもがやっと宿題をやり始めた!とほっと一息…と思ったら、
名前だけ書いて止まっている!
ぼーっとしている!
消しゴムで遊んでる…
ということはありませんか?

宿題なんてさっさと終わらせれば、その分遊ぶ時間だって増える。どうしてそんなこと分からないの…と思っているお母さんは多いはず!
実は、発達障害の子どもたちが、宿題に集中できない理由はたくさんあるんです。
2.だから時間がかかる…集中できない発達障害の子あるある
発達障害の子どもが宿題に集中できない理由はたくさんあります。
宿題を始めたはずなのに途中で手が止まってしまうのは、脳のエネルギー不足が原因かもしれません。
人が行動を起こすとき、脳は大きなエネルギーが必要です。
特に「宿題」という嫌なイメージのあるものに取り組むとき、さらに大きなエネルギーが必要なんです。
そのエネルギーは、その行動が終わるまでずっと同じ量が必要ではありません。
車のエンジンのように、行動を始めるときにだけたくさんのエネルギーが必要になるのですが、1人ではなかなかエネルギーを持続することが難しいのです。
きっと子どもたちはこう思っています。
宿題イヤだなぁ…
だけど、明日持って行かないといけないしなぁ…
やば!お母さん怒ってる!
やりたくないけど、しょうがないかぁ…
やっぱりイヤだなぁ…やりたくないなぁ…
こんな状態で、サクッと始められるわけはないのです。
そのほかにも、
・いつになったら宿題が終わるのか、見通しが立たなくて不安
・宿題がつまらなくて、ついつい別のものに興味が移る
・宿題が難しすぎて分からない
・量が多くて途中で疲れてしまう
など、様々な理由があります。

それでは、サクサクと宿題が進めるようにするには、どうすればいいのでしょうか。
3.秘策①宿題をサクサク進められる魔法の言葉
さあ、ここから宿題をサクサク進めることができる集中力UPの秘策をお伝えしていきますよ。親子で宿題のイライラを乗り越えて行きましょう!
こんなことありませんか?2~3問だけ解いて子どもの手が止まってしまった!そんなとき、お母さんはついつい、
「まだいっぱい残っているよ!」
「まだ2問しかできてないじゃない!」
と声をかけていませんか?
宿題の序盤は、まだまだエンジンがかかり切っていない状態。脳はエネルギーを欲しています。そんなときにネガティブな声をかけると、子どもは一気にやる気と自信をなくしてしまいます。
宿題に集中できない子どもをネガティブな言葉でけしかけるのではなく、エネルギー不足を補うような対応をすれば、子どももスムーズに宿題に取り組めるはずです。
子どものエネルギーになるもの。それはお母さんの注目と肯定的な声かけです!
◆お母さんからの肯定的な声かけ
自分が「宿題」という嫌なものを頑張っているときに、お母さんが全然こちらを見てくれない…ということで、やる気がなくなってしまう子どももいます。
お母さんもお忙しいので、ずっと子どもの隣にいてあげることは難しいかもしれませんが、
「宿題始めたのね」
「進んでるね」
「がんばってるね」
と注目してあげましょう。
お母さんが自分の行動に気づいてくれていることで、やる気がでてきます。「ファ~イトッ!」など明るい口調で励ましてあげるのも効果的ですよ。
◆終わっていることに着目した声かけ
お母さんが、
「おっ!もう1問終わったんだね」
「もうここまで進んだね!」
と終わっていることに着目して肯定的な声かけをしてあげましょう。

「1問終わった」と言われたら次は2問目だと分かりますよね。こんな風に声をかけると、子どもは次の問題に目を向けやすくなります。
「もう半分終わったね!」
「もう1ページ終わったね!」
と子どもの様子を見ながら、宿題の進み具合に応じて声をかけてあげてくださいね。
まだ問題が解けていなくても大丈夫!
「椅子に座れたね」
「連絡帳で確認したのね」
「鉛筆、準備したんだ」
こんな風に、何かしら「終わった行動」はあるはずです。
「ゲーム終わらせたのね」「おやつ食べ終わったのね」など、宿題に関係ないことでもOKです!
子どもが宿題を始めたら、お母さんは終わったことに注目して肯定的な声かけをこまめに行うことで、子どもの手が止まらず、宿題をサクサク進めることができます!
4.秘策②「ご褒美」でやる気を倍増させる
宿題に対するイヤなイメージを、払拭することは難しいことです。お母さんだって、大人になったからといって宿題が大好き!というわけではないですよね。
宿題に対するネガティブなイメージって、相当根深いものだと考えた方がよさそうです。
宿題嫌いになる原因は、
・宿題を忘れて先生に怒られてしまった
・誤答を友だちに指摘されて恥ずかしかった
・宿題のせいで遊ぶ時間が減る
・とにかくメンドクサイ
など、いくつかの理由が考えられます。
嫌なものをスムーズに進めるために必要なもの、それはご褒美です!
「宿題が終わったらおやつにしようか!」
「宿題が終わったらゲームしていいよ!」
こんな風にご褒美を用意することで、子どもが宿題にさっと取り組めるようにするのは有効です。
ご褒美を用意すると、宿題の途中での声かけも、バリエーションが増えますよね。「もう半分終わったよ!あと半分でおやつだから頑張って!」と子どもを励ますことができます。
また宿題が多いときや、子どもが疲れやすいタイプだったりするときは、途中でご褒美を用意するのもアリです。
途中でご褒美タイムを設ける場合、短い時間で子どもが満足するご褒美を考えましょう。
ゲームやテレビは時間がある程度必要ですし、残りの宿題をやりたがらなくなってしまうおそれがあります 。
「ここまで終わったら、チョコ1個食べる?アメちゃん1個食べる?それともお母さんがマッサージしてあげようか?」
こんな風に小さなご褒美をいくつか準備して、子どもに選ばせると満足度が高くなります。
宿題をしながらおやつは食べちゃダメ!という考えは捨てて、お子さんに合ったやり方を実践することが大切。
子どもがやる気になりそうなご褒美を用意して、肯定的な声かけをこまめに行いましょう!
息子はこの2つの方法で、宿題がサクっと終わるようになり、パステル総研のオリジナル教材や通信教材まで手が伸びるようになりました。
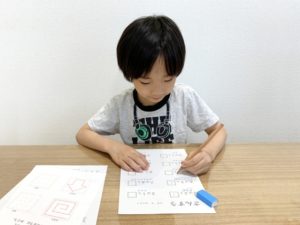
5.秘策③適切なレベルの宿題を適切な量だけ取り組む
①お母さんが肯定的に、終わったことに注目して声をかける
②ご褒美を用意する。宿題の途中でもOK!
この2つの秘策を使っても、どうしても宿題が進まないケースが2つあります。
それは、
・宿題が難しすぎる
・宿題の量が多すぎる
という場合です。
そもそも、学習の理解度は個人差がありますし、子どもの体力や家庭の事情もそれぞれです。 それなのに、クラス全員一律で同じ宿題に取り組む必要はどこにあるのでしょうか?
同じ宿題でも、簡単すぎる子もいれば、難しすぎる子だっているはずです。
まず、お母さんが「宿題って何のためにやるんだろう?」と考えなければいけないと思います。 宿題が子どもにとってプラスになるようにしていきましょう!
◆①宿題が難しすぎる場合
宿題をすると、ひどい癇癪を起こしたり、時間がかかりすぎたりする場合は、学習の習得度に大きな遅れがないか学校と相談することも必要です。
本来宿題は、授業で扱ったことの復習として出されます。適正な時間で終われないなら、授業の内容が分かっていないという可能性が高いです。
学習に遅れがある場合は、
・先生に宿題の内容を変えてもらう
・家庭で子どもの学習レベルにあったものに取り組み、それを宿題として扱ってもらう
などの対応をとりましょう。
宿題が「子どもの学習の理解を高めるもの」だとしたら、子どもに合ったものを取り組まないと意味がないですよね。
◆②宿題の量が多すぎる場合
日本の教育は反復学習が大好きです。漢字を何度も書いて練習したり、同じようなドリル問題を繰り返したり。
分かっているのに繰り返す必要ってあるのでしょうか?
数をこなすよりも、理解しているかどうかの方を大事!量が多すぎる場合は、先生に量を減らしてもらうようにお願いしてOKです。
まずは子どもがサクッと終わらせられる量まで減らして、宿題や勉強への抵抗をなくしていくのがいいと思います。

私も、自分の子ども時代は「宿題は絶対にしないといけないもの」と思っていました。忘れてしまったときは親にも先生にも叱られましたし、この世の終わり!というレベルで落ち込みました。
ですが、発達科学ラボのトレーナー・リサーチャーたちに話を聞くと、宿題の内容も量も、子どもの特性や理解度に合わせてアレンジしている人ばかり!私の宿題に対する考え方を柔軟にしてくれました。
子ども一人一人が、無理なく学習への理解を深められる形にアレンジしていいんです!適切なレベルの宿題を、適切な量取り組むようにすれば、宿題ができないという子はいないはずです。
小学校に入学すると、宿題がつきもの。サクッと終わらせたいなら、
①子どもの理解度に合った宿題を適切な量取り組む
②肯定的な声かけを絶えず行う
③ご褒美でやる気をアップさせる
という集中力UPの3つのポイントをぜひ試してみてくださいね。
宿題については、こちらでも解説しています。ぜひチェックしてくださいね!
▼▼おこさまの脳を育て学ぶ力を伸ばす秘訣はこちらです!▼▼