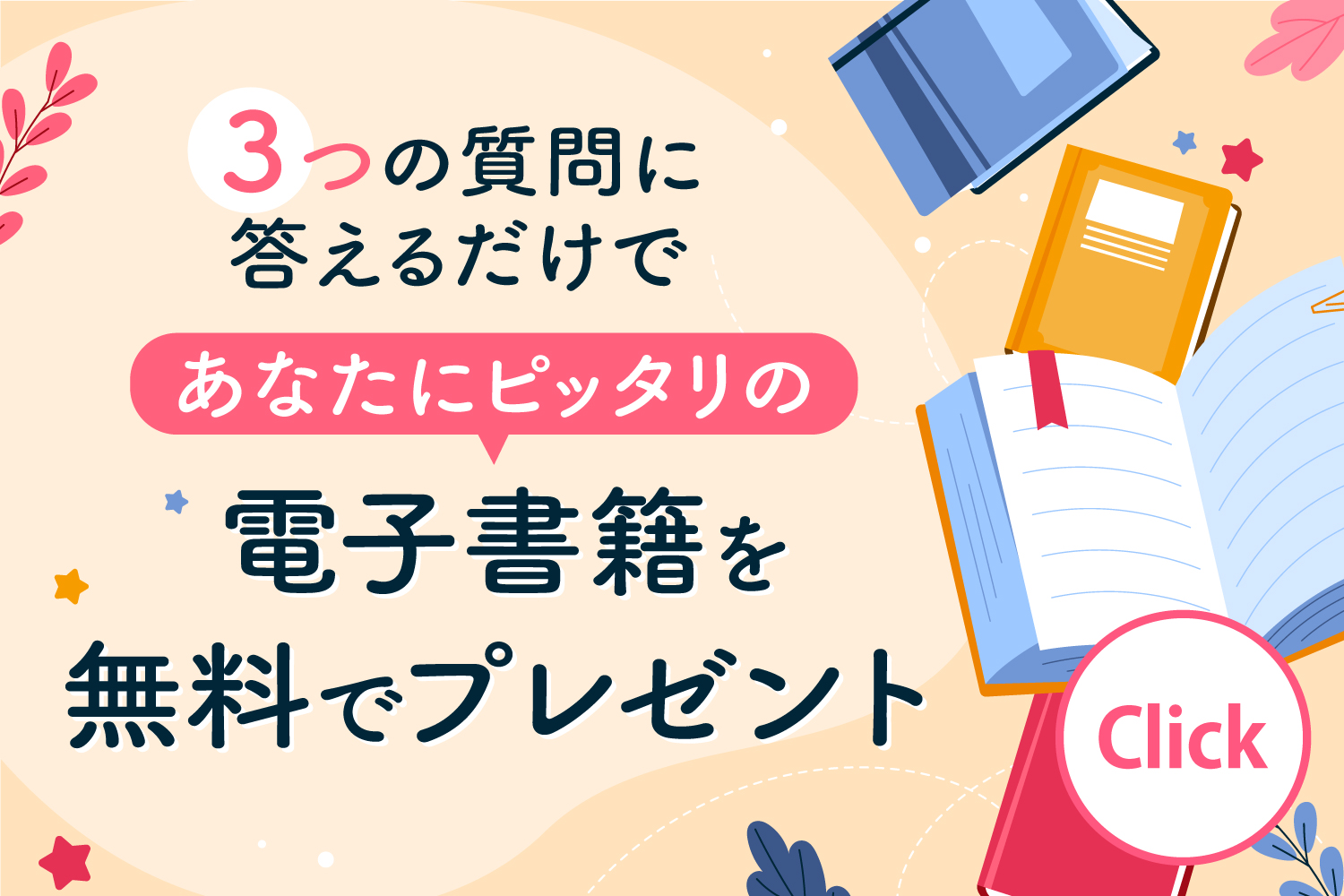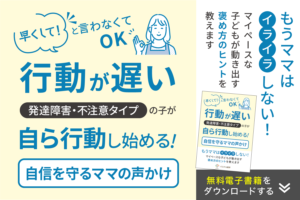発達障害・ADHDの息子が鉛筆や爪など、いろんな物を噛む「噛み癖」があります。何度注意してもやめられません。どのように対処したらいいでしょうか?
5歳・男の子のママ

何でも噛むという「噛み癖」があると、周囲の目も気になってしまうこともあり、ついつい注意してしまいますね。息子もよく鉛筆などを噛んでいて悩んでいました。私が実際に行った噛み癖がある息子への対応についてお伝えしますね。
発達科学コミュニケーション リサーチャー 石井花保里
【目次】
1.噛み噛みし過ぎで、いつもでボロボロ…発達障害グレーゾーンの息子の文具達
2.「どうしても噛んじゃうんです!」噛み癖のある子どもなりに意味があった
3.噛み癖は注意しなくても大丈夫!噛む行為へのおススメ対応3選
①噛んでいい物を与える
②テンションを上げる声掛け
③落ち着ける環境を作る
1.噛み噛みし過ぎで、いつもでボロボロ…発達障害・ADHDの息子の文具達
発達障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)の子どもの中には、ついつい物を噛んでしまう噛み癖のある子もいて、悩んでいるお母さんが多いですね。
・鉛筆はいつもぼこぼこ
・消しゴムはボロボロ
・自分の爪を噛みすぎて切るところがない…
そのほか、お箸、ゴム製の物、小さい硬いおもちゃなど、なんでも噛んでいますね。
発達障害・ADHDの私の息子も小さい頃から物を噛む噛み癖がありました。
それがあまりにひどかったのです。
お箸は噛んですぐに先を折ってしまうため、2ヶ月に1回は買い替えていました。
鉛筆は芯まで噛むので、周囲からもびっくりされます。
歯ブラシに至っては、変えてもたちまち毛が開いてしまうので、大量買いをしていました。
一人で遊んでいても、ちょっと見ると何かいつも噛んでいるので、
「やめなさい」
「また噛んでるよ」
と何度も注意していました。
そのときはやめても、いつの間にかまた噛んでいます。
もう、どうしたらいいの?と私もとても悩んでいました。

注意してもやめられない、何でも噛んでしまう噛み癖には、実は、その子なりに意味があったのです。
今回は、私が息子に行った噛み癖がなくなる解決策についてお伝えしていきますね。
2.「どうしても噛んじゃうんです!」噛み癖のある子どもなりに意味があった
どうして発達障害・ADHDの子どもには、ついつい物を噛むという行動になることがあるのでしょうか?
それは、噛む行為にはその子どもなりの意味があるからです。
まず、子どもがどんなときに噛んでいるか観察してみましょう。
・手持ち無沙汰になっている
・ボーっとしている
・集中している
・ストレスがある
このようなときによく身の回りの物を噛んでいると思います。
これは感覚遊びとして噛んでいる場合が多いです。
感覚遊びとして、噛む感覚を楽しんでいるのです。
子どもはやることがなくなってしまったときに、とりあえず自分の好きなことをしようとしますよね。
発達障害・ADHDの子どもには、感覚を感じすぎる子がいます。そのため、感覚遊びを好み、身近にある物を噛んでしまいます。
もともと、赤ちゃんの頃から子どもは、口に物を入れて、情報を収集しています。
それほど、口は感覚が敏感な部位なのです。
口に入れて感覚情報を脳に送っています。
強く噛むと歯に力の入る感覚が得られる鉛筆や、弾力があって心地よい感覚の消しゴム、噛み切ることができる爪は、自分の好きな感覚刺激であることが多いです。
覚醒が下がっていてボーっとしているときや、集中しているときも同じように感覚遊びをしています。
不安を感じたりイライラしたりしているときにも、噛み癖がでることがあります。
気持ちを落ち着かせようとしたり、ストレスを発散させるために行っています。
発達障害・ADHDの子どもは特に、好きな感覚を得ようとして爪などを噛み、気持ちを落ち着かせようとします。
このように、子どもなりに噛む行為には理由があったのです。
けれど、学校など人の多い場所や、公共の場で物を噛んでいると、周りの人に不快感を与えてしまいます。

なんでも噛むことは不衛生だし、爪を噛むと菌が皮膚に入る可能性もあります。
不安な気持ちを落ち着かせたり、感覚遊びとして行っている噛み癖は、発達障害・ADHDの子どもなりに意味があるので注意してやめさせることは難しいのです。
そこで私は別の方法で噛む行動をやめさせることに成功しました。
3.噛み癖は注意しなくても大丈夫!噛む行為へのおススメ対応3選
お母さんの工夫次第で、注意してもやめられない何でも噛む噛み癖に対応できますよ。
私のおススメ対応3選をご紹介していきますね。
◆①噛んでいいものを与える
どうしても物を噛んでしまうのであれば、安全に噛んでもいい代替の物を与えると効果があります。
今は、噛み癖に対応した物が売られていますし、乳幼児用の歯固めグッズも用いてもいいと思います。
息子にはシリコンでできた「噛むグッズ」を与えていました。
何か噛み始めるとそれを渡したり、自分からそれを噛んだりしています。
やわらかい物や硬い物など色々な感覚を好むので、同じものだと飽きてきます。
そのため、様々な種類を用意しておきました。
これなら噛んでも大丈夫と子どもは安心して噛めますし、親も衛生的に安全に噛んでいるので、注意することがなくなります。
注意することがなくなると、噛む行為自体がだんだんと落ち着いてきました。
親が注意をしないことが、噛み癖をやめさせる秘訣なのです。
今では、息子には「噛むグッズ」も必要がなくなりました。
◆②テンションをあげる声掛け
ボーっとしていて覚醒しておらず、物を噛んでいるときには、覚醒を上げるような関わりをすると噛み癖が減ることがあります。
息子は車や運動が好きなので、ボーっとしていて噛む行為が始まれば、「車のおもちゃで遊ぼう」「外で自転車に乗らない?」っと、本人が好きな遊びに誘っていました。
すると、噛む行為のことは忘れて「車で遊ぶ!」「外に行こう!」と言って好きな遊びにうつれました。
噛むことに注目するのではなく、本人が好きなことができるよう気持ちの切り替えが大事です。
子どもが大好きなこととテンションが上がるような声掛けを工夫してみてくださいね。
◆③落ち着ける環境を作る
不安やストレスを感じている場合には、本人の不安を取り除いて落ち着ける環境を作ることも大切になります。
まずは、お母さんが子どもの不安を聞いてあげましょう。
「何か心配なことがある?」と優しく声を掛けてみましょう。
発達障害・ADHDの子どもは自分の言葉で表現しにくいこともあります。
その場合は、不安なときにどう対応したらいいのかについて、前もって子どもと一緒に考えてもいいと思います。
噛む行為以外の感覚で、何か刺激があれば落ち着く場合もあります。
例えば、やわらかいボールなどを握らせるなどの別の感覚刺激です。ぜひ、お子さんに合ったものを一緒に考えてみてくださいね。

いかがでしたか?
何でも噛む噛み癖のオススメ対応3選は
①噛んでいい物を与える
②テンションを上げる声掛け
③落ち着ける環境を作る
です。
発達障害・ADHDの子どもの噛み癖には意味があります。
お母さんがお子さんの様子をよく観察して、環境を整えたり、楽しい声掛けをしていきましょう。
ご紹介した方法をぜひ試してみてくださいね。
発達障害・ADHD幼児の困りごとについてはこちらでも解説しています!
\「早くして!」は効果なし/
子どもが自ら動き出す方法を教えます
↓↓↓
ADHDタイプの困りごとを解決する方法をたくさん紹介しています!
▼ご登録はこちらから
▼無料小冊子プレゼント▼
育てにくい子が3ヶ月で変わる!
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
↓↓↓
執筆者:石井花保里
(発達科学コミュニケーション リサーチャー)
(発達科学コミュニケーション リサーチャー)