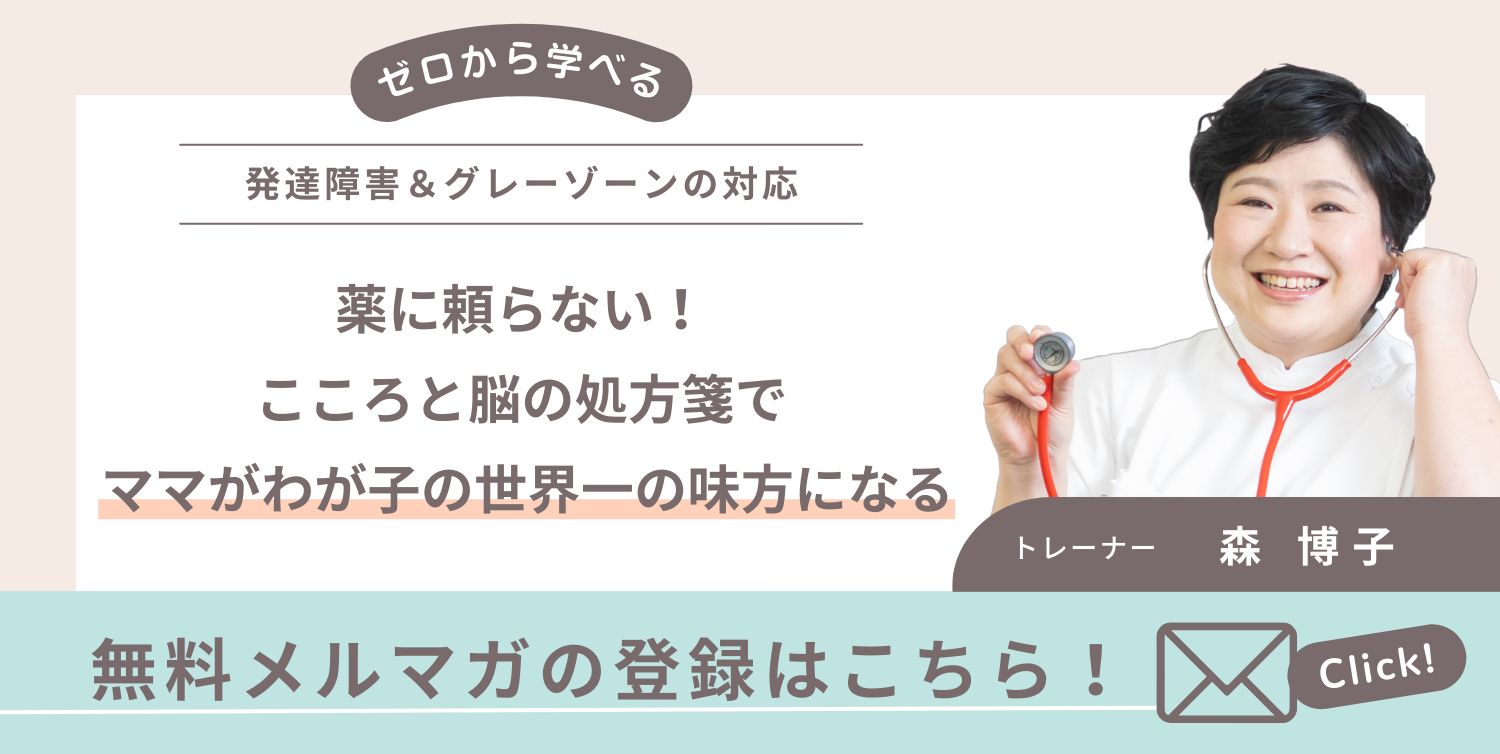「もう、母親やめたい…助けて!」思うようにいかない発達障害の子の育児に自信を失い、誰にもわかってもらえずに限界まで1人で抱え込んでしまっていませんか?発達障害の育児やめたい!と疲れたママの心がスーッと楽になる処方箋をお届けします。
【目次】
1.「母親やめたい」と思うことありませんか?
2.「お母さんやめます!」と発達障害の子どもに言ってしまった私
3.発達障害の育児やめたい!と疲れたママの心がスーッと楽になる方法
◆自分の気持ちと向き合う
◆ゴキゲンになる方法を持つ
1.母親やめたい!と思うことありませんか?
皆さんは「もう母親やめたい!」「助けて!」そう思ったことはありませんか?
うんうん、とうなずく方が多いと思いますが、何となく、それを大っぴらに発言するのは気が引ける…と思う方が大部分でしょう。
それはなぜかというと、日本には「母性神話」という考え方が広く知られているから。
「母性神話」とは、
・母親は自分のことはさておいて、子どもに尽くすことが愛(母性愛)である。
・女性には、生まれつき「母性愛」が備わっている。
・だから、母親は育児をするのが当然である。
という考え方です。
今どきそんな古くさい考え方なんて…と思いますが、今でもまだ、この考えは日本の社会では根強く残り、広く信じられているのです。
「母親やめたい」と大きな声で言いにくい、なんてひどい母親だろうと思われるのではないか、と心配してしまう理由は、ここからくるものなのです。
「子どもが思い通りに動いてくれなくて焦ってしまう」
「いつもイライラしてばっかりいる」
「なんだか育児が楽しくないな…」
そのような悩みは、誰にでもあるもの。
とはいえ、日本のお母さんたちがぶち当たる育児環境はそんな不安や悩みを吐き出しにくい環境なのです。
だから、それを誰にも話すことができず、
「育児やめたいと思う自分って、なんてダメなお母さんなんだろう」
「私がお母さんじゃない方が、この子は幸せなのかもしれない」
と落ち込んでしまうことがあるのです。

しかも、発達障害の特性のある子どもを育てるお母さんたちは、さらに追い詰められています。
お子さんの特性からくる行動に悩んだり、期待通りの行動をしてくれないことにがっかりしてしまうことがあるからです。
目が合っても笑いかけてくれない、どんなに大きな声で呼んでも言うことを聞いてくれない、常に落ち着きがなく走り回るのでしつけがなっていないって思われる。
このような落ち込みがどんどん積み重なってくると、「もう母親やめたい!」と発達障害の子育てが限界に感じてしまうのです。
発達グレーゾーンの困り事を
大人に持ち越さない
親子のコミュニケーションがわかります
↓↓↓
大人に持ち越さない
親子のコミュニケーションがわかります
↓↓↓
2.「お母さんやめます!」と発達障害の子どもに言ってしまった私
私には、発達障害の注意欠如・多動症(ADHD)タイプの小学2年生の息子と、やんちゃ盛りの4歳の息子がいます。
長男の多動と攻撃的な特性に悩んでいた1年半前より発達科学コミュニケーションを習得し、今では子どもへの対応で困ることはほぼない日々を送っています。
そんな私も、仕事の忙しさや、夫への不満、同居している義両親への気遣いなどのストレスがたまり、自分の中のイライラが止められなくなったことがありました。
そしてある週末、それが爆発してしまったのです。
ゲームに夢中で、なかなかやめられない子どもたち。
それを怪訝な顔で見ているけど、注意しない夫。
様子をみている私に対し、機嫌が悪いように見える義両親。
体調が悪かったことも重なり、イライラが止まらなくなり、ついに、子どもたちに対して、
「わたし、お母さんやめます!」
と宣言してしまったのです。

それまで何度も「子育てやめたい」と思ったことはありましたが、口にしたのは初めて。
はじめは笑いながら聞いていた子どもたちも、いつもと違う母の様子に戸惑い、ついには泣き出してしまいました。
何度も「ごめんなさい、ちゃんとやるから」と言う子どもに対し、口から出てくる言葉は辛らつなものばかり。
暴走した私の心は、もう自分の意志では止められなくなっていました。
その日、何度も何度も「母ちゃん」と呼んでくれる子どもに、私が返事をすることはありませんでした。
そして、号泣しながら眠ってしまった子どもたち。
その寝顔を見ながらも、自分の気持ちはおさまりません。
翌朝も怒りがおさまらない私に対し、子どもたちはおびえた顔で話しかけてきます。
そして、朝の身支度を自分たちのチカラで完璧に仕上げた子どもたち。
そんな子どもたちをみて「やればできるじゃない」「よし、合格」と思ってしまった私。
「はっ」としました。
私は、何に合格を出してるんだろう。
子どもたちを怖がらせて言うことを聞かせる。こんなの、何の意味があるんだろう。
急激に冷めていく怒りと、このままの気持ちで登園・登校させてはいけない、と我に返った私。
長男を見送るときに、「ごめんね、母ちゃんに戻ったよ」と言うのがやっとでした。
すると、それを聞いた長男の顔がぱーっと笑顔になりました。
何度も何度も振り返りながら、「母ちゃん!!母ちゃん!!いってきまーす!!」と繰り返し、嬉しそうに手を振る長男を見て、胸が痛み涙が止まりませんでした。
そのときの長男の顔は、今でも目に焼き付いています。
3.発達障害の育児やめたい!と疲れたママの心がスーッと楽になる方法
今回、私の「お母さんやめます!」宣言のお話をしましたが、きっとどんなお母さんにも、こういう状況って思い当たる節があると思うんです。
でも子どもにとって、「お母さんやめます」という言葉は、どんなに重いものなのかを、私は身をもって知ることができました。
皆さんには、こんな経験はできればして欲しくありません。
「母親やめたい!」と思っちゃう気持ちは止めなくていい。その気持ちを子どもにぶつける前に、自分の中だけでおさめられたらいいのです。
ですので、発達障害の育児やめたい!疲れた!限界!と、感情が爆発してしまう前に、試してほしい方法をお伝えします!
◆1.自分の気持ちと向き合う
発達障害の子どもの育児をしていると、思うようにいかないことも多くあります。そんな時に、どうしてもイライラしてしまうことあると思うんです。
その時に、笑顔でいよう、優しいママでいようなんて無理して思わなくていいのです。まずは自分のありのままの気持ちを知ることが大切です。
そのため怒りを感じたら、自分に「今の気持ちは何点?」って質問してみてください。
怒りというのは第二次感情だ、と言われています。
何もないところからある日突然生まれるものではなく、ツラさ、イライラ、不安などのネガティブな感情がたまってあふれ出たものなのです。
このネガティブな感情のことを第一次感情と言います。
私の例だと、
第一次感情:身体がツライ、夫への不満、義両親に対する気疲れ、子どもが言うことを聞かずがっかりすることによる、苦しみ、悲しみ、困惑、嫌悪など
第二次感情:「母親やめたい!」怒り
というワケです。
怒りが爆発しないようにするためには、怒りの第一次感情をためないようにするのが得策。
でも、自分の気持ちとはいえ、すべてが簡単にコントロールできるワケではありませんよね。
ですので、自分の中にネガティブな感情が今どのくらいたまっているのかをまず知ることが大切なんです。
お母さんは普段から、子どもや家のことなど、自分以外のことばかりを意識して過ごしていますよね。
そこをあえて、1日何度か、自分だけと向き合う時間を作ってみます。
自分のことを考えるのに慣れないうちは少し時間がかかるかもしれません。
慣れてくると1分ほどのすき間時間でできるようになるので、通勤の車の中や、1人でお風呂に入るときなどを利用するとよいですね。
今の気持ちを点数化するには、0から10のメーターをイメージします。
快適、ゴキゲン、ルンルンなど気分がいい場合は低い点数、イライラ、めそめそ、ムカムカなど、自分の中にたまっているネガティブな感情が多いほど点数が高くなります。
これが6点以上であれば危険ゾーン。ネガティブな感情を減らす行動をしてみましょう。
ネガティブな感情を減らす行動は人によりさまざまですが、自分がゴキゲンになれる方法をいくつか持っておくとよいですね。
では、次にゴキゲンになれる方法をご紹介していきます。

◆2.ゴキゲンになる方法を持つ
発達障害の子どもの育児をしていると、どうしても子どものことを優先しがちで、ママのことは後回しになってしまうことが多いのではないでしょうか。
だけど、ママだって1人の人間。自分が好きなことをしたり、好きなものを眺めたり、そんな時間を持つことも大切なことなのです。
ママの心が楽になれることが、発達障害の子どもの育児には欠かせません。
ゴキゲンになる方法として私の場合は、
・アルバムやスマホの中の子どもたちの写真を見返す。
・「きついときにかけてほしい言葉カード」を作っておき、ネガティブな感情が増えたら壁に貼って、子どもや夫に声をかけてもらう。
・身体がきついときは、家事をお休みする。
・子どもたちからもらった手紙や、一緒に拾ったどんぐりなどを、お気に入りの箱に入れて「宝物ボックス」を作り、それを眺める。
などを実践しています。
時間をかけなくても、簡単にできることはたくさんあります。
いかがでしょうか?
怒りが抑えられないことは、誰にでも起こること。子育てやめたいと思った自分を決して責めないでくださいね!
そんなときは、自分の心の声を聞き、自分を責めるのではなく、いたわり、ほめる。そしてゴキゲンになる。
そんなポジティブサイクルを作って、「お母さん」というステキなお仕事を楽しめますように。そんなお母さんたちを応援しています。
「母親やめたい!」と思う気持ちが軽くなる方法、他にもご紹介しています!
執筆者:森博子
(発達科学コミュニケーションクリエイター)
(発達科学コミュニケーションクリエイター)