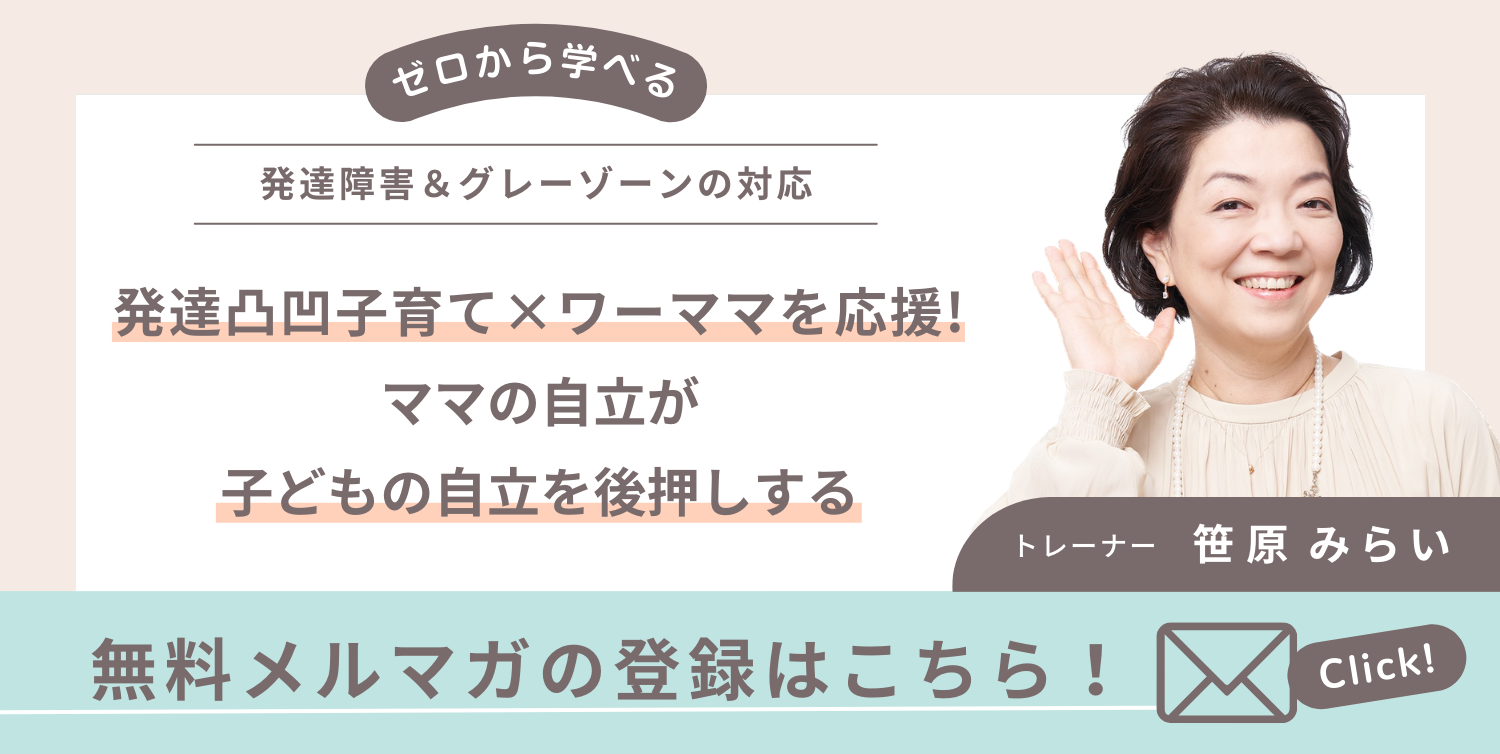| 自閉症スペクトラムの子どもが楽しく過ごしていたのに「急に怒る」そんな経験ありませんか?発達障害ASDタイプの子どもの怒り爆発スイッチの原因を知り対応したら、中学生の兄が優しくなるというオマケまでついてきた私の経験をお伝えしますね。 |
【目次】
1.自閉症スペクトラムの子どもの「急に怒る」理由がわからない!
2.自閉症スペクトラムの子どもの怒り爆発スイッチはこれ!
◆クイズで怒った場面
◆食事中の会話で怒った場面
3.怒りは2次感情
4.怒り爆発スイッチに効いた対応とは?
◆クイズで怒った場面
◆食事中の会話で怒った場面
5.自閉症スペクトラムの怒りっぽい娘の対応で兄への思わぬ効果が!
1.自閉症スペクトラムの子どもの「急に怒る」理由がわからない!
みんなで楽しく遊んでいるときに自閉症の子どもが急に怒る。
周りはどうして怒っているかわからず、きょとん顔。
そんな経験ありませんか?
我が家には、発達がゆっくりで発達障害自閉症スペクトラム(ASD)の傾向がある小2の娘がいます。
なんでもない場面ですぐにキレてカーッとなり、あまりに怒りっぽいので対応に困ることがありました。
例えばこんな場面です。
私と娘で楽しくクイズをしていました。
私が問題を出して娘が答えます。
娘の回答に
「ピンポーン!正解です!」
「ブブ~!不正解でーす♪」
なんて盛り上げながら、楽しい時間を過ごしていました。

すると急に娘が怒りだしてしまいました。
楽しくクイズをしていただけなのに、急に怒る意味がわかりません。
あるいは、こんな場面。
夕食の団欒の時間、私と娘と中学生の息子の3人で食事をしていました。
「今日は学校でどんなことがあったの?」
というような、何てことはない普段の楽しい会話の最中です。
突然娘がガタン!と立ち上がり
「家出してやる~!大っ嫌い!もう私なんていなくてもいいんでしょ~!」
なんて怒りが大爆発。娘がどうして怒ったのかさっぱりわかりません。
こんな感じで、娘は怒る必要がないような場面で怒ってしまうことがありました。もちろん周りはなぜ怒り出したのか意味がわかりません。
発達科学コミュニケーションで発達の知識をつける前の私は
「楽しく遊んでいるのに何?うんざり!」
「構ってほしくて家出とか言ってるんでしょ?面倒臭い!」
と、こんな風に思っていたのです。
しかし、私が発達科学コミュニケーションを学んで娘の特性を理解すると、娘がこの場面で怒りを爆発させる理由が分かりました。
2.自閉症スペクトラムの子どもの怒り爆発スイッチはこれ!
◆クイズで怒った場面
発達障害の自閉症スペクトラムの子どもはとにかく否定されるのが苦手です。
否定を強く受け止めてしまいます。
クイズで急に怒り出した場面ですが、私が発した「ブブ~!」の効果音が悪かったのです。
ピンポーンはいいのですが、不正解の「ブブ~!」により、否定されたというメッセージを強く受け止めてしまったのです。
もちろん、こちらは不正解を思い知らせてやろうとかそういったネガティブな意味は全くありません。
ただ単にクイズを盛り上げようとして効果音を使っているのです。
ところが、こちらの思惑に反して、娘はこの効果音によりとても嫌な気持ちになってしまうということがわかりました。

◆食事中の会話で怒った場面
発達障害の自閉症スペクトラムはコミュニケーションの障害です。
こちらが普通に会話しているつもりでも、感じ方や受け取り方が独特で偏りがあるのです。
ネガティブな情報を受け取りやすく、悪い方に物事をとらえてしまいます。
そしてどんどん不安になっていくことがあるのです。
食事中に私が息子とちょっとでも会話していると、娘は自分が無視されたと思ってしまうようです。
息子は中学生なので会話の内容も大人に近くなり、娘は入れないこともあります。
会話に入れないとどんどん悪いようにとらえてしまうのでしょう。
単にお母さんとお兄ちゃんが食事中の雑談をしているだけなのに、「無視された」「私のことが嫌いなんだ」と感じてしまいます。
少し発達がゆっくりな子なので、理解も追いつかないのもあります。
「私以外の人が楽しそうにしている」と受け取ると、
「私は楽しくないのに」
「無視されているんじゃないか」
「嫌われているんじゃないか」
と不安になってしまうのでしょう。
そして、「みんな嫌い!家出する!」と怒りが爆発してしまうのです。
人間は誰しも怒りを感じることがあると思います。怒りの感情はどうして起こるのか事項でお伝えします。
3.怒りは2次感情
「怒り」の感情が起こる前には「不安」「悲しみ」「寂しさ」などの1次感情があります。
「怒り」は1次感情によって沸き上がる2次感情なのです。
娘はクイズに不正解したとき、お母さんに否定されて「悲しい」と思ったかもしれません。
また、お母さんとお兄ちゃんのおしゃべりに入れなかった時には、自分だけ仲間はずれで「寂しい」と思ったのかもしれません。
このように、怒りの奥に隠れている1次的な感情があるのです。
子どもが表面に出している怒りの感情だけに目を向けるのではなく、その奥に隠れている感情に気づいてあげることが大切です。
つまり、1次感情が怒りの爆発スイッチなのです。
だから、どうして怒っているのかお母さんが気が付いてあげて、その1次感情に寄り添って理解してあげると、「気持ちをわかってくれた」と、怒りも収まってきます。
また、子ども自身も自分の怒りの原因に気が付くとだんだんと怒りの感情もコントロールできてくるのです
次項では私が娘に具体的にどんな対応をしたのかお伝えしますね!

4.怒り爆発スイッチに効いた対応とは?
◆クイズで怒った場面
娘がクイズ不正解の「ブブ~!」という効果音が苦手であると理解してから、不正解の時は効果音を使わないことにしました。
不正解であったときも
「なるほど~!そう考えたのね。」
と一旦受け止める発言を入れてから、静かな声で「不正解です」と伝えるようにしました。
こうすると娘はクイズをしていて怒ることはなくなりました。
◆食事中の会話で怒った場面
娘が怒りだしてしまったときには、丁寧にこの場面の状況を娘に説明しています。
「お母さんはあなたのことが大切で大好きなんだ。
今はお兄ちゃんと話していたけれど、あなたを無視しているとか嫌いだからではないよ。
お兄ちゃんもお母さんとお話ししたいことがあるんだよ。
お兄ちゃんは自分の部屋にずっといるから、食事の時しかお母さんとお話できないよね。
お兄ちゃんはお母さんとお風呂にも入れないし、一緒にも寝ていないね。
あなたとはお風呂に一緒に入っているし、寝るときもいつもいっしょで、その時に楽しくお話しているよね。
お兄ちゃんもね、あなたみたいにお母さんとお話したい気持ちがあるんだよ。」
と、こんなふうにです。
兄は思春期でいつも自分の部屋にこもっていることが多く、食事の時くらいしか家族で過ごすことはありません。
そういった息子の様子も含め、娘には説明しています。
すると、娘も少しずつですが理解することができているようです。
娘は兄である息子に理不尽に怒られたりすることもあるのですが、実は娘はお兄ちゃんのことが大好きなのです。
息子がいないときに私にこっそり
「お兄ちゃん、お母さんとお風呂に入れないからかわいそうだね。」
なんて言っていました(笑)
お兄ちゃんの立場をわかっているんだな、と成長を感じ、こんな発言をするなんてかわいいなあと思います。

5.自閉症スペクトラムの怒りっぽい娘の対応で兄への思わぬ効果が!
娘に「お兄ちゃんと食事中に会話する理由」の説明を続けていたら思わぬ効果もあったのです。
それは息子の娘への態度の変化です。
息子も娘の「家出する!」という発言が出ると、
「お前、ウザイな~!家出なんてできないくせに!」
なんて娘の発言にイライラと怒っていたのですが、私が娘にしている説明を耳にしているせいか、息子の態度も変化してきています。
娘への発言や態度が優しくなっているなと感じます。
息子にも「お母さんが自分の気持ちを理解している」と伝わっているのだろうな、と感じます。
こういう間接的な肯定のメッセージは思春期に効くということをぜひおぼえておいてくださいね!

さて、怒らなくていいような場面で怒りだしてしまう娘への対応についてお伝えしてきました。
私が娘の特性を理解できると、本人にとっても怒りたくて怒っているわけではないことがわかるようになりました。
私も娘に対し「なんて怒りっぽい子どもだ!」と怒る意味がわからくてイライラしていたのがなくなりました。
私の経験がみなさんの楽しい子育てのお役に立てればうれしいです。
知的発達がゆっくりなゆったりIQっ子でも発コミュの対応で伸びるんです!お母さんのイライラがなくなり、子どもが伸びるのは親のスタンスが変わるからなのです。子どもを伸ばしたいお母さんはお読みくださいね。
発達障害の子育てが辛いというお母さんのお悩み相談に回答しています。自閉症スペクトラム障害やゆったりIQっ子の子育てが辛いお母さんはぜひ読んでくださいね!
▼【2023年3月最新刊】ワーママの罪悪感をゼロにする!▼
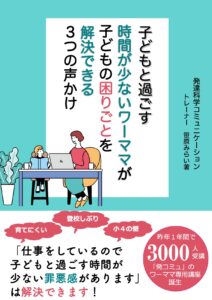
▼▼子どもと過ごす時間の質を高める方法をお伝えしています!コチラをダウンロードしてください▼▼
▼ゆったりIQっ子が支援級で伸びるヒミツ!▼
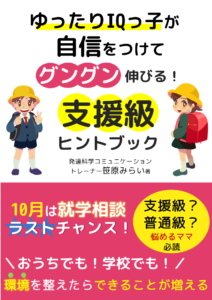
▼▼支援級見学でのポイントをお伝えしています!コチラをダウンロードしてください▼▼
▼夏休みの追い込みにも、新学期からも、宿題で怒り出すなら要チェック!▼
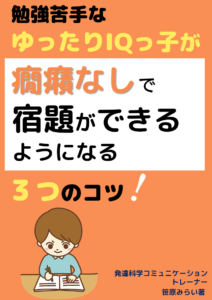
▼▼ゆったりIQっ子が「癇癪なし」で宿題ができるようになる取り組み方についてお伝えしています!コチラをダウンロードしてください▼▼
▼ついガミガミ言ってしまうママはぜひ読んでください!▼
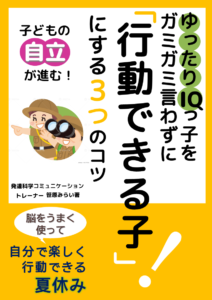
▼▼ゆったりIQっ子が「行動できる子」になるコツをお伝えしています!コチラをダウンロードしてください▼▼
▼学校に行きさえすればいいんじゃない!もっと大事なことがあるんです!▼
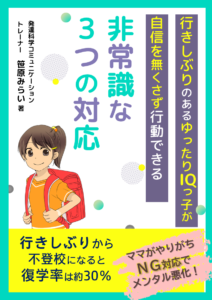
▼▼行きしぶりのゆったりIQっ子へのの非常識な対応をお伝えしています!コチラをダウンロードしてください▼▼
▼学校との連携で不安解消!子どもの良さを先生に伝えるサポートブック付き!▼
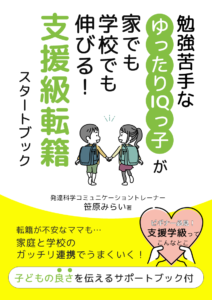
▼▼支援級転籍に不安を感じるなら、ぜひこの本を読んでみてくださいね!▼▼
発達障害の子どもときょうだい児がいっぺんに成長しちゃう発コミュのヒミツをお伝えしています!
執筆者:笹原みらい
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
(発達科学コミュニケーショントレーナー)