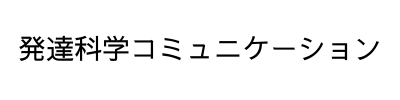1 「友達なんていらない」は本音じゃない。高IQ児が孤立する本当の理由とは?
「うちの子、友達なんていらないって言うんです」
そんなご相談をいただくことがよくあります。
一見、マイペースな子に見えるかもしれませんが――
実はこれ、“わかってもらえなかった経験”を重ねた子の、心の防衛反応なんです。
高IQの子どもたちは、知識が豊富で思考が深く、言葉づかいもどこか大人びていることがあります。
けれどその分、「話が難しすぎて伝わらない」という場面が多くなります。
伝えたかったのに、伝わらない。
わかってほしかったのに、ぽかんとされた。
そんな経験が積み重なると、子どもはこう思うようになります。
「どうせ言ってもムダ」
「一人でいた方が楽かも」
それが「友達なんていらない」に変わっていくのです。
でも――本当は、“わかり合いたい”と思ってる。
その気持ちは、ちゃんと子どもたちの中にあるんです。
実際、「話が伝わらない」のはIQが高いからでも性格がキツいからでもなく、
“伝え方を知らない”だけ。
これ、実は【スキルの問題】なんです。
だから大丈夫😊
伝え方は、あとから育てていける力なんです。
なぜ「高IQの子の話が伝わらないのか?」
その“すれ違いの理由”と、
「どうやったら伝わるようになるのか?」というヒントをお伝えしますね♪

2 伝わらない理由は“知識の差”ではなかった?
「頭が良すぎて、周りの子に話が通じないんです。」
これも、高IQの子を育てているママたちからよく聞くお悩みのひとつです。
たしかに、高IQの子どもたちは、興味のあることを深く掘り下げていたり、語彙や情報量も多くて、話す内容がどこか“大人っぽい”こともありますよね。
けど、“伝わらない理由”は、知識の差そのものではないんです。実はもっと根本的なところで、「前提がズレている」ことが多いんです。
たとえば、こんなことがありました。
学校で「月」がテーマの制作をしたとき、ある子が「月にはウサギ」というイメージで、ウサギの折り紙を貼ったり、絵を描いたりしていました。
それを見た息子が、思わずこう言ったんです。
「え!?月にウサギなんかいるわけないでしょ!?
酸素ないし、水もないし、生きられる環境じゃないよ!」
本人は、科学的に正しい知識を伝えたつもり。
けど、周りの子たちは「え…なんでそんなマジレス?」と、空気が凍ってしまいました。
これは、“知識の差”ではなく、「前提としている世界観のズレ」によって起きたすれ違いなんです。
このように、高IQの子が「伝わらない」と感じる背景には、
実はこんな “3つのズレ” があることが多いんです。
🔹1. 正しさにこだわりすぎてしまう
高IQの子は、論理的に物事を考えるのが得意。
だからこそ、「間違っていること」にすぐ気づくし、それをそのままストレートに伝えてしまうことがあります。
けど、子ども同士の世界では、“正しいかどうか”より、“どう伝えるか”の方が大事にされることも多いんです。
「それ、ちがうよ」って言われたら、相手の子はびっくりしたり、ムッとしたり…悲しくなったり…。たとえ善意でも、「言い方」で関係がこじれてしまうことも。
🔹2. 言葉の“意味”や“イメージ”がズレている
同じ言葉を使っていても、その言葉にどんなイメージを持っているかは、人によって全く違います。
たとえば――
息子は学校で「月」について天体の授業で習ったあと、「月には酸素がない」「生物は住めない」ということを、きちんと理解して覚えていました。
だからこそ、クラスで「月」をテーマに制作したとき、他の子がウサギの折り紙を貼っていたのを見て、こう言ったんです。
「え!?月にウサギなんかいるわけないでしょ!
酸素ないし、水もないし、生きられないって習ったでしょ!?」
本人は、「みんなも授業で習ったんだから、同じように理解しているはず」
と思っていたんです。
けど、他の子たちにとっては、「月=お月見=ウサギのお話」という昔話や文化的イメージの延長線で描いていただけ。
「え…なんでそんな本気で言ってくるの?」
「楽しく作ってるだけなのに…」
そんな空気が流れ、息子はぽつんと孤立してしまいました。
これは、“知識の差”ではなく、「その言葉が表している世界観の違い」で起きたすれ違いです。
息子の中では、“月=科学的な存在”というリアルなイメージ。
けど、周りの子たちは、“月=ふんわり楽しいイメージ”で話していた。
このズレに気づけないと、「わかってもらえない」「伝えるのが怖い」という気持ちに繋がってしまうのです。
🔹3. 話が飛びすぎて“ドミノの途中”から話してしまう
これは一番よくあるズレ。
高IQの子どもたちは、頭の中で“何枚も先のドミノ”まで見えていることが多いんです。
けど、相手はその“最初の一枚”が見えていない。だから、途中から急に話されると「???」となってしまうんです。主語が抜けているなんて子もいます。
本人はちゃんと説明しているつもりでも、前提の共有がないから、話が通じない。
その経験が続くと、本人も「もういいや」と諦めてしまう。
こうしたズレは、「頭が良いからしょうがない」ことではなく、実は“伝え方のスキル不足”によるのなんです。
けど、安心してください!
この“伝える力”は、あとから育てていけます。
では、どうやってその「伝える力」を育てていくのか?
私が実際にやってきた関わり方を、具体的にお話ししていきますね♪

3 我が家の転機は“ママの話し方”が変わったことでした
実は、うちの子も昔は、「通じない」「伝わらない」でよくモヤモヤしていました。
一生懸命話しているのに、相手の子に伝わらない。どんどん話が深くなっていくのに、返ってくるのは「へぇ〜」「なんか難しいね」だけ。上級生に「生意気!」なんて言われたこともありました。
けど、ある時ふと気づいたんです。
「もしかして、“伝わらない”って、話の内容じゃなくて“話し方”の問題なんじゃないかな?」って。
それから私が意識したのは、“例え話”を使って話すこと。たとえば、話し始めたあとに、「たとえば〇〇って感じかな?」と、子どもがイメージしやすい例を挟むようにしてみたんです。
たとえば――
「ママ、疲れちゃった・・・。HPが1^^」
みたいな感じです。
すると、うちの子が少しずつ変わり始めたんです。
私の“例え話”を聞いて、真似してくるようになっていきました。
学校でのやり取りでも、同じように「たとえば〜ってことだよ」って話すようになっていったんです。
もちろん、すぐにうまくできたわけじゃありません。
けど、“伝え方”を意識するようになってから、話が伝わる体験が増え、自信もついていきました。
なにより、本人が友達と楽しそうに話し始めたことが、私にとっては大きな変化でした。
これが、我が家の「伝わらない」が「つながる」に変わった瞬間でした。
ママが“伝える姿”を見せてあげるだけで、子どもは少しずつ「伝える力」を育てていける。
では、この“例え話モデリング”を、どんな風に日常で取り入れたらいいのか?
具体的なステップでお伝えしていきますね♪

4 ”伝える力”はママが育てられる!家庭でできる例え話モデリング3ステップ
「伝える力って、どうやって育てればいいんですか?」
私がよく受けるご質問です。
子どもに“伝える力”を教える必要はありません。
ママが“見せる”だけで、ちゃんと育ちます。
ここでは、私が実践してきた
例え話モデリングの3ステップをご紹介します♪
✅STEP①:ママが例え話を使って話す
まずは、ママ自身が“伝える姿”を見せることからスタート!
何かを説明するときや、気持ちを伝えるとき――
ちょっとした“例え話”を入れてみてください。
たとえば:
「ママ、今日はもうHP1って感じ。ポケモンだったら瀕死状態だよ〜」
「急に予定が変わったの、ちょっと残念。
サッカーでゴール目前にホイッスル鳴ったみたいな気分だよ〜」
子どもがよく知っているものに置き換えると、
「そういうことか!」ってスッとイメージできるんです。
これが、伝えるって“工夫できるんだ”という最初の気づきになります。
✅STEP②:子どもが例え話を使ったら、すかさず褒める
子どもが真似して例え話を使ってきたとき――
それは、もう“伝える力”の芽が出始めた証拠!
「その言い方、すごくわかりやすかったよ!」
「今の説明、ナイス例えだったね〜!」
こんな風に声をかけて、“伝わった経験”を成功体験として残すことが大切です✨
✅STEP③:相手の“好きなもの”で例えられるように一緒に考える
そしてもう一歩先へ。
お友だちとの会話で伝わらなかったときは、
「どう言えばよかったかな?」を一緒に考えるチャンスです!
「◯◯くんって電車好きだったよね?
じゃあ、“山手線なのに新幹線の速さで話した”って例えたらどうかな?」
相手の好きなもので例えることで、
伝わらなかった会話が“つながる会話”に変わっていきます。
そしてここには、「相手の気持ちを考える力」もちゃんと育っていくんです。
この3ステップ、どれも“特別なスキル”ではありません。
ママの声かけひとつで、「通じない子」が「伝える達人」に育っていくんです。
次の章では、なぜこの“伝える力”が、ギフテッドや高IQの子どもたちにとって将来、大きな武器になるのか?その理由を、未来の視点からお話していきますね✨

5 “わかってもらえない子”が“つながる子”に変わる!ママの声かけで育つ「伝える力」
IQが高い。知識がある。言葉が早い。
そんな風に、「頭の良さ」ばかりが注目されがちなギフテッドや高IQ児。
けれど、どれだけ頭が良くても、それを“伝えられなければ”周りから理解されず、孤立してしまうことがあります。
そしてその孤立こそが、本来持っている才能や好奇心の芽を摘んでしまう最大のリスクなんです。
だからこそ今、育ててあげたいのは――「伝える力」=“つながる力”。
それは難しいことでは決してありません。
ママが日常の中で「こうやって伝えると、伝わりやすいんだよ」と見せてあげるだけで、子どもは自然と“誰かに届く伝え方”を身につけていけます。
私が出会ってきたたくさんの子どもたちの中で、まわりとつながれるようになってから、
グンと挑戦するようになった子たちがたくさんいます。
理解されることで、自分を信じられるようになる。信じられるようになると、前に進める。そんな子どもたちを、もっと増やしたいと思っています。
そしてこれは、どんなIQでも、どんな診断でも関係ない。ママにしかできない、いちばん身近な教育だと思うんです。
“伝える力”は、才能を孤立させずに、誰かとつながりながら活かせる力に変えていく力。
まずは、今日から、例え話ひとつでも大丈夫。
ママのその一言が、子どもの未来を変えていきます✨
(発達科学コミュニケーショントレーナー)