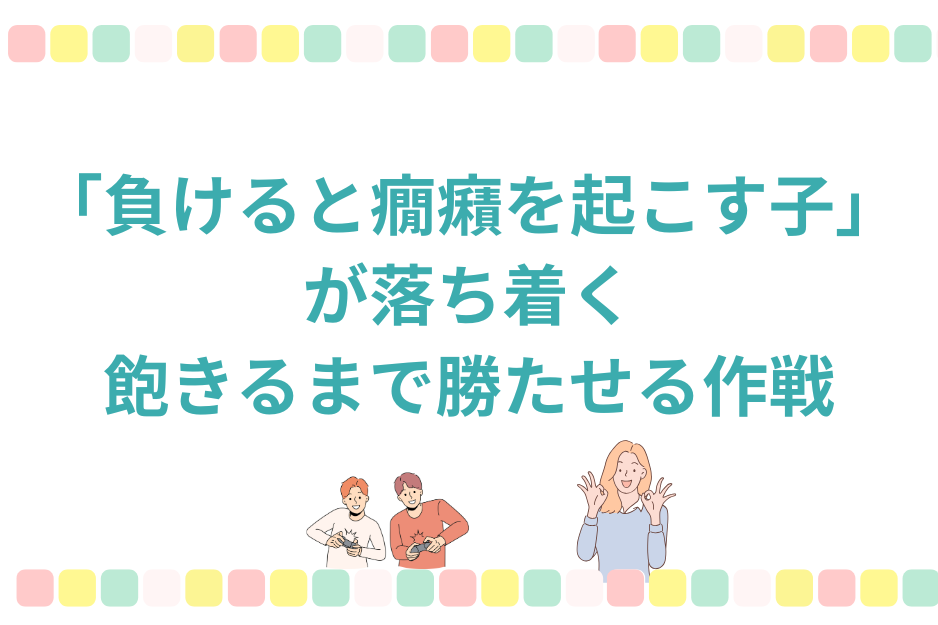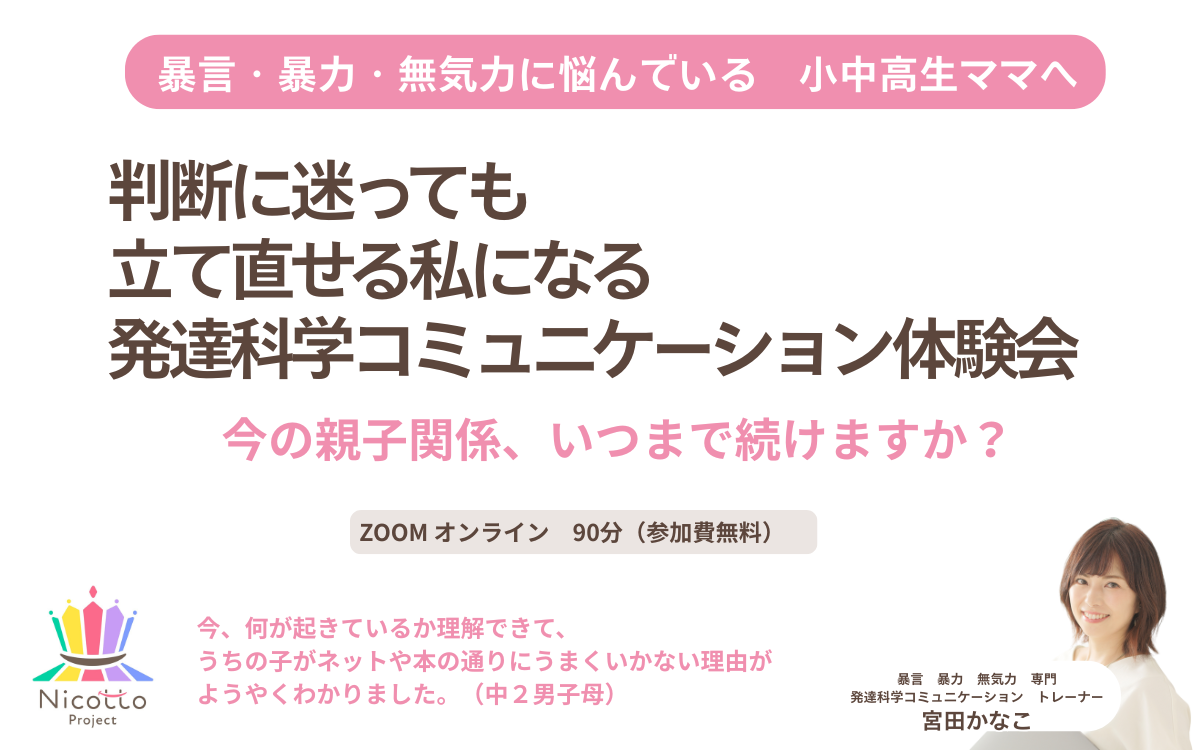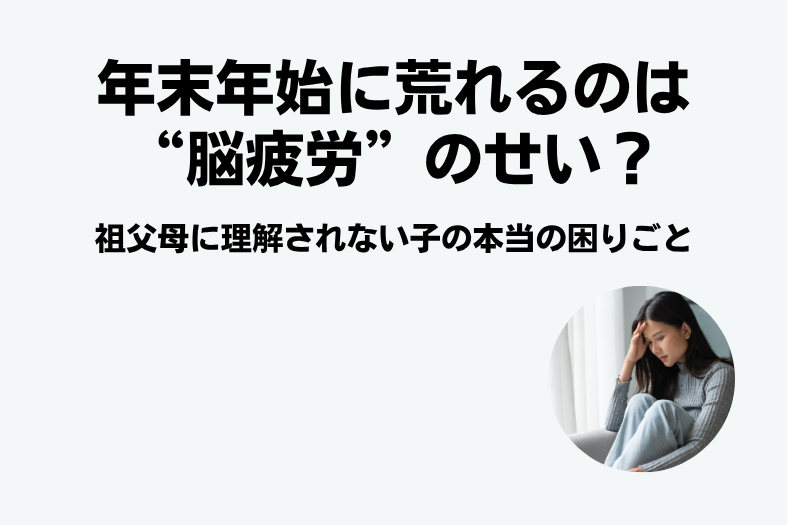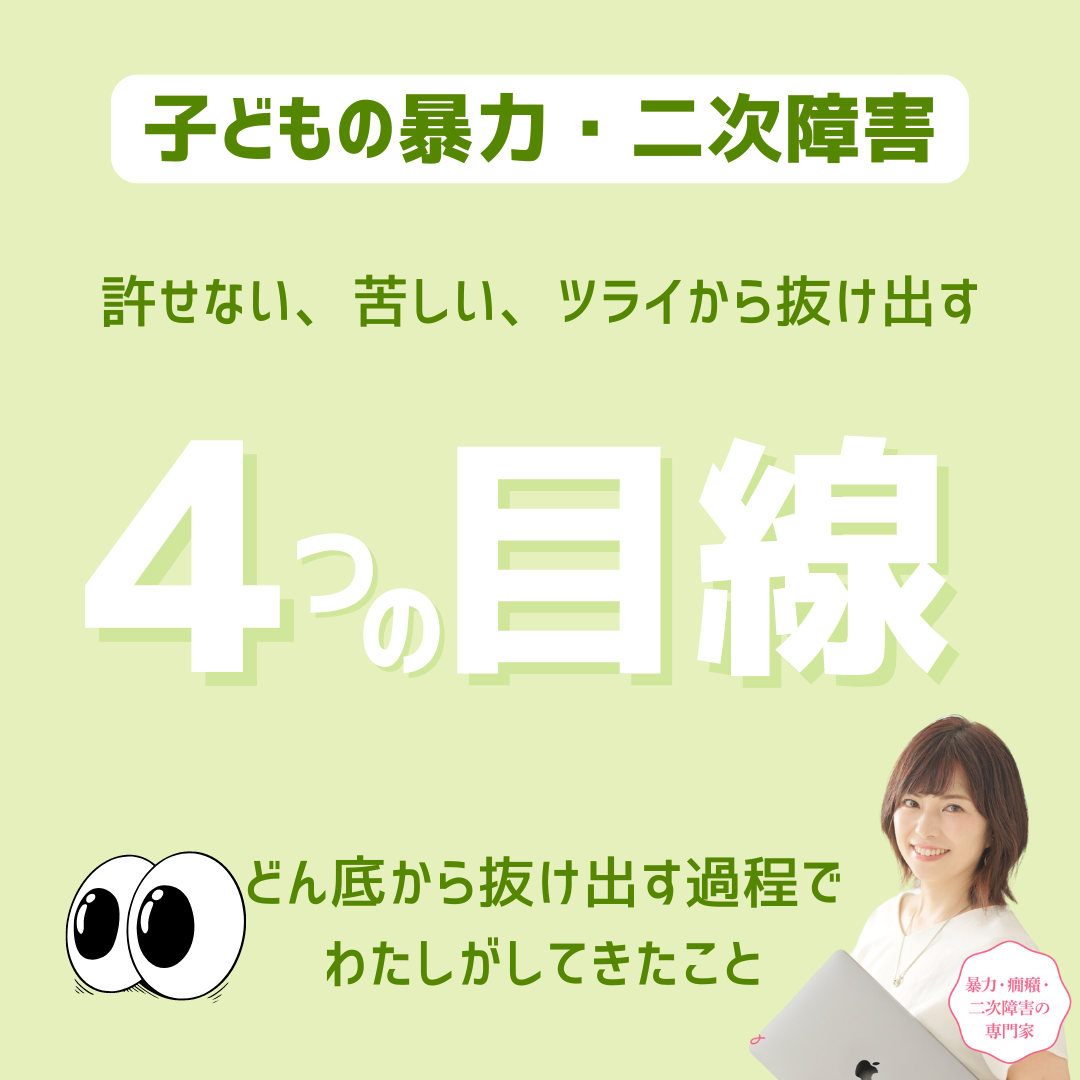「うちの子、負けると怒るんです」
「ゲームで負けるたびに癇癪を起こして、家族で楽しめないんです…」
本気でしつけているのに、うまくいかない。
そんな悩みを抱えている方はいませんか?
実は、わが家もそうでした。
ですが、“非常識”に見える方法を選んだことで、子どもの癇癪が激減し、親子の時間が穏やかなものへと変わっていったんです。
癇癪が止まらなかった長男が今では笑って負けを受け止められるように
コロナ禍で外出が難しくなった頃、わが家では親子で麻雀や桃鉄などのゲームを楽しむようになりました。
…といっても、当時は“楽しむ”どころではなかったのが正直なところです。
長男は負けるたびに怒鳴ったり、物を投げたり、時には「もうやらない!」と部屋にこもってしまうことも。
そのたびに、家族みんなが気を遣ってゲームは毎回“強制終了”となっていました。
ところが今では、長男もすっかり落ち着き、負けても笑顔で「次は勝つぞ~!」と切り替えられるようになったんです。
癇癪に効いた、わが家の作戦「飽きるまで勝たせる」
私が実践したのは、少し“非常識”に聞こえるかもしれませんが、「飽きるまで勝たせる作戦」です。
これを話すと、「そんなの甘やかしじゃない?」「負けを教えることも大事じゃない?」という声をいただくこともあります。
もちろん、その気持ちもよくわかります。
実際、私自身も最初はそう思っていました。
ですが、脳のことを学ぶなぜこの作戦がいいのかを理解できるようになりました。
感情のコントロール力がまだ未熟な時期に「負けたことを我慢しなさい」と求めても、子どもにとっては、それが“トラウマ”になってしまうこともあるのです。
「当たり前のしつけ」がうまくいかないのはなぜ?
子どもの癇癪に困ったとき、多くの親はこう考えます。
-
負ける経験も大事だから、しっかり教えなきゃ
-
我慢する力を育てなきゃ
-
感情をぶつけるのは良くないって伝えなきゃ
けれど、脳の発達から見るとこの関わり方には落とし穴があります。
なぜなら、「悔しさを感じても切り替える力」「我慢する力」は、脳の発達が土台になるからです。
その土台が未熟なうちに、「負けても我慢しなさい」と言われても、子どもはただただ“つらい経験”として記憶してしまうのです。
親の対応が変われば、子どもは変わる
子どもの癇癪が減った理由。
それは、私自身、大人の行動を変えたからでした。
勝たせてあげた上で、「そのやり方、すごいね!」「その発想、私にはなかったなぁ!」と、勝ったことではなく、“工夫や考え方”をしっかり認める。
そして、親も負けた時には、「うわ〜悔しいけど、上手だったなぁ!」と本気で負けを楽しむ姿を見せました。
子どもは言葉ではなく、「行動」から学ぶと言われています。
親が“本気で負ける”姿を見せる。悔しさと向き合うけれど、それに負けない気持ちも見せる。
その姿こそが、いちばんの教育でした。
「しつけ」よりも、「脳の育ち」を見る子育てへ
あの頃の私は、「負けても我慢できる子に育てたい」と本気で願っていました。
けれどもその“しつけ”が、息子の心を締めつけてしまっていたのかもしれません。
脳科学と出会い、発達科学コミュニケーションと出会ってから、私はようやく気づけたのです。
ママが捨てた常識の数だけ子どもは夢に近づける!
私たちの常識は、脳の育ちからすると逆効果のことがとても多いです。
もともと素直だったはずの子どもが反発をするのは、脳からのSOSサインだと捉えるようになると、親子の関係は全く違うコミュニケーションになるのです。
だからこそ、しつけや、常識や、一般論ではなく、目の前の子どもの脳の発達に寄り添った対応を知ってほしいと、心から願っています。
子どもの癇癪に悩むあなたへ 体験会のご案内
「もうどうしたらいいのか分からない…」
「このままじゃ、いつか子どもの心が壊れてしまうんじゃないか…」
“脳のクセに寄り添う関わり方”を知らないからかもしれません。
もし今、
-
子どもがすぐ癇癪を起こして困っている
-
しつけのやり方が間違っていたかも…と感じている
-
子どもの心を傷つけずに関わる方法を知りたい
そんな方がいたら、ぜひ一度、体験会にいらしてください。
あなたのせいじゃありません。
うまくいかないのは、「やり方」を知らなかっただけです。
この夏、親子の関係が変わるきっかけをつかんでみませんか?
2026年こそ、親子関係を変える第一歩を。
無料体験会実施中!
「うちでも変われる?」
「どう関わればいいの?」
「こんな悩み、私だけ?」
そんな不安がある方は、
ぜひ体験会にいらしてください。
どんなママも初めは不安です。
だけど、同じ悩みを抱えた仲間がいると
その瞬間から心がすっと軽くなります。
暴言・暴力・無気力な子どもが動き出す
“脳を育てる関わり方”を、
あなたのご家庭でも体感してみませんか
▼画像をクリックして詳細を見る