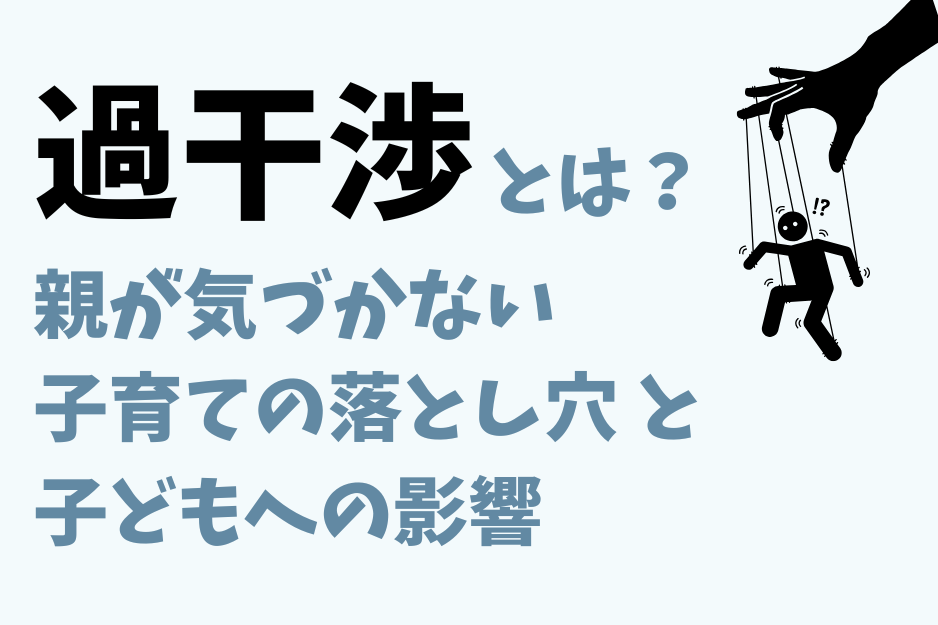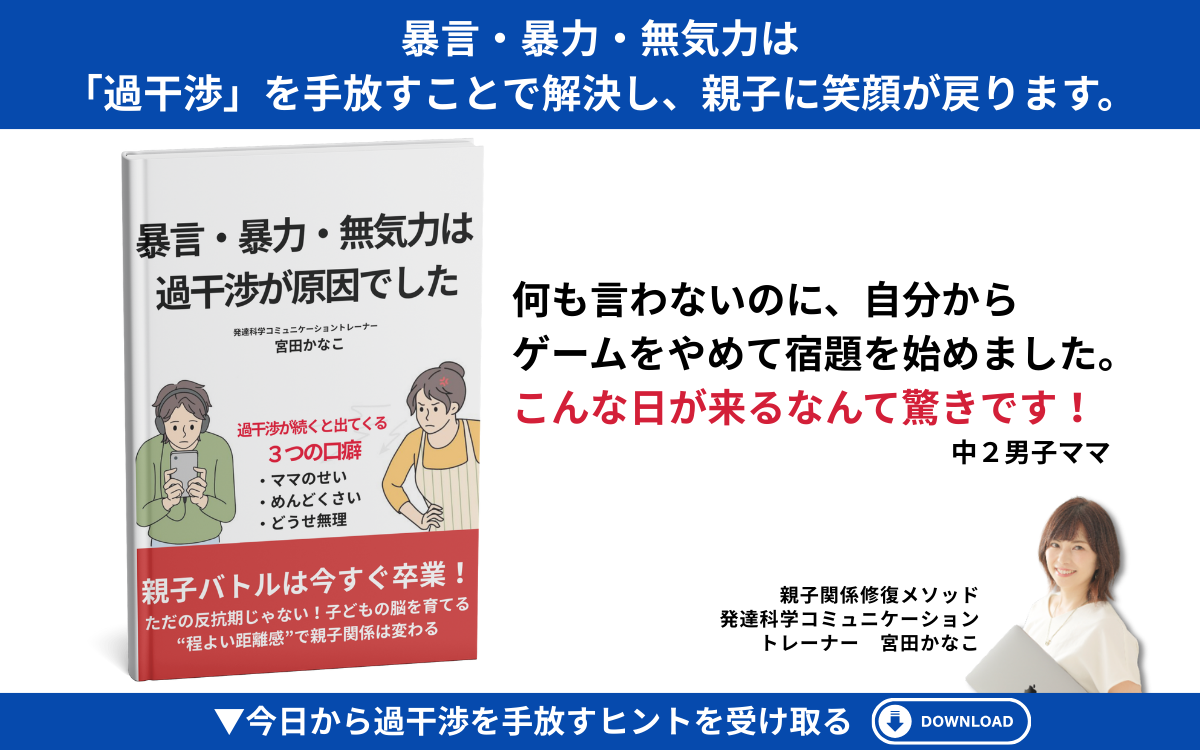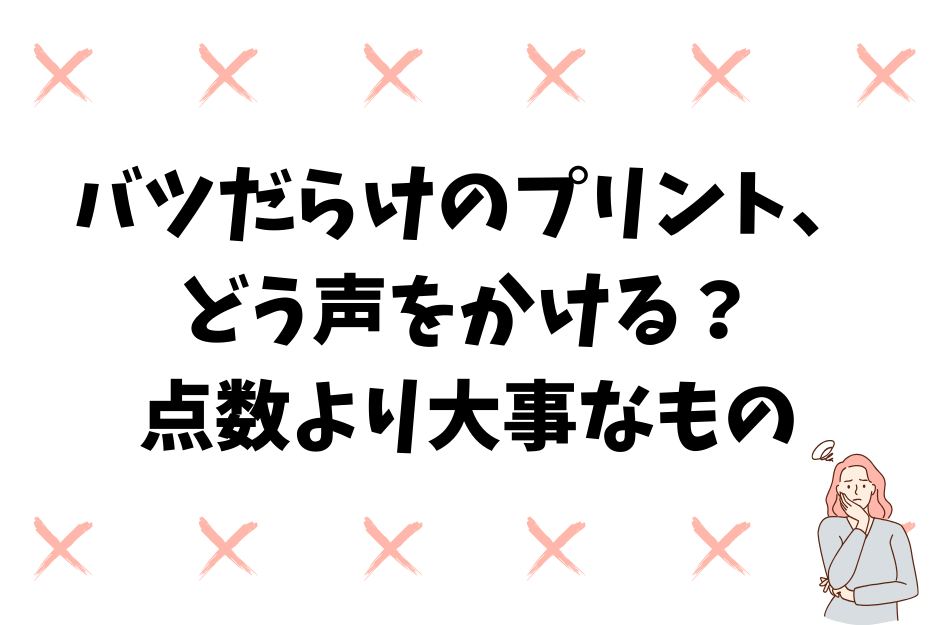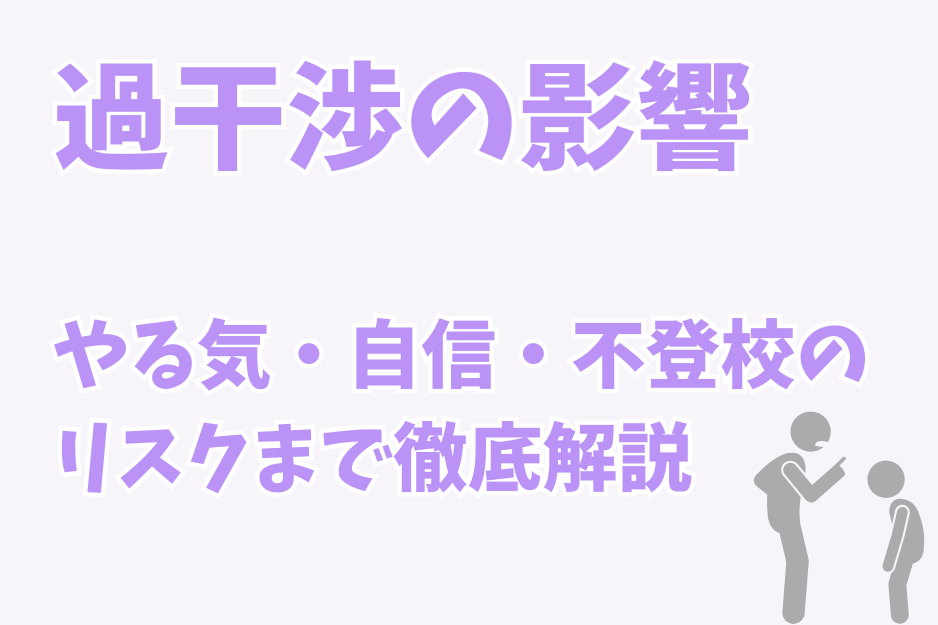「宿題しない」「すぐキレる」「無気力」…それは反抗期ではなく“過干渉”のサインかもしれません。親が無自覚で陥りやすい過干渉子育ての特徴と、子どもの脳や自信に与える影響を解説します。
過干渉とは?親が気づかない落とし穴
「なんで宿題やらないの?」「早く準備しなさい!」
気づけば毎日、子どもに口を出していませんか?
実はその「よかれと思った一言」が、
子どもの自信や意欲を奪ってしまうことがあります。
これが「過干渉子育て」の落とし穴です。
過干渉とは?
一言でいえば、 「子どもに脳を使わせない子育て」 です。
子どもが自分で考える機会を、親が先回りして奪ってしまうこと。
「忘れないように言ってあげよう」
「失敗しないように準備してあげよう」
その気持ちは愛情からですが、
子どもは自分で考えるチャンスを失ってしまいます。
親が気づきにくい“過干渉のサイン”
こんな関わり、していませんか?
-
宿題や提出物を毎回チェックしてあげる
-
子どもの代わりに先に答えを出してしまう
-
「早くして!」「忘れないで!」が口ぐせになっている
-
子どもの行動にイライラして、つい口をはさむ
これらは一見“しっかりした子育て”に見えますが、
実は子どもの「自分でやってみよう」という気持ちを削いでしまいます。
子どもに起きる影響
過干渉が続くと、子どもは…
-
自分で決められない
-
失敗を極端に恐れる
-
すぐに「ママのせい!」と反発する
-
暴言・暴力・無気力、不登校へと進むこともある
「なんでうちの子だけ…?」と思ったら、
その背景には“過干渉”が隠れている可能性が高いのです。
落とし穴から抜け出すために
大切なのは、 「気づくこと」 です。
過干渉に気づけたら、
次はほんの少し声かけを変えるだけで、
親子関係はグッと楽になります。
詳しい方法は、
こちらの小冊子や他の記事でお伝えしていますので、
ぜひ続けて学んでくださいね。
▼親子バトルを今すぐ解消したい方は
画像をクリックするとダウンロードできます
こちらの記事もおすすめです▼
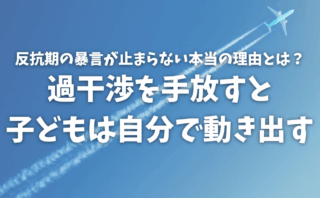
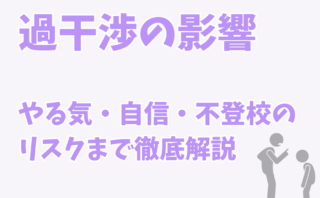
まとめ
-
過干渉=子どもに脳を使わせない子育て
-
親は無自覚でやってしまうからこそ、気づくのが第一歩
-
子どものSOS(暴言・暴力・無気力・不登校)の背景に過干渉がある
「もしかして私も…?」と気づいた時が、変わるチャンスです。