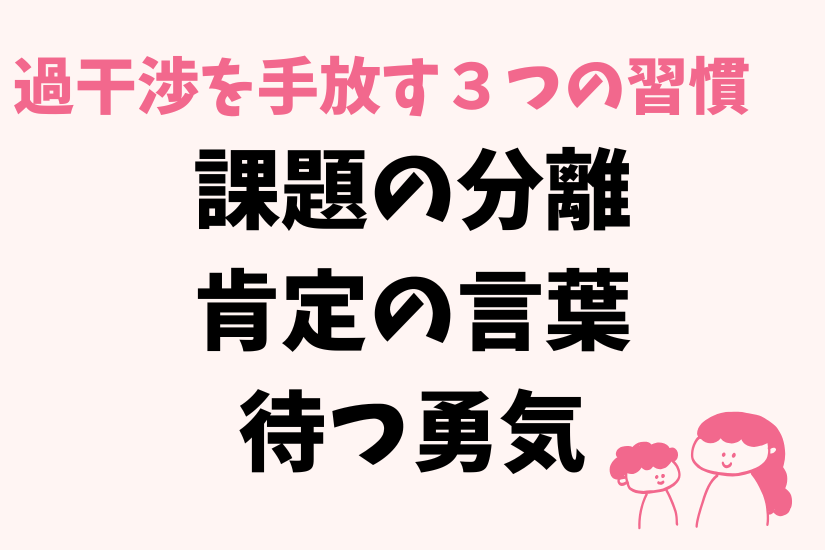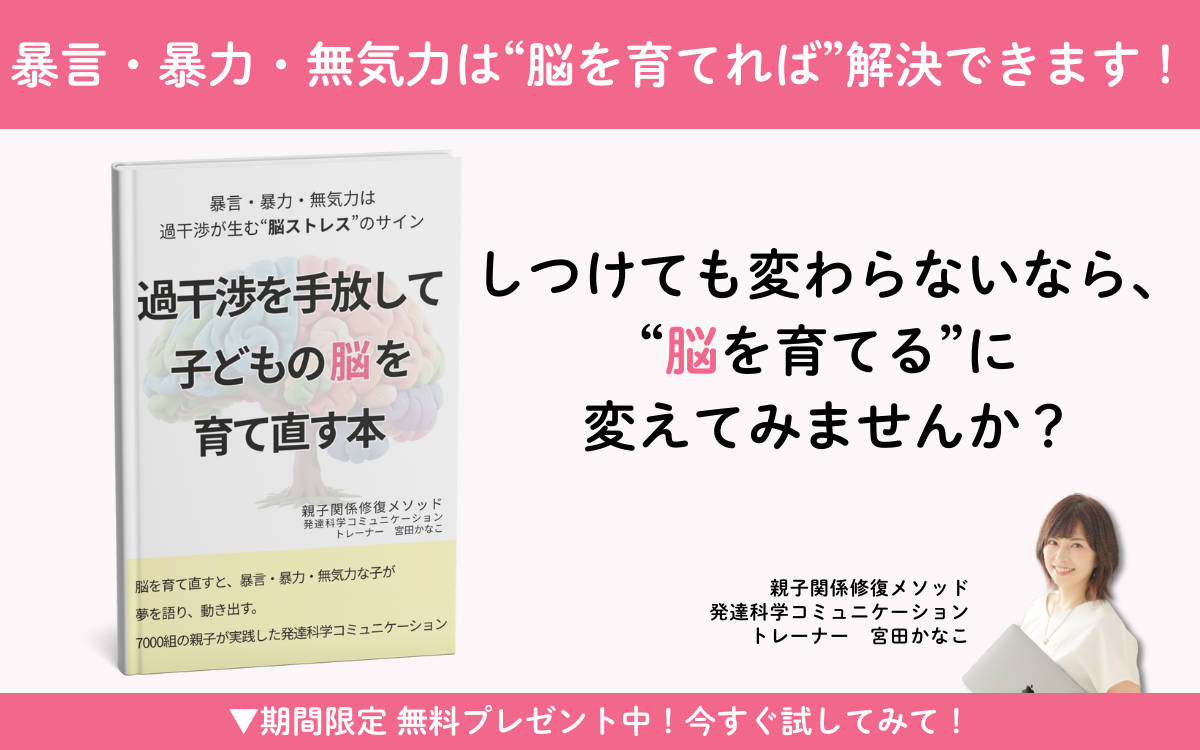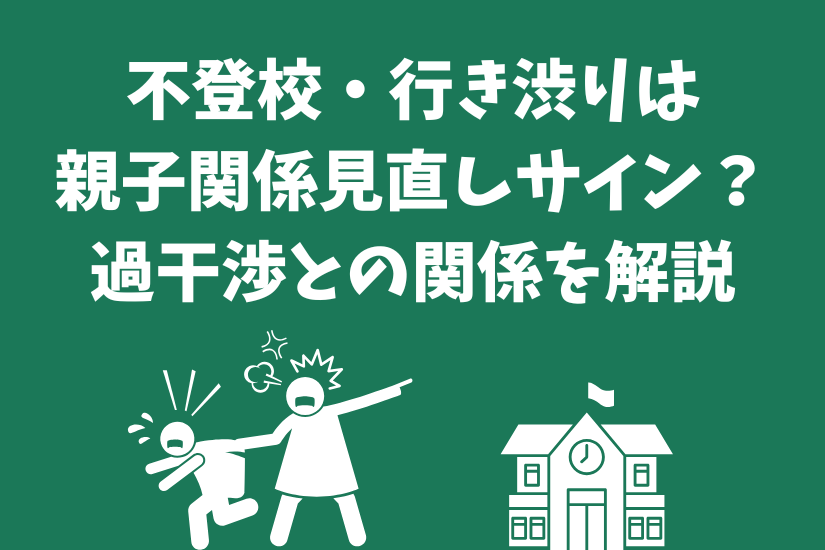「過干渉はよくない」とわかっていても、実際にどう手放せばいいのか分からない…
そんなママは多いのではないでしょうか。
過干渉は「子どもに脳を使わせない子育て」。
手放すには、日常の小さな習慣を変えることから始まります。
課題の分離を意識する
「誰の課題なのか?」を切り分けること。
-
宿題をやるかどうかは子どもの課題
-
提出物を忘れて困るのも子どもの課題
ママが背負うのは「見守ること」だけ。
親の課題ではないからです。
口を出す代わりに、「困ったときはサポートするよ」と伝えれば十分です。
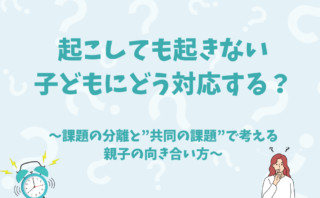
起こしても起きない子どもにどう対応する?〜課題の分離と”共同の課題”で考える親子の向き合い方〜
起こしても起きない子どもにどう対応すればよいか悩んでいませんか?課題の分離と”共同の課題”で考える親子の関係を見直すヒントご紹介。起きられないことを本人が自覚をし、親を頼っていることは信頼の証です。本人の自立に向けた対応を紹介しますね。

信じるという行為もまた、課題の分離
子どものことを信じること! ゲームやYouTube三昧で勉強しない、お風呂になかなか入らない早く寝ない、朝起きない学校や習い事を行きしぶる、不登校、昼夜逆転・・・ これらに悩んでいるあなたにとって子ども(相手)のことを信じることがいちば...
肯定の言葉を増やす
過干渉が強いと、「まだやってないの?」「早くしなさい!」など否定的な言葉が増えます。
これを意識的に 肯定の言葉 に変えていきましょう。
-
「もう始めたんだね」
-
「そこまでできたんだ」
-
「助かるよ」
たった一言で、子どもの脳は「もっとやりたい」というモードに切り替わります。
待つ勇気を持つ
先回りして手を出さず、子どもが動き出すのを待つ。
これは一番難しいですが、最も大切な習慣です。
「待つ=放任」ではありません。
必要なときはすぐに支えられる位置にいながら、子ども自身の挑戦を尊重することが信頼につながり
ます。
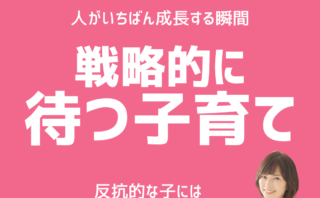
人がいちばん成長するのは、相手を信じて待っている時
人がいちばん成長するのは、相手を信じて待っている時。受講生のMさんは、空白の1週間にたくさんの気づきがありました。成功することも大事だけれども失敗経験が何より学びです。一筋縄にはいかない子育てだからこそ、戦略的に「待つ」子育てを!
実際にやってみると…
-
「宿題やりなさい!」と言わなくても自分で始めるようになった
-
「どうせ無理」と言っていた子が挑戦できるようになった
-
親子の会話が減るどころか、笑顔が増えた
そんな変化を体験するママは少なくありません。
まとめ
過干渉を手放すには、特別なことは必要ありません。
-
課題を分ける
-
肯定の言葉を増やす
-
待つ勇気を持つ
この3つの習慣が、子どもの脳を育て、親子関係を整える大きな一歩になります。
▼過干渉ってどうやって手放す?
画像をクリックするとダウンロードできます