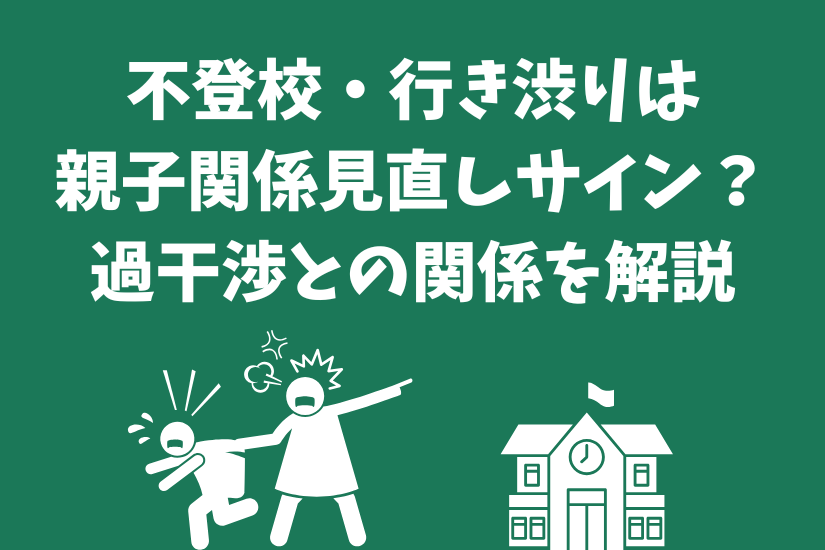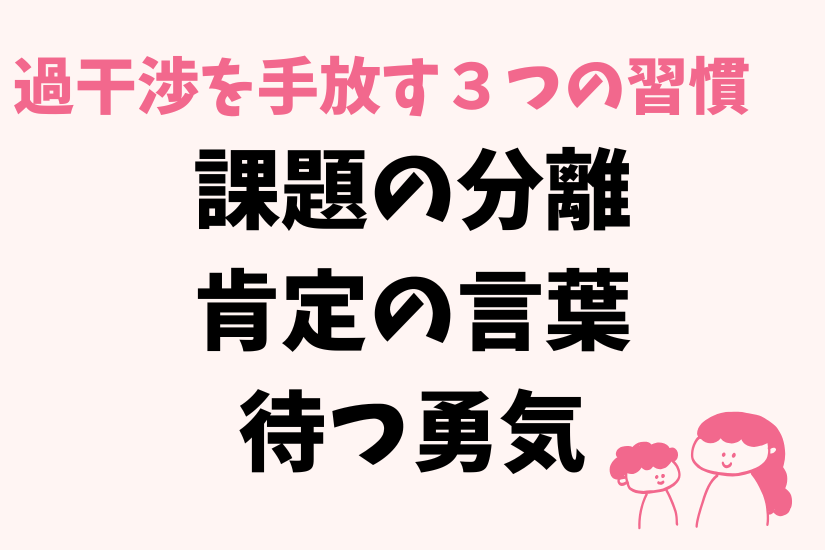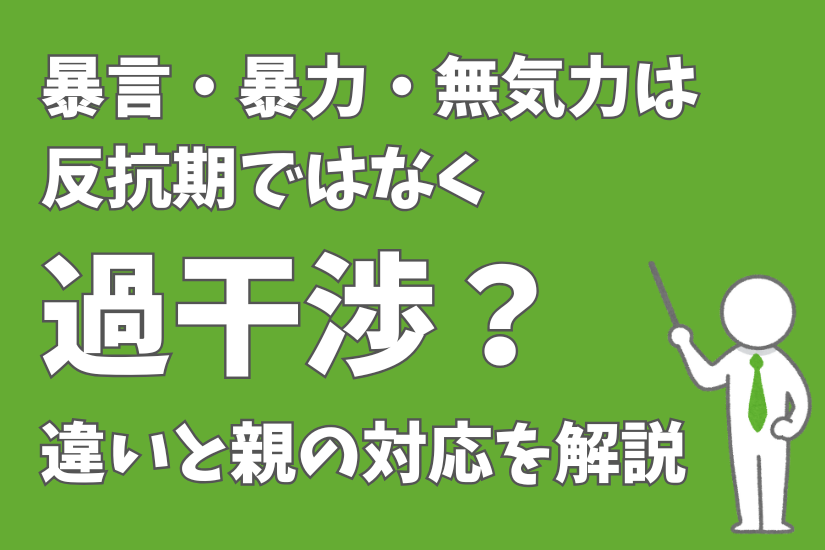新学期が始まると、「学校に行きたくない」と言い出す子や、朝になるとお腹が痛い・頭が痛いと言って動けなくなる子が増えます。 これを「怠けている」「甘えている」と感じてしまう親御さんも少なくありません。
しかし、不登校や行き渋りは、子どもが心の中で出している SOSサイン でもあるのです。
不登校・行き渋りの背景にあるもの
不登校や行き渋りの原因は一つではありません。
友達関係、勉強のプレッシャー、環境の変化など複雑に絡み合います。
その中でも見落とされやすいのが 家庭での過干渉 です。
「忘れ物はない?」「早く準備して!」と毎日声をかけ続ける。
良かれと思ったその関わりが、子どもに「見張られている」「信じてもらえていない」という感覚を残し、登校への意欲を削いでしまうことがあります。
過干渉が子どもの不登校につながる仕組み
安心できる家庭がプレッシャーの場になる
本来は休息できるはずの家庭で「やるべきこと」を常に指摘されると、子どもは家でも緊張状態になります。
自己効力感の低下
「自分でできた!」という感覚が育たないまま、失敗体験ばかりが積み重なります。
→ 「どうせ無理」「行っても仕方ない」と不登校につながりやすくなります。
親子バトルの悪循環
「学校行きなさい!」という声かけが逆に反発を生み、行き渋りを強化してしまいます。
ではどう関わればいい?
不登校や行き渋りのときに大切なのは、 学校に行かせることよりも安心を回復させること です。
-
行かない子を責めない
-
「あなたを信じているよ」と伝える
-
学校以外での小さな成功体験を積ませる
これが子どもにとってのエネルギー回復につながります。
▼ママに暴力を振るう発達凸凹反抗期の子は「欲求5段階説」を満たせばなくなる!
親ができる小さな一歩
「行かないとダメ!」と焦る気持ちを手放し、
「今日はどんなふうに過ごす?」と子どもの主体性に委ねてみましょう。
安心できる家庭が戻ってくると、子どもは再び「挑戦してみよう」という気持ちを取り戻します。
まとめ
-
不登校・行き渋りは子どものSOSサイン
-
背景には家庭での過干渉が隠れていることも多い
-
大切なのは「学校に行かせること」より「安心を取り戻すこと」
親が関わり方を変えれば、子どもはまた歩き出せます。