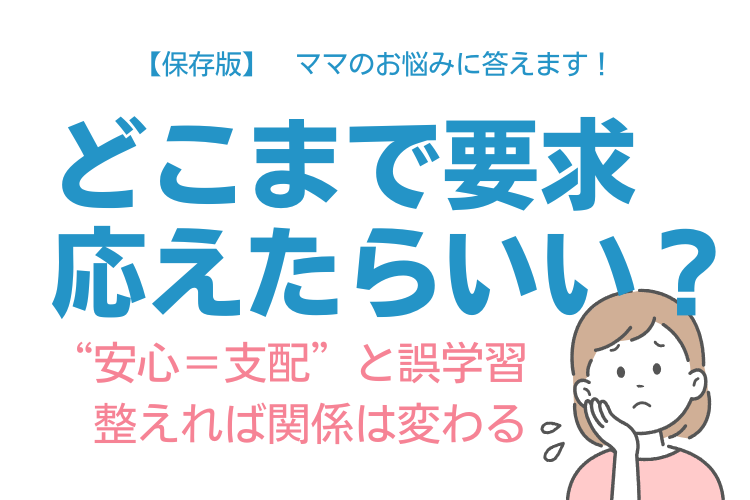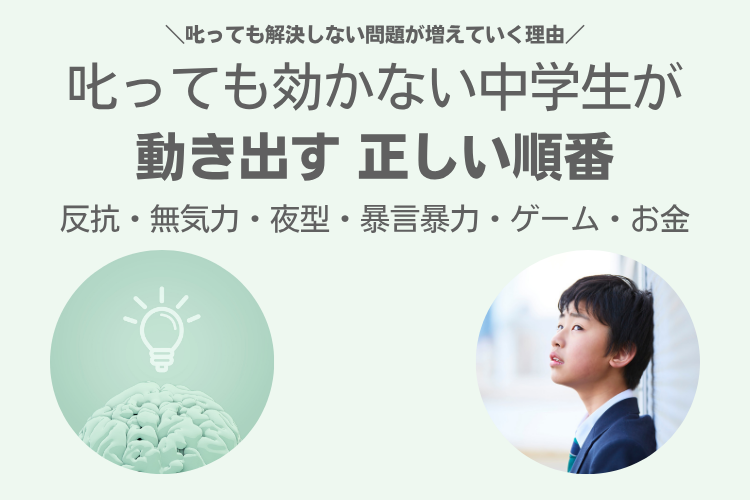「買って」「髪結んで」「スマホ貸して」「一緒に寝て」
最初は可愛いお願いだったのに、最近は少しでも断ると、暴言を吐く、怒鳴る、泣く、暴れる、噛み付く・・・。
「どこまで応えていいのかわからない」
「応えるとつけあがる気がして怖い」
そんなふうに悩んでいませんか?
実はその“要求の多さ”や“支配的な態度”の裏には、わがままではなく脳の誤学習が隠れています。
支配的な行動は「安心を取り戻すための誤学習」
子どもの行動には、すべて理由があります。
一見わがままに見える行動の裏にも、「安心したい」「つながっていたい」というサインが隠れています。
けれど安心の取り方を間違って覚えてしまうと、「支配」や「要求」でしか
安心を感じられなくなるのです。
たとえば、
ママが言うことを聞いた → 安心
ママが拒否した → 見捨てられた
という“誤った安全サイン”が脳に定着します。
つまり、怒る・泣く・噛む・暴言を吐くなどの行動は、「安心を取り戻すための誤作動」です。
ここで叱っても届かないのは、脳の中で「警戒モード(扁桃体)」が常時ONになっているから。
その状態では、理性を司る前頭前野は働かず、話も通じにくくなります。
「応える=甘やかし」ではない理由
お母さんが悩むのはここです。
「応えたらもっと支配が強まるのでは?」
けれど、誤学習のある脳にとって大事なのは“安心を一度取り戻すこと”。
要求に応えることは、甘やかしではなく、脳の緊張をリセットする作業なのです。
脳科学的にみても、安心を感じてはじめて前頭前野が働き出し、「考える」「我慢する」「聞く」ができるようになります。
つまり、
応えることは、落ち着かせるための“入口”。
行動を正すのは、そのあとでいいのです。
誤学習を上書きする4ステップ
支配や要求を「やめさせる」より、「新しい安心の取り方を教える」ほうが先。
そのための具体的ステップはこちらです。
ステップ1:保留
「わかった、少し考えさせてね」
→ すぐに動かず、“待てる時間”を脳に体験させます。
ステップ2:受容
「そう思ったんだね」「そう感じたんだね」
→ 感情を否定せず、扁桃体を落ち着かせます。
ステップ3:理解
「髪が気に入らなかったんだね」
「スマホ見て落ち着きたかったんだね」
→ 行動の理由を理解してもらえることで、
“安心回路”が少しずつ動き出します。
ステップ4:共感
「ママもそういう気持ちになることあるよ」
→ 同じ側に立つことで、支配から信頼へ。
この順番を守るだけで、
「支配で安心を確保する」誤学習が、
「共感で安心できる」正しい回路に上書きされていきます。
ASD特性が誤学習を強めるケースも
こだわりが強い、予定変更が苦手、感覚過敏がある。
そんな特性を持つ子どもの場合、「いつも通り」が崩れると脳が大きなストレスを感じ、誤学習が強化されやすくなります。
ASD特性は“障害”ではなく、“安心の取り方が極端に偏りやすい脳の個性”。
だからこそ、叱るよりも“予測と安心”を渡すことが大切です。
お母さんができる3つの実践
-
見通しを持たせてあげる
「このあと〇〇するよ」と先に伝える。 -
感情ではなく事実で伝える
「今9時になったね」「できたね」など具体的に。 -
安全に支配できる体験を与える
「ママはあなたの考えを聞くね」と選択肢を渡す。
子どもの支配や要求は、わがままでも反抗でもなく、
“安心を得るための誤学習”。
お母さんが一度受け止めることで、
「支配しなくても安心できる」新しい神経回路が育ちます。
焦らず、「応える=脳の安心を整える」つもりで関わってみてくださいね。
関連記事