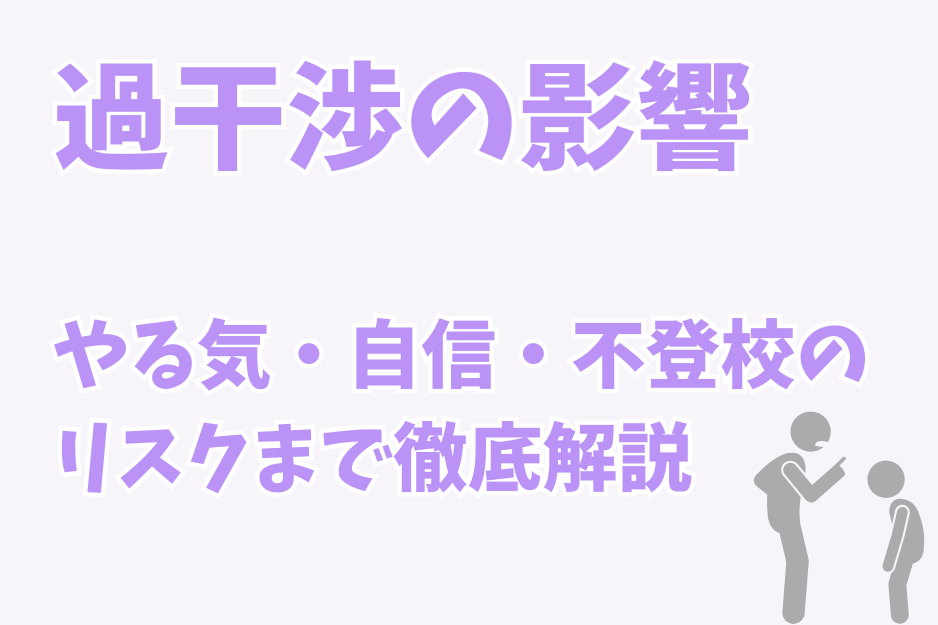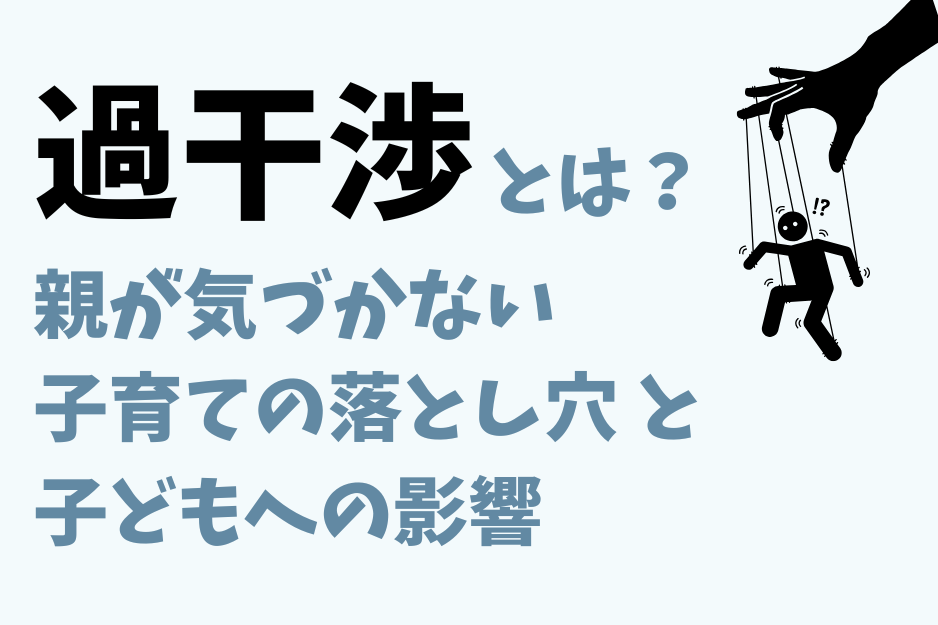「子どものために」と思ってかけている言葉や行動が、逆に子どものエネルギーを奪ってしまうことがあります。 それが 過干渉子育て です。
親としては無意識でも、過干渉が続くと子どもの脳は育ちにくくなり、思春期に大きな問題行動となって表れることがあります。
やる気がなくなる(無気力になる)
「宿題やったの?」「忘れ物ない?」と
毎日確認され続けると、子どもは
「ママが言うからやる」という受け身の思考になってしまいます。
その結果、自分から動こうとする力=やる気が育ちにくくなります。
自信を失う
過干渉は「あなたは一人でできない」という無言のメッセージになります。
小さな失敗を経験するチャンスを奪われることで、
子どもは「どうせ無理」と口にし、自信をどんどん失っていきます。
問題行動や不登校につながる
やる気や自信をなくした子どもは、
家庭内で暴言や暴力を繰り返すこともあります。
「ママのせい!」と反発したり、学校に行けなくなったり、
心のSOSを行動で示すようになるのです。
思春期に出やすいSOSサイン
-
「ママのせい!」と責める
-
「めんどくさい」が口ぐせ
-
「どうせ無理」と挑戦を避ける
-
家ではキレやすく、外ではいい子を演じる
これらは ただの反抗期ではなく、過干渉によるSOSサイン
である可能性が高いのです。
放っておくと将来どうなる?
子ども時代に過干渉を受け続けると、
大人になってから「アダルトチルドレン」と呼ばれる生きづらさに直結します。
・人の顔色をうかがい続けてしまう
・自分の意見を言えない
・人間関係が長続きしない
といった問題が出てきます。
どうすればいいの?
大切なのは「過干渉をやめる」こと。
ただし、急にすべてをやめるのは難しいですよね。
そこで次回は、過干渉を手放すための具体的な第一歩をお伝えします。
今のうちに「自分の関わり方を変えてみよう」と意識することから始めてみてください。
まとめ
過干渉は「子どもに脳を使わせない子育て」。 やる気、自信、そして将来の人間関係までも影響してしまう、大きな落とし穴です。
けれど、気づいた今こそチャンス。 子どもは親の関わり次第で、いつからでも変わっていけます。
▶ 「過干渉が子どもに与える影響」について詳しく読む
▶「ママのせい!」「めんどくさい」「どうせ無理」子どもの口ぐせはSOSサイン