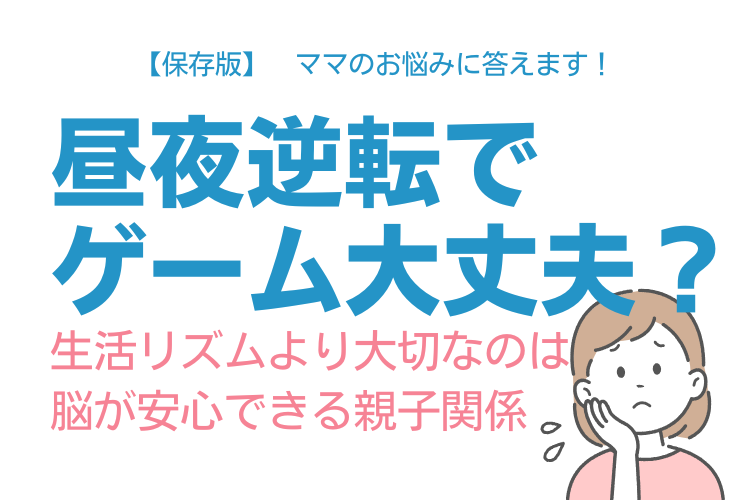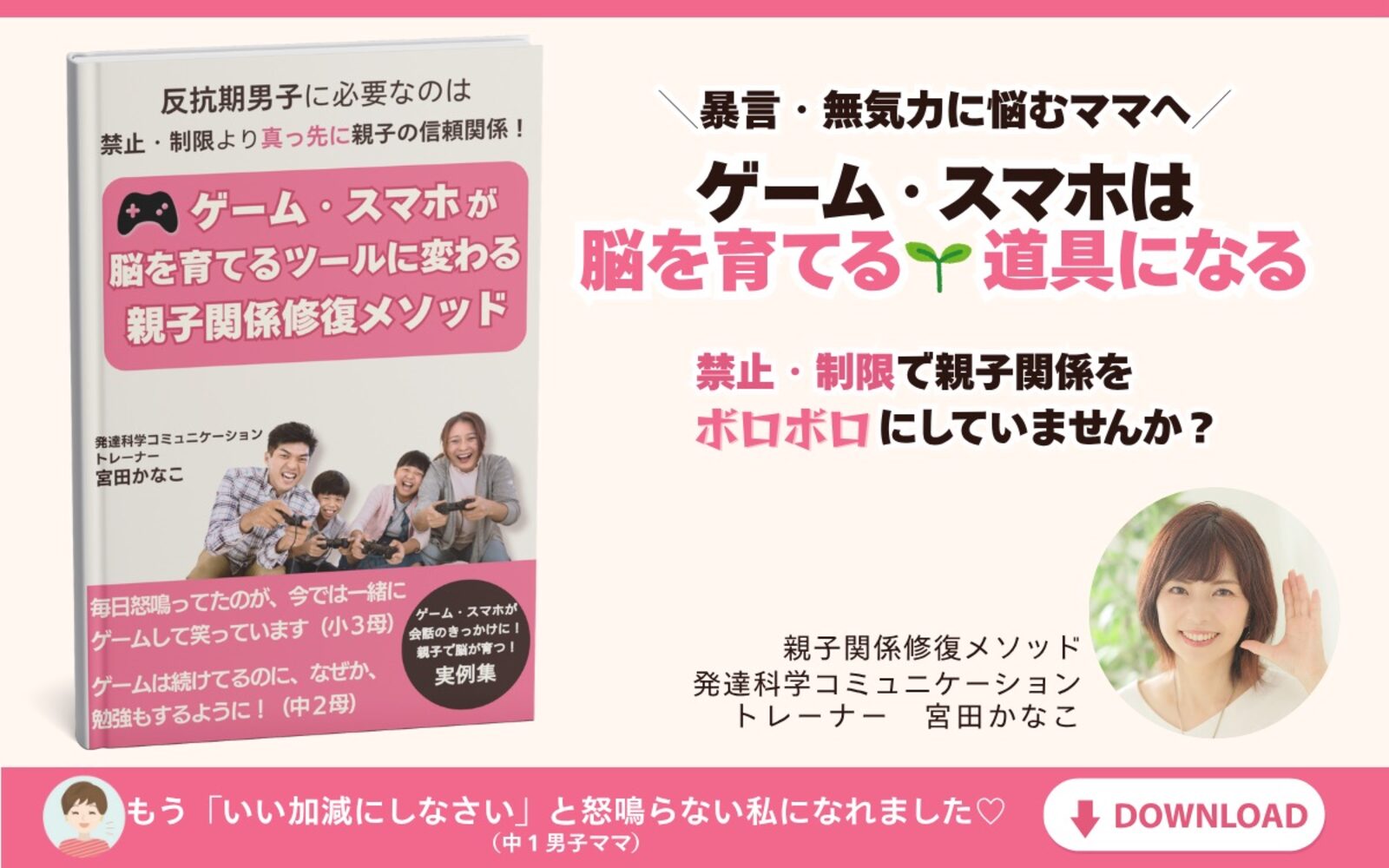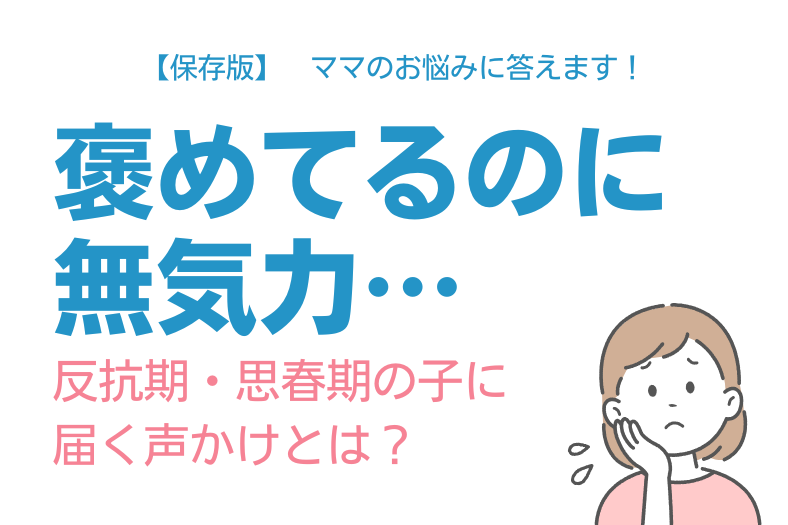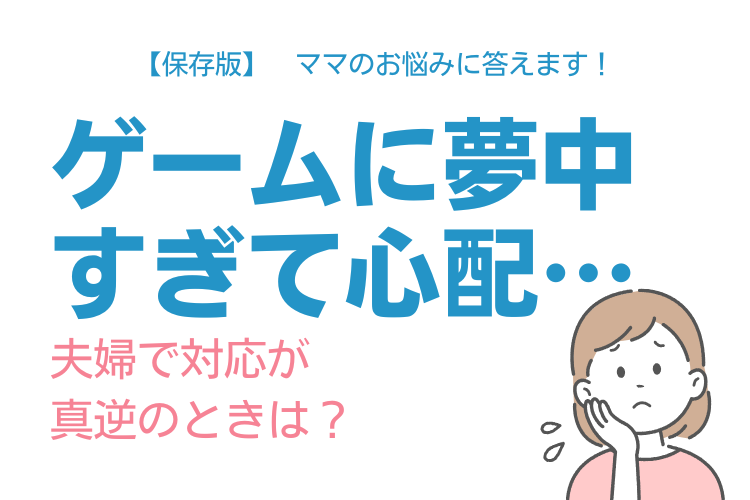「また夜更かし…」「朝が起きられない」「ゲームばかりで昼夜逆転…これって依存?」と不安になるママへ。
実は“脳のSOS”を見逃しているだけかもしれません。
生活リズムより大切なのは、安心できる親子関係です。
特に昼夜逆転やゲームへの没頭が続くと、「もう依存なんじゃないか」「将来どうなるんだろう」と焦ってしまうお母さんも多いです。
親として不安になるのは当然です。
けれども、発達科学の視点で見ると、その行動の裏には“脳のSOS”が隠れています。
昼夜逆転は「ズレたリズム」ではなく「守りの反応」
子どもが夜に活動し、朝起きられなくなるのは、単なる怠けや生活習慣の乱れではありません。
脳はストレスを受けると、「自分を安心させる時間帯」を探そうとします。
昼間に学校や人間関係で緊張状態が続く子ほど、夜に“安心できる時間”を求めて活動が活発になることがあります。
つまり、昼夜逆転は「ストレス過多な昼を避け、安心を取り戻そうとする脳の防衛反応」なのです。
ゲームは「逃避」ではなく「安心の再現」
ゲームに夢中になるのも同じです。
ゲームの世界では、ルールが明確で、結果が見えやすく、
「自分の行動がうまくいく」感覚が得られます。
これは、日常生活で感じにくくなっている
“自己効力感(できた!という実感)”を取り戻す行動。
つまり、ゲームは子どもにとって
「安心」と「達成感」を一時的に回復する場所なのです。
生活リズムを正す前に、“親子関係のリズム”を整える
昼夜逆転を直そうとして、「早く寝なさい!」「朝起きなさい!」と生活面から立て直そうとするお母さんも多いです。
けれども、まず整えるべきは“生活リズム”ではなく、“親子関係のリズム”。
子どもが安心して話せる時間、安心して受け止めてもらえる会話のテンポ。
そこが回復すると、自然と行動も安定していきます。
ブレないお母さんの軸が、脳の安心を育てる
昼夜逆転やゲーム漬けの行動は、脳が「安心できる場所」を探しているサイン。
このとき大事なのは、お母さん自身がブレずに、
「何が正しいか」よりも「今、安心しているか」を見ていくことです。
たとえば、夜中に起きてゲームをしていたとしても、暴言がなく、穏やかに過ごせているなら、脳が落ち着いている証拠。
「朝は眠くなっちゃうね」「今度は昼に一緒に見てみようか」と、少しずつ“昼の安心”を広げていけばいいのです。
昼夜逆転も、ゲーム漬けも、“ダメな行動”ではなく“安心を求める行動”。
焦って叱るより、「何に安心を感じているのか」を見つけてあげること。
それがお母さんのブレない軸となり、やがて子どもの脳のリズムを整える力になります。
▶ 子どものゲーム問題に夫婦で意見が合わない!発達科学で解決法を解説!
賢いママは考え方そのものをアップデートしています!