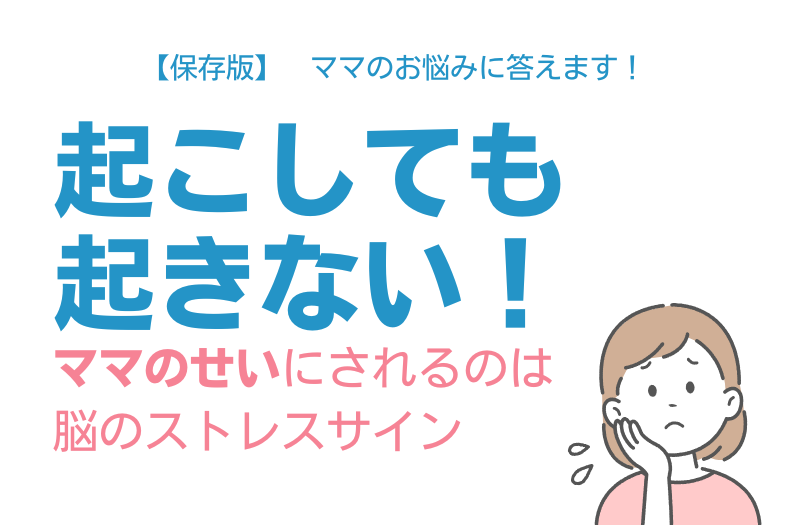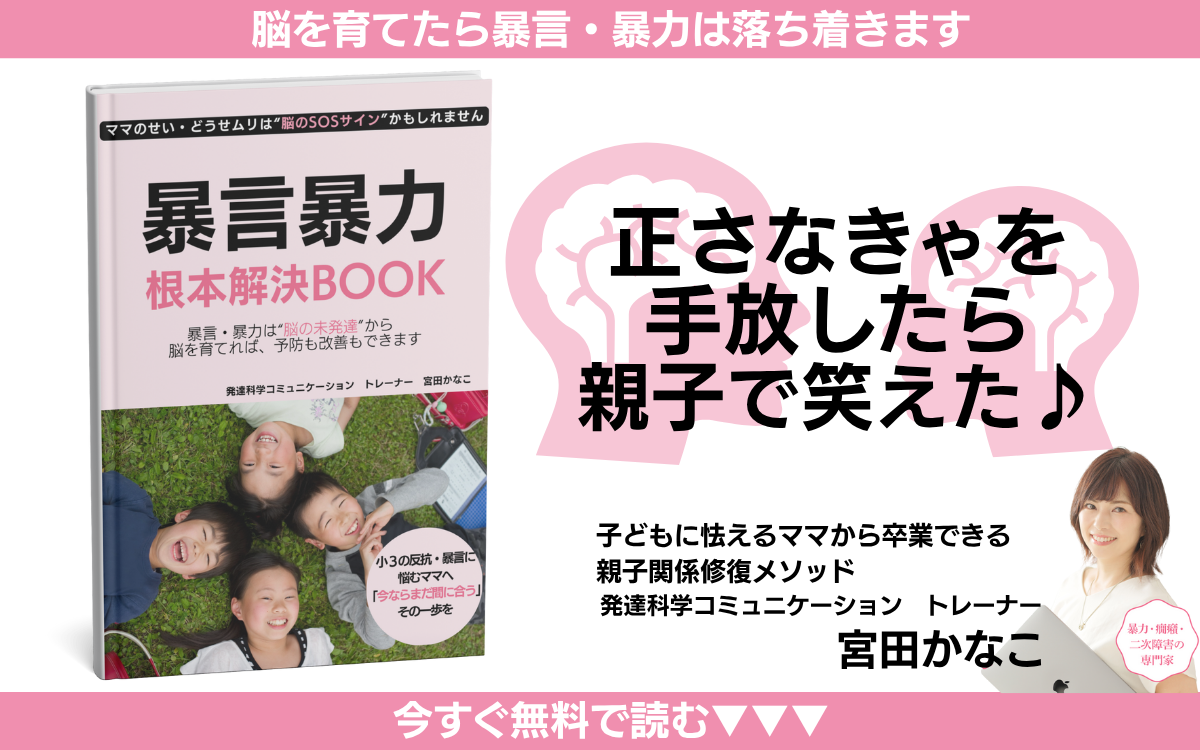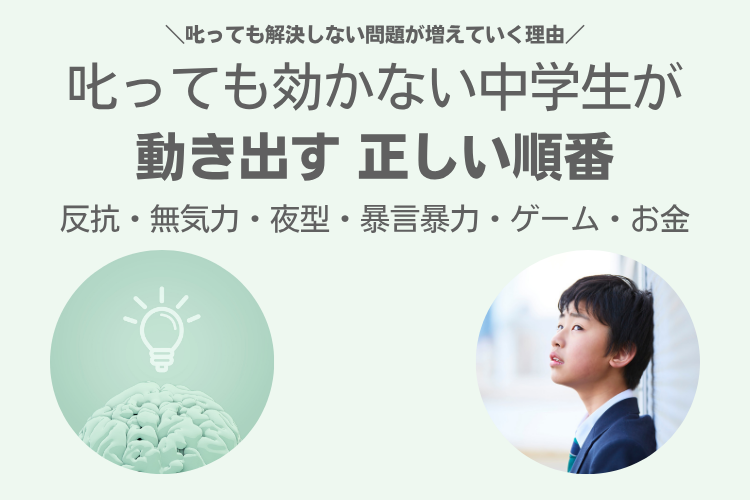朝の時間、「起こしてって言ったのに起きない!」「結局ママのせいにされる!」そんなやりとりで一日が始まること、ありませんか?毎朝バトルになってしまうと、「私の言い方が悪いのかな」「どうしたら起きてくれるの?」と自分を責めてしまうお母さんも多いでしょう。けれど、ここに大切な視点があります。それは、子どもは起きたくないわけではない、ということです。
起きたいのに起きられない。それは脳がストレス状態にあるサイン
発達科学コミュニケーションでは、行動が起こる背景の、脳の状態に注目します。
朝、起きられないのは“やる気がない”からではなく、脳にストレスや負荷がかかっているから。
たとえば、前日の人間関係のトラブル、プレッシャーの強い授業、夜の寝つきの悪さなどが積み重なって、脳が「これ以上刺激を受けたくない」とブレーキをかけているのです。
つまり、怠けているのではなく、守っている状態。
このブレーキは、意志の力ではどうにもできません。
だからこそ、朝の声かけで“正しさ”を押し出すと、脳はさらにストレスを感じてしまうのです。
「ママのせい!」の裏側にある本当の気持ち
朝起こしても起きないのに、「起こしてくれなかった」「ママのせい」と怒る。
これは矛盾しているようで、実は脳の防衛反応です。
自分を責めるより、誰かのせいにした方が心がラクという無意識の働きなのです。
心の中ではちゃんとわかっています。「ママのせいじゃない」って。
ですが、脳がストレス状態にあると、自分を守るために“責める対象”を外に向けてしまうのです。
このときに叱ったり、理屈で返したりすると、脳はさらに“守りモード”に入り、「もう話したくない!」とシャットダウンします。
発達科学コミュニケーションでは、行動の始まりと途中でこまめに肯定する25%ルール
発達科学コミュニケーションでは、行動の始まりと途中でこまめに肯定する25%ルールがあります。
つまり、「起きられるようにする」のではなく、「起きたい気持ちを守る」。
これが、回復への第一歩です。

たとえば、こんな声かけをしてみましょう。
×「なんで起きられないの?」
◎「起きたいのに、うまくいかないのがつらいね」
×「もう遅刻だよ!」
◎「体が動かないときって苦しいよね」
結果を指摘するよりも、気持ちをわかってもらえたと感じた瞬間、脳は安心してエネルギーを取り戻していきます。
「起きたい気持ちを守る」とどう変わる?
脳が安心を取り戻すと、少しずつ考える力と行動する力が戻ってきます。
「明日は早く起きてみようかな」
そんな小さな前向きな気持ちが芽生えるのは、気持ちを理解された経験が積み重なった証拠です。
だからこそ、朝の対応で一番大切なのは、行動をコントロールしようとしないこと。
焦らず、心のエネルギーを満たす時間を作ることです。
「なるほど、脳の仕組みだったんだ」と知るだけで変わる
行動の裏には、必ず理由があります。
そしてその理由は、子ども自身にも説明できないほど複雑です。
お母さんが「怠けてる」と思うより、「脳の仕組みの問題なんだ」と理解することで、親子の関係は穏やかに整い始めます。
なぜなら、“責める”より“理解する”方が、脳にとって安全だから。
安心が溜まれば、子どもは自然と動けるようになります。
それが、発達科学コミュニケーションという、脳を育てて行動を引き出すアプローチです。
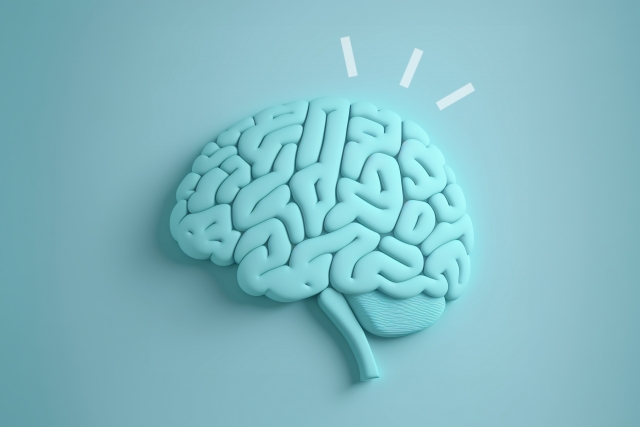
焦らなくて大丈夫です
朝のバトルは、誰にでもあります。
一気に解決しようとせず、まずは「起きたい気持ちを守る」と決めるところから。
そこから少しずつ、脳は安心を取り戻し、行動が変わっていきますよ。
こちらの記事も併せて読んでみてくださいね
朝起きない発達凸凹キッズが朝起きられない本当の理由 “脳の余白”でスッと動ける子に変わる
▼ママのせい・どうせムリは、脳のSOSサイン!
今すぐできることがあります。
画像をクリックするとダウンロードできます