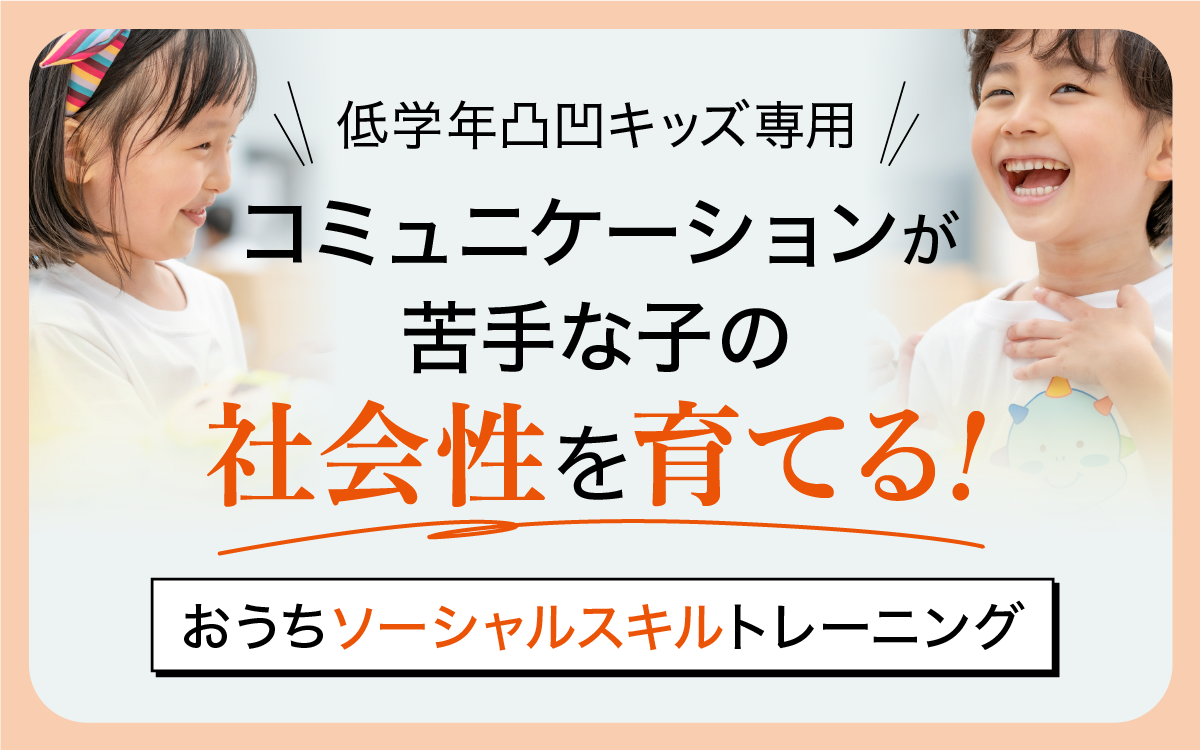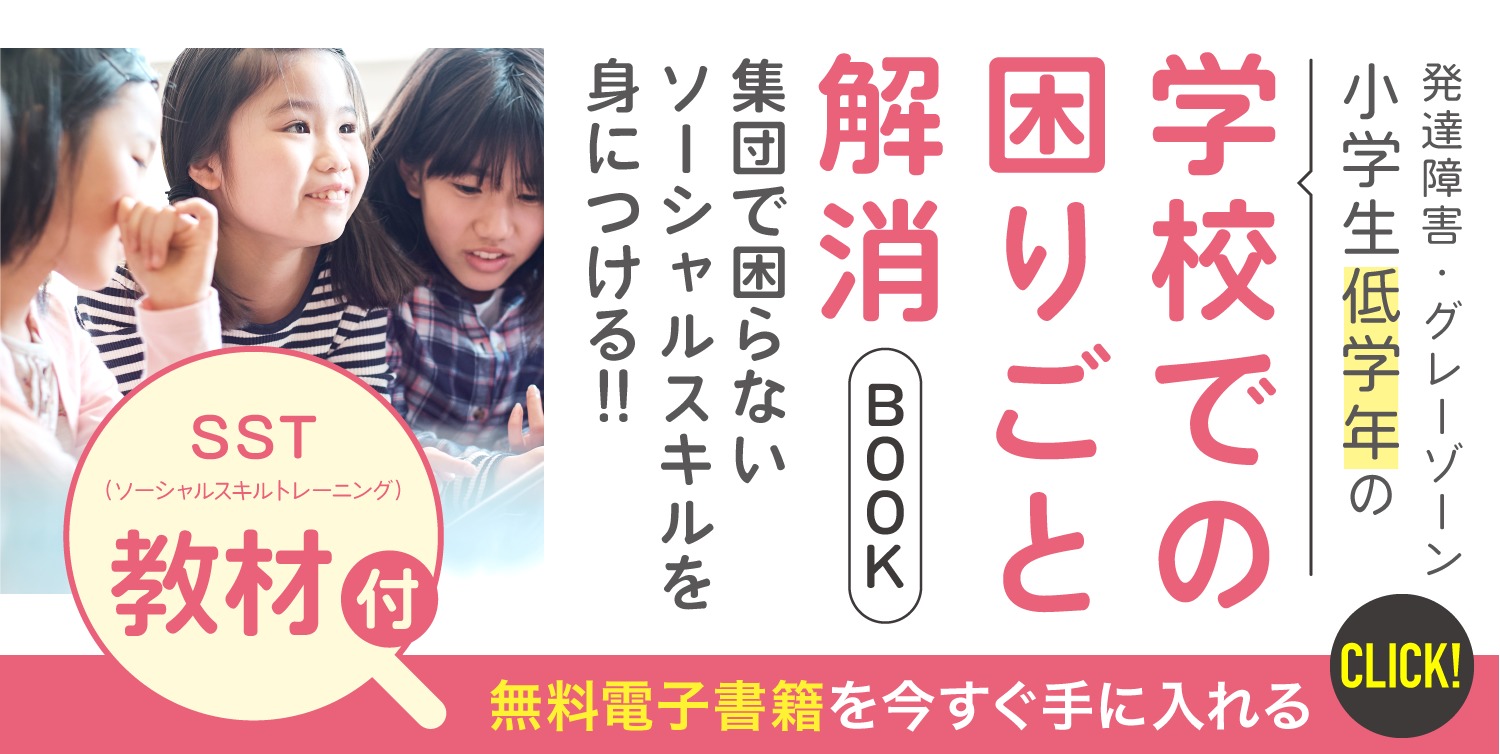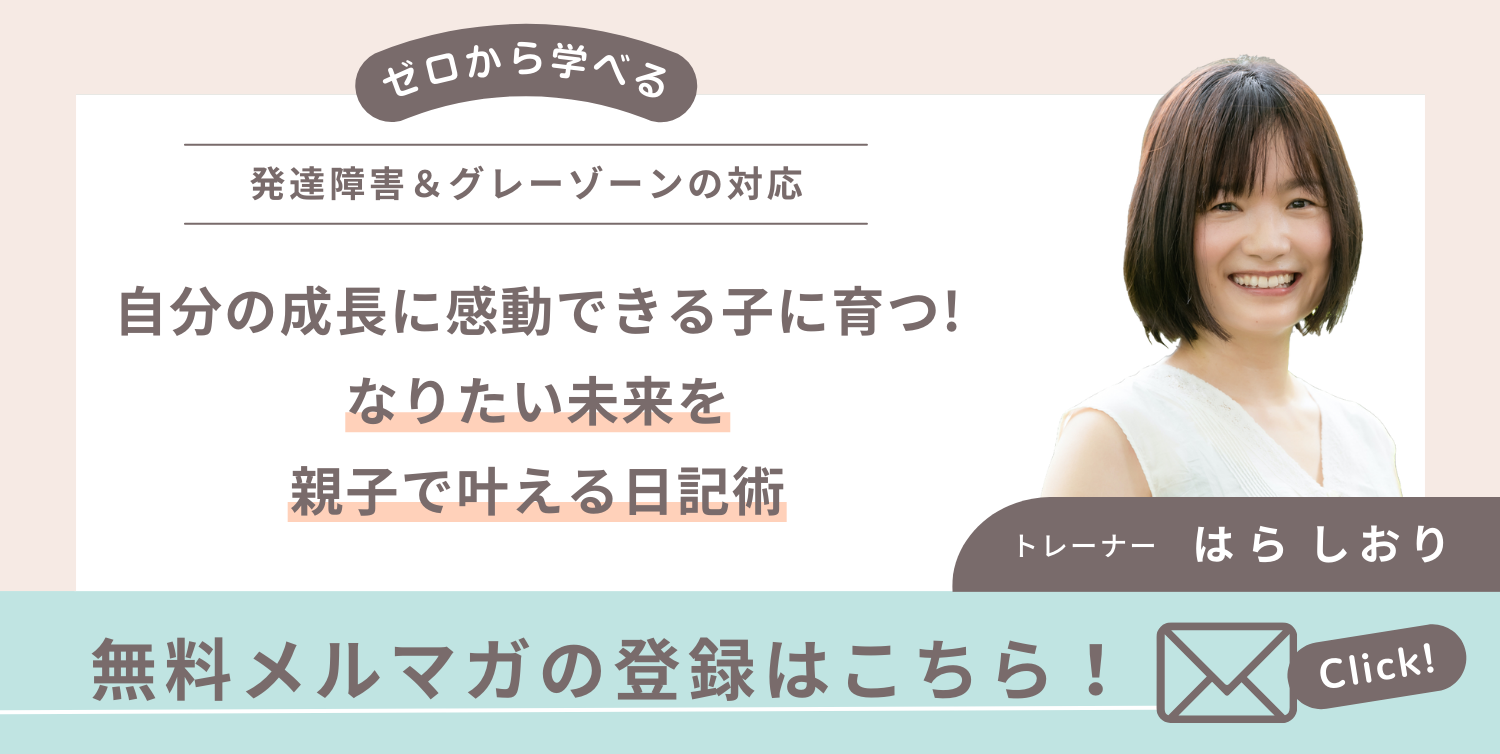小学生になると友達関係がどんどん複雑になります。特に女子の友達関係は小学2年生がターニングポイントになることを知っていますか?公的データや脳科学の観点からその理由が考えられます。その時期を迎えるまでに家庭でできることをお伝えします。
【目次】
1.小学生女子の友達関係は小2がターニングポイント?!
◆公的データ「学年別いじめ認知件数」から見えてくること
◆脳科学的観点からみた女の子の発達段階
2.小学校低学年の女子の友達関係が複雑になる2つの理由
①女の子は「言葉の力」を持つから
②発達特性による自己中心性が優位になりがちだから
3.友達関係トラブルになる前に!親子のコミュニケーションを整えよう
1.小学生女子の友達関係は小2がターニングポイント?!
小学校に上がると心配になることの一つが子どもの友達関係ですよね。
特に女の子は男の子よりも発達が比較的早く、友達関係も複雑になる傾向があります。
そこで友達関係の1つのターニングポイントが、小学校2年生であることをご存じですか?これは、公的なデータと脳科学的観点から裏付けされているのです。

◆公的データ「学年別いじめ認知件数」から見えてくること
令和5年度に出された文部科学省の調査結果の概要から、いじめがあると認知されているピークは小学校2年生との結果が分かりました。
この調査によると、近年いじめの定義が少し変わったそうです。
小学校では、
・冷やかし、からかい、悪口、脅し文句などの口撃的なもの
・軽くぶつかられる、遊ぶふりをして叩かれる、蹴られるといった、激しい暴力とまでは言えないものの遊びやふざけあいの中で起きること
これらもいじめとして多く起きているとのことです。

◆脳科学的観点からみた女の子の発達段階
脳科学的に、右脳と左脳の発達のバランスの観点から女の子は9歳前後で一つの転換期を迎えると言われています。
「小3の壁」「9歳の壁」という言葉を聞いたことはありませんか?
それを「小4」と言ったり10歳と言ったり、諸説ありますが、共通するのは、このくらいの時期は幼児とはちょっと違ってくるので、取り扱い注意!ということ。
女の子のほうが発達が早いので、小学校2年生での対応で未来が変わってくるのです。
友達関係がうまくいかない女の子の“伝える力”や“やりとり力”を、ママとのロールプレイで楽しく自然に身につける方法を、無料小冊子でご紹介!
2.小学校低学年の女子の友達関係が複雑になる2つの理由
小学生女子の場合は、どんどん友達関係は複雑になり、こじれやすくなっていきます。
その理由は2つあります。
◆①女の子は「言葉の力」を持つから
一般的に、女子の方が言葉の発達は早いと言われています。
言葉でのコミュニケーションを盛んに行う女の子のお友達関係では、こじれるときも言葉が刃になることが多いです。
問題なのは、言葉は言った瞬間に消えてなくなるため、リアルタイムで聞いていないと仲裁しづらいのが現実です。
また、小学生になると、自分の感情に蓋をしてしまいがちなことも。
その場ですぐに解決できずにモヤモヤを抱えやすいため、嫌な言い方をした子はそれに気がつかないですし、嫌なことを言われた子はネガティブな記憶を脳にためることになる。
そういうことが積み重なる可能性があります。

◆②発達特性からくる自己中心性が優位になりがちだから
小学校の低学年ではまだ、自己中心性が優位になることがあるということです。
自己中心性とは、いわゆる「ジコチュー」ということではなく、自分自身のことも客観的にみることができずに、自分の考えを意識することが難しい状態をさします。
ですので、「○ちゃんにあなたがしたことと同じことをされたらどう思う?」という問いかけは、実はうまく想像できていないケースも多いです。
年齢的には、3歳から少しずつこの傾向は弱まっていくのですが、発達障害・グレーゾーンの傾向がある子どもたちはゆっくりな場合が多いですし、大人になっても完全にはなくならないものです。
特に、小学生のお友達関係は「この子と遊びたい!これをして遊びたい!」という想いが強い場合が多いです。
その想いが強いと「○ちゃんも同じ気持ちだ」と思い込んで誘ったり、自分の知っている情報は相手も知っていると思って会話を進めたり、ということが起きて、食い違いやトラブルにつながるのです。
女の子の友達関係の悩みを解決する方法をこちらでもご紹介▼▼
女子は男子に比べ、 集団生活では外面をよくしているケースも多いので、発達に課題があったとしても、先生たちや周りのお友達には気づかれないケースが多いのが現状です。
女の子の「友達関係がうまくいかない!」そんな悩みを、ママとの関わりで楽しく解決できるヒントが満載!ワーク付きの無料小冊子はこちらから。
3.友達関係トラブルになる前に!親子のコミュニケーションを整えよう
もし、お母さんが「もしかして、うちの子…」という、わが子の発達特性からくる友達関係のつまずきに気づいたならば、まずはご家庭でしっかりと脳にアプローチするコミュニケーションをしていきましょう!
その子に合ったコミュニケーションをとることで、
少しずつ周りのことが見えるようになってくる!
見通しがもてるようになってくる!
素直な受け答えができるようになる!
こんな風に変わり始めます。
お母さんがモヤモヤをリカバリーできるような関わり、女子トークのストレスを和らげる関わりがとても大事です。
だからこそ、うまくケアできる親子関係を作っていってほしい。それも小学校低学年、小学校2年生までに作ってほしいという想いがあります。
では具体的には何をしたらいいの?という方、ぜひ親子関係をスムーズにして子どもの成長を加速させる発達科学コミュニケーションを学んでみませんか?
お子さんの未来がきっと良い方に変わりますよ!
女の子の友達関係の悩みを解決するためにママができることがわかります▼▼
▼親子の自分を信じる気持ちが育つこと間違いなし!
脳を成長させるためのダイアリーの活用術をこちらの無料書籍でお伝えしています。▼
▼不安が強くて繊細な発達グレーっ子の「春」が変わる!なりたい未来を親子で叶える日記術
アドベントダイアリー▼
https://www.agentmail.jp/lp/r/8627/79279/
様子見で後悔しない!おうちでできる関わりを始めてみませんか?
執筆者:はらしおり
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
(発達科学コミュニケーショントレーナー)