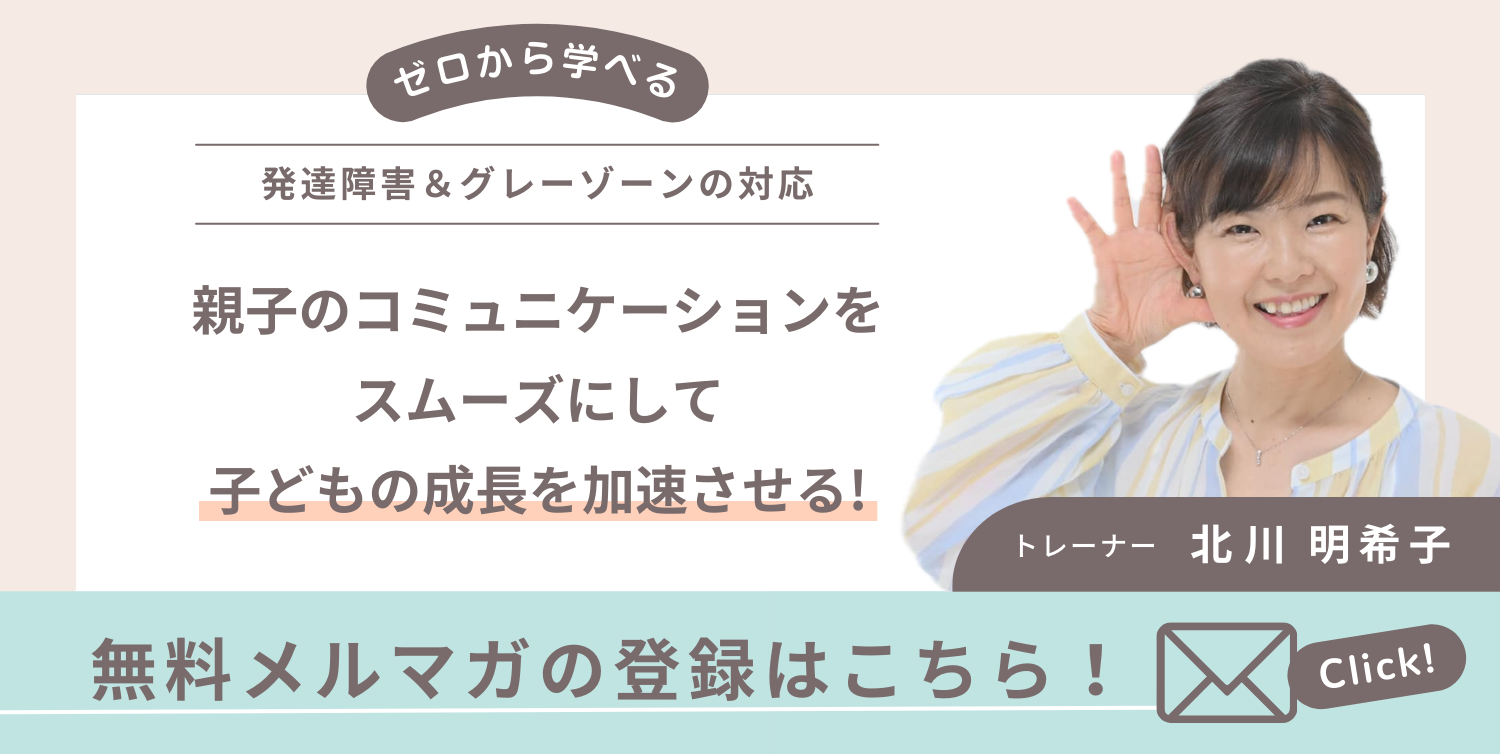わざと人の嫌がることをする子どもを何とかしたい!「なんでこんなに反抗的なの?」とイライラするお母さんへ。それって試し行動かもしれません。試し行動の原因を理解することで、対応のコツがわかりますよ。
【目次】
1.わざと人の嫌がることをする子どもは試し行動をしている?
子どもの困った行動はいくつかあれど、わざと人の嫌がることをする子どもにイラっとすることはありませんか?
わざと物をひっくり返したり、わざとゆっくり歩いてみたり。
どう考えても「わざと」だよね、と思われる行動。
ママが急いでいる時や次にやって欲しいことがある時などに限ってこんな行為が見られます。
私の娘が小1の時も反抗的な行動が見られました。
特別支援学級に通うダウン症の娘で毎朝付き添い登校をしています。
娘のわざと嫌がることをする行動は、登校や学校のお仕度の時によく見られました。
・「危ないから端を歩いて」と注意しても道路の真ん中を歩く
・ファイルをわざと床に落とす
・隣のクラスへ行って座り込む
・お着替えする体操服を放り投げる

なかなか準備が進まないので、
「早くして!」「なんでそんなことするの!」
とイライラしながら声をかけていました。
今思えば、このような嫌がらせの行動は「試し行動」だったのだろうと思います。
2.試し行動とは?
試し行動とは、子どもがママの愛情を確認するための行動で、わざと普段から注意されていることをやる困らせ行動です。
幼児の時期にはよく見られる行動ですが、子ども自身も「これをやるとママが嫌がる」「ママが怒る」ということは理解しています。
そして、試し行動でどこまでやればママが怒るのかどうか試しています。同時に、ママの注目を引きたい気持ちがあります。
ママが「もうやめなさい!」「いい加減にして!」と怒っても、「自分に注目してくれている」「かまってくれている」と子どもの気持ちとしては「嬉しい」なのです。
とくに、発達障害やグレーゾーンの子どもは、脳の発達が未熟な部分があり、行動とは矛盾した感情を持っていることがあります。
ダウン症の娘が学校のお仕度のタイミングで試し行動が出ていたのは、仕事に行く時間が迫り、「早くしようよ」「こっちが先だから」とわたしのイライラがでやすいタイミングだったからです。
ママは自分のことを丸ごと認めてくれているのだろうかと不安になっていたのが原因です。

ここでママが怒ってしまうと子どもにとっては嬉しいご褒美になってしまう。
では、こんな時ママはどんな対応をとればよいのでしょうか?
3.ママがイライラしない2つの対応
◆①無視にならないスルー
わざと嫌がることをする行動には、ママの「スルー力」を磨くことです。
スルーと言っても無視ではありません。
まず、嫌がらせ行動からはいったん視線を外しましょう。視界に入るとどうしてもイライラしてしまいますからね。
視線をふーっと外したまま微笑みを作ってみましょう。
景色を眺めたり、教室の掲示板へ目を移したりするといいですね。
子どもは、ママの注目が欲しくてわざと嫌がることをするのにママが無反応だったら…
試し行動は子どもにとっては無意味になります。
娘がファイルや体操服を床に投げた時、私は表情はかえず「あらあら」と微笑みながら拾いあげました。

ポイントは子どもの言動や行動に反応しないことです。
そのうち「ママの注目=ご褒美」が得られない試し行動はなくなっていくでしょう。
◆②次の行動に誘導する
2つ目は「次の行動に誘う」です。
わたしの場合はここで「じゃあ連絡帳を出してこようか!」と笑顔で誘います。
娘も笑顔で「わかったー」と立ち上がりました。
これでスムーズに朝のお仕度が進むようになりました。
そこですかさず肯定です。「連絡帳、ちゃんと出せたね」と笑顔で声掛け。
怒られる注目より、褒められて笑顔のママの方が子どもにとっては何倍ものご褒美になり、好ましい行動が定着していきます。
このようにどんな自分も認めてもらえる安心感と次の行動に移すきっかけを与えてあげましょう。
今まで怒られてばかりだった子どもは、ママの怒りのポイントを探る行動をします。
ここでお母さんが過剰に反応すると、子どもの試し行動もエスカレートします。
ここをスルーで乗り越えることで、親子のコミュニケーションがグンと良くなります。
ママが怒ってばかりだと、子どもも怒りっぽい子になっていきます。怒りが習慣にならないことが大事。
子どもの行動に伴っているのはどんな気持ちなのか、よく観察してみてくださいね。
執筆者:北川明希子
(発達科学コミュニケーション トレーナー)
(発達科学コミュニケーション トレーナー)